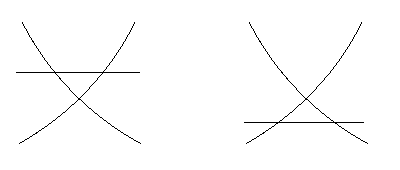
[ 注記]
既存の原稿の「ユニバーサル・モデル」という用語は、本論では、
「トリオモデル」という用語に変更した。(意味は同じ。)
この論考で扱うのは、「均衡と不均衡」の問題である。「均衡とは何か?」「不均衡とは何か?」ということを考える。
すると、結果的にわかるのは、こうだ。大事なのは、「均衡」ないし「不均衡」という個別状態ではなくて、「秩序」ないし「不秩序」という全体状況なのである。
こういう違いが大切だ。そして、後者では、「均衡に達することで万事解決する」というふうにはならないのだ。
「秩序/不秩序」は、経済における「平常時/不況時」というふうに理解してよい。ただし、経済に限らず、もっと広い学問領域にも適用できる。いわゆる「複雑系の科学」というものに相当する。従来、「非線形科学」「カオス理論」「カタストロフィ理論」「ナッシュ均衡」などがあった。それらは、複雑な事象を説明しようとするものだった。しかし、そのどれもが、経済を説明するには不適切だった。
なぜか? そのどれにも、一番肝心なことが欠けていたからだ。それは「均衡と不均衡」だ。これこそが経済学の核心となる。その核心を「秩序理論」は示すことができる。
秩序理論によれば、従来の経済学がなぜ間違った結論を出してきたか、その理由もわかる。簡単に言えば、こうだ。従来の経済学(というより一般的な科学)は、「均衡」を前提としてきた。しかるに、現実の社会現象や自然現象は、「均衡」と「不均衡」が入り乱れている。そのせいで、単純な原理から、非常に複雑な現象が起こる。なのに、単純に「均衡」だけを前提として考えてきたから、従来の考え方は、現実を正しく把握できなかったのだ。
[ 付記 ]
数式的に言えば、こうだ。従来の自然科学は、何らかの方程式を書いたりといたりすることを目的としていた。そこでは「等式」が書かれた。「X=Y」のように。しかし、秩序理論が扱うのは、「等式」ではなく、「不等式」の世界なのである。「X<Y」のように。そこで大切なのは、代数的な計算ではなく、幾何学的な位置関係となる。
基本を述べよう。
経済などの複雑な現象については、「均衡/不均衡」という観点から、二つに区別することができる。その区別は、何か? 個別の状態について、「均衡であるか/不均衡であるか」ではない。全体状況について、「均衡が自然に成立するか/均衡が自然に成立しないか」である。──そして、その両者を、「秩序/不秩序」と区別する。
「均衡/不均衡」というのを考えようとしているが、実は、これは、核心的な違いではない。そもそも、世の中の状況のほとんどは不均衡なのである。
具体的に例を示そう。化学的な「濃度平衡」の例だ。( → 2月27日 )
いま、水中に食塩を落とす。すると、食塩は水中に溶けて拡散していく。このとき、溶液の各部を見ると、濃い部分と薄い部分がある。濃い部分から薄い部分へと、食塩は拡散していく。そして、最終的に、濃度は均一になる。
ここで、最終的に濃度が均一になった状態では、「平衡」(= 均衡 )が達成されている。ただし、途中では、濃度の濃い部分と薄い部分との間で、不均衡状態となっている。しかし、そのような不均衡があっても、特に問題があるわけではない。不均衡があっても、その不均衡を埋める方向に、状態が変化していく。不均衡は小さなものであるし、この不均衡ゆえに状態は変化していく。
ところが、食塩を落とす量が、ある一定量に達すると、飽和する。それ以上に入れた食塩は、溶けずに、沈殿する。
このときもはや、状況が決定的に変化している。ここにある不均衡は、もはや小さなな不均衡ではなく、大きな不均衡である。そして、この不均衡は、自然な状態では解決されない。「食塩が溶けにくいのならば、もっと食塩を入れてやれ」という思って、どんどん食塩を入れても、溶ける量は変化しないまま、単に沈殿する量が増えるだけだ。
結局、世界には、二つの状況がある。「均衡」が自然に成立する状況と、そうでない状況と。そして、その二つの状況は、不連続的につながる。
この二つの状況の不連続的な関係を本質的に考えようとするのが、「秩序理論」だ。
秩序理論は、物質を扱う自然科学ならば、特に必要はないとも言える。自然科学では、たいてい、状況は一意的に決まるからだ。(たとえば水の沸点は一意的に決まる。)こうなると、状況を、等式で説明することもできる。
しかし、社会的な現象では、状況は一意的に決まらないものだ。(たとえば好況も不況も千差万別である。)こうなると、等式で説明することは難しい。
具体的に言おう。たとえば、食塩水の沈殿する量ならば、その量は一意的に決まるから、等式で説明することもできるだろう。しかし、経済学における貨幣供給量の効果などは、その量は一意的ではないから、等式では説明しがたい。
しかし、である。たとえ等式では説明できなくても、何らかの関係はわかるはずだ。少なくとも、最も重要であるはずの、大小関係などについては、わかるはずだ。大小関係がわかれば、幾何学的な位置関係もわかる。そういうことを探ろうとするのが、秩序理論だ。
秩序理論で最も大切な適用対象は、経済学だ。経済学においては、均衡と不均衡が非常に重要となる。
経済学において、不均衡という状態は、実は、ごくありふれた状態である。たとえば、「ある商品を考えたとき、唯一の価格が決まり、需要と供給がぴったりと一致する」ということは、現実にはありえない。価格はあちこちの店でバラバラであるし、需要と供給もバラツキがある。たとえば、ある店では価格が高すぎて在庫が多く、別の店では価格が安すぎで品切れになる。また、一国全体でマクロ的に全商品を見ても、時系列で言えば、売れ行きが良くなったり悪くなったりで、在庫量が変動する。──つまり、生産量と需要がぴったりと一致することはありえない。「需要不足」や「需要超過」は、たえずどこかで発生する。
ただし、「需要不足」や「需要超過」は、短期的には少しぐらいは存在するが、価格を通じた需給の調整がなされるので、放置すれば、自然に不均衡は解消されるはずだ。食塩の濃度がしだいに均一化されるのと同様である。
ところが、平常時には、そうなるとしても、不況のときには、そうならない。もともと「需要不足」(需給ギャップ)があるが、放置すればどんどん不均衡が解消するということはない。つまり、放置すれば不況が自然に解決するということはない。
では、なぜか? ここが最も肝心のことである。その答えをいきなり言おう。それは、「均衡点は固定的でない」ということだ。
均衡点というものは、実は、どんどん移動していくのである。食塩や砂糖で言えば、飽和する量は、温度によってどんどん変化する。では、経済学では?
修正ケインズモデルで言おう。「需要超過」があると、均衡点は右上に移動する。「需要不足」があると、均衡点は左下に移動する。均衡点は、決して固定されているわけではなく、状況に応じて移動する。そして、均衡点に近づくとき、同時に、生産量が変化する。需要超過のときには、均衡点に近づくとき、生産量は増える。需要不足のときには、均衡点に近づくとき、生産量は減る。
この際、均衡点がどこにあるかが、非常に重要な問題となる。
平常時ならば、均衡点は一定の領域の内部にあって、均衡点に近づくことで状況が改善する。しかるに、不況時ならば、均衡点は一定の領域の外部にあって、均衡点に近づくことで状況が悪化するのだ。──前者が「秩序」であり、後者が「不秩序」である。
「均衡/不均衡」というのは、単なる個別状態のことである。「秩序/不秩序」というのは、均衡や不均衡が何をもたらすかという全体状況のことである。
「秩序」という全体状況にあるときは、状態が「不均衡」から「均衡」へと向かうことで、全体的な状況は改善する。
「不秩序」という全体状況にあるときには、状態が「不均衡」から「均衡」へと向かうことで、全体的な状況はかえって悪化する。
つまり、「不秩序」のときには、「放置すれば、均衡点に近づく」ということは成立するのだが、「均衡点に近づけば、状態が改善する」ということは成立しないのだ。結局、「放置すれば、状態が改善する」ということは成立しないのだ。
「不秩序」のときには、社会の各人は、自己にとって利益のある行動を取るが、そのことで、全員の状態がかえって悪化する。各人としても、「利益」をめざせばめざすほど、「不利益」になる。そういう倒錯的な現象が起こる。この現象を「合成の誤謬」と呼ぶ。
では、こういうときには、各人は、どうするべきか? 逆に、自己にとって不利益な行動を取るとよいのだ。そうすると、全員の状態が改善する。各人としても、自己にとって利益になる。つまり、各人は、「自己にとって不利益な行動」を取ることで、逆に、「自己にとって利益を得る」というふうになる。(「囚人のジレンマ」と似ている。)
とはいえ、「全員の状態が良くなることをめざして、各人が自己にとって不利益な行動を取る」というのは、現実には困難だ。それは、「自然にそうなる」とか「均衡する」とかいうのとは、反対の行動だからだ。
ここでは、心理的な要因が大きく影響する。具体的に言おう。全員が協調的であるときと、全員が利己的であるときでは、結果が異なるのだ。全員が協調的であれば、「協力行動」が実現して、「不秩序」から「秩序」へと移行することができる。逆に、全員が利己的であれば、「協力行動」が実現せず、「不秩序」のまま、状態は悪化するばかりだ。(「囚人のジレンマ」と似ている。)
こういう区別は、大切だ。なぜなら、古典派の経済学にはない考え方だからだ。
古典派の経済学では、「全員が利己的に行動すれば、全体の状況は改善する」と信じられてきた。「市場原理」とか「パレート最適」とかいう概念がそうだ。それが成立しないのは、特別な例外的な場合か、競争が不完全なときに限られ、基本的にはそれが成立する、と信じられてきた。──しかし、そういう概念は、「秩序」のときには成立するとしても、「不秩序」のときには成立しないのだ。
端的に言えば、「放置すれば、均衡が実現して、状況は最適になる」ということが、不秩序のときには成立しないのだ。
例を示そう。全員が善人ならば、人々は協調する。金を出し合って、公共財を整備して、社会は改善される。逆に、全員が悪人ならば、人々は協調せずに利己的にふるまう。公共財を盗んだり、他人の金を盗んだりして、社会は悪化していく。
つまり、「不秩序」である全体状況では、利己的な行動は社会を崩壊させるのだ。そこでは、「神の見えざる手」などは、ありえないのだ。
こう理解すれば、われわれの取るべき態度もわかる。われわれの前には、二つの選択肢がある。
もちろん、後者が正解だ。そして、後者を取れば、なすべきこともわかる。不秩序のときになすべきことは、「放置すること」ではなくて、「不秩序から秩序へと、全体状況を変えること」なのだ。そしてまた、不秩序のときには、大切なのは、全体状況を変えることだけであって、単に各人が当然な行動をするだけでは、状況はかえって悪化するのだ。それが「合成の誤謬」だ。
とにかく、「秩序と不秩序の二つの状態がある」と理解することが大切だ。そしてまた、「不秩序においては、秩序における常識が成立せず、むしろ、常識とは逆のことが成立する」と理解することが大切だ。
不況のさなかでは、人々はしきりに最善行動を取ろうとする。そうして均衡点に近づこうとする。しかし、それは、正しいことではなくて、悪いことなのだ。こういうふうに価値判断の基準が逆転するという全体状況を、はっきりと理解するべきなのだ。──それが、「秩序理論」の教えることだ。
同等のことは、経済学において、「貯蓄のパラドックス」や「合成の誤謬」という用語で知られている。しかし、なぜそういうことが起こるかという基礎的な原理については、考察がされなかった。秩序理論は、その基礎的な原理を、包括的に理解しようとする。
秩序理論は、一般の自然科学とは異なる。自然や社会の現象を、定量的に解明することはできない。未来がどうなるかを、定量的に予測することもできない。では、何ができるか? 未来について予測するのではなくて、未来を変える方法を教えてくれるのだ。
たとえば、「この先に穴がある。だから、その穴に落ちるだろう」と予測するのではなくて、「このままでは穴に落ちるだろう。だから、穴に落ちないためには、こう対策するべきだ」と教えてくれるのだ。
たとえて言おう。川で小舟に乗っている。平常のときならば、「放置すれば小舟は安定する」と言える。しかし、川の下流に滝が見えたときは、そうではない。このままでは、滝から落ちてしまう。「放置すれば小舟は安定する」と言っても、無意味である。その「安定」とは、「滝から落ちて、沈没したあとの「死」のことだ。そんなものは、むしろ、避けるべきだ。では、どうやって避けるか? ある古典派経済学者は、「放置せよ。神の手に委ねよ」と叫ぶばかりだった。別の古典派経済学者は、「自分自身のために最善を尽くせ。全力でオールを漕げ」と叫ぶばかりだった。しかし、いずれの勧告に従っても、効果はなかった。個人の力は微力である。どんどん滝に近づくばかりだった。しかし、「秩序理論」には、こう書いてあった。「個人の利益を犠牲にしてでも、全体の利益をめざせ」と。そこで各人は、オールを捨てた。かわりに、隣の小舟同士で、ロープを結び合った。すると、全員のロープがつながって、岸辺に達した。全員は救われた。
このたとえ話は、あくまで、たとえ話だ。ただし、その奥には、根元的な原理がある。その根元的な原理を、このあと説明していくことにしよう。
( ※ 秩序理論は、単に、人々に方法を示唆するだけでなく、自然における真実も教えてくれる。それは進化論との関係だ。このことは、別の論考で述べる。)
本論の目的は、均衡と不均衡について解明することだ。ただ、結果的に、もっと大きなことをなすことに至る。それは、いわば、「ジグソーパズルで、最後の一片をパチンとはめて、全体を完成させること」である。
とすれば、その前に、ジグソーパズルの断片を、すべて明示しておいた方がいいだろう。つまり、既存の知識を、ずらりと並べておいた方がいいだろう。そこで、それらを、ざっと列挙しておく。
経済学(特にマクロ経済学)については、すでに私の「小泉の波立ち」のあちこちで、いろいろと説明してきた。これらについて、あらかじめ理解しておく必要がある。特に、「トリオモデル」および「修正ケインズモデル」については、熟読しておく必要がある。この二つをよく理解しておかないと、本論は十分に理解できない。
「均衡」について、モデル論ふうに、これまで話題にしたこともあった。以下では、ふたたびざっとまとめておこう。これらは、もともとは他人の主張であり、それに私のコメントを付けたものである。細かな話は、参考箇所や、既存の文献を参照してほしい。)
「均衡」については、前項で述べたことのほかにも、他の理論がいろいろとある。まだ紹介していなかったものなので、ここで、ざっと紹介しておこう。(詳しい話は、既存の文献を調べてほしい。)
「囚人のジレンマ」を 2×2 から、n×m に拡張できる。つまり、n人の人間がいて、m個の戦略がある、と。ここでは一般に、複数の均衡点が存在することがある。たとえば、「最適の均衡点」と「次善の均衡点」がある。そして、いったん「次善の均衡点」に位置すると、「最適の均衡点」へ移るのが困難となる。そういうことがある。
各人が当然な行動をしている限りは、「次善の均衡点」から「最適の均衡点」へ移ることができない。「次善の均衡点」から「最適の均衡点」へ移るためには、各人が当然な行動をするのではなく、もっと別のことをする必要がある。
均衡点はひとつだけあるとは限らない。古典派経済学では、均衡点はワルラス的均衡点という唯一の点があるはずだった。しかし、ナッシュ均衡のように、均衡点が複数ある、という場合もある。
「均衡点が複数ある」ということは、2次元のグラフでは、「曲線の交点が複数ある」ということを意味する。あるいは、「ポテンシャルの極小値が複数ある」というふうにも示せる。
「ナッシュ均衡」や「複数均衡点」は、「合成の誤謬」を説明するように見えるので、経済学には非常に有益であると想像されている。
( ※ ただし、ここでいきなり解答を言うと、その想像は正しくない。つまり、「ナッシュ均衡」や「複数均衡点」は、「合成の誤謬」とは関係ない。しかし「囚人のジレンマ」は、「合成の誤謬」と関係がある。実は、「囚人のジレンマ」をある方向に拡張すると、「ナッシュ均衡」になるが、「囚人のジレンマ」を別の方向に拡張すると、「合成の誤謬」になる。どちらも「囚人のジレンマ」を基礎に置くが、「ナッシュ均衡」と「合成の誤謬」とでは、拡張する方向が異なるのだ。)
「各人が利己的な行動を取ると、全体状況が最善になる」ということは、資源配分においては成立する。これはミクロ経済学の基本だ。
では、そういうことは、マクロ的にも成立するか? 全体状況が「秩序」であるときには、成立する。しかし、「不秩序」であるときには、成立しない。(「合成の誤謬」である。)
実際、不況のときを見てみよう。設備や労働者が、余剰となって、遊休している。ここでは資源の最適配分などはなされていない。
結局、こうだ。
資源配分の問題があるのは、資源が不足しているときだけだ。資源が養生になっているときには、配分の問題はない。
お菓子が5個あって、7人が欲しがっているのならば、「どう配分するか」という問題が発生する。しかし、3人が欲しがっているだけなら、2個は余る。この余った分は、引き取り手がいない。そういうときには、資源配分の問題は生じない。「パレート最適」は、意味をなさない。
具体的に言おう。不況のとき、設備や労働者が遊休しているときには、どこにどう配分するかなんていうことは考えないでいいから、とにかく働かせるべきなのだ。高度な技術者が単純労働をするのはもったいないが、たとえもったいなくても、失業しているよりはマシだ。とにかく、雇用の口を作って、働かせるべきなのだ。そして、景気が回復して、設備や労働者が引く手あまたになったら、そのとき、「パレート最適」によって、効率的な配分をなせば追い。
とにかく、「パレート最適」が意味をもつのは、均衡が実現しているときだけだ。
「将来を予測できること」というのは、大切なことだと考えられている。特に、自然科学では、予測ができることが大事だと考えられる。(それが「法則」だ。)
そこで、「将来の予測」ということで、いくつかのタイプを並べてみよう。
このうち、最後のタイプのものが問題となる。たとえば、「美人投票」だ。
「美人投票」の優勝者を予測するには、どうすればいいか? 「最も美しい人」(自分がそう判断する人)を選んでも、予測がうまく当たるとは限らない。「他の人々が選びそうな人」を推測すると、予測は当たる。客観的に何がどうのこうのというよりも、人々が主観的にどう思うかということが大切なのだ。
投機も同様だ。株価が上がるか下がるかを予測するには、現実の状況がどうであるかを予測するよりは、人々が株価について「上がると思うか下がると思うか」を予測するべきなのだ。なぜなら、ある株が上がるか下がるかは、その企業が客観的にどうであるかよりは、人々がその株を売るか買うかに依存するからだ。そしてそれは、人々が株価について「上がると思うか下がると思うか」に依存する。
この説は、ケインズの主張による。
この説のポイントは、二つある。
一つは、現実世界の変動が人間心理に依存する、ということだ。自然界の法則や原理ではなくて、人間の心理によって、「こうなりそうだ」と思った方向に現実世界が変動してしまう。
もう一つは、古典派経済学との対比だ。古典派経済学の主張では、「投機は均衡する」というふうになる。たとえば、小麦の価格が上昇したとしよう。すると、投機家は、「将来は小麦価格が下がるだろう。だから今のうちに、小麦を売っておこう」と思う。そして市場で小麦を売る。だから一時的に上がった価格は、投機によって下がる。かくて、市場価格は均衡点に収束する。このようにして、市場は自然に安定するはずだ。
しかるに、ケインズの考え方では、そうはならない。小麦価格が上昇したとしよう。すると、「さらに小麦は上がりそうだ。だったら、小麦を今のうちに買っておけば、大儲けができる」と信じる人が多くなる。かくて、小麦を買う人が多くなるので、価格はどんどん上昇していく。市場価格は一点に収束するどころか、その逆になる。かくて、市場価格は、常に大きな変動にさらされる。
結局、人間心理による影響は、古典派によれば「安定」であり、ケインズによれば「不安定」である。
( ※ 現実には、どうか? バブル期を見ると、こうだ。初めのころは、ケインズの説のとおり、資産価格はスパイラル的に上昇した。しかし、バブルがはじけると、元の価格に近づくようになった。ここは、古典派の言うとおりになったと見えた。ところが、資産価格は、単に下がっただけでなく、下落が行き過ぎて、元の価格よりもさらに下がってしまった。「みんなが売るから自分も売る」というわけだ。これは、ケインズの説の通りだ。現実を見ても、株価は上がらないままの状態がずっと続いた。古典派に属する竹中大臣は、「必ずいつか株価は上がる。だから株を買おう」と主張しているが、国民は株を買わない。つまり、「いつか上がるから買おう」とするのではなく、「みんなが買わないから自分も買わない」というふうになっている。)
古典力学では簡単な法則ですべては決まる。しかし簡単な法則では片付かない現象を解明しようとして、昔からいろいろと理論が提出された。それらを総称して、「複雑系の科学」と呼ぶことがある。
そこで扱う現象は、「予測可能」ではないものばかりだ。たいていは、対象があまりにも複雑な動きをするので、予測不可能となっている。
ただ、予測不可能であっても、「決定論的」であると見なされるものも多い。つまり、「結果は初期条件から一意的に決まるはずだ」と思われているものが多い。
たとえば、気象だ。「将来の気象は、現在の気象に対して、一意的に決まるはずだ」と思われている。「一意的に決まるはずなのに、将来を予測できないとしたら、それは、単に人間の能力が劣っているからにすぎない」というわけだ。そして、「だから、コンピュータのハードやソフトを非常に優れたものにすれば、いつかは完全に将来の気象を予測できるようになるだろう」と信じたり、さらに、「気象だけでなく、あらゆる複雑な現象も、やがては完全に予測できるようになるだろう」と信じたりする。
ただし、カオス理論は、こういう方法に原理的な限界があるだろう、ということを推測させる。
「線形/非線計形」という区別は、「複雑系の科学」において重視される。
古典力学などの物理現象は、たいてい、1次関数までの微分方程式で示される。たとえば、ニュートンの法則は、2次関数で示されるが、これは、1次関数の微分方程式の解となっている。
線形というのは、数学的に言えば、「1次関数であること」である。ただ、その前提としては、次のことがある。
f(x) + f(y) = f(x+y)
このような関数 f(x) を、「線形」であると称する。それは f(x) が cx という1次関数であるのと同値である。(ただし c は定数である。このことを証明するのは、高校生レベル。)
なお、一般的には、「線形」というのは一次関数であることを意味する。つまり、 f(x) が cx+d という形であることを意味する。
物理学では、「非線形である」というのは、「複雑な関数である」というのと、ほぼ同義である。たとえば、振り子の動きだ。初歩的には、 sin という三角関数を1次式で近似することで解を得るが、正確には、もっと複雑な動きを取る。そういう複雑な動きを示す複雑な関数は「非線形である」と称される。
ニュートン力学は大きな成果をなしえた。それは「初期条件を知れば、その先の動きを精確に予測できる」というものだ。そして、その考え方を敷衍して、ラプラスの悪魔というものが考えられた。
この悪魔は、初期条件を知ることで、その後の世界の動きをすべて予測することができる。すなわち、この先の未来の事象のすべては、すばらしい数学的能力をもつ悪魔が、あらかじめ予測している、というわけだ。いつ、どこで、誰が、何をするか。そのすべては、とっくの昔から、彼にはわかっているのだ。なのに、同じことを人間が知ることができないとしたら、それは単に、人間の数学的能力が劣っているからにすぎない。──そういうわけだ。
物理的な現象は、たいてい、微分方程式で記述できる。だから、微分方程式を解く方法さえわかれば、あとは高度な演算能力があるだけで、将来について予測できるはずだ、と考えられた。
さらに、コーシーは、「普通の微分方程式には必ず解がある」ということを証明した。前頭はますます有望と思われた。
ところが、ポアンカレは、「(特別な場合を除いて)一般的には、微分方程式は解けない」ということを証明した。これは衝撃的な出来事だった。
ともあれ、微分方程式は、「解の存在することはわかっても、その解を知ることはできない」のが普通であるわけだ。
さらに、「微分方程式で記述できる現象は、実は、限られたものでしかない」ということが明らかになった。微分方程式は、「すばらしく広い範囲で適用できる」と思われたのだが、実は、古典物理学の範囲内に適用できるだけにすぎず、しかも、そのうちで最も簡略化された場合に適用できるだけにすぎない、とわかった。ここで一部の人々は絶望的になった。
ところが、まだ近似的に計算するシミュレーションという方法があった。それはコンピュータの発達により、大きな成果をもたらした。この方法も有望と思えた。
とはいえ、そこでもやはり、「現実の世界を扱うには、変数があまりにも巨大になりすぎる」という問題が生じた。これをベルマンは「次元の呪い」と称した。たとえば、経済の現象を調べるのに、世界中の数十億人の人間とか、数限りない商品の種類とか、マネーの分布とか、途方もない数の考慮対象がある。そのすべてをシミュレーションすることなどは、とうていできない。
結局、人間は、神のごとき予測能力は持てそうにないとわかったわけだ。
すでに述べたことをまとめてみよう。
まず、ニュートン力学の成功があった。
それを見て、「その方法を拡張しよう、そうすれば世界のすべてを理解できる」という期待が生じた。
しかしそれは、「ラプラスの悪魔」をめざすのと同じであり、不可能な夢想だ、とわかった。
そこで、完全な予測はできないまでも、可能な限り真実をつかもうとして、古典物理学とは別のアプローチが生まれた。それは、「物事を単純化して理解する」という古典物理学とは反対に、「物事の複雑さを理解する」というアプローチだった。
しかし、そうやっていろいろと理解しても、新たな真実を理解できたのではなくて、「真実には届かない」ということを理解するばかりだった。真実というのは、原理や原則であって、単純なものなのだ。そういう単純なものをとらえることが大切なのに、複雑さばかりを理解しても、それは、「真実を知る」というのとは、別のことをやっているにすぎなかった。
特に、経済だ。経済という複雑に動くものを、何とかして理解しようと、人々は努めた。カオスや、フラクタルや、カタストロフィなど、そういう理論を用いてけんっきゅうした。しかしいくら研究しても、経済については何もわからないままだった。「これこれの経済現象は、このモデルでこう記述できます」というふうに、我田引水をするぐらいが、関の山だった。何らかの新しい知見を、その理論から得ることは、ほとんどできなかった。
そのあと、二十一世紀になって、「トリオモデル」および「修正ケインズモデル」というモデルが現れた。ここでは、「均衡/不均衡」ということが、非常に重大だ、とわかった。
ここで、「秩序理論」が登場する。
「均衡/不均衡」ということは、経済学において重要だが、実は、経済学だけでなく、もっと広い領域においても、重要なのである。
複雑な動きをするものは、経済学だけでなく、気象など、さまざまなものがある。その多くは、「複雑系の科学」の対象となる。ただ、そのうちのある範囲のものは、「均衡/不均衡」という原理で説明できる。
「均衡/不均衡」というのは、単純な原理である。しかし、その単純な原理から、複雑な動きが生まれる。その一例が、経済だ。経済は、複雑な動きをなす。複雑な動きは、複雑な原因からう真れると考えら絵りゃすい。しかし、そうではない。複雑な要素をいちいち考慮する必要はない。たとえば、莫大な人間を考慮したり、莫大な商品を考慮したり、莫大な企業を考慮したり、……というふうに、いちいち考慮する必要はない。考えるべきことは、「均衡/不均衡」ということだけだ。このことを、基本的な原理として理解するだけでいい。それだけで、経済の複雑な動きは、ほぼ正確に記述できる。(ケインズの言い方では、「精確に間違うよりは、おおざっぱに正しい方がいい」となる。)
ともあれ、以下では、いよいよ、秩序理論そのものに踏み込もう。
このあとで秩序理論に踏み込むが、その前に、もう一つ、参照しておく概念がある。そして、これは、秩序理論において重要な位置を占める。それは、「閾値」という概念だ。
(「閾値」という単語は、「いきち」または「しきいち」と読む。どちらも正しいが、私としては、音読みで、「いきち」と読んでほしいと願う。心理学では、「いきち」と読むのが普通である。)
「閾値」という概念は、目新しいものではない。生物学や物理学で、ひろく知られている。「ある値を境界として、状態が不連続に変化する」とき、その値を、「閾値」と呼ぶ。
最もわかりやすいのは、水の沸点や凝固点だ。ある温度を境として、固体が液体となったり、液体が気体になったりする。その温度の値は、「閾値」となっている。
化学でも、なじみのある概念である。電子や原子や分子は、ある値を超えたエネルギーを持つと、別の領域へ移動することができる。(量子力学では、これを確率的に考えるが。)
生物学では、神経に感知される最小限度の刺激を、閾値と呼ぶことがある。つまり、その値を境界として、「感知不可能」と「感知可能」とに区分されるわけだ。
閾値という概念は、さまざまな分野で、すでに知られている。ただ、これを、社会的な現象にも適用する試みが、近年はなされるようになった。特に、「閾値と均衡」というテーマで、研究されることも多い。( → 「閾値 均衡」というキーワードで、インターネット検索をするといいだろう。)
「閾値を境界として、状態が不連続に変化する」という経済状況がある。そういうことを、経済学で数理的に研究する試みがある。
たとえば、商品の普及率だ。初期の普及率が、将来の普及について決定的な違いをもたらすことがある。普及率がいったん閾値を超えれば、その商品は広く普及するが、普及率が閾値を超えないままだと、その商品は自然消滅する。
具体例のひとつは、情報端末だ。「ミニテル」および「キャプテン」がある。この二つは、どちらも「ビデオテックス」と呼ばれる情報端末であって、1980年代に実用化された。ただし、成功したのは、先進国中で、フランスの「ミニテル」だけだった。日本の「キャプテン」を初めとして、他国のものはいずれも普及しないで自然消滅した。
では、その違いは? フランスでは、「ミニテル」の端末が無償で国民に配布された。しかし日本などでは、端末は有償であった。それが初期の普及率に決定的な違いをもたらした。フランスでは、「ミニテル」がひろく普及したので、それにともなって、さまざまなシステムも発達した。日本では、初期に誰も端末を持たないので、システムもほとんど発達しなかった。
結局、初期の普及率が、閾値となったのである。
別の具体例は、患者の少ない病気の治療薬だ。患者の数が、ある一定数を超えれば、採算に乗る。だから、製薬会社が治療薬を生産して、市場で価格が形成され、需給は均衡する。
ところが、患者の数がある一定数を超えないと、生産に手間がかかる割には、売上げをたいして見込めない。しいて生産するとすれば、コストがかかって、患者の負担が数百万円にもなりそうだが、そんな高価なものを買える患者はほとんどいない。当然、売上げを見込めない。だから、結局、患者の数が一定数以下となる治療薬は、生産されない。(市場がないから、均衡点も存在しない。)
ここでは、患者の数が、閾値となっている。閾値を超えれば生産され、閾値を超えなければ生産されない。
「閾値を境界として、状態が不連続に変化する」ということは、社会状況にも当てはまることがある。社会心理学で数理的に研究する試みもある。
ここでは、閾値は、何らかの「状態」についての数値ではなくて、「参加する人間の数」である。(数は、絶対数または比率。)
具体例のひとつは、談合だ。関係者の全員が談合に参加すれば、全員が利益を得る。しかし、誰かが「ぬけがけ」をすれば、当人だけが利益を得て、残りの全員は損をする。ここでは、談合への参加者の数に、閾値がある。(一人か二人が談合をしても談合は無効だが、談合をする人の数が「全員」という閾値に達すれば談合は成功する。)
一般的に、「みんながそうすれば、状況が逆転する」というタイプの現象がある。これは「合成の誤謬」と原理的には同じである。このタイプの社会現象については、すでに研究した学者がいて、研究書を出している。( → 「社会的ジレンマ」山岸俊男 )
「合成の誤謬」は、「囚人のジレンマ」と関係がある。そこから推察されるように、閾値は、「囚人のジレンマ」と関係がある。
( ※ 以下の話は、すぐ上の研究書からの、引用である。ただし、わかりやすく書き換えている。)
「囚人のジレンマ」については、「最適の戦略は何か?」という問題がある。これについては、専門家があれこれと考えたすえ、単純な「しっぺ返し」の戦略が最強だ、とわかった。つまり、「相手が協調的ならば、こちらも協調する。そうして二人とも利益を得る。しかし、相手が非協調的であれば、こちらも非協調的にする。そうして二人とも不利益を得る」つまり、「相手だけにいい思いをさせることはない。相手が非協調的なときに、こちらは協調的にはならない」という戦略だ。(ただし、初期値は、ランダムであるとする。)
実際、専門家の提案したさまざまな戦略のうち、この「しっぺ返し」の戦略が最強だ、とわかった。
ところが、である。専門家たちの間に、素人が参加すると、専門家と対決して、さらに上回る成果を出す戦略が現れた。それは「常に協調的」という戦略である。相手が「しっぺ返し」の戦略をとるとき、「常に協調的」という戦略を取る。すると、その素人の方が、良い成績を収めることができるのだ。
では、この「常に協調的」という戦略が最強であるのか? そうは言えない。なぜなら、相手が「常に非協調的」という戦略をとると、「常に協調的」という戦略を取った素人は、いいカモにされて、ボロ負けしてしまうからだ。
ここで、たくさんの人間がいて、たくさんの回数のゲームをさせてみよう。すると、わかることがある。「常に非協調的」という人(エゴイスト)の数が多いか少ないかで、「常に協調的」という人が有利になるか不利になるかが決まる。エゴイストが少ないときには、協調的な行動は有利である。しかし、エゴイストが多いときには、協調的な行動は不利である。
だから、ここでは、「エゴイスト数によって閾値が決まる」と考えられる。エゴイストの数が閾値を超えれば、協調的な行動は不利。エゴイストの数が閾値を超えなければ、協調的な行動は有利。
( ※ 細かい話を言おう。実は、「しっぺ返し」戦略で、初期値をランダムにしないで、常に初期値を「協調」にすると、最強の戦略となる。ただし、誰もがそういう政略をとると、全員が「常に協調」を取ったのと同じことになってしまう。これでは、話が詰まらない。)
すでに、二つの分野で閾値を示した。自然科学と、社会科学。どちらに現れるも面「閾値」と呼ばれる。しかし、両者の違いに注意しよう。
この両者は、たいして違いはないように思えるかもしれないが、決定的に異なるのだ。
なぜか? 後者は、単なる心理的なものにすぎない。たとえば、百万人の人間がいるとして、百万人がそろっていっせいに心を変えることは、簡単である。単に各人が心を変えるだけでいい。たとえば、「純ちゃん大好き」と言っていた百万人が、「真紀子解任」のあとで、一夜にして「純ちゃん大嫌い」になることは、容易に起こる。
一方、現実の状況は、そう簡単ではない。「自動車を急に百万台生産する」とか、「携帯電話をいきなり百万台売り尽くす」とか、そういうふうに現実の状況を一挙に大変革することは、非常に困難だ。
もう少しわかりやすく言おう。現在の景気を、不況から好況に変えさせたいとする。ここで、「自動車や食品やサービスなどを、30兆円程度、いきなり生産を拡大する」というのは、まず不可能だ。生産を直接的に急拡大させることは不可能である。しかし、人々の心がいっせいに動いて、「国全体で 30兆円の消費を増やす」ということは、不可能ではない。「消費を増やせば利益になる」と全員が確信すればよい。そういうふうに人々がいっせいに心を変えることは、たやすいことではないとしても、決して不可能ではないのだ。人々がいっせいに虚偽を信じるということは不可能かもしれないが、人々がいっせいに真実を信じるということは十分に可能なのだ。
そこで、この二つの閾値を、用語で区別することにしよう。次のように。
この両者の関係については、後述する。
既存の理論については、すでに示した通りだ。これで、道具はすべて手に入った。推理小説でいえば、「必要な情報はすべて開示されました」と名探偵が宣言した段階である。
そこで、以後、本格的に考察を始めることにしよう。
閾値(特に状態閾値)の本質は何か? それを考えてみよう。
閾値を超えると、ある状態から別の状態へと、変化する。それはつまり、「不連続性がある」ということだ。
これは大切なことだ。なぜなら、「あらゆる状況は連続的に変化する」という「連続性への信仰」が、人々の心にあるからだ。
その最たる例が、「市場原理」である。「常に均衡点に収束するはずだ」という「ワルラス的均衡」ないし「ワルラス的調整過程」ということは、「連続性」というものを仮定した上で、成立する。そして、その仮定が成立するならば、その主張も正しい。つまり、「連続性」という仮定が成立すれば、古典派経済学は正しい。
しかるに現実には、その仮定が成立しない。「下限直線」や「下限均衡点」があるせいで、「連続性」は成立しないのだ。それゆえ、古典派経済学は正しくない。
そして、ここでは、「連続性」が成立しなくなる境界が、「下限直線」や「下限均衡点」である。これが「閾値」となって、状態を不連続にしている。
ここに、話の根幹がある。
閾値(特に状態閾値)によって、状態が二つに分断される。つまり、均衡の状態と不均衡の状態とが、閾値によって分断される。その境界線に、不連続性が現れる。
ここで、注意しよう。このように「均衡」と「不均衡」に分断されることは、必ずあるとは限らない。場合によっては、「均衡だけ」になることもあるし、「不均衡だけ」になることもある。
一般的にいえば、古典力学の世界は「均衡だけ」だし、カオス的な世界は「不均衡だけ」である。たいていはそうだ。
ただし、「秩序」と「不秩序」が併存することもある。そして、その両者が「閾値」という境界線で接する。──これが「閾値」の本質だ。
つまり、「閾値」とは、「均衡」と「不均衡」との境界線となるものだ。そして、その境界線の前後で、いちじるしい差が現れる。片側を見れば秩序だが、もう片側を見れば不秩序だ、というふうになる。この境界線のある領域こそが、最も問題となるのだ。
( ※ この意味で、「カオス」理論がなぜ役立たないかも、わかる。「カオス」理論は、「不均衡」について説明することはできるが、「均衡」と「不均衡」との境界線について説明するには、あまり有効ではないのだ。──こういうふうに、「カオス理論」の位置づけがなされる。)
ここで、均衡と不均衡について、その本質を考えてみよう。とはいえ、いきなり理論を出してもわかりにくいから、具体的な例を挙げてみよう。次のような例がある。
これらはいずれも、「均衡/不均衡」の例となる。
すなわち、ある閾値までは、安定的な状態が続く。何かを加えると、加えた分は吸収されて、均衡した状態は変化しない。しかし、閾値を超えると、加えた分は吸収されなくなり、均衡状態が崩れる。
では、これらに共通する本質は、何だろうか?
上の例を見て、その本質的な意味を考えよう。本質的な意味は、「許容量オーバー」だ。
つまり、閾値がある。その閾値が許容量となる。この許容量までは、加わった分を受け入れることができる。しかし、許容量を超えると、もはや加わった分を受け入れられな君らう。それが本質だ。
とはいえ、こう述べても、たいしたっことはない。単に「閾値」を「許容量」と言い換えただけのことだ。わかりやすく理解されるが、それだけのことだ。
しかし、こういうふうに理解すれば、数学的な表現が可能となる。
先に、「線形性」という概念を紹介した。この概念を使えば、次のようにまとめることができる。
先の例に当てはめれば、こうだ。(閾値に達するまでの状態のみ。)
いずれも、ある閾値までは、線形性が続く。すなわち、
f(x) = ax (ただす a は定数。)
という式が成立する。しかるに、閾値を超えると、状況が一変する。 f(x) は、次のいずれかになる。
では、それは、何を意味するのか?
不均衡の意味を考えよう。そのために、食塩と水の例を取ろう。
閾値(溶解度)までは、食塩は水に溶ける。食塩をさらに加えても、特に変化はない。しかし、閾値を超えると、変化が起こる。加えた食塩は、もはや溶けない。溶けない分は、沈殿する。
ここで、加えた量 x と、溶ける量 f(x) の間に、すぐ上で述べたような関係が成立する。
このことを、数式的に表現すると、次のようになる。
さて。 δ という値を、次のように定義しよう。(これは、差に当たる値。)
δ = ax − f(x)
すると、次のようになる。
つまり、 x が閾値以下のときには、 δ がゼロである。しかし、 x が閾値を超過したときには、 δ がプラスの値となる。この δ は、沈殿した量である。
簡単に言えば、こうだ。
閾値に達するまでは、 f(x) と ax とは「等式」で結ばれる。差は存在しない。しかし、閾値を超えると、 f(x) と ax とは「不等式」で結ばれる。差が存在する。そして、その差が、何らかの形となって現れる。食塩と水の場合で言えば、それは「沈殿」という形を取る。
経済学に移って、考えよう。
経済学における不均衡とは、何だろうか? 「小泉の波立ち」でいろいろと述べたことを理解すれば、次のようにわかる。
「経済学における不均衡とは、需給ギャップ(特に需要不足)のことである」
これは、「不均衡の本質は許容量オーバーだ」ということと、どう関係するだろうか? その答えは、こうだ。
「経済学における許容量とは、需要の上限のことである」
これが肝心だ。これこそ経済学における不均衡の本質だ。
詳しく言おう。古典派的な需給曲線( 乂 型のグラフのモデル)によれば、需要に上限はない。価格を下げれば、右下がりの曲線をたどって、需要はいくらでも増えるはずだ。しかし、トリオモデルによれば、そうではない。需要には、上限がある。(下図参照。)
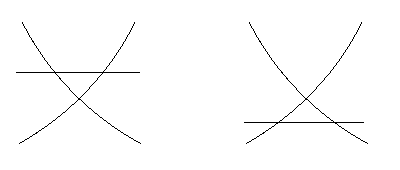 |
左側の図では、均衡点が下限直線よりも下にある。需要は、右下がりの需要曲線をたどって、どんどん右下に移ろうとするが、下限直線にぶつかったところで、阻止される。阻止された点(需要曲線と下限直線の交点)が、需要の上限を決める。
こうして決まった需要の上限が、「許容量」だ。この許容量を上回った生産をすると、上回った分は、市場では吸収されない。その分は、在庫となる。ちょうど、加えられた食塩が溶けずに沈殿するように。
同様のことは、金融市場についても言える。この場合、縦軸は、「価格」ではなくて「金利」となる。下限直線は、「金利ゼロ」を意味する。資金の需要は、需要曲線をたどって、どんどん右下に移ろうとするが、下限直線にぶつかったところで、阻止される。阻止された点が、資金の需要の上限を決める。これが「許容量」となる。この許容量を上回った資金を供給すると、上回った分は、金融市場では吸収されない。その分は滞留する。
本章で述べたことをまとめてみよう。
ともあれ、物事の基本は理解されたわけだ。つまり、「不均衡」という一番の基本は、理解された。そこで、このあといよいよ、「秩序理論」の本体部分に踏み込もう。
「小泉の波立ち」 表紙ページへ戻る |