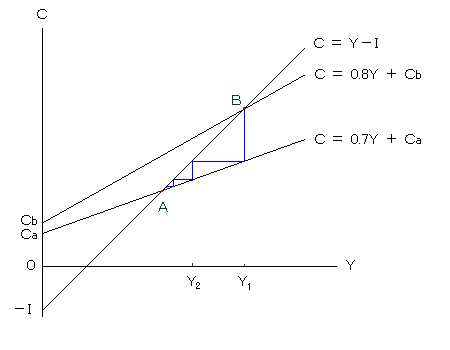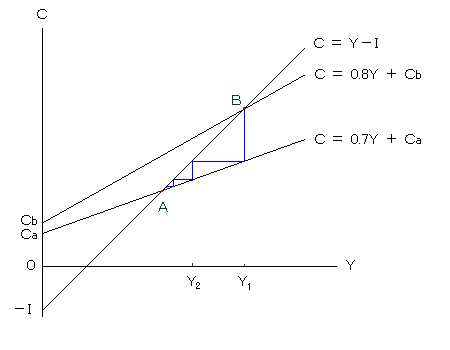[ 2002.08.24 〜 2002.09.02 ]
《 ※ これ以前の分は、
2001 年
8月20日 〜 9月21日
9月22日 〜 10月11日
10月12日 〜 11月03日
11月04日 〜 11月27日
11月28日 〜 12月10日
12月11日 〜 12月27日
12月28日 〜 1月08日
2002 年
1月09日 〜 1月22日
1月23日 〜 2月03日
2月04日 〜 2月21日
2月22日 〜 3月05日
3月06日 〜 3月16日
3月17日 〜 3月31日
4月01日 〜 4月16日
4月17日 〜 4月28日
4月29日 〜 5月10日
5月11日 〜 5月21日
5月22日 〜 6月04日
6月05日 〜 6月19日
6月20日 〜 6月30日
7月01日 〜 7月10日
7月11日 〜 7月19日
7月20日 〜 8月01日
8月02日 〜 8月12日
8月13日 〜 8月23日
8月24日 〜 9月02日
のページで 》
● ニュースと感想 (8月24日)
8月17日 では「修正ケインズモデル」について説明した。その最後で示した (i) ,(ii) のうち、 (ii) について示そう。 [ (i) については、前日までに示してきた。今日は、いったん 8月17日 に帰って、そこから再出発するわけだ。]
(ii) を再掲すれば、次のとおり。
修正ケインズモデルでは、時間的に無限循環(スパイラル)が発生するが、その無限循環のはてに、収束する。つまり、発散することはなく、ゼロになることもなく、一定の値に留まる。── その収束する先が、「収束点」である。
このことについて、次の 《 I 》 と 《 II 》 のことを、追記的に説明しておく。
《 I 》 スパイラルが収束すること
このスパイラルは無限循環をなすが、それは一定の点に収束する。このことに留意しよう。
「スパイラルが無限に進行する」という話を聞くと、一見、程度も無限にひどくなりそうな印象がある。たとえば、
「デフレスパイラルが生じるのか。だとすると、経済は無限に小さくなるのだな。(最後にはゼロになるのだな。)」
というふうに。しかし、そんなことはないのだ。経済は無限に小さくなっていくことはない。スパイラルは、収束する。そして、収束する先が、「収束点」である。── そのことを、「修正ケインズモデル」は教えてくれる。
さらに、もっと別のこともわかる。「マクロ経済は不安定構造だ」ということの意味だ。
マクロ経済は不安定構造を取る。いったん状況が悪化すれば、その悪化の状況がさらにスパイラル的にひどくなる。……ここまでは、すでにわかっていた。しかし、そのことについて、もっとよくわかったことになる。
状況が悪化すると、その悪化の度合いはさらに増すが、しかし、無限に増すわけではない。奈落の底までどこまでも落ちるわけではない。悪化の度合いは、頭打ちである。(底打ち、というべきか。)
だから、「不安定構造」というのは、図形的には、「∩」型というよりは、富士山のような裾広がりの形と言っていいだろう。(端のあたりが水平になって、ある一定量よりはなかなか下がらないわけだ。)── そういうことがわかったわけだ。
(となると、先に示した「不安定構造」の図は、「∩」型から、富士山のような裾広がりの形へ、書き直した方がいいかもしれない。)
《 II 》 景気の回復過程
先に示したのは、景気の悪化する過程だった。そのときは、交点 B から、交点 A へと移行していった。
では、景気の回復する過程では、どうか? 交点 A から、交点 B へと移行していくときは、どうなるのか? 青線を逆にたどるのだろうか?
( ※ 状況としては、限界消費性向が 0.7 の直線から、限界消費性向が 0.8 の直線へ変わる。)
正解を言おう。そうではない。青線を逆にたどるのではない。別の経路をたどる。それは、次のような経路だ。
- 交点 A から、「 C = 0.8Y + Cb 」の直線まで、上方に移動する。
- その交点から、「 C = Y−I 」の直線まで、右方に移動する。
- 1 と同様に、その交点から上方に移動する。以下、同様に繰り返し。
結局、対比的に示せば、次のようになる。
- 景気が縮小するとき……
交点 B から、 ∨ 状に囲まれた領域を、階段状に進む。そして、左下にある交点 A へ収束する。
- 景気が拡大するとき……
交点 A から、 ∧ 状に囲まれた領域を、階段状に進む。そして、右上にある交点 B へ収束する。
後者の場合にも、前者の場合と同じように、スパイラルは収束するわけだ。
[ 付記 ]
両者のスパイラルは、収束の仕方は同じだが、方向が異なる。(グラフでは逆方向になる。)
・ 景気悪化の過程では、階段が下方と左方に進む。
・ 景気回復の過程では、階段が上方と右方に進む。
この違いは、どうして生じるか? ちょっと考えれば、すぐにわかる。現在の位置と、消費性向の直線との、位置関係による。「現在位置 → 消費性向の直線」と進むわけだが、その相対的な位置関係が異なる。
( ※ つまり、景気悪化の過程では、交点 A から、低い消費性向の直線へ。景気回復の過程では、交点 B から、高い消費性向の直線へ。── 換言すれば、消費性向が現状より上がれば景気は良くなり、消費性向が現状より下がれば景気は悪くなる。)
[ 参考 ]
さて。勘のいい人ならば、すぐにわかるだろうが、「景気回復のスパイラル」という過程は、ケインズの「乗数理論」と本質的には同じである。そのことを、次項で示そう。
● ニュースと感想 (8月24日b)
前項の続き。
前項の説明に続いて、「乗数理論」(乗数効果)について示そう。
「乗数理論」は、経済学の教科書に記してあるとおりだ。つまり、次のことだ。
「投資が一定量増えると、その分、生産が増えて、所得も増える。しかも、所得の増えたのに応じて、さらに二次的に(消費性向の分だけ)生産がまた増える。その二次的に生産が増えて、所得が増えたのに応じて、さらに三次的に生産がまた増える。……こういう過程が無限に続いて、級数的に生産が増えていく。」
これは実は、前項で述べたことと、本質的にはまったく同じだ。「級数的に増えていく」というのが、「階段状に増大して、右上の収束点に収束する」ということだ。
細かな点を言えば、違いもある。それは、出発点と最終点だ。新たな出発点と最終点は、次のようにして決まる。
- 乗数理論では、最初のきっかけは、「消費性向の向上」ではなくて、「投資の拡大」である。このとき、投資が I から Ie に拡大したとする。
- すると、「 C = Y−I 」の直線は、少し下方にシフトして、「 C = Y−Ie 」というのが、新たな直線となる。
- このとき、交点 A を下方にシフトさせた位置(新たな直線上の位置)を A’ と記すことにする。
- 新たな直線と、元の「 C = 0.7Y + Ca 」という直線との交点を、E と書く。交点 E は、元の「 C = 0.7Y + Ca 」という直線の上で、A よりも右上にある。
- 出発点は A’ である。最終点は E である。A’ から出発して、E にたどりつく。その際、∧ 状の領域をたどって、階段状に進む。そうして 点 E に収束する。だから、点 E は、収束点である。
※ 一応、注釈しておく。
・ ゆるい傾きの線は、消費性向に依存する。所得から決まる消費の額。
・ 45度の線は、消費から決まる「生産」(所得)の額。
・ 一方が増加すると他方も増加する、というスパイラル関係を図は示している。
結局、前項における「景気の回復過程」と、本項における「乗数効果」とは、本質的には同じような経路をたどることがわかる。(出発点と最終点は異なるが、本質的には同じような経路。)
以上のことから、ケインズの「乗数理論」の位置づけもできる。
・ ケインズの論法では、代数的に級数で示している。
・ 修正ケインズモデル(本項)では、グラフの階段状の経路で示している。
・ 両者は、そういう違いがあるが、示していることは同じことである。
つまり両者は、同じことを、代数で示しているか、グラフで示しているか、という程度の違いでしかないわけだ。
では、どちらも同じことを示しているのだとしたら、本項で示したことは、意味がないのだろうか?
そうではない。同じことを、別の数学的表現で示すということは、「見方を変える」という意味がある。そして、「見方を変える」ことによって、それまでは見えなかった新たな事実が、見えるようになるのだ。
[ 付記 ]
新たに見えるようになったこととして、どんなことがあるか? たとえば、次のことがある。
ケインズは、これと同等のモデルを使って、次のように主張した。
・ 需給ギャップが生じたときは、生産の縮小した状態に落ち着く。
(修正ケインズモデルで言えば、「収束点 A に収束する」。)
・ 乗数効果というものがある。
(修正ケインズモデルで言えば、「収束点 E に収束する」。)
この二つを主張した。そして、この二つは相互関連がなく、別個のことだと見なされた。
しかし、修正ケインズモデルを使ってグラフで表示すれば、この二つは本質的にはそっくりなことなのである。上記の通り、「収束点が A であるか E であるか」という程度の違いでしかない。
両者の違いは、きっかけが「需要減少か投資増加か」ということに起因する。それによって、出発点と到達点の違いはある。しかし、「生産」と「所得」の「相互影響」によって、「スパイラルの収束」という意味をもつ、というところは、まったく同じである。つまり、本質的には、両者は同じようなものなのである。
そういうことが、グラフを見ることで、明らかとなる。
( ※ 明日以降は、修正ケインズモデルを用いて、さらにいろいろと考察していく。)
( ※ なお、舞台裏を明かしておこう。私自身、修正ケインズモデルというものを使って考察をすることで、それまでは気づかなかったことに、いろいろと気づくようになった。その考察や発見の結果を、ここのところ記述しているわけだ。別に、結論が先にあって、そのために我田引水で、このモデルを利用したわけではない。このモデルを利用すると、それまでは見えなかったことが、新たに見えるようになったのである。── 新たなモデルが新たな真実を告げてくれたわけだ。)
● ニュースと感想 (8月25日)
「経済波及効果」について。
前項では、二つの階段状のスパイラルについて「そっくりだ」と述べたが、もちろん、異なる点もある。その違いのうち、最も大きな違いは、きっかけだ。
(1) 「消費性向の向上」の場合
特にきっかけは、必要ない。消費性向の向上にともなって、自然に景気は回復していく。
(2) 「公共投資」の場合
この「公共投資」がきっかけとなる。そして、これをきっかけとして、従来の消費性向のままで、スパイラル的に生産が拡大していく。(乗数効果)
このとき、最初の分(「きっかけ」となる公共投資の分)と、そこから派生的に生じる分とは、区別される。前者は、「自立需要」と呼ばれ、後者は、「派生需要」と呼ばれる。
( ※ グラフで言うと、前者は、階段状の線の、1番目の分である。後者は、階段状の線の、2番目以降の分の総和である。 「 0.71+0.72+0.73+ …… 」)
( ※ 「経済波及効果」という言葉も使われる。これは、後者を示す。── ただし、両者を示すこともあるようだ。やや曖昧な言葉。とはいえ、本項では、後者のみを示すことにする。)
さて。
上の (2) のことは、まあ、当たり前ではある。「公共事業を増やすと、その金額を上回る効果があり、その上回る分を『経済波及効果』と呼ぶ」というわけだ。
ただし、ここでは、注目すべき点がある。それは、次のことだ。
「公共事業の分は、それを享受する産業が指定されるが、経済波及効果の分は、それを享受する産業が指定されない」
つまり、
「公共事業の恩恵は、特定産業に偏るが、経済波及効果の恩恵は、全産業に及ぶ。(偏りなしに)」
たとえば、こうだ。政府が1兆円の公共事業を増やすと、それによって土建産業が1兆円の売上げ増加となる。1兆円はまるまる土建産業の売上げとなる。ただし、そこから派生する効果は、土建産業に限らず、他の産業に広く及ぶ。たとえば、土地購入費とか、労働者の給料とか、ガソリン代とか、……さまざまな領域に支出される。そうなると、売上げを増やすのは、「土建産業だけ」ということにはならない。(たとえば、土地購入費に使った金は、地主があれこれと他分野で散財したり、貯蓄を通じて銀行から全産業の投資に回ったりする。「金は天下の回りもの」だ。)(実際には、細かいことを言えば、少しは偏りはあるだろうが、細かいことは無視する。)
では、これがなぜ大事か? それは、次項の問題と関連する。解答は、次々項で。
● ニュースと感想 (8月25日b)
ここまでに述べた「景気回復」の過程は、「消費性向の上昇」によるものだった。
一方、ケインズのモデルでは、「公共投資」による「景気回復」をめざす。また、「減税」による「景気回復」もある。
これらについて、修正ケインズモデルで説明しよう。まず、前項で示したグラフを、ふたたび掲げる。
ここで、経路をたどると、時間的に次のように移動する。
B ─┬→ A ─┬→ A’─┬→ E
景気悪化 公共投資 乗数効果
上記の経路について、一応、解説しておこう。(グラフを見ればすぐにわかるし、言わずもがなだが。)
- B から A へ移動するのは、スパイラル的な景気悪化の過程である。
- A から A’へ移動するのは、公共投資による下シフトである。
- A’ から E へ移動するのは、スパイラル的な乗数効果の過程である。
ここで肝心なことは何か? それは、「出発点 B と、到達点 E とは、異なる」ということだ。つまり、「景気が回復しても、元の状態には戻らず、別の状態に移る」ということだ。
これは非常に重要なことだ。
ケインズのモデルでは、そうはならない。出発点と到達点は、同じである。つまり、景気が回復すれば、元の状態に戻る。簡単に言えば、こうだ。
「経済が縮小した状態では、総需要が減っている。だから、総需要が減った分、政府が需要を追加してやれば、元の総需要に戻る。ゆえに、減った総需要が、元の総需要まで回復するから、状態も元の状態に戻る」
というわけだ。しかるに、修正ケインズモデルでは、そうはならない。元の状態には戻らず、別の状態に移るのだ。
では、修正ケインズモデルでは、なぜ、そういう違いが出るか? (「景気悪化後に、公共投資によって需要拡大をした場合。)
これには、二つの答え方がある。
(1) 「なぜ修正ケインズモデルは、ケインズのモデルとは、異なる結果を出すか?」
この質問に対する答えは、「修正ケインズモデルは、ケインズのモデルよりも、数学的に厳密だから」と言える。ケインズのモデルでは、消費性向の低下を見ないとか、投資の増加をあとで上方シフトする形にする(定数を減じる形にしない)とかで、数学的にはいい加減な表現方法をしていた。そういういい加減な表現方法を取らず、是正した表現方法を取るのだから、ケインズのモデルとは異なる結果を出して当然なわけだ。
(2) 「なぜ修正ケインズモデルでは、出発点と到達点が異なるのか?」
この質問に対する答えは、こうだ。「位置が異なるのは、状況が異なるからだ」。つまり、修正ケインズモデルでは、「出発点と、到達点とで、状況が異なるから、位置も異なるのだ」と。
出発点と到達点を比べると、後者では、「消費の縮小」&「投資の拡大」というふうに状況が変わっている。こういうふうに状況が異なるから、グラフ上の位置も異なるわけだ。
このことについて、詳しくは、次項で考察する。
● ニュースと感想 (8月26日)
前項の続き。
前項に引き続いて、次の問題を提出する。
「景気悪化後に、公共投資によって需要拡大をした場合、出発点と到達点とが異なる(つまり B と E )。そういうふうに異なるのは、両者の状況が異なるからだ。── では、両者の状況は、いったい、どういうふうに異なるのか? また、両者の状況が異なるというのは、良いことなのか悪いことなのか?」
これは、前項の説明をさらに発展させた問題だ。このことについて、考察しよう。
まず、前項で述べたことからもわかるとおり、これは修正ケインズモデルに固有の問題である。修正ケインズモデルにおける出発点と到達点とは異なる。だから、その違いが問題となる。
一方、ケインズのモデルでは、出発点と到達点とは同じである。つまり、「総需要が縮小したあと、公共投資をすれば、(総需要が回復して)元の状態に戻る」となる。出発点と到達点とに、違いはない。
では、修正ケインズモデルでは、違いはどうして生まれるのか? 違いはどういうものなのか? ── これが、そもそもの問題となる。
そして、この問題に対する答えは、この修正ケインズモデルだけを見ていても、わからない。モデルでは、グラフにおける点の位置としてしか表示されない。そこで、実態を知るには、モデルを離れて、現実に即して考えるべきだ。
では、現実に即せば、どういう違いがあるのか? ここで、いきなり答えを言えば、次のようになる。
「修正ケインズモデルにおける出発点と到達点とでは、次の違いが生じる。
・ 消費が減ったまま投資が増えるので、消費と投資の比率が変更される。
・ 消費と投資とで、支出の分野が異なれば、成長する分野も異なる。
という2点だ。」
こうしたことは、言われてみれば、当たり前と思えるだろう。ただ、当たり前ではあっても、当たり前でないほど重要な意味をもつ。以下で、詳しく説明しよう。
(1) 比率の変更
まず、状況を見よう。
初めは、消費性向の低下が発生して、総需要が縮小した。そのあとで、総需要の縮小を補うため、投資(公共事業)を追加した。……となると、総需要は元の状態に戻ったが、総需要の内実は変化したことになる。量的には同じでも、質的には変化したことになる。
消費 C は減って、投資 I が増えた。民需は減り、官需(公共事業)が増えた。つまり、民需と官需の比率が変化した。(グラフで言えば、こうだ。交点 B よりも、交点 E は下に位置する。それはつまり、縦軸 C の値が異なることを意味する。交点 B よりも交点 E は、消費 C が少ない。)
ケインズ派は、これを見て、こう主張する。「総需要( C+I )さえ元の値に戻れば、それでいいのだ。マクロ的な総需要だけが大事なのだ」(つまり民需と官需の比率は無視する)と。
なるほど、それは一つの見識である。たとえば、目的が「失業の解決」だけならば、これで「失業の解決」は済むだろう。
しかし、われわれのめざすものは、それだけではなかったはずだ。「失業の解決」だけではなく、「不況の解決」である。特に、「倒産の解決」である。それは、ケインズ流の「総需要の拡大」で、可能なのか?
換言すれば、こうだ。「総需要が元に戻った」という状況で、同時に「民需の縮小と官需の拡大」が発生したとき、「不況の解決」は可能なのか?
(2) 景気回復後の状況
上記の問題に対する答えを言おう。次のようになる。
「不況の解決にあたっては、総需要をもとの状況に戻すだけではなダメで、民需と官需との比率も元に戻さなくてはならない。」
これを換言すれば、次のようになる。
「不況の解決にあたっては、産業間の比率を勝手に変えてはならない。」
さらに換言すれば、次のようになる。
「不況の解決にあたっては、失業者だけを見るべきではなく、企業をも見るべきだ。」
このことは、わかりやすく言えば、次のようになる。
- ある分野で失業が発生し、同時に、別の分野で新規雇用が発生すれば、失業の問題は解決する。(ケインズの主張通り。)
- ある分野で倒産が発生し、別の分野で売上げ増加があっても、それが不自然な形で起こるのであれば、経済はいびつな形になる。
具体的に示そう。民需が減って、官需が増える。これにともなって、民生産業で倒産が続々と発生して、土建産業で売上げ増加が発生する。これは、良いことなのか悪いことなのか?
ケインズ派ならば、「良いことだ」と答えるだろう。「それで総需要は回復した。失業問題は解決した。万歳」と。
しかし、実際には、このとき、元の状況に戻ったわけではない。失業者の問題だけは解決するが、別の問題が発生する。次のように。
(i) 企業にとって
個々の企業にとっては、問題は解決しない。土建産業だけは売上げが伸びるが、他の産業は売上げが伸びない。パソコンとか電器製品とかサービスとか、そういう産業では、売上げが縮小したままだ。
このとき、国全体の総生産高は同じだとしても、産業間の比率が変わってしまっている。そういうふうに、元とは違う状況になってしまうのだ。
しかも、これは、自然な形で起こるわけではない。「IT需要の増加にともなって、IT産業が伸びる」というのならば、自然な形である。しかし、「政府が一時的に公共事業を拡大する」というのは、いびつな形である。つまり、国全体の産業構造が、いびつな形に変わってしまうわけだ。
いびつな形、と呼ぶのは、ただの悪口ではない。理由がある。なぜなら、放置すれば、この一時的な状況は、自然な形に戻るからだ。つまり、不況が解決すれば、もはや公共事業を増やしておく必要はないのだから、一時的に増やした公共投資は、元の水準まで縮小する。すると、どうなるか? ケインズ派ならば、「総需要が同じならば、経済も同じさ。何も変わらない」と主張するだろう。しかし、実際には異なる。公共事業が急激に縮小すれば、産業間の比率も変わる。(元に戻る。) 土建産業の売上げは急激に縮小し、他の産業が急激に伸びる。
このことは、次の二つのデメリットを意味する。
・ 一般の産業にとっては、景気回復が数年間、遅れる。
・ 土建産業にとっては、急拡大と急縮小という、二重の無駄が起こる。
この二つのデメリットは、別の意味でもデメリットとなる。それを次に示す。
(ii) 労働者にとって
上記の二つのデメリットは、企業にとってデメリットになるだけでなく、労働者にとってもデメリットとなる。
・ 一般の産業では、需要縮小にともなって、失業が発生する。(数年間)
・ 土建産業では、需要拡大にともなって、雇用が発生する。(数年間)
しかしその分は、数年後には、余剰労働力となって、解雇される。
つまり、統計的に失業者の数だけを見て、「こちらで失業が発生しても、あちらで新規雇用が発生すれば、数の帳尻は合う」というふうに考えても、ダメなのだ。人間を数字として扱うだけではダメなのだ。人間というのは、「失業統計の単なる数字の1だけにすぎない」とケインズ派は考える。しかし、そうではない。数だけ考えて、帳尻が合っていても、ダメなのだ。そんなことでは、多大な無駄が発生する。
具体的に示そう。優秀な専門家がいたとする。(土建産業以外であれば、どんな分野でもいい。読者であるあなた自身だと思えばいい。) この専門家は、優秀な専門技術を持っていたので、高給を得ていた。しかるに、不況にともなって、リストラで、失業した。その後、政府の公共事業にともなって、土建産業で新規雇用が発生したので、彼は肉体労働者として雇用された。ただし、頭は良くても肉体は貧弱なので、ごく薄給である。その後、景気回復にともなって、公共事業が縮小した。貧弱な肉体しか持たない彼は、失業した。そこで、元の専門家として復職しようとしたのだが、数年間のブランクで、彼の専門知識はすっかり錆びついていたし、時代の変化も早いので、彼は復職できなかった。仕方なく、元の会社の夜間警備員として、薄給で雇用されるだけだった。
こういうふうに、労働者にとっては、多大なデメリットとなる。しかし、これは、労働者が虐待されているわけではない。企業が労働者を虐待しているわけではない。そもそも本質的に、国全体で経済効率が低下したのである。
優秀な専門家を、ただの肉体労働者として雇用する。こんなことをすれば、労働資源が無駄になる。そういう無駄なことをやるから、国全体では途方もない無駄が発生する。結局、労働者が損をするだけではない。企業もまた損をするのだ。実際、日本のIT産業は、景気悪化にともなって、技術者の数を大幅に減らしたので、国際競争力を大幅に減じている。だから、労働者も損をしたし、企業も損をしたのである。
国全体で馬鹿げた無駄なことを行なえば、労働者も企業もともに損をするしかない。
( ※ この見本は、毛沢東時代の中国が見事に示した。「知識人はブルジョアだ」というスローガンのもとで、技術者や専門家を冷遇し、工場労働者ばかりを優遇した。技術者や専門家は、もてる知識を捨てて、工員として働くこととなった。そのあげく、国家経済は、見事に破壊された。……「労働力の質を見ずに、労働力の数だけを見る」というケインズ派は、毛沢東時代の中国と同じであるわけだ。皮肉を言えば、毛沢東はたぶん、コミュニストではなく、ケインジアンであったのだろう。)
(iii) 消費者にとって
同様の無駄は、消費者にとっても発生する。
総需要が一定のもとで、土建産業が拡大して、民生産業が縮小する。となると、国民の得るものも異なるものとなる。土建産業が拡大するので、道路やダムなどの社会資本が増える。民生産業が縮小するので、自動車やパソコンやサービスが縮小する。かくて、国民の得るものも変わる。国民は、道路やダムを手に入れるが、その分、自動車やパソコンやサービスを失うのである。
単純化していえば、「国家の財産が増え、個人の財産が減る」わけだ。実質的な増税と同じである。
ここで、注意してほしい。公共投資が増えると、その分、総需要は増える。しかし、国民の実質的な所得はちっとも増えないのだ。
具体的に示そう。国民が、500万円の所得を得て、500万円の支出をしていたとする。(貯蓄の分は、企業が投資に回して支出するので、これも支出と見なす。400万円の消費と 100万円の貯蓄なら、貯蓄の分は企業の投資。) さて、今、支出が縮小して、500万円から 450万円に減ったとする。それにともなって、所得も 450万円に減ってしまった。ここで、政府が 50万円の支出をする。そうすると、生産は 500万円に回復する。では、国民の所得は、500万円に回復するか? 名目的には、500万円に回復する。しかし、そのうち 50万円分は、政府に徴収される。国民は、残りの 450万円が手取りとなる。国民が得るものは何も変わらない。国の得るものが増えるだけだ。
結局、国民としては、 50万円分、余計に働くようになった。その分、失業は減った。しかし、働く量は増えても、得る金は変わらないのである。つまり、タダで働いているわけだ。無賃労働をしているわけだ。奴隷となったわけだ。それでも、失業しなくなったのだから、彼は失業者ではなくなる。彼は、無賃労働者という奴隷であって、失業者ではない。この意味で、「失業を解決する」というケインズ派の目的は、見事に達成されたわけだ。
( ※ 実際には、特定の人が失業者から奴隷に転じるわけではなくて、国民全体が少しずつそうなる。失業していない人は、労働時間が増えるが、たとえ所得が増えても、増税で金を奪われるので、労働増加の分、無賃労働をするのと同じこととなる。)
● ニュースと感想 (8月27日)
前項 で述べたことについて、いくつか補足的に述べておく。
[ 付記 1 ]
前項の説明では、話を簡単にするため(というよりは核心を示すため)、「経済波及効果」の分は考慮していない。
現実には、「経済波及効果」( → 8月25日 )があるので、その分を考慮するべきである。つまり、
・ 最初の公共事業の分については、前項の説明がそのまま当てはまる。
・ 派生する分については、前項の説明が当てはまらない。
(派生する分は、土建産業だけでなく、全産業に及ぶので。)
となる。こういうふうに、若干の考慮を追加して、補正するわけだ。(「主」だけでなく「副」も見るべし、ということ。当たり前。)
なお、「経済波及効果」というのは、それがすべて波及し終えるまでに、時間がかかる。( → 8月18日 の 《 I 》 )
だから、上記の「派生する分」というのは、あるにはあるにしても、1年目のころは、あまり考慮しなくていいことになる。「1兆円の公共事業を追加すれば、国全体の総需要が2兆円ぐらい増えるぞ」とケインズ派は主張するが、まともに信じない方がいい。1年目には、1兆円は土建産業だけに回る。残りの1兆円が他の産業にまで行き渡るには、まだまだ長い時間が必要なのである。
実際、政府や民間研究所のよくやる「経済波及効果の試算」というやつでも、「1年目にこれこれ、2年目にこれこれ、……」というふうに、数年分を考慮する。そういうふうに、数年もの時間がかかることを前提とする。(ただし、なぜか、産業間の違いには目をつけないようだが。「土建産業ばかりが先にいい思いをする」ということは、禁句であるようだ。)
[ 付記 2 ]
「公共支出は土建産業に集中する」というふうに前項では示した。
実際には、そうする必要はない。他の形の公共支出も考えられる。一番有名なのは、軍事支出だ。これだと、土建産業に限らず、非常に多くの産業で支出がなされるので、あらゆる産業が売上げを伸ばす。ゆえに、景気回復効果は高い。
具体的な例は、高橋財政のころや、朝鮮特需のころに見られる。いずれも、軍事支出にともなって、デフレから好況へと、見事に景気を反転させた。どうせケインズ流に「有効需要」と唱えるのであれば、公共事業という「土建産業だけで」よりは、軍事支出という「全産業で」の方が、ずっと有効であるわけだ。
ただし、国民にとっての損得は、どちらも同じである。どちらにせよ、増えるのは国の富であり、個人の富ではない。ダムや道路のかわりに、戦車やミサイルが増えるだけだ。自分の自動車やパソコンが増えるわけではない。結局、どちらにせよ、「働けど働けどなおわが暮らし楽にならざり」である。しょせんは、無賃労働の奴隷となることには、変わりはない。
奴隷になりたくなければ、働いて稼いだ金を、国が使うのではなく、自分自身で使うしかない。つまり、「減税」だ。この件は、何度も述べたとおり。( → 政府か国民か )
[ 付記 3 ]
「穴を掘って埋める」というのでもいい、とケインズは主張した。
実は、このことは、本質を突いている。実際、「穴を掘って埋める」にしても、「無駄な道路を作って残す」にしても、「無駄な軍艦を作って太平洋に沈没させる」でも、国民にとっては大差ないのだ。国民にとっては、いずれも、無駄働きをするだけだからだ。せいぜい、「どの省庁の奴隷になるか」というぐらいの違いにしかならない。
だから、ケインズの主張は、正しくは、逆に理解するべきなのである。
俗説:
「たとえ穴を掘って埋めても、公共事業と同様に、すばらしい効果がある」
正解:
「たとえ公共事業をしても、穴を掘って埋めるのと同様に、無駄になるだけだ」
( ※ ジョークのようだが、真面目である。ジョークを言っているのは、私ではなく、ケインズの方だ。「穴を掘って埋めてもいい」なんて、漫才そのものだ。これが本当ならば、日本中の民間企業は、何も生産しないで、「穴を掘って埋めました」という書類だけを提出して、巨額の金をもらえばよい。日本人は、何もしないで、形式的な書類を出すだけで、莫大な金を得るわけだ。そして外国から自動車やパソコンをいくらでも買えるわけだ。……馬鹿げた話だ。これを漫才だと理解できないような経済学者は、自分の頭がそもそも漫才になっているのだ。経済学者を辞して、漫才師になった方がいい。ただし、ボケ役で。)
[ 付記 4 ]
ケインズ本人は、「穴を掘って埋める」というのは、ジョークのつもりで言ったのかもしれない。どうせ公共事業をやるにしても、「道路を作る」というのと、「道路を作って壊す」というのと、どちらをやるべきかは、一目瞭然だからだ。
実際、ケインズの時代には、先進国でも社会資本整備はまだ不十分だった。だから、社会資本整備をやるべきところは、いくらでもあった。「穴を掘って埋める」というのを、文字通りにやる国が現れるとは、本気では信じてもいなかったのかもしれない。
だから、「穴を掘って埋める」という馬鹿げた事業は、ケインズの時代にはあまり現実性のない話であって、それ以前とそれ以後のみ、具体化したことになる。
それ以後の例は、もちろん、現在の日本だ。「タヌキ専用道路」だの、「本四架橋を3本」だの、「東京湾横断道路」だの。無駄の極致。
それ以前の例は、世界的に有名な例がある。エジプトのピラミッドだ。エジプトの王は、ピラミッドという無益なものを作るために、人々を奴隷化して、こき使った。
そして、それと同じことを、今の日本国民は強いられているわけだ。昔は王に強いられたことを、今は政府に強いられている。となると、人類は 4000年ほどの間、少しも進歩していないことになるのだろうか。
( ※ エジプトの王は、ケインズ理論を知っていたのかもしれない。あるいは話は逆で、ケインズは、エジプトの王の真似をしたのかもしれない。)
( ※ 本四架橋を「世界に起こるべき日本の偉業」と称える主張がある。エジプトの王と同じ発想だ。そのうち日本にも、ピラミッドがいくつかできそうだ。ただし、日本には地震があるから、ピラミッド変じて、ガレキの山となるかも。たとえそうならなくとも、もともとガラクタの山だが。)
[ 付記 5 ]
「公共事業によって、景気が回復しても、国民の富は増えず、政府の富ばかりが増える」と述べた。
こう述べると、「まさか」と思うかもしれない。「土建産業が繁栄するだけでなく、全産業が繁栄するはずだ」と思うかもしれない。しかし、実際には、前項(前日分)で述べた通りなのだ。
なるほど、先に述べたように、「経済波及効果」の分はある。その分だけなら、土建産業以外でも、繁栄する。しかし、最初の「公共事業」の分は(つまり1年目の大部分は)「土建産業だけが繁栄する」と言えるし、「国民は富を得られない」と言えるのだ。
そのことは、マクロ的に、産業の状況を見ればわかる。国全体で、土建産業が売上げを伸ばして、他の産業は売上げを伸ばさない。つまり、他の産業では、生産が増えない。生産が増えなければ、国民の手にも入らない。国民は、(土建産業で)いっぱい働くが、そうして増えるのは、国の富だけであって、国民の富ではないのだ。国民が働いて手に入れるものは、「所得」ではなくて、「無」であるのだ。つまり、いっぱい働いたことで、名目的に所得を増やしても、実質的には何も得られない。
ただし、である。このとき同時に、錯覚が発生する。それは、「物価上昇」による錯覚である。
景気が回復すると、物価が上昇する。このとき、国民は、「増税」によって富を失うだけでなく、「物価上昇」によっても富を失う。どちらにしても、富を失うという点では、同じである。しかし、その文句を言い方が異なる。増税ならば、「増税をするな!」と文句を言うが、物価上昇では「物価上昇をするな!」と文句を言う。このとき、「悪いのは物価上昇だ!」と勘違いする。
物価上昇が起こると、「国民の富が奪われる」ということが、隠蔽されるのだ。1%の増税があれば、1%の富が奪われることがはっきりとわかる。しかし、5%の物価上昇と4%の賃上げがあれば、1%の富が奪われることははっきりとはわからない。
このとき国民は、「物価上昇はけしからん」と憤慨する。しかし本当は、そうではない。物価上昇は、中立的であって、損でも得でもない。ただ、名目所得が上がっていると、自分の富が奪われていることに気づきにくいのだ。
政府は、国民が気づきにくいのに乗じて、物価上昇のとき、実質的な増税を行なう。そうやって国民の富を奪う。(いわゆる財政黒字だ。)そして、なぜ奪うかと言えば、道路やダムなどの無駄な公共投資をしたから、その費用をまかなうためだ。(その結果、人々は無駄働きすることになる。働いて得た金を増税で奪われるからだ。)
とにかく、公共事業は、国民の富を奪う。ただし、物価上昇があると、そのことを隠蔽できるわけだ。国は、さんざん国民の富を奪っておきながら、「私は奪いませんよ。奪うのは、私じゃなくて、物価上昇ですよ」と、知らん顔ができるわけだ。
( ※ そして、それにだまされる無知な人々が、国を責めずに、「物価上昇」という現象を責める。「物価上昇はけしからん! 国民の富が奪われる!」と。本来ならば、誰が富を失ったかだけでなく、誰が富を得たかを考えるべきなのだ。なのに、金を奪った相手をほったらかして、物価上昇という現象のせいにする。これはいわば、自分の財布から金を盗んだ泥棒をほったらかして、その日の気象のせいにするようなものだ。お門違い。)
( ※ 誰が富を失って誰が富を得たか? それを考えるといい。富を失ったのは、国民だ。富を得たのは、国だ。国が国民の財布から金を奪った。その金で勝手に道路やダムに散財した。ただし、財布から金を盗んだあとで、水増しした紙幣を財布に残しておく。すると、無知な国民は、いつ金を盗まれたのか、わからなくなる。あげくは、盗んだ金で自分を雇用してくれるというので、感謝する。「泥棒さん、ありがとう。あなたが雇用してくれるので、失業しないですみました」というわけだ。金が自分の財布から出たとは気づかないまま。……要するに、ケインズ経済学というのは、「泥棒に感謝しよう」という主張なのだ。誇張のように聞こえるかもしれないが、決して誇張ではない。)
[ 付記 6 ]
次の反論があるだろう。
「ケインズ派の主張が正しくないとしても、それでもとにかく、不況が続くよりはマシだ。土建産業ばかりが儲かって、他の産業があまり儲からないというのは、好ましくないかもしれない。しかし、全産業がみんな儲からない不況よりはマシだ。」
そこで、この反論に対して、説明しておこう。
なるほど、土建産業が繁盛すれば、そのことで、総需要が拡大して、不況から脱する。それはそうだ。一時的には。だから、一時的な「痛み止め」にはなる。
しかし、である。このとき、産業間で、「比率の変更」が生じたのだ。(前日に記述したとおり。) そして、この比率は、変更されたあと、いつかまた元に戻る。つまり、土建産業が縮小して、他の産業が拡大する。そのとき、二次的な問題が発生するのだ。── 土建産業での、大量の失業発生である。(これ自体、再度の不況の発生の原因となりうる。大量の失業発生は、すぐには解決されないまま、需要の縮小をもたらすからだ。)
だからこそ、経済を「いびつな形」に変えることは、好ましくないのである。
ケインズ派の主張は、「今すぐ殺されるより、数年後に殺される方がマシだ」というようなものだ。まあ、たしかに、マシかもしれない。しかし、殺される方にとっては、どちらにしても、まっぴらごめんだ。
結語。一時しのぎの方法で病状を取りつくろうよりは、根本から病気を治すべきなのだ。「片腕を一本ちょん切っても、足をもう一本つければ、それでいいだろう」なんていう、勝手な変更は好ましくないのだ。
[ 付記 7 ]
上の説明に対して、次の反論があるだろう。
「景気回復時に、大量の失業が発生するのであれば、そのまま土建産業で雇用していればいいではないか。つまり、ずっと公共事業を増やしていればいいではないか。そうすれば、失業はずっと発生しない」と。
なるほど、話を失業問題だけに限れば、こういう論理は成立する。たしかに、公共投資をずっと増やしたままにしていれば、それでそれで、不況を脱していられる。(財政赤字はどんどん拡大するだろうが。)
これは、修正ケインズモデルで言うと、「交点 E にずっと留まっている」「交点 B には移らない」ということだ。 ( → 図 )
しかし、である。そうだとすると、他の産業は、ずっと縮小したままだということになる。土建産業が繁盛して、他の産業は繁盛しない。そういう状態がそのままずっと続くことになる。それは、もちろん、好ましくない。(たとえば、東芝や日立をつぶして、くだらない土建産業ばかりが生き延びるわけだ。)
では、公共投資を減らせばいいか? いや、そうすれば、土建産業で大量の失業者が発生する。(他の産業では簡単には吸収されない。いわゆる「雇用のミスマッチ」が発生するだけだ。土建産業から新興産業への労働力移転は、そう容易にはできない。昨日まで道路を作っていた人が、明日から急にパソコンのプログラムを書くわけには行かない。)
それでもとにかく、「雇用のミスマッチ」で発生した失業を解消させようとすれば、多大な景気刺激が必要となる。その結果は、土建産業と、他の産業との、双方が繁盛するが、それはつまりは、ひどいインフレという状態だ。
結局、どうなるか? 産業間の配分を勝手に変更し、そのあとまた逆に変更する(元に戻す)と、そのたびに、無駄な失業(ミスマッチ失業)が発生する。そして、その失業を解決しようとして、景気刺激をしてインフレ率を上げても、失業はなかなか解決できないままだ。となると、残るのは、「高いインフレ率と高い失業率」である。
だから、ケインズ政策がもたらすものは、「スタグフレーション」なのである。「失業率を下げよう」という、そのことばかりにこだわって、経済体質をいびつにする。適材適所とは逆のことをするので、経済体質は劣化し、生産性は悪化する。失業者のための勤め口はできるが、慣れない仕事を強いられて、働いても働いても低所得である。そういうふうになる。そして、それはまさしく、ケインズ政策の狙いでもあるのだ。「奴隷になること」「無賃労働をすること」「無駄をすること」(穴を掘って埋めること)こそ、ケインズの狙いだったのだから。
「無駄をすること」(穴を掘って埋めること)というのは、「生産性を低下させる」ということであり、つまりは、「スタグフレーションをもたらす」ということである。だから、ケインズ政策にとって、スタグフレーションは、必然なのである。スタグフレーションは、ケインズ政策にとって、避けようとしたものではなくて、まさしく狙っていたものなのだ。
( ※ 「狙ってなんかいないぞ」とケインズ派の主張する人もいるだろう。そういう人は、自分が何をしているか、理解していないのである。あえて地獄をめざしながら、「自分は地獄をめざしてはいないぞ」と主張しているのと同じだ。自分が何を破壊しているかを理解できないのである。自分で穴を掘って、自分で落ちて、「どうしてかな?」)
( ※ ケインズ政策の根本的な欠陥は、ここにある。つまり、「生産性の低下」である。そして、それゆえ、古典派の多くの人々が「生産性の向上」を主張するのである。不況のときに、「生産性の向上」を唱えて需給ギャップを拡大しようというのは、狂気の沙汰だが、古典派がこういう狂気の沙汰を主張するのも、ケインズ派が輪をかけて狂気の沙汰であって、「生産性の悪化」を主張するからだ。……結局、今の経済学というのは、古典派とケインズ派による、「狂気の二重奏」である。物事の本質を見極めず、表面的な経済事象だけを見ていると、こういうことになる。)
( ※ 表面的な症状ばかりにこだわると、状況をかえって悪化させる。これと似た話は、医学でもある。「風邪で高熱が出たのか。では、解熱剤を」と処方する。すると、熱は下がって、症状は収まった。しかし、熱が下がったせいで、ウィルスがどんどん増殖して、風邪はますます悪化した。── 症状と本質。その違いを理解することが大切だ。不況の本質は、失業でもないし、生産性の悪化でもない。それらはただの症状だ。何が本質かは、このホームページの読者ならば、わかるだろう。そして、めざすべきことは、症状を直接的にいじること[対症療法]ではなく、本質を治療することなのだ。)
[ 付記 8 ]
ここまでは、ケインズ政策への批判をいろいろと述べてきた。しかし、こうした批判が当てはまらないような、例外的な場合がある。それは、「公共事業が無駄にならない」場合だ。
では、公共事業が無駄にならない場合とは? それは、次のような場合だ。
・ 景気対策で一時的に追加されたのではなく、長期的に計画された場合。
・ 発展途上国などで、社会資本が不十分である場合。
こういう場合には、その公共事業の必要性が十分にチェックされて、「必要だ」「やった方がよい」「かけた金以上の効果がある(投資効率が1以上である)」というふうに判断されるのだろう。だから、こういう場合にまで、「ケインズ政策はダメだ」ということにはならない。
この件、これまで何度か、述べてきたとおり。
[ 余談 ]
念のため、補足しておく。私は別に、ケインズを攻撃しているわけではない。むしろ、ケインズを非常に尊敬している。修正ケインズモデルというのは、名前のごとく、ケインズの主張を修正したものにすぎない。骨格は、ケインズに依拠している。その意味で、ケインズの才能は、大いなるものがあった。ケインズは、正解にたどりつくことはできなかったとしても、正解にたどりつくための橋頭堡を残しておいてくれた。この点、古典派なんかとは、雲泥の違いだ。
ただ、ケインズの理論では、不正確なところがあった。それは、「消費性向の低下」を無視したことである。そして、それを、私は修正したわけだ。
とにかく、ケインズの結論は不正確ではあったが、ケインズの業績は大きなものである。責任が誰かにあるとしたら、ケインズ自身ではなくて、ケインズの理論を発展させることのできなかった、以後の何十年もの間の、経済学者の方にあるのだろう。
● ニュースと感想 (8月28日)
修正ケインズモデルに戻って考えよう。
景気回復策として、ケインズは「公共投資」を示した。しかし、「投資」には、「公共投資」のほか、「民間投資」もあるはずだ。そこで本項では、「民間投資」について考えよう。
ケインズは、民間投資や消費性向は、操作できないもの(独立して決まるもの)であると見なした。操作できるのは公共投資だけだと見なした。── そして、そういう前提の上に立ったから、「公共投資を増やすしかない」と結論したわけだ。
しかし、私は、すでに別の見解を示している。民間投資や消費性向は、操作不可能な量ではなく、操作可能な量である。これらは、「金利」「物価上昇率」の二つを変動させることで、操作ができる。
具体的に言えば、金利と物価上昇率の影響は、次のようになる。
- 金利が下がると…… (上がると逆)
- 投資には、補助金が出るのと同じ。(貸出金利低下)
- 貯蓄には、補助金が減るのと同じ。(預金利率低下)
- 消費には、補助金が出るのと同じ。(貯蓄の逆だから)
- 物価上昇率が上がると…… (下がると逆)
- 投資には、補助金が出るのと同じ。(実質金利低下)
- 貯蓄には、補助金が減るのと同じ。(実質利率低下)
- 消費には、補助金が出るのと同じ。(貯蓄の逆だから)
ともあれ、こういうふうに「金利」や「物価上昇率」を操作することで、「投資」「貯蓄」「消費」を変化させることができる。
( ※ なお、言わずもがなだが、説明すると: 金利は直接、操作できる。物価上昇率は、他の経済政策を通じて間接的に、操作できる。「物価上昇率」の方は、「需要統御理論・簡単解説」で「アメとムチ」という形で示した。)
( ※ 消費の額は、生産・所得の関数と見なされる。それ以外に、ここでは、消費性向で、消費の増減を考えている。ケインズは前者のみに着目し、後者を無視している。)
ケインズの主張には、「金融政策」という観点がすっぽりと抜け落ちている。いろいろとグラフを書いているが、それを説明するときに、「金利」という言葉はまったく現れない。そういうふうに、金融政策を無視するから、「財政政策しかない」と結論するわけだ。(何であれ、無視すれば、それが見えなくなるのは、当然だ。)
しかし、実際には、金融政策というものは、無視するべきではない。では、無視するべきではないとしたら、どう理解するべきか? ── このことは、修正ケインズモデルでは、次のように結論できる。
「金利の低下による投資の拡大」という形で、投資 I を増やすことができる。そのことで、「 C = Y−I 」という直線を、下シフトできる。それが金融政策の影響である。
次の図で言えば、こうなる。
不況の際、交点 A に留まっているとする。このとき、「 C = Y−I 」という直線を下シフトすると、交点 A から交点 A’に移動する。すると、需要増加とスパイラル効果によって、交点 A’から交点 E に移行する。
これは先に示した図である。先に示したときも、「 C = Y−I 」という直線を下シフトするものがあった。それは、投資 I の増加だった。そして、投資の増加は、先に示したときは「公共投資」の増加だったが、今度は「民間投資」の増加なのである。
そして、そのいずれであるにせよ、結果は同じなのである。つまり、公共投資であれ、民間投資であれ、とにかく、投資の増加があれば、それは、「 C = Y−I 」という直線を下シフトさせることで、状況を、「 A → A’→ E 」というふうに移行させるわけだ。
結局、次のようにまとめることができる。
・ 投資には、「公共投資」のほか、「民間投資」もある。
・ 「投資の拡大」には、前者でなく後者を拡大してもよい。
(公共投資の方は、財政政策で。民間投資の方は、金融政策で。)
・ どちらであれ、「投資の拡大」としての効果は同じである。
[ 付記 ]
上の最後に、「どちらであれ……効果は同じである」と述べたが、前項で述べたことを勘案すれば、あらゆる意味で同じというわけではない。
たしかに、ケインズ的な「総需要の管理」という意味では、同じだ。しかし、前々項で述べた「比率の変更」という問題が発生する。
公共投資の場合は、土建産業ばかりが繁盛する。民間投資の場合は、投資関連産業が繁盛する。後者は、前者よりも、産業の広がりが大きく、それだけ経済的な効果が高い。
ただし、いずれにしても、「投資の拡大」であるから、「消費の拡大」ではない。GDPの6割は個人消費であるから、産業の6割は「投資拡大」の恩恵を受けずに放置されてしまう。
だから、「公共投資の拡大よりは、民間投資の拡大の方が好ましい」とは言えるが、「民間投資の拡大よりは、投資と消費の双方の拡大の方がもっと好ましい」と言える。
ここで、原則を示すと、何かを拡大するための方法は、次のように異なる。
- 土建産業の振興 …… 公共支出の拡大 (ケインズ的)
- 投資関連産業の振興 …… 金利の低下 (マネタリスト的)
- 個人消費の拡大 …… 減税
こういう違いがある。通常、この三つのうち、最初の二つは実施済みである。それだけで効果があるなら、それでいい。しかし、それだけで効果がないときは、三つ目の「減税」が必要となる。
( ※ 実を言うと、最初の二つはそもそも効率が悪くて金を無駄にするので、三番目の「減税」だけを実施するのがもっとも好ましい。)
[ 補説 ]
本項で述べたことの位置づけを示そう。
本項の話(「公共投資でなく民間投資でもよい」ということ)は、読んだあと、「何だ、当たり前じゃないか」と思うかもしれない。たしかに、当たり前だ。しかし、この当たり前のことを、グラフによって示した、ということが肝心だ。
ケインズの主張では、「民需が足りなきゃ、官需を増やせ」というだけであり、公共投資一辺倒であった。そこには「金融政策」との関連は、まったくなかった。
しかし、「投資」というものに、「公共投資」のほか「民間投資」というものを勘案することで、このグラフに「金融政策の影響」というものを入れることができるようになったのである。
ケインズのモデルでは、縦軸は「 C+I 」であり、これは常に一定であった。(Yが一定である限り、C が減って I が増えても、C+I は同じ。)
しかし、修正ケインズモデルでは、縦軸は「C」である。これだと、たとえ C+I は同じだとしても、C が減って I が増えるという状況は、元の状況とは異なった状況となる。そして、そのことは、交点 B から( A と A’を経由して)交点 E への移行に相当するのである。
そして、この点に関しては、I が公共投資であっても民間投資であっても、同じなのである。
[ 補説 ]
ケインズのモデルでは、「 C+I 」という総需要だけに着目して、その内実である C と I の違いに着目しない。……実は、これは、現代の経済学の根本的な欠点なのである。
そもそも C と I は別々なのだから、区別して当然だ。なのに、両者をひっくるめて、とにかく「需要を増やせ、だから投資だけを増やせ」と主張する。ケインズ派であれ、古典派であれ、どちらもそうだ。(官と民の違いはあるが。) それに対して、私は、「需要を増やせ、だから投資と消費をともに増やせ」と主張する。ここに、現代の経済学と私との決定的な違いがある。
現代の経済学は、需要(投資と消費)の半面しか見ていない。いわば、片目をつぶっている。だからこそ、不況という現象にぶつかったとき、「投資を増やせ」と主張したあげく、設備投資も公共投資も増やせない状況にぶつかって、右往左往するハメになるのである。
( ※ 次項以降では、さらに話を進めて、「減税」について考察しよう。)
● ニュースと感想 (8月29日)
景気回復策として、「公共投資」「民間投資」についてすでに述べた。このあと、「減税」について考えよう。
ケインズは、減税については、次のように主張した。
- 減税も公共投資も、財政政策という意味では同じである。
- 減税の方は、公共投資に比べて、効率が悪い。なぜなら、支出の第1段階で、消費に回されるのは、限界消費性向の分(0.7)だけであるからだ。残りの分(0.3)の方は、貯蓄に回って、眠ってしまう。その分、効率が悪い。
これは、教科書に書いてあるとおりだ。ただ、上の第2項の方は、ほとんど無意味である。貯蓄に回る分は、無駄になるわけではなく、単に眠るだけだ。だったら、その眠る分を見込んで、最初の減税額を増やせば、同じことになるからだ。
たとえば、公共事業に7兆円を費やす案があるならば、対案となるのは、7兆円の減税でなく、10兆円の減税(と将来の3兆円の増税)である。こうすれば、どっちみち、同じことだ。( → 後述の [ 付記 1 ] )
肝心なのは、上の第1項の方だ。「減税も公共投資も、財政政策という意味では同じである」というのが、ケインズの主張だ。なるほど、「有効需要の縮小」という意味では、たしかにそうなるだろう。
しかし、修正ケインズモデルでは、解釈が異なる。不況の原因は、単なる「総需要の縮小」ではなくて、「消費の縮小」(消費性向の低下)である。……この点、ケインズの主張とは、大きく異なる。
ケインズは、「総需要が縮小したなら、総需要を増やせばいい。それで元に戻る」と考えた。修正ケインズモデルは、「消費が縮小したら、消費を増やせばいい。それで元に戻る」と考える。そして、「消費が縮小したときに、投資を増やせば、消費と投資の割合が、変わってしまう。それゆえ、元の状態には戻らず、別の状態に移ってしまう」と考える。
結局、増やすべきものは、投資ではなく、消費なのだ。「公共投資を増やせばいい」という考えが悪いだけでなく、「民間投資を増やせばいい」という考えもまた悪い。正しくは、「消費を増やすこと」なのだ。
だから、「減税は、公共事業に比べて、直接的に有効となる割合が低い」というケインズ派の主張は、お門違いであるわけだ。減税か否かは、政府の財政支出の効率の良し悪しの問題ではない。もっと別のことが問題となっているのだ。
ここでは、次のことが狙いとなっている。
・ 「投資の拡大と消費の拡大を、最適化する」
(投資拡大の一辺倒でなく、消費の拡大も同時に実施する。)
・ 「全産業で需要を拡大する」(特定産業だけでなく)
減税には、こういう狙いがある。そのことを理解するべきだ。
ただし、実際には、理解していない人が多い。「投資拡大の一辺倒でやれ」(消費の拡大は不要だ)と唱えたり、「土建産業だけ拡大せよ」(他の産業は知ったこっちゃない)と唱える人が多い。)
( ※ 上の2項のうち、1項目の「投資と消費の比率の最適化」は、以前、「タンク法」の一環として述べたことがある。[ 4月26日 付近 ] その際は、「消費の拡大には減税で」と示してきた。なお、上の2項のうち、2項目の方は、ここ数日、何度か述べてきたとおり。)
[ 付記 1 ]
「減税だと、一部の金が眠るが、その眠る分を見込んで、最初の減税額を増やせば、同じことだ」と先に述べた。このことについて、解説しておこう。
これに反対して、「減税を余分に実施すると、将来の増税が大規模になる。その増税が難しい」とチンタラいう人もいる。
それはそうだ。しかし、そういうのは、経済学説ではなくて、政治学説である。「政治家のかく汗を減らすにはどうすればいいか?」「政治家が楽ができるようにするにはどうすればいいか?」ということは、政治的な問題であって、経済的な問題ではない。財務省の役人にとっては、大問題だろうが、経済学的にはまったく意味がない。
経済学的には、どうか? 貯蓄となって眠る金を渡すことは、まったくの無意味か? それについては、以下で示す。
[ 付記 2 ]
貯蓄となって眠る金を渡すことは、まったくの無意味か? 実は、これは減税の方法いかんによる。
・ 通常の所得税減税ならば、無意味どころか、マイナスの効果がある。
・ 累進制でなく比例制の減税なら、プラスマイナスはない。
・ 累進制でも比例制でもなく、均等(同額)ならば、プラスの効果がある。
これはなぜかというと、所得の違いで、消費性向の違いが生じるからだ。
具体的に示そう。金持ちは消費性向が低く、貧乏人は消費性向が高い。だから、減税をすれば、金持ちは貯蓄し、貧乏人は消費する。それをマクロ的に見ると、モデルとなった消費性向が得られる。
さて。注意しよう。このマクロ的な消費性向は、既存の所得に従った消費性向だ。だから、所得に比例する減税をすれば、その消費性向に従って消費が増えるから、別に、何も変わらない。
では、均等(同額)の減税をすれば? 金持ちは応分以下の額しか得られず、貧乏人は応分以上の額を得られる。つまり、
・ 消費性向の低い人は少しの金しか得られない。(世の中の少数)
・ 消費性向の高い人は多くの金を得られる。(世の中の多数)
となる。かくて、国全体では、消費性向は以前よりも上昇する。だから、均等配分の減税は、消費性向の向上をもたらすのだ。(消費性向の高い人を重視する、加重平均の結果である。)
ケインズ派は、「減税しても、その一部が眠るから、その分、無効になる」と主張する。しかし、そうではないのだ。減税の配分の仕方しだいで、無効にもなるし、有効にもなる。そこに気づくことが大切だ。
( ※ ケインズ派の主張は、「国民の間で消費性向の分布がある」ということを無視して、単に平均値だけを見ているわけだ。実際には、分布があるから、各層に対する配分を変更することで、分布の状態を変えることができる。)
[ 余談 ]
経済というものについて、根本的に考えよう。ケインズ派は、あまりにも粗っぽくマクロ的な数字だけを見る。しかし実際には、もっと細かく見るべきなのだ。
一人一人の状態を見るとわかるが、金というものは、同じ金額でも、その価値が異なる。金持ちにとっての百万円と、貧乏人にとっての百万円とは、価値が異なる。金持ちに百万円を与えても、高級ワインが一本、彼のオシッコに変化するだけだが、貧乏学生に百万円を与えれば、彼は大学を卒業して国家経済に多大な貢献をなす。金持ちは不況で百万円を失っても、貯金通帳の数字が少し減るだけだが、貧乏人が不況で百万円を失えば、これまで形成してきた家や家族や生命を失う。だから、単に「金を使えばいい」と主張するのではなく、「金がどう使われるのか」を考えるべきなのだ。
そもそも、経済というものは、ただの数字ごっこではない。人間の生命や人生を左右するものだ。経済学者には、人間的な愛や優しさが必要だ。それを忘れると、経済を単なるモデルごっこと考えるだけになる。たとえ人が死んでも、「このゲームでは登場する人数が一人減ったな」と思うだけになる。さしずめ、小泉あたりが、その筆頭だろう。彼にとっては、国民が一人死んでも、数字が一つ減ることしか意味しない。
そしてまた、多くの経済学者も、事情は同様である。彼ら経済学者は、愛や優しさや人間性を失えば失うほど、科学的になったと思って、威張るのだ。
● ニュースと感想 (8月30日)
減税について、次項で深く考えるが、その前に、留意すべき点がある。それを示しておく。
ケインズの発想では、「国民が金を使わなければ、政府が金を使う」というふうになる。では、国民が金を使わないとき、総需要が縮小するのは、なぜか? つまり、消費が減ったとき、投資が増えないのは、なぜか?
ここで注目するべきは、「セイの法則」だ。それによると、次のようになるはずだ。
「個人の消費が減っても、貯蓄が増えて、その分、投資が増える。だから、消費と投資の和である総需要は、変化しない」 …… (*)
さらに、「その量(消費と投資の和)は、供給によって決まる。供給と需要は等しくなる」というのが「セイの法則」だ。しかし、このことはともかく、今は、話の前段である (*) だけに注目しよう。
上の (*) は、通常は成立する。なぜなら、消費が減れば、貯蓄が増えて、その分が投資に回るからだ。つまり、金融市場を通じて、「貯蓄 → 投資」という形で資金が流れるからだ。(細かいことを言えば、滞留する分とか、貨幣の総量とか、そういうこともあるが、ここでは、そういうことは無視する。マネタリズムふうに言えば、貨幣の総量を一定に保つことで、自動的に金利が調整されて、消費が増えれば投資が減るし、消費が減れば投資が増える。)
ただし、である。それが成立するのも、「金利ゼロ」になるまでの話だ。いったん「金利ゼロ」になると(「流動性の罠」の状態になると)、もはや、この「貯蓄 → 投資」という流れは発生しなくなる。かくて、 (*) は、成立しなくなる。
つまり、「金利ゼロ」という状態になると、「総需要は一定である」という説は(原理的に)成立しなくなるわけだ。このことは重要である。
そこで、状況の違いを明示するために、次のように区別することとしよう。
- 「真の不況」……金利をゼロまで下げても、不況のままである。
- 「仮の不況」……金利をゼロまで下げれば、不況でなくなる。
つまり、「不況」という状況にも、上の2種類があるわけだ。そして、現状が「真の不況」であるか、「仮の不況」であるかは、金利をゼロに下げたときに、判定できる。
(金利をゼロに下げるまでは、どちらであるかは判定しづらいが、とにかく金利をゼロに下げれば、判定できる。)
- 金利をゼロまで下げても、まだ不況のままであるなら、「真の不況」である。
- 金利をゼロまで下げて、もはや不況から脱したなら、「仮の不況」であった。
「仮の不況」ならば、金利低下で不況から脱することができるのだから、何も問題はない。「金利低下を迅速に実施できるかどうか」というだけの問題にすぎない。(ただし、ぐずぐずしていると、たとえ現状が「仮の不況」であっても、状況がどんどん悪化して、「真の不況」に変化してしまうこともある。1990年代前半の日本経済がそうだ。)
一方、「真の不況」ならば、金利低下だけでは、もはや片付かない。金利はすでにゼロになってしまった(それでも効果がない)のだから、もはや金融政策の余地はない。他の方策しか、残されていない。
そこで、「減税」が問題となる。特に、その「財源」が問題となる。
(次項に続く。)
[ 付記 1 ]
誤解を避けるために、解説しておく。
上の赤字強調部分では、次のように述べた。
「金利ゼロ」という状態になると、「総需要は一定である」という説は(原理的に)成立しなくなる。
さて。このことは、「金利ゼロのときだけ、総需要が一定でなくなる(需給ギャップが発生する)」ということではない。金利ゼロでなくても、総需要が一定値を割る(需給ギャップが発生する)ことがある。
ただし、たとえ需給ギャップが発生しても、「今は不況だが、金利低下によって解決できるはずだ」という状況もある。それが「仮の不況」という状況である。
[ 付記 2 ]
「仮の不況」のときは、個人消費が縮小しても、金利低下をすれば、投資が拡大する。だから、総需要は一定に保たれるはずである。(「セイの法則」の成立。)
しかし、金融当局が愚かだと、それが成立しなくなる。たとえば、市場金利がどんどん低下しているときに、「公定歩合は下げないぞ」という方針を出すと、金利は高めのままとなるので、投資の伸びが抑制される。かくて、「総需要は一定に保たれる」ということが成立しなくなる。
だから、日銀が(金融市場の)市場経済に逆らった操作をすれば、不況が発生することもあるのだ。では、そういう馬鹿げたことを、実際にすることは、あるか? ある。馬鹿げたことに、それが日銀のポリシーだからだ。彼らは、自らの職務を、こう主張する。
「日銀は、物価の門番だ。物価の安定こそ、最優先課題だ。金利を下げると、物価が上昇するかもしれない。だから、市場が需要不足のせいでどんどん金利の低下が発生したとしても、そんなことは気にせず、日銀はとにかく、物価上昇を予防するために、金利を高めに維持するべきだ。本来の市場水準は金利ゼロでも、日銀は金利をもっと高めに維持するべきだ」
彼らの頭のなかには、金利と物価上昇率との、相関関係が図式化されているのである。だから、消費と投資のバランスが崩れて、金利が低下したときに、「金利低下 = 物価上昇」というふうに、短絡的に反応する。そのせいで、「需要縮小」という「物価下落傾向」が発生したときに、「物価上昇」を懸念する。物価下落の可能性が高まれば高まるほど、物価上昇防止のための措置(金利上昇)を取る。
やるべきことと正反対のことをやるのだから、日銀の方針を取る限り、状況はどんどん悪化するはずなのである。
( ※ ジョークのようだが、ジョークではない。1990年代前半の日銀の金融政策について、FRBが先日 、「金利をもっと迅速に下げるべきだった」という報告を出したが、日銀はこれに反発している。もちろん、自己反省など、したこともない。彼らの頭では、金利は、物価とだけ関連づけられるのだ。「消費と投資との関係」とか、「市場金利に見る景気状況」とか、そういう経済の実態を無視して、単に「物価上昇率」という指標しか見ない。馬鹿のひとつ覚え。単細胞。思考の硬直化。……その結果が、1990年代前半の景気悪化だ。無知ほど怖いものはない。)
[ 付記 3 ]
1990年代前半の景気悪化は、「仮の不況」であったか?
これは、実は、難しい問題だ。たしかに、日銀が金利を迅速に下げなかった、という事実はある。しかし、日銀がゼロ金利にすれば不況を脱したか、というと、なかなか微妙なところである。もしかしたら、「仮の不況」ではなくて、このときすでに、「真の不況」であったのかもしれない。
一般に、バブル破裂が急激かつ大規模であれば、その後の景気悪化は、手に負えなくなる可能性がある。消費が大幅に縮小したあとでは、「金利を下げれば投資が大幅に増える」ということは、成立しにくくなっている。(たとえ話。通常ならば、薪を火にくべれば、火は大きく燃え上がる。しかし、火が消えかかっているときには、薪を大量にくべても、大きな火にはならない。火が消えかかってからあわてても、遅いのだ。)
1990年代前半の日本と同様に、2001年秋以降の米国も、「仮の不況」であるか、「真の不況」であるかは、微妙なところである。FRB金利は 1.5% 程度を続けたが、これをゼロ金利にしても、急激に景気が回復する見込みは、あまりなさそうだ。(投資が急に増えるとは思えない。)
結局、「仮の不況」であるか、「真の不況」であるかは、あまり大きな問題とはならない。どちらであろうと、対策としては、「減税」を実施するのがベストである。となれば、「真の不況であるかもしれない」というリスクがある以上、リスク回避のためにも、「減税」を実施した方が利口だろう。
[ 付記 4 ]
上記では、(セイの法則の)「話の前段の (*) だけに注目しよう」と述べた。では、話の後段に注目すると、どうなるか? つまり、「需要は供給に一致する」という問題については、どうなるか?
この件は、すでに説明済みである。トリオモデルのところで説明した。
( ※ 再度、説明すると、……下限直線があるので、その影響が出て、「需要は供給に一致する」ということが成立しない。なぜなら、需要曲線が左シフトして、均衡点が急激に下がると、下限直線に邪魔するので、均衡点に達することができなって、需給ギャップが発生するからだ。)
● ニュースと感想 (8月31日)
前項 では、「真の不況」と「仮の不況」の区別をした。なぜこういう区別をしたかというと、これは「減税」の話にとって大切だからである。
減税には、財源が必要だ。その財源として、「民間引き受け」の国債を発行すると、金融市場から金を吸い上げることになる。そのとき、金融市場における金の滞留(金利ゼロ)との関連が問題となる。
減税の財源となる国債が、「民間引き受け」と「日銀引き受け」の、どちらであるかで区別する必要がある。そこで、次の (1) (2) に分けて、考えよう。
(1) 民間引き受けの国債
(2) 日銀引き受けの国債
本項では (1) について述べ、次項では (2) について述べる。
(1) 民間引き受けの国債
減税の財源が、民間引き受けの国債であったとする。このとき、減税のための国債発行にともなって、金融市場から金を吸い上げることになる。すると、どうなるか? 資金の逼迫が起こるのではなかろうか?
第1に、「真の不況」の場合。
真の不況の場合には、資金の逼迫は起こらない。
真の不況ならば、金利をゼロにしても投資は増えない。つまり、需給ギャップがある状態で、金利をゼロにしても、量的緩和をしても、投資は増えない。資金は、行き先をなくして、金融市場で滞留している。
ここで、国債を発行して、減税を実施すると言うことは、どういうことか? 金融市場に滞留していた金を、国債で吸収して、国民に渡すことで、使わせる、ということだ。眠っていた金を、目覚めさせる、ということだ。だから、その分、需要が増える。
もう少し細かく言おう。世の中には、金を使いたくない人(貯蓄する人)と、金を使いたい人(消費する人)とがいる。前者から金を借りて、後者に渡せば、国全体の消費は増えることになる。そして数年後に、増税によって、借りた金を返すことになる。(後者から前者へ。)
ここでは、国民間の貸し借りが発生する。そして、そのことで、国全体の消費性向を向上させるわけだ。なぜ消費性向が向上するかと言えば、消費性向の低い人の金を借りて、消費性向の高い人に渡すからである。
そして、このとき、資金の逼迫は起こらない。眠っていた金(使い道のない金)を使うだけだからだ。別に、その分、投資が減るわけではない。
( ※ なお、細かく言うと、現況が「真の不況」だとしても、資金の逼迫が起こることもある。それは、大規模な減税を実施した場合だ。こうすると、需給ギャップが解消して、さらにお釣りが来るから、そのお釣りの分、景気刺激効果が出て、資金逼迫が発生する。……ただ、この分は、「真の不況」ではなくて、「仮の不況」の分と考えてよい。「仮の不況」の分なら、資金の逼迫が起こって当然である。ま、当たり前の話。)
第2に、「仮の不況」の場合。
仮の不況の場合には、資金の逼迫が起こる。このことが問題となる。
通常、ケインズ政策を論議するときは、上述の「真の不況」の場合を前提としている。そして上述のように、あれこれと議論を進める。たしかに、それはそれでいいだろう。
しかし、現実には、「真の不況」ではなく、「仮の不況」であることもある。そうなると、もはや前提が崩れるわけだから、話は異なってくる。
というわけで、「真の不況」と「仮の不況」とを、区別するべきなのだ。
では、「仮の不況」であるときは、どうなるか? そもそも定義からして、「仮の不況」のときは、金利をゼロにしなくても投資が増える。だから、金利をどんどん下げていけば、どんどん投資が増えていく。結局、金利を下げていけば、金利がゼロになる前に、十分な投資喚起ができる。かくて、不況は金融政策だけで解決する。(さもなくば、「真の不況」となって、定義に反する。)
さて。こういうふうに「利下げ」だけで不況が解決できる状況において、「利下げ」のかわりに、「減税」をすると、どうなるか? もちろん、投資を増やすかわりに、消費を増やすことになる。つまり、「需要」の喚起という点では同じであっても、その「需要」の内実が異なるわけだ。(「投資」と「消費」の比率の変更、というふうに考えてもよい。4月下旬に述べたとおり。)
これはこれで、特に問題はない。不況のとき、「利下げ一辺倒」による「投資拡大」一辺倒が最善であるとは限らないから、「減税」による「消費拡大」も併用するといいだろう。つまり、「利下げ」と「減税」との比率を適切にして、「投資拡大」と「消費拡大」との比率を適切にするといいだろう。(ケース・バイ・ケースで。)
また、両者の比率のほか、両者の総額も大切である。大きな不況のときには、両者の総額も大きくする必要がある。(例:投資拡大を 10兆円、消費拡大を 20兆円、合計 30兆円。)
さて。「仮の不況」のときには、ここで問題が起こる。投資拡大と消費拡大がぶつかりあって、金を奪い合うことがあるのだ。それが資金の逼迫だ。
具体的に示そう。景気刺激策が過大になって、消費も投資も過剰に拡大しようとする。すると、限られた資金を、両方で奪い合うことになる。企業は「投資」をしたいので、高金利であっても借金しようとする。消費者は「消費」をしたいので、高金利であっても「貯蓄」を取り崩そうとする。── つまり、国民の「貯蓄」をめぐって、企業と消費者とで、金を奪い合うことになる。かくて、金融市場で、資金の逼迫が起こる。
これが「クラウディング・アウト」だ。この件については、マネタリストが批判した。次のように。
「不況だからといって、公共事業を増やすのは、無駄だ。たとえ公共事業を増やしても、資金の逼迫が起こって、金利が高くなり、民間の投資が減る。つまり、公共事業が増えた分、民間企業の投資が減少する。あちらが増えて、こちらが減る。差し引き、トントン。ゆえに、景気回復効果はない」
と。これは、「公共事業」に対する批判である。ただし、「減税」に対しても、同じ論法は成立する。つまり、たとえ「減税」をしても、「消費」が増えた分、「民間投資」が減るので、差し引きしてトントンであり、景気刺激の効果はないことになる。
この「クラウディング・アウト発生」という説は正しいか? それについては、経済学で、しばしば話題になってきた。そして、「 100% そのまま正しいとは言えないとしても、ある程度は正しい」というふうに言われることが多い。(実は、私も、以前は、こういう主張を信じてきた。)
しかし、である。本項における先の区別を理解すれば、本当のことを理解できるだろう。── 「クラウディング・アウトが成立するか否か」は、「真の不況か、仮の不況か」に依存するのである。
- 「真の不況」であれば、需要喚起策を取っても、滞留していた資金が減るだけであって、民間投資のための資金が奪われることはない。つまり、資金の逼迫のせいで、民間投資が縮小することはない。
(だから、真の不況のときは、ケインズの説明通りであり、マネタリストの批判は当たらない。)
- 「仮の不況」であれば、たやすく民間投資が増加するから、資金の逼迫が発生する。つまり、需要喚起のために、(民間引き受けの)国債を発行して、消費を拡大すると、すぐに資金需要が増えて、民間投資のための金が奪われる。
(だから、仮の不況のときは、マネタリストの説明通りであって、ケインズ流はうまく成立しない。)
なお、このとき、需給面にも着目するといい。次のように。
- 「真の不況」のときは、「需給ギャップ」がある。それを解決するために、需要喚起策を取ったとしても、まだまだ需給ギャップは残っている。だから当面、金利はゼロのままだし、資金は余剰で滞留している。このことは、需要が増えて、需給ギャップが解消するまで続く。
- 「仮の不況」のときは、「需給ギャップ」は表面的なものにすぎない。このときは、金融政策だけでたやすく「需給ギャップ」を解消することができる。こういうときに、減税や公共事業などをやりすぎると、民間投資のための資金が奪われてしまう。(そのせいで、供給力増強ができずに、インフレを招きやすい。)
まとめ。
「公共事業」や「減税」は、景気刺激効果がある。しかし、資金の逼迫を起こしたあと、金利の上昇を通じて、「民間投資」を減少させることがある。こうなると、生産拡大は頭打ちで効果がなく、物価上昇だけが発生しかねない。(メリットはなく、デメリットだけがあるわけだ。)
これは「クラウディング・アウト」の問題だ。そして、この問題が発生するか否かは、「真の不況」であるか「仮の不況」であるかで決まるわけだ。(つまり、「真の不況」であるか「仮の不況」であるかという状況の違いを無視して、一律に「景気刺激策によってクラウディング・アウトが発生するか否か」を論じても、無意味である。)
[ 付記 1 ]
具体的な経済政策として、どうすればいいかを、ざっと示す。
(a) 真の不況のとき
「真の不況」のときは、クラウディング・アウトの心配をせずに、十分な景気刺激策をするべきである。具体的な策は、「公共事業」か「減税」か、どちらか。(ただし、前者よりも、後者が好ましい。このことは何度も説明してきたとおり。)
なお、金融政策は無効である。金利はすでにゼロになっていて、これ以上は下がらないからだ。多少の景気刺激をしたあとも、金利はいまだに超低金利だから、クラウディング・アウトの心配は不要である。(クラウディング・アウトの心配が必要なのは、状況が「仮の不況」になったあと。)
(b) 仮の不況のとき
「仮の不況」のときは、需給ギャップは利下げだけで解消可能である。こういうときに、利下げや公共事業や減税などの景気刺激を、過度に実施するべきではない。そうすれば、クラウディング・アウトにより、民間投資が食われて、弊害が発生する。
とはいえ、過度では困るが、過度でなければ実施した方がいい。過度か否かの境目は、現況の景気しだいである。景気が過熱していれば景気刺激はしない方がいいし、景気が悪ければ景気刺激をした方がいい。
具体的には、物価上昇率や失業率を見て、総合的に判断する。物価上昇率が高くて、失業率が低ければ、景気が過熱していると見る。物価上昇率が低くて、失業率が高ければ、景気が悪いと見る。物価上昇率は、3%ぐらいがメド。
( ※ 両者がともに高かったり、両者がともに低かったりすると、ポリシー・ミックスの出番となる。→ 4月25日 の前後 )
[ 付記 2 ]
すぐ上の (a) (b) の説明からもわかるとおり、「真の不況」のときは、事情はケインズ的であり、「仮の不況」のときは、事情はマネタリズム的[古典派的]である。つまり、ケインズ的な主張と、古典派的な主張とで、そのどちらが正しいかは、状況しだいであるわけだ。
なお、このことは、本質的に考えれば、当然である。
・「真の不況」のとき……
需給ギャップが発生している。ゆえに事情はケインズ的。
・「仮の不況」のとき……
需給ギャップが発生していない。ゆえに事情は古典派的。
両者の違いは、トリオモデルにおける「不均衡状態/均衡状態」という違いと同等でもある。
[ 付記 3 ]
グラフでは、どう説明されるか?
滞留していた金がある。それが、国債を通じて、民間投資や消費に回されるわけだ。だから、使われなかった金が使われるようになった分、需給ギャップが減るわけだ。(つまり有効需要が増える。)
この需要増加は、修正ケインズモデルのグラフでは、次の二つのいずれかである。
・ 「民間投資」の増加 …… 「 I 」の増加。
「 C = Y−I 」という直線を下シフトさせるわけだ。
・ 「消費」の増加 …… 「消費性向の定数」( Ca )の増加。
「 C = 0.7Y + Ca 」という直線を上シフトさせるわけだ。
上の二つがあるが、そのいずれも、景気拡大効果は実質的に同じである。下のグラフを参照。
なお、このこと(滞留していた金を有効利用する需要増加策)が成立するのは、あくまで、「真の不況」の場合(需給ギャップがある場合)である。いったん需給ギャップが解消したら、上述のような需要増加効果はなくなる。かわりにクラウディング・アウトの問題が発生する。
( ※ 「修正ケインズモデル」は、あくまで、不均衡状態の動的な変化を見るだけだ。均衡状態の動的な変化を見るものではない。)
● ニュースと感想 (9月01日)
前項の続き。
(2) 日銀引き受けの国債
前項では、減税の財源としては、「民間引き受け」の国債の場合だった。では、「日銀引き受け」の国債の場合だと、どうか? ── 実は、この場合は、事情がまったく異なったものとなる。反対とか類似とかではなくて、別次元となる。
これまで、修正ケインズモデルを使った説明をしてきた。それはあくまで、ケインズの説明を拡張したものだった。しかし、「日銀引き受け」の国債を使うという経済政策は、「タンク法」である。これはもはや、ケインズの説明とは、まったく別の基盤に立つ。そこでは、新しい発想が必要となる。
それは何か? 「物価上昇効果」である。つまり、「貨幣価値の変動」である。
「貨幣価値の変動」は、ケインズ的な考え方では、何も影響がない。総生産であれ、総所得であれ、実質価格だけが問題であって、名目価格の変動は関係ないからだ。
しかし、タンク法の考え方を理解すれば、「貨幣価値の変動」は、次のような効果があるとわかる。
例示的に示そう。
今、500兆円の生産をしているとする。所得ももちろん、500兆円となる。(「所得 = 生産」という式が成立するからだ。) さて、このとき、 50兆円の減税をすると、どうなるか?
名目価格では、550兆円の所得があることになる。一方、生産は 500兆円である。つまり、生産以上の所得がある。となると、「所得 = 生産」という式が成立しなくなる。これが重要だ。
ここでは一見、国民の富が自動的に増えたように見える。しかしもちろん、そんなことはない。富は増えない。人は生産量の分しか入手できない。ここでは単に、物価上昇が発生するだけだ。つまり、生産が 500兆円で、所得が 550兆円なら、その差額は、物価上昇で埋めるしかない。( 550/500 = 1.1 という割合で、物価上昇[貨幣価値低下]が発生して、差額を埋めるわけだ。)
ただし、である。物価上昇は、減税の実施した直後には、まだ発生しない。金がまだ使われていないときは、物価上昇はまだ発生しない。そして、やがて金が使われるにつれて、需要拡大が徐々に起こって、物価が徐々に上昇する。
ここで、錯覚が生じる。金が使れたあとでは、金の価値が減った(物価上昇が起こった)ことに気づくのだが、金がまだ使われていないうちは、金の価値がまだ減っていない(物価上昇がまだ起こっていない)。── 50兆円の減税を実施したとして、その金がすべて使われたあとでは、物価上昇のせいで減税の分が帳消しになるのだが、その金がまだ使われていないうちには、50兆円の得があると錯覚する。( → 3月07日 )
すると、どうなるか? 減税直後は、実質所得が増えていなくても、実質所得が増えたと思い込む。だから、その分、消費が増える。(所得拡大による消費拡大の効果。)
グラフで示せば、次のようになる。(下図を参照。)
実際の生産が Y だとする。これは本来、所得に等しい。ところが、錯覚のせいで、( 500兆円 → 550兆円 だから)1.1倍の Y があると感じられる。(実際、名目価格では、1.1倍になる。)
消費は、元々は、「 C = 0.7Y + Ca 」という式で決まった。ところが、今や、Y は 1.1倍あると錯覚されているわけだから、「 C = 0.7・1.1・Y + Ca 」、つまり、「 C = 0.77Y + Ca 」という式で決まる。これはつまり、限界消費性向が「 0.7 → 0.77 」というふうに、1割向上したのと同じ効果をもつ。
( ※ 数学的に言えば、所得が1割増えたという錯覚は、「 Y' = 1.1Y 」というふうに示せる。その Y' に対して、「 C = 0.7Y' + Ca 」という式を取れば、この直線は、「 C = 0.7Y + Ca 」という直線に比べて、傾きが 1.1 倍である。)
こうして、限界消費性向が上がることになる。すると、先に述べた「景気回復の過程」と、ほぼ同じ事情になる。先に述べたときは、「限界消費性向が 0.7 から 0.8 へ拡大した場合」というふうに説明したが、今度は「限界消費性向が 0.7 から 0.77 へ拡大した場合」となるわけで、いずれも同様の事情となる。つまり、今度も、消費性向の上昇にともなって、交点 A から交点 Bのそばへ、移行していくのである。( → 前回の説明は、8月24日 。経路は、下のグラフで、水色の線。)
結局、タンク法で減税をした場合は、名目所得の上昇が起こるが、それは、実質所得の上昇をもたらさないとしても、限界消費性向の上昇をもたらすのであって、そのことによって、「交点 A から交点 B のそばへ」というふうに状況を移行させるわけだ。
ついでに、比較していえば、次の通り。
・「民間引き受けの国債による減税」では、Ca が増大する。
(限界消費性向ではなくて、初期定数の増加。前項で述べたとおり。)
・「公共事業」では、 I が増大する。
(消費の直線は変化しないまま、所得の直線[ 45度 ]が下シフトする。)
結論。
タンク法では、「物価上昇」つまり「貨幣価値の変動」を通じて、「限界消費性向」を向上させることによって、需要拡大がもたらされる。
( ※ ここでは、「貨幣数量説」に基づく「タンク法」と、とケインズ理論に基づく「修正ケインズモデル」が統合的に説明されている。その意味で、古典派とケインズ派の統合が、一歩進んだことになる。)
[ 付記 1 ]
上記では、「錯覚がある」というふうに説明した。(この錯覚は、「タンク法の減税によって所得が増えたと思い込む」という錯覚だが、「貨幣価値は変動しない」という錯覚と同じだから、「貨幣錯覚」と呼んでも構わない。)
この錯覚は、金が使われないうちは、たしかにある。しかし、金が徐々に使われるにつれて、物価上昇が発生するので、この錯覚はだんだん消えていく。そして、金(減税の分のすべて)が使われた段階で、物価上昇はすべてなされたことになる。もはやこれ以上の物価上昇効果はなくなる。だから、ここで錯覚は消える。そして、錯覚が消えた段階で、消費拡大効果も消える。
しかし、それはそれで、問題はない。物価上昇がすでにすっかり発生するということは、需要がすでにすっかり拡大したということなのだから、もはや景気はすっかり回復したことになる。だから、景気が回復した時点で、消費拡大効果が消えるのは、それはそれで好ましいわけだ。(景気回復後に、なおも消費拡大効果が残っていれば、インフレとなるので、好ましくない。)
[ 付記 2 ]
上記では、「錯覚」という言葉を使った。この錯覚は、景気回復後には、消える。では、錯覚が消えたとき、消費性向はふたたび低下するのだろうか?
いや、そうではない。このときもはや、景気回復にともなって、所得の増加が起こっているから、消費性向は自然に回復しているのである。不況のときは、不安ゆえに、消費性向が低下していた。( 0.8 → 0.7 )。しかし、不況を脱すれば、消費性向はまた元の水準に戻るはずだ。( 0.7 → 0.8 )。となると、錯覚による消費性向の上昇( 0.77 )が消えたとしても、あとには自然に高まった消費性向( 0.8 )が残ることになる。
[ 付記 3 ]
上記では、「錯覚がある」というふうに説明したが、これは、「長期的に見れば錯覚である」あるいは「国民全体で見れば錯覚である」という意味だ。「短期的に見れば」あるいは「一人一人の個人を見れば」、錯覚ではなく、まさしく現実となることもある。大まかに見ればともかく、細かく見れば、バラツキが生じるわけだ。── 具体的に言えば、次のようなバラツキが発生する。
- 「減税が行なわれた直後は、まだ物価上昇が発生していないが、このとき、減税の分の全額を使い切ってしまった人」……こういう人は、減税の分、まるまる得をする。(錯覚ではなく現実に得をする。)
- 「所得よりも消費の少ない人(貯蓄をする人)」……こういう人(国民の大多数)は、物価上昇の分、貯蓄が目減りするので、その分だけ、損をする。
こういう損得が発生する。つまり、
「早く多く消費をした人ほど得をして、遅く少なく消費した人ほど損をする」
というふうになる。
( ※ こういうことは、「需要統御理論・簡単解説」で、「アメとムチ」効果として説明したとおり。)
[ 補説 ]
関連した話を述べる。(特に読まなくてもよい。)
上記では、「錯覚」という言葉を使った。ただ、これは、バブル期の「錯覚」とは、本質的に異なる。その違いに注意しよう。
バブル期の「錯覚」は、真の錯覚である。国全体の富は変わらないのに、資産インフレが発生すると、「国全体の富が増えた」と思い込む。( → 5月06日 資産インフレの妄想 ) そして、そういう妄想に基づいて、過剰消費する。そのあと、「実は富は増えていなかった」と気づいて、消費が急減する。
一方、上記の「錯覚」は、まったく別のものだ。50兆円の減税があると、「 50兆円の得がある」と思って、金を使う。しかしここでは、その 50兆円は、まるきりの錯覚ではないのだ。次の二つの意味で。
・ 早く金を使った人は、まさしく得をする。(前述。アメとムチ。)
・ 需要拡大の効果で、まさしく所得が増える。
後者について、説明しよう。減税によって、景気が回復する。すると、そのことで、まさしく所得が増える。だから、「富を得た」というのは、まったくの錯覚ではないわけだ。
ただ、ここでは、物価上昇も発生する。その分、損をしたと感じられる。「 50兆円の減税があった。さらに景気回復で 40兆円の所得増加があった。なのに、物価上昇で、50兆円の損失が発生した。悔しい! 物価上昇のせいで、差し引き、10兆円の損だ!」と思い込む。(何だか変な計算だが。)
しかし、そもそも初めに述べたとおり、タンク法というのは、損得はない。「得をしたと感じられる」だけだ。50兆円の減税で、得をしたと思い込んだとしたら、そう思い込んだ方が悪い。本当は、「 50兆円の得と 50兆円の損が発生した」のではなくて、初めから「損得なし」なのだ。
ただし、「40兆円の所得増加」というのは、別途発生する。これは、景気が回復したことによる所得増加であり、労働時間が増えたことによる所得増加である。労働時間が増えたわけだから、「棚からボタ餅」ではないし、その意味で、得をしたことにはならない。しかし、得はしなくても、まさしく「財布の金額」は増えたのである。(その分、遊ぶ時間は減るが。)
結局、50兆円の減税で、「得をした」というのは錯覚だが、「富が増えた」というのは錯覚ではない。「働かないで金を得る」というのは錯覚だが、「働いて金を得る」というのは錯覚ではない。
そういう意味で、バブル期の錯覚とは、まったく異なったものである。バブル期の錯覚は、金がないのに「金がある」と思い込みながら過剰消費することだ。タンク法の錯覚は、金があるのに「金を使いたくない」と思いながらに過小消費する人々に対して、「もっと金があるぞ」と錯覚させることで、適正に消費させることだ。バブルの錯覚は過剰消費をさらに拡大させるだけだが、タンク法の錯覚は過少消費を適正水準に戻すのである。バブルの錯覚は現実から遊離した夢を見ることだが、タンク法の錯覚は縮こまった弱気を正気に戻すことである。その本質的な違いを理解することが大切だ。
前記の [ 付記 2 ] からもわかるように、景気回復後には、実際に消費性向が上昇する。だから、最初に錯覚があったとしても、最後には「錯覚が現実になる」ことになるわけだ。バブルの錯覚では、「夢を見たあと、夢から覚めて現実に気づく」ことになるが、タンク法の錯覚では、「夢を見たあと、夢が現実になる」ことになる。両者は、根本的に異なる。
たとえて言えば、酔っぱらった誇大妄想狂には、酒を与えない方がいい。一方、臆病すぎて前進できないような弱気の人には、少し酒を飲ませて、酔わせて、カラ元気をつけた方がいい。そういうことだ。同じ酒でも、使い方しだい。酒は毒にも薬にもなる。錯覚もまた同様だ。
● ニュースと感想 (9月02日)
これまでに述べた景気回復策を、整理してみよう。次のような表にまとめることができる。
| | 拡大対象 | 拡大分野 | グラフ | 不況脱出後 |
| 量的緩和 | 投資(民需) | 投資関連
産業 | 所得直線の
下シフト | 平常
(金利調整で) |
| 公共事業 | 投資(官需) | 土建産業 | 所得直線の
下シフト | 赤字が残る |
| 減税(民間国債) | 消費 | 全産業 | 消費直線の
上シフト | 赤字が残る |
| 減税(タンク法) | 消費 | 全産業 | 消費直線の
傾き Up | 平常 |
各項を順に説明すると、次の通り。
( ※ 表中で、「グラフ」というのは、「修正ケインズモデルのグラフ」のこと。)
- 量的緩和
- 民間の投資を拡大する。
- 投資関連産業が恩恵を受ける。
- 所得を意味する直線( C=Y−I )が、下シフトする。
- 不況脱出後は、金利を上げるだけでよい。特に赤字が残ることはない。
- 公共事業
- 公共投資を拡大する。
- 土建産業が恩恵を受ける。
- 所得を意味する直線( C=Y−I )が、下シフトする。
- 不況脱出後は、財政赤字が残る。国民は増税されて、富を失う。(不況期に、国が公共事業で富を得た分、不況不況脱出後に、国民が増税で富を失う。)
- 減税(民間引き受けの国債)
- 消費を拡大する。
- 全産業が恩恵を受ける。
- 消費を意味する直線( C= 0.7Y− Ca )が、上シフトする。定数 Ca の上昇。
- 不況脱出後は、財政赤字が残る。国民は増税されて、富を失う。(不況期に、国民が減税で富を得た分、不況不況脱出後に、国民が増税で富を失う。借りた分は返す、ということであり、当然。)
- 減税(タンク法)
- 消費を拡大する。
- 全産業が恩恵を受ける。
- 消費を意味する直線( C= 0.7Y− Ca )の、傾きが Up する。限界消費性向の上昇。
- 不況脱出後は、特に赤字が残ることはない。国民は、景気回復前には「減税」で富を得たが、その分、景気回復後に「物価上昇」で富を失った。物価上昇は、すでに発生済みだから、このあとさらに物価上昇が続くこともない。平常状態となる。( → 4月29日 タンク法と増減税 )
さて。以上のように整理すると、何か、わかることがあるだろうか? ある。それは、景気回復の過程だ。次の図を参照。
タンク法では、消費性向を上昇させる。この場合は、消費性向の上昇にともなって、交点 A から交点 B へ、水色の線をたどって移行する。
他の三つ(公共事業,民間投資,減税[民間引き受けの国債])では、いずれかの直線の上シフトまたは下シフトによって、二つの直線の間隔が開き、それにともなって、交点 Aから交点 E へ移行する。
こういう違いがある。このことは、次項において、重要な意味をもつ。
[ 補足 ]
「減税(民間引き受けの国債)」については、「上シフト」のほか、「消費性向の上昇」(傾きの変化)を併用することもできる。このことについては、先に述べた。( → 8月29日[ 付記2 ] 。減税の配分方法を「均等(同額)」にすることで、消費性向の向上が可能となる。)
[ 参考 ]
上記では、景気回復の方法として、四つの方法を示した。これらは、不況のときにおける景気拡大策である。
さて、不況でもないときに、(好況をめざして)景気拡大策を取ることがある。参考として、これについて言及しておこう。(特に読まなくてもよい。)
こういう政策には、代表的なものとして、次の二つの政策がある。
| | 拡大対象 | 拡大分野 | グラフ | 不況脱出後 |
バブル
(資産インフレ) | 投資(民需) | 資産市場
(土地・株) | 資産インフレの
おこぼれ効果 | 不況
(バブル破裂) |
過剰減税
(民間国債) | 消費 | 全産業 | 所得直線の
下シフト | 赤字が残る |
これらの本質は、前項の [ 付記 4 ] で述べたとおりだ。つまり、次のようにまとめられる。
・ これらは、「適正消費」から「過剰消費」に移す政策であり、好ましくない。
・ 「不況脱出」は、「過少消費」を「適正消費」に戻す対策であり、好ましい。
では、上の二つの政策を実際に取って、過剰消費をしたら?
そもそも、人は生産する以上の富を得ることはできない。生産する以上の富を得るとしたら、借金をしていたことになる。だから、当然、いつかはそのツケを払わなくてはならなくなる。── つまり、過剰消費をすれば、いつかは過少消費しなくてはならなくなる。そして、いつかは過少消費しなくてはならなくなったとき(借金を返さなくてはならなくなったとき)、不況が発生する。これは必然である。
( ※ こうして長期的に帳尻を合わせるわけだ。ツケ払い。── これは、避けえないことだ。もし避けえるとしたら、人は、働かないで富を得ることになる。そんな馬鹿なことはありえない。バブル信者以外は、そういう真実に気づくはずだ。)
上の二つの政策は、そういうふうに「過剰消費を起こす」という点では、同じである。ただし、本質的に異なる点もある。次の (1) (2) のような違いがそうだ。
(1) バブル
「資産価値が増えた」と錯覚したあとで、「実は資産価値は増えていなかった」と気づく。すると、(実際には高値で資産を売却したわけではないので)単に貯蓄を取りつぶしていただけだと気づく。貯蓄が減ったと気づくので、消費を減らす。
このとき、景気悪化にともない、政府には財政赤字が蓄積する。その分、国民は、増税を迫られる。国債発行によって、当面の増税は猶予されるが、国債残高の膨張は、将来の増税を確実に意味する。
国民は、消費を減らし、所得を減らし、借金のみが増える。結局は、富は不変なまま、浪費をしたわけだから、尻ぬぐいの必要がある。初めに楽しく、後で苦しい。
(2) 過剰減税
景気が良いときは、増税をして財政赤字を縮小するべきなのだ。なのに、いい気になって、さらに減税を実施する。そのことで、景気拡大効果が循環的に続く。
ただし、そのままだと、物価が上昇して問題となる。そこで、金利を上げる。これによって物価上昇が防止できるので、「景気は良く、物価上昇は低い」というふうになる。通貨相場も上がり、通貨の信認が上がる。政府は喜ぶ。(レーガノミックスなど。「強いドル」。)
しかしここでは同時に、問題が発生する。高金利は、需要を抑制するが、この際、需要である消費と投資のうち、消費よりも投資を抑制する。その結果、生産力は伸び率が下がり、経済体質は悪化する。また、投資の抑制で、職場の拡大が進まないので、失業率も高い。(実際、レーガノミックスの時期には、失業率が高かった。)
また、過剰減税は過剰消費を意味するから、赤字がどんどん蓄積する。(レーガノミックスでは、財政赤字と貿易赤字の拡大で、「双子の赤字」が巨額に発生した。)
結局これは、「将来の富を食いつぶす」政策である。「今が良ければ、明日のことは知ったこっちゃない」というわけだ。当然、将来的には、赤字をつぶすために景気悪化の時期が来る。(レーガン2期目〜ブッシュ時代。)
こういうわけだから、不況以外のときには、「減税による景気刺激は良くない」と言えるわけだ。その失敗の見本が、レーガノミックスである。初めに楽しく、後で苦しい。
[ 余談 1 ]
上の (2) では、「高金利は……投資を抑制する」と述べた。これはつまりは、クラウディング・アウトだ。マネタリズムやサプライサイドに従ったレーガノミックスが、クラウディング・アウトの弊害に陥る、というのは、逆説的でもある。(クラウディング・アウトの問題を指摘したのは、マネタリズムなのだから。)
なお、「景気があまり悪くないときに、やたらと減税をすると、クラウディング・アウトが起こる」ということは、先に「仮の不況」のところで述べた。( → 8月31日 )
[ 余談 2 ]
上の (2) では、「過剰減税が好ましくない」ということを示した。
そこで、「不況でないとき、減税をしたら失敗した。だから不況であるときも、減税をしない方がいい」と思う経済学者が多い。「あつものに懲りてなますを吹く」というふうになる。似て非なる失敗体験に懲りて、過剰に「減税は悪い、減税は怖い」と、恐れおののいているわけだ。臆病なのである。
そして、こういう臆病な人々が、世間の大半を占める。「減税よりは金融政策で」と唱える経済学者がそうだ。また、「減税はけしからん」と思い込んでいる政治家もそうだ。米国にも日本にも多い。世の中、臆病者ばかり。
( ※ こういう人々が、「金融政策で」と唱えたすえ、バブル[資産インフレ]を引き起こす。結局、レーガノミックスを恐れて、バブルを引き起こすわけだ。上の「過剰消費」の二つの政策のうち、後者を恐れて、前者を引き起こす。似たり寄ったり。同じ穴のムジナかな。)
( ※ では、正しくは? 「不況のときは消費を拡大し、好況のときは過剰消費を抑える」という、当たり前のことだ。こういう当たり前のことをするには、勇気がいる。財務省あたりは正反対だ。「不況のときには財政赤字だから緊縮予算、好況のときは財政黒字だから大盤振る舞い」としたがる。これが臆病者の政策。)
《 翌日のページへ 》
(C)
Hisashi Nando. All rights reserved.