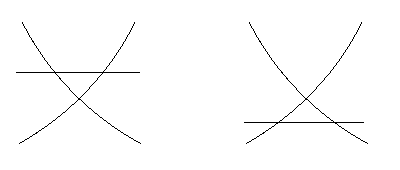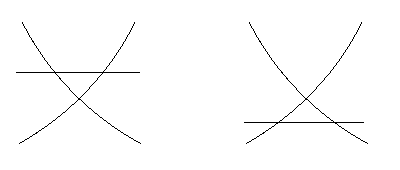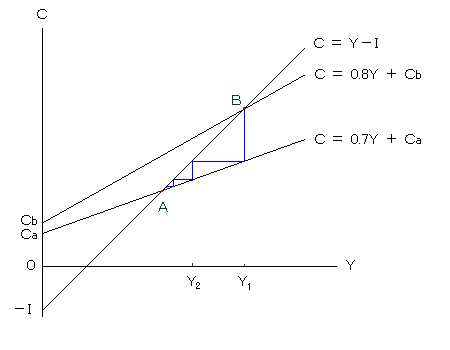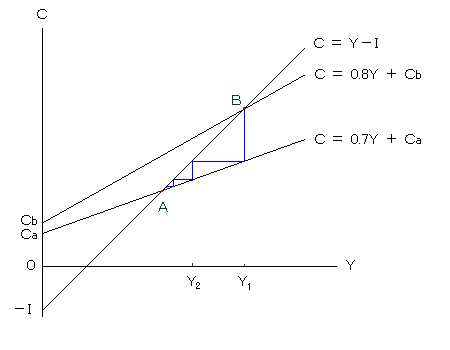[ 2002.08.13 〜 2002.08.23 ]
《 ※ これ以前の分は、
2001 年
8月20日 〜 9月21日
9月22日 〜 10月11日
10月12日 〜 11月03日
11月04日 〜 11月27日
11月28日 〜 12月10日
12月11日 〜 12月27日
12月28日 〜 1月08日
2002 年
1月09日 〜 1月22日
1月23日 〜 2月03日
2月04日 〜 2月21日
2月22日 〜 3月05日
3月06日 〜 3月16日
3月17日 〜 3月31日
4月01日 〜 4月16日
4月17日 〜 4月28日
4月29日 〜 5月10日
5月11日 〜 5月21日
5月22日 〜 6月04日
6月05日 〜 6月19日
6月20日 〜 6月30日
7月01日 〜 7月10日
7月11日 〜 7月19日
7月20日 〜 8月01日
8月02日 〜 8月12日
8月13日 〜 8月23日
のページで 》
● ニュースと感想 (8月13日)
本日から、新しい段階に進む。
これまで、トリオモデルによって、いろいろと説明してきた。「静的に」 → 「おおざっぱに動的に」という順で。
このあとは、「もっと細かく動的に」という方針で説明していこう。
これまでの説明でわかったことは、「需給ギャップ」というものが発生するメカニズムはわかった。── さて、そこで問題は、次のことに移る。
「いったん発生した需給ギャップは、自然に解消するのか?」
という問題だ。
古典派の経済学の立場によれば、次のように考えるだろう。
「均衡点というものがある。均衡点に落ち着くのが、最も自然かつ安定的である。だから、需給ギャップというものが生じても、それは自動的に解消して、やがては均衡状態に至るはずだ」
「仮に、そうならないとしたら、それは、状況が完全競争の状態にないからだ。だから、状況を完全競争の状態にすれば、ちゃんと均衡状態に至るだろう。」
「ゆえに、不況解消のためには、うまく均衡に至れるように、規制緩和や競争の促進をすればよい。さらには、シグナルなどを出して、市場をいっそう競争的にすればよい」
上のような古典派の説が一般に出回っている。しかしながら、現実の日本経済(十年不況)を見れば、その説の示すようにはなっていない。
第1に、均衡点があっても、なかなか均衡点にたどりつけない。(下限直線に阻止されているので。)
第2に、近年、インターネットなどの普及により、情報(シグナル)が氾濫したし、また、規制緩和も進んだ。だから、いっそう競争的になった。にもかかわらず、やはり、不況は解決しない。
結局、現実の経済は、古典派の学説とは違っているのだ。つまり、「いったん生じた需給ギャップは、自然に解消することはない」と言えるわけだ。少なくとも、経験的には。
では、このことは、どう説明されるのだろうか? 古典派の学説がそうなるのは、古典派が需給曲線と均衡点のあるモデルを使うからだが、そういう古典派のモデルではなく、トリオモデルを使えば、うまく説明できるのだろうか?
それが新たな課題となる。
[ 付記 ]
ここで示したのは、あくまでも、古典派である。ケインズ派はもちろん、ここには含まれない。
ケインズは、「需給ギャップはそのままでは解消できない」というふうに言っている。そのあとは、「だから放置すればうまく行く」とは言わずに、「だから政府が有効需要を創出しなくてはならない」と言っている。
ただ、「均衡点に自然に落ち着く」という考え方は、ケインズ派にもある。この点は、数日後に、後述する。
● ニュースと感想 (8月13日b)
前項(本日別項)の続き。
前項で示したのは、
「いったん発生した需給ギャップは、自然に解消するのか?」
という問題だった。
では、この問題を解くには、どうすればいいか?
ここで、トリオモデルに戻ろう。この問題は、トリオモデルでは、次のことと等価である。
「『左側の図 → 右側の図 』というふうに移るには、どうすればいいか?」
つまり、
「『不均衡状態 → 均衡状態 』というふうに移るには、どうすればいいか?」
ということだ。
( ※ なぜ等価かと言えば、左側の図[不均衡状態]では、需給ギャップがあり、右側の図[均衡状態]では、需給ギャップがないからだ。このことは、図を見て考えれば、すぐにわかるはずだ。)
ここで、振り返ろう。数日前まで考えてきたのは、
「左側の図 ← 右側の図」
という変化だった。そして、それの意味することが、「需給ギャップの発生」だった。
今度は、違う。このあと考えるべきことは、
「左側の図 → 右側の図」
という変化である。そして、それの意味することが、「需給ギャップの解消」である。
かくて、問題の位置づけができたことになる。(見通しを良くするわけ。)
さて。問題の位置づけができたあとで、いよいよ、本格的に考えてみよう。
「左側の図から右側の図に移るには、どうすればいいか?」
この問題を考えるには、動的に考える必要がある。つまり、需給曲線を動かす必要がある。── ただし、である。需給曲線を動かすと言っても、話は単純ではないのだ。
「需給ギャップの発生」を考えたときは、「需給曲線が左シフトする」というふうに考えたが、そういうふうにさせる原因としては、「外生的な力によって」というふうに想定した。それはそれでよい。
しかし、「需給ギャップの解消」を考えるときには、需給曲線をシフトさせる原因を、「外生的な力によって」というふうに単純に片付けることはできないのだ。もっと複雑になる。
なぜか? 何らかの経済的な操作を施せば、それが他に影響するからだ。つまり、「相互影響」があるからだ。── 換言すれば、「内生的な力」が発生するからだ。
具体的に例を示そう。
先に、「需給ギャップの発生」を考察した。このときは、「需要の急減」(需要曲線の左シフト)だけを想定した。実際には、このとき同時に、「供給の急減」(今日曲線の左シフト)も発生するだろうか? 実際には、そういうことはあるまい。いくらかは、供給能力が減少したとしても、需要の急激な減少に追いつくほどではあるまい。……しかも、先に示したように、トリオモデルでは、三本の線の「相対的な位置関係」だけが問題となる。供給曲線が、いくらか左シフトしたとしても、それを上回る量で、需要曲線が大きく左シフトすれば、供給曲線の小さな動きは無視できる。単に「需要曲線が左シフトした」というふうに見なしてよい。── そういうわけで、「需給ギャップの発生」を考察するときには、相互影響は、あまり考慮しなくてよい。
では、「需給ギャップの解消」を考察するときは、どうか? このとき、需要曲線が左右に動いたとき、それに影響を受けて、供給曲線がどう動くかは、まだはっきりとわかっていない。同様に、供給曲線が動いたとき、それに影響を受けて、需要曲線がどう動くかは、まだはっきりとわかっていない。とりあえずは、無視できず、「何らかの影響がある」と見なすべきだろう。── だから、ここでは、「相互影響」を考慮する必要がある。
実際、具体的な例がある。それは、いわゆる「インフレ・スパイラル」や「デフレ・スパイラル」だ。「インフレ・スパイラル」では、
「需要増加」→「所得増加」→「生産増加」→「需要増加」……
という無限循環のスパイラルが生じる。「デフレ・スパイラル」でも、同様のスパイラルが生じる。(増減が逆なだけ。)
こういうふうに、需要と供給との相互影響がある。この相互影響を考慮する必要がある。
しかし、である。ここで示した「インフレ・スパイラル」や「デフレ・スパイラル」は、「状況は均衡点に近づく」とかいうのとは、正反対の動きをなす。「状況を安定化する」のではなくて、「状況を不安定化する」のである。……これは、古典派の示すこと(「自由放任主義」「神の見えざる手」)とは、逆のことだ。
では、本当は、どうなのか? 放置すると、状況は、安定化するのか、不安定化するのか? ── それが問題だ。
(翌日分に続く。)
● ニュースと感想 (8月14日)
需給曲線の動的な変化を見る。すると、需要と供給との間には「相互影響」があるとわかる。その相互影響が、どう働くかが問題となる。相互影響によって、状況は、どうなるのか? 状況は、安定化するのか、不安定化するのか? ── ここまでが、前項で示した問題提起だった。
さて。これに対する解答を与える前に、別の方向から問題を考察してみよう。
以前、第3章では、次のように示した。
- ミクロでは、経済は、安定した構造をもつ
- マクロでは、経済は、不安定な構造をもつ
そして、このことを、次の図(ポテンシャルの図)で示した。
つまり、ミクロでは、状態に多少のブレがあったとしても、自然に元の状態に戻る。一方、マクロでは、状態に多少のブレがあると、そのブレがさらに拡大していく。(図を参照。前者は安定構造、後者は不安定構造。)
つまり、ミクロでは状況は安定的であり、マクロでは状況は不安定的である。── そして、これが最終的な解答となる。経済を動的に見たとき、状況が安定的か不安定的かは、ミクロとマクロとで異なるわけだ。
こうして先に解答を知れば、そのあとで理由を説明することができる。すなわち、「相互影響」という言葉を使いながら、次のように説明することができる。
( ※ 以下ではトリオモデルを使って説明するが、特に下限直線を必要とはしないので、単純な需給曲線を使って説明してもいい。)
ポイントは何か? 相互影響の有無である。ミクロとマクロとでは、相互影響の有無が異なる。
まず結論を簡単に言えば、次のように図式化できる。
・ マクロでは …… 相互影響 あり …… 不安定的
・ ミクロでは …… 相互影響 なし …… 安定的
これについて説明すれば、次のようになる。
- マクロ
マクロでは需要曲線と供給曲線に「相互影響」がある。それは「スパイラル的」な影響である。需要と供給のうち、一方が増減すれば、他方も同じ方向に増減して、そのことが循環的に拡大していく。
- ミクロ
ミクロでは需要曲線と供給曲線に「相互影響」がない。需要と供給のうち、一方が増減したからといって、他方が増減するということはない。
さらに詳しく説明すれば、次のようになる。(「需要」と「供給」の間に、「所得」が介在しているか否かがポイントとなる。)
(1) マクロ
マクロでは、「需要」と「供給」の間に、「所得」というものが介在する。たとえば、次のように。
総需要の増加 → 総生産の増加 → 労働所得の増加 → 総需要の増加
ここでは、需要と供給がスパイラル的に増加していく。「総需要の増加」が「総生産の増加」をもたらすのは、当たり前のことだが、「総生産の増加」が「総需要の増加」をもたらすのは、間に「所得の増加」が介在するからである。……マクロ的には、こういうことが成立するわけだ。
(2) ミクロ
ミクロでは、「需要」と「供給」の間に、「所得」というものが介在しない。たとえば、上の (1) の図式にならって
需要の増加 → 生産の増加 → 労働所得の増加 → 需要の増加
という図式を書く。(一国全体ではないので、「総」という字が抜けている。)
さて。この図式を見て、これが成立するかどうかを考えよう。ミクロ的な例としては、布団産業を取る。(別に、布団でなくても何でもいいが。)
まず、布団産業において、「需要の増加 → 生産の増加」というのは、十分に成立する。(布団の供給能力に制限がない限り、需要が増えた分だけ生産も増えるので、それは成立するはずだ。)
では、「生産の増加 → 労働所得の増加」というのは、成立するか? これも成立する。布団の売上げが増えれば、布団産業の労働者の所得は増える。(原則的に。)
では、「労働所得の増加 → 需要の増加」というのは、成立するか? これは成立しない。なぜか? 布団産業の労働者の所得が増えても、他の産業の労働者の所得は増えるわけではない。だから、いくら布団産業の労働者の所得が増えても、布団の需要の増加はもたらされないのである。
( ※ 厳密に言えば、微小な効果はある。布団産業の労働者が、全国民の 0.1% いるとすれば、その 0.1% の労働者で所得が増えた分、総需要が増える効果も 0.1% ぐらいはあることになる。しかしそんなものは、無視できる程度でしかない。だから、そんなものは、無視していいのである。……それがミクロ経済を考えるときの立場だ。)
結語。
「所得の増加 → 需要の増加」ということは、マクロ的には成立するが、ミクロ的には成立しない。それゆえ、需要と供給のスパイラル効果(相互影響)は、マクロ的にはあるが、ミクロ的にはない。(「ない」というのは、「皆無」ということではなくて、「無視できる」ということ。)
付言。
標語ふうに言えば、ミクロとマクロの違いは、次のように言える。
・ 部分市場における「需要と供給」の関係を見るのが、ミクロ。
・ 全体市場における「需要と供給と所得」の関係を見るのが、マクロ。
( ※ ここで、「部分市場」というのは、特定の産業の市場である。全体市場というのは、一国全体の市場である。……普通は。)
( ※ なお、ユーロのように、市場が国境を越えて一体化している場合には、一国だけではなくてユーロ全体を見てもよさそう思える。しかし、需要と供給と所得の関係が一国内で片付く[つまりGDPにおける輸出入の割合が小さい]場合には、一国だけで考えてよいだろう。「GDPにおける輸出入の割合」というのがポイントとなる。)
なお、第3の道として、古典派の考えもある。それは、こうだ。
・ 全体市場において、「需要と供給」だけの関係を見て、「所得」を見ない。
こういうふうに「所得を見ない」というところに、古典派の欠陥がある。大切な三要素のうち、一要素が欠落しているから、真実を知ることができないのだ。
たとえて言えば、カラーテレビで、色の3原色のうちの1色が欠落しているようなものだ。しかも、経済学では、事情はもっと悪くなる。三要素のうちの一要素が欠落すると、三分の一だけ間違うのではなくて、反対の結論を出すようになる。正解率が 0% であるというより、−100% となる。
それが「合成の誤謬」だ。これはデフレ期に発生する。というわけで、デフレ期には、古典派は完全に間違った答えを出すわけだ。
( ※ マネタリズムは? マネタリズムは、一国全体の経済を考える。しかし、「所得の効果を考えない」という点では、他の古典派[サプライサイドなど]と同様である。だからマネタリズムは、古典派に分類される。古典派に分類されないのは、ケインズ派だけだ。ケインズ理論は、所得の効果を考慮する。)
[ 補説 ]
以上では、話の基本を述べた。もう少し細かく見ると、基本は基本として、例外的な事情も見出されるので、少し説明しておく。
(1) 「所得」を通じた効果の有無
「所得」を通じた効果があるのは、原則としての話である。現実には、必ずそれが成立するとは限らない。
生産活動が増えれば、その分、労働者の賃金は増える。これが原則だ。まずは残業手当が増えるだろうし、さらに、企業業績の向上にともなって、企業利益の配分を受けるだろう。それができなけなければ、ストライキなどをして、正当な取り分を得る。
ところが、現実には、そういうことが起こらないこともある。たとえば、2002年の春だ。円安によって輸出企業は業績を好転させたが、労働者が得たのは、賃上げどころか賃下げであった。トヨタに至っては、2002-08-08 の各紙の報道によると、かつてない莫大な利益を得ている。利益率が 10% ほどになるから、もう「儲かって儲かって仕方ない。金が湯水のごとく余っている」という状況である。それにもかかわらず、労働者はその配分を受け取れない。(賃上げ率はゼロ。)
こういうふうになると、いくら生産が増えても、所得増加を通じた需要増加の効果は現れない。別に政府が大幅な減税をしなくても、各企業がどんどん賃上げをすれば、日本の景気は回復方向に向かうのだが、日本の企業は景気悪化のためにせっせと努力しているのである。
( ※ ここでは、「各企業が最善を求めると、マクロ的には状況が悪化していく」ということが成立しているわけで、「合成の誤謬」という状態である。……ここではもちろん、「放置すれば状況が良くなる」という古典派的なことは成立しない。)
(2) 市場規模の大きい場合
「所得の増加 → 需要の増加」ということは、市場規模が小さい場合には、無視してよい。たとえば布団産業は、市場規模が小さくて、労働者の数も少ない。だから、布団産業の労働者の所得増加が、布団の需要にはほとんど結びつかない。ゆえに、これを無視できる。
一方、市場規模が大きい場合には、そういうことを無視できるとは言いきれなくなるかもしれない。日本において最大規模の産業は何か? 自動車産業である。そこで従事する人々の生み出す生産量は、日本経済全体の1割程度にもなる。この場合には、「所得の増加 → 需要の増加」ということは、1割程度は成立することになる。まったく無視できるとも言いきれない。
しかしまあ、それはそれだけのことだ。話が根本から崩れるわけではない。自動車産業のような場合には、ミクロ的に話を済ませると不正確になるので、マクロ的な見方も少しは考慮した方が正確に論議できる、というだけのことだ。
とにかく、需要と供給の相互影響を、「無視するのがミクロ経済学」、「無視しないのがマクロ経済学」……というふうに、立場の違いを理解しておけばよい。
一般的に言えば、通常の個別産業を考えるときは、市場規模は自動車産業ほどは大きくないのが普通だから、需要と供給の相互影響(所得を通じた効果)を無視してよい。
(3) 産業間の中和
布団産業や自動車産業で、「所得」を通じた効果は少しはある、というふうに補足した。しかし、実を言うと、このことはあまり考慮しなくてもいいのだ。(つまり、「常に無視していい」とも言える。)
なぜか? それは、産業間で、プラスとマイナスを中和する効果があるからだ。たとえば、自動車産業で需要が増えて、自動車産業の労働者の所得が増えたとする。このとき、マクロ的に総需要が一定であれば、自動車産業で需要が増えた分、他の産業の需要が減る。自動車がたくさん売れた分だけ、パソコンとか外食とか被服とかレジャーとか、そういう他産業の需要が減る。(総需要が一定だから。) こうなると、自動車産業の労働者の所得が増えた分、他の産業の労働者の所得は減る。だから、自動車産業の労働者の所得がいくら増えても、そのことで自動車の需要が増える効果はないわけだ。(自動車産業の労働者が自動車を多く購入するようになっても、他の産業の労働者が自動車を少ししか購入しなくなる。差し引きして、チャラ。)
これが本質的だろう。となると、やはり、ミクロ経済では、「所得」を通じた効果は無視していいわけだ。
● ニュースと感想 (8月15日)
需要と供給との間に「相互影響」があるか否かは、マクロとミクロで異なる、── ということを前項で示した。つまり、マクロでは相互影響があるが、ミクロでは相互影響がない。それゆえ、マクロでは状況が不安定的だが、ミクロでは状況が安定的である。
ただ、ここには、ちょっと論理の飛躍がある。「マクロは不安定的だ」ということは、「相互影響がある」ということから結論できるが、「ミクロは安定的だ」ということは、「相互影響がない」ということからは結論できない。「相互影響がない」ということは、「不安定的になる要因がない」という意味で、マイナスを排除するが、かといって、積極的に「安定的になる要因がある」という意味で、プラスをもたらすわけではない。
「ミクロでは状況が安定的だ」という積極的な理由は、別のことから結論される。それは、「ワルラス的調整過程」である。
「ワルラス的調整過程」とは何か、と言えば、経済学の教科書に書いてあるとおりだ。簡単に言えば、「普通の需給曲線を描いたとき、その交点たる均衡点に自然に落ち着く」ということだ。(こうして得られた均衡が「ワルラス的均衡」である。)
この件については、とりあえずは、こういう教科書的な理解で十分である。とにかく、
「ミクロでは、状況は安定的になる。その理由は、ワルラス的調整過程が働くからだ」
と理解しておけばよい。(もっと詳しいことは、またあとで再論する。)
さて。ここで、見通しをざっと示しておこう。
前項では、トリオモデル( or 需給曲線)のもとで、ミクロとマクロの違いを示した。それは、需要と供給の動的な変化に関して、「相互影響があるか否か」もしくは「相互影響を無視できるか否か」ということである。
ここに、ミクロとマクロとの本質的な違いがあるのだ。そのことを理解しよう。
ミクロとマクロとの違いは、単なる「個と全体」というような違いではない。まして、「ミクロの総和がマクロになる」ということもない。ミクロをいくら寄せ集めようと、マクロにはならないのだ。ミクロとマクロには、本質的な違いがあるのだ。── それは、たとえて言えば、「偏微分と微分」のような違いである。
ミクロとマクロを比べれば、ミクロの方がはるかに簡単だ。ミクロでは、需要曲線と供給曲線の変化を動的に考える必要はなく、「あらかじめ与えられている」と仮定してよい。なぜなら、個別産業でどんな変化が起ころうと、それは一国全体での総需要を変化させることにはならないからだ。── だから、「××が一定だと仮定すれば……」という、経済学お得意の論理が、ミクロでは需要について適用できるのだ。
マクロでは、そうは行かない。マクロでは、動的に考えるとき、需要と供給の相互影響を考える必要がある。それゆえ、事情はずっと複雑になる。
ミクロとマクロには、そういう違いがある。にもかかわらず、この事情を無視して、複雑なマクロを簡単なミクロのようにとらえようとすると、どうなるか? もちろん、マクロの事実を正確に認識できず、誤ってしまう。── そして、そういうことをするのが、「古典派経済学」だ。
古典派経済学というものは、「マクロはミクロの延長だ」とか、「マクロはミクロの総和だ」とか、そういうふうに考える。そして、「ミクロで適用できる論理は、そのままマクロでも適用できる」と考える。── そこには、もちろん、間違いがある。では、その間違いは、どこに由来するかといえば、「需要と供給との相互影響について十分に考慮していない」という点に由来するのだ。
古典派経済学は、「需給曲線だけで話は済むぞ」というふうに単純に考える。需要と供給の動的な変化についてはろくに考えないし、需要と供給の相互影響についてもろくに考えない。単に「放置すれば、自然に均衡点に落ち着く。だから放置すれば、万事片付くさ」と簡単に考える。それが現実にはうまく行かないと判明すると、「それは理屈が間違っているからじゃない。理屈が成立しないように、邪魔者があるからだ。つまり、完全競争を阻止するものがあるからだ。そういう邪魔者を排除すれば、きっと理屈通りにうまく行くさ」と考える。
そうではないのだ。需要と供給には、相互影響がある。そのことが状況を、安定させずに、不安定にするのだ。そういうふうに、マクロにはミクロとは根元的に違う点があるのだ。
そのことに初めて気づいたのは、ケインズだった。この意味で、ケインズは、実に偉大である。
ただ、ケインズは、需要と供給の変化をグラフによって考えることはできたが、古典派の需給曲線とは結びつけなかった。だから、古典派とのつながりが稀薄であったし、古典派との関係が不明であった。
しかし、今、トリオモデルがある。これを使えば、ケインズと古典派の関係をうまく理解することができる。
- ケインズの言う「需給ギャップ」は、トリオモデルの「需給ギャップ」に相当する。( ∀ という形の水平線部分にあたる。)……つまり、古典派の需給曲線では見えなかったものが、トリオモデルでは見えるようになった。
- ケインズの言う総需要と総供給の変化は、トリオモデル( or 需給曲線)における、需要曲線と供給曲線の時間的な変化(動的な変化)に相当する。つまり、トリオモデルに対して、時間軸を垂直に立てて、その時間軸上での変化を見れば、ケインズの言う総需要と総供給の変化を見ることができる。
このように理解されるわけだ。
さて。ここでは、一種の解答が与えられたことになる。
そもそも、最初の問題は、「トリオモデルを動的に考えるとどうなるか」つまり、「トリオモデルで時間的な変化を見るとどうなるか」ということだった。そして、それは、ケインズのめざしたことと一致するのである。
ここでいきなり解答を言えば、こうなる。
「トリオモデルを動的に考えるとき、その最も単純なモデルはケインズによって与えられた」
と。そこで、次項では、(トリオモデルを動的に考えるときの)最も単純なモデルとして、ケインズのモデルを取り上げよう。
[ 付記 ]
ダメな古典派の例としては、「マネタリズム」がある。「Xパーセントルール」などを持ち出して、「貨幣供給量だけを調整すれば経済は安定的に成長する」などと主張する。
ここでは、需給については、何も考えていない。需給ギャップについても考えないし、需要と供給の相互影響についても考えない。単に「貨幣、貨幣」と九官鳥のように繰り返すだけだ。
たしかに、「貨幣」に注目することは大切だ。しかし、だからといって、他の面を無視してよいことにはならない。物事の半面だけを見て、それでおしまい、というわけには行かないのだ。
マネタリズムというのは、こういうふうに、「物事の半面しか見ない」という偏った理論だ。しかし、どういうわけか、これが現在では最も優勢である。日銀などは、これの信奉者で埋まっている。財務省もそのようだ。世界的にも、IMFはがちがちのマネタリズム信者ばかりだ。日本の経済学者も、「量的緩和つきインフレターゲット」などと主張している人が多いが、彼らもまたマネタリストだ。
こういうふうに、物事の半面ばかりを見て、需給ギャップに少しも注目しない経済学者がそろっている。悲しむべきことだ。そして、そういう経済学者たちの無知のツケとして、日本は長らく不況に苦しむことととなったのである。
● ニュースと感想 (8月15日b)
「インフレのコスト」という話を、「需要統御理論・簡単解説」に、加筆した。(特に読まなくてもよい。)
● ニュースと感想 (8月16日)
需要と供給とのマクロ的な関係については、ケインズの示したモデルがある。「45度線」というような言葉で示したモデルである。このモデルについては、先に示した。( → 7月24日 の (2) )
ともあれ、こういうモデルがあり、広く知られている。(経済学の教科書か、イミダス 2002年度版 などで、調べてほしい。初歩的な知識だから、知っている人も多いだろう。)
さて。このケインズの出したモデルは、実は、そのままでは、正しいとは言えないのだ。
ケインズのモデルでは、次のようになっている。(先に7月24日でも示したとおり。、)
Y = C+I (つまり C = Y−I )
C = 0.7Y + Ca
( …… ただし、 Y は生産。 I は投資。 C は消費。 Ca は定数。
0.7 というのは、[限界]消費性向。別の値でも良い。)
1番目の式は、「生産 = 需要」ということだ。(需給ギャップなし)
2番目の式は、仮定である。(モデル化と言ってもいい。)
そして、1番目の式と2番目の式の交点を、「均衡点」として得る。
これがケインズのモデルである。このモデルでは、上記の2個の式に従って2本の直線を引く。その両者の交点が問題である。
・ 両者の交点が、やや左下に位置するとき …… デフレギャップがある。
・ 両者の交点が、適切な点に位置するとき …… ギャップなし。
・ 両者の交点が、やや右上に位置するとき …… インフレギャップがある。
というふうになる。(このあたり、細かい事情は、教科書を参照。インフレギャップについては、後日また言及する。)
以上が、ケインズのモデルだ。このモデルは、事情をごく簡単に示したものとしては、原理的には正しい。ただ、一つ、難点がある。それは、「消費性向は一定だ」と仮定している点である。そのせいで、「需給ギャップがない状態から、需給ギャップがある状態へ」という変化が、うまく示せないのである。さらには、「需給ギャップがある状態から、需給ギャップがない状態へ」という変化も、うまく示せない。……そのせいで、ケインズは、次のように主張した。
“ 「消費性向が一定だから、デフレギャップを解消するには、Ca に相当する量(何らかの定数)を増やさなくてはならない。それには「投資」または「公共事業」を増やさなくてはならない。「投資」が金利低下でも増えないのならば、「公共事業」を増やすしかない。”
こう考えて、ケインズは、「公共事業」を増やそうとした。しかし、それが現在ではまともな政策ではなくなったのは、周知の通りである。
では、ケインズの難点は、どこにあったか? それは、「消費性向が一定だ」と考えたところだ。実際には、消費性向は、変化する。「消費性向が一定だ」と考えるのは、モデルを簡単にするための便宜上の仮定に過ぎず、実際には、消費性向は変化する。特に、不況の変化は、「総需要の縮小」が主因だから、そこでは消費性向の変化が非常に大きな意味を占めるのだ。
この「消費性向」というのは、「平均消費性向」と理解してよい。とすれば、「消費性向の変化」というのは、「限界消費性向の低下」および「初期定数 Ca の低下」の双方を意味していると理解してよい。── ともあれ、こういうふうに、「消費性向の変化がある」と考えるわけだ。
そして、このように修正したものを、「修正ケインズモデル」と呼ぶことにしよう。
修正ケインズモデルでは、消費性向の変化がある。つまり、「需要の縮小」として、「限界消費性向の低下」および「初期定数 Ca の低下」が発生する。そうなると、どうなるか? もともとは正常な経済状態にあっても、「需要の縮小」にともなって、二つの直線の交点が左下に移動する。このとき、デフレギャップが発生する。
具体的に例を示そう。限界消費性向が 0.8 で、初期定数 が Cb のときに、需給は均衡していたとする。(ただし Cb > Ca )。そのあと、限界消費性向が 0.7 に低下し、初期定数が Ca に低下する。すると、二つの直線の交点が左下に移動する。このとき、デフレギャップが発生する。
こうしてデフレギャップが発生したとする。そのあと、「限界消費性向の上昇」および「初期定数 Ca の上昇」があれば、デフレギャップは解消して、元の正常な経済状態に戻れる。(そういうふうに限界消費性向や初期定数を上げるには、減税をすればよい。公共事業は不要。)
( ※ グラフで描けば、こうなる。横軸を Y ,縦軸を C とする。45度線を引いて、それを下方に I だけ移動すれば、「 C = Y−I 」という直線が得られる。45度線よりも傾きの弱い直線 「C = 0.8Y + Cb 」という直線も得られる。二つの直線の交点 B も得られる。交点 B では、状態は普通の景気である。このあと、傾きが 0.8 から 0.7 に低下し、Cb が Ca に減少すると、「 C = Y−I 」という直線との交点 A を得られる。交点 A は、交点 B よりも左下に位置する。交点 A では、交点 B よりも生産量が低い。その差が需給ギャップに相当する。)
( ※ ここではグラフは示さない。次項でグラフを示す。)
このように理解すれば、ケインズの考え方に基づくモデル(修正ケインズモデル)は、マクロ経済のモデルとして、とりあえずは有効である。
このモデルは、モデルとしては簡単すぎるところもあるが、ともかく、簡単なモデルとして、それはそれなりに、おおざっぱに有効である。細かな点では問題があるとしても、基本的な点では核心をつかんでいるからだ。
[ 注記 ]
以上を読んで、「何だ、当たり前じゃないか」と思うかもしれない。しかし、これは序言のようなものだ。
このあと、「修正ケインズモデル」を使って、非常に大きな話に進んでいく。初めのとっかかりは、ごく小さなものにすぎないが、このあと、巨大な話に進むのだ、というふうに心構えをしておいてほしい。
簡単に言えば、「修正ケインズモデル」というのは、「経済を動的に考えること」の、最も単純な形であり、同時に、最も核心的なことである。このこと自体は、小さな芽のようなものにすぎないが、このあと、さらに芽がどんどん成長して、巨大な樹木のようになる。
本日の分は、「なあんだ」と馬鹿にしたりせずに、「基礎中の基礎だ」ということで、深く心に留めておいてほしい。
( ※ 次項では、グラフを示す。そのグラフといっしょに、あらためて理解し直してほしい。)
● ニュースと感想 (8月17日)
「修正ケインズモデル」の位置づけをしよう。それはまた、ケインズ理論の位置づけということでもある。
前項では、「修正ケインズ・モデル」を提出した。それは経済学的には、どういう意味があるか?
すでに示したように、トリオモデルでは経済を動的に考えようとした。つまり、需要や供給の時間的な変化を考えようとした。そして、その単純な形が、修正ケインズモデルで示されるのである。
需要や供給の時間的な変化(動的な変化)というのは、たとえば、次のようのようなものだ。
需要減 → 生産減 → 所得減 → 需要減 → ……
これは、デフレ・スパイラルである。 ( cf. 8月14日 のインフレ・スパイラル。)
ここでは、需要と供給(生産)との「相互影響」が見られる。そして、こういうことは、古典派のモデル(静的な需給曲線だけのモデル)からは得られなかったものなのだ。そういう動的なこと(つまり「相互影響」)が、修正ケインズモデルからは得られるわけだ。
これが「修正ケインズモデル」の位置づけである。つまり、経済の動的な状態を示すモデルである、と。
ただし、この位置づけを結論するには、説明を要する。ケインズの述べたこと(普通の教科書に書いてあること)だけでは、上記の位置づけを結論できない。この位置づけを結論するには、説明が必要となる。その説明を次に述べよう。(かなり大切なことである。)
修正ケインズモデルでは、前項で示したように、2本の直線を引く。では、この2本の直線の「交点」は、何を意味するか? それが問題だ。
( ※ なお、2本の直線は、前項における2個の式に相当する。2番目の式に相当する2番目の直線は、需要の変化[消費性向の変化]に応じて、交替が可能である。一見、消費性向が 0.8 と 0.7 の2本の直線を含めて、計3本の直線が引かれるようにも見えるが、実は、2番目の直線が交替するだけである。)
「この交点は、均衡点である」という説がある。たいてい経済学の教科書では、そう書いていている。しかし、それは正確な記述とは言えない。なぜなら、それを「均衡点」と呼ぶにしても、修正ケインズモデルにおける「均衡点」(交点)と、需給曲線の「均衡点」(交点)とは、別の種類のものだからだ。
たいていの経済学者は、この違いを意識しない。「どっちも、2本の線の交点だ。そこが(方程式の)『解』だ。つまり、そこだけが可能となる点であり、そこ以外では可能とならない。だからどっちも同じようなものだ」と解釈しがちだ。しかし、そうではないのだ。両者はまったく別の種類のものなのだ。
たいていの経済学者はれは、話を数学モデルのレベルで済ませてしまっている。「交点とは方程式の解だ」と言って、それだけで片付けてしまって、そのモデルが何を意味しているかという本質を見失ってしまっている。それでは真実を理解できない。
そこで、本質を考えよう。
(1) 需給曲線における交点
需給曲線における交点は、「ワルラス的調整過程」における均衡点である。これはまさしく、「均衡点」と呼んでいい。次の図を見よ。
この図で、左側の図のように示せる。この一番下の状態が、均衡点である。
この均衡点は、「ここが最も安定的な状態」であることを示す。ここから左右にズレれば、また一番下の均衡点に戻ろうとする。しかし、この均衡点以外の点が、ありえないわけではない。単に「他の点にはなりにくい」「他の点になれば均衡点に戻りたがる」というだけだ。それだけのことでしかないのだ。
このモデルを数学の方程式の問題として解くならば、交点だけが正解となる点として許容され、それ以外の点は不正解の点なして許容されない。しかし、需給曲線の場合は、均衡点だけが「絶対唯一の許容される点」となるわけではない。単に「その均衡点が安定的である」というだけであり、他の点も十分に許容されるのだ。
( ※ ただし、「他の点は安定的ではないので、他の点から均衡点に移りやすい。)
( ※ たとえば、価格が均衡点の価格に比べて高すぎたり安すぎたりすれば、均衡点の価格に収束していく。また、量が多すぎたり少なすぎたりすれば、均衡点の量に収束していく。── 実際、価格には、ある程度のバラツキが生じるものだ。量も、在庫の増減が発生するのを見ればわかるとおり、期間内で増えたり減ったりして、ある程度のバラツキが生じるものだ。いずれにせよ、均衡点以外の状態がある程度は許容される。)
(2) 修正ケインズモデルにおける交点
修正ケインズモデルにおける交点は、ワルラス的調整過程における交点とはまったく異なる。それは、「安定的な状態」というのを意味するのではない。(ここを誤解している教科書が多い。たいていは、前記のように、「どっちも交点だから、どっちの同じようなものだろう」と勝手に思い込んでいる。)
では、本当は、どうなのか? 修正ケインズモデルにおける交点は、(時間の経過につれて発生する)逐次的な変化の「収束点」を意味しているのである。── これは、(変化の落ち着く先の)「収束点」であって、(状態が安定的になる)「均衡点」ではない。
これは、結論である。いきなり結論を出したので、すぐには理解できないだろう。そこで、以下で、詳しく説明する。
そもそも、動的に考えると、本項の最初に述べたように、
需要減 → 生産減 → 所得減 → 需要減 → ……
というスパイラルが生じるものだ。このスパイラルは、修正ケインズモデルでは、どう解釈されるか? それは、2個の方程式の循環として解釈される。
C = Y−I
C = 0.8Y + Cb
C = 0.7Y + Ca
1番目の式と2番目の式の交点が B である。(需給ギャップなし)
1番目の式と3番目の式の交点が A である。(需給ギャップあり)
B は、A よりも、右上にある。
さて。初めに、B という点にあったとする。そのあと、消費性向が低下して、2番目の直線から3番目の直線に、状態が変化したとする。すると、どうなるか?
「交点 B から 交点A に移る」というのが、従来の解釈である。それはそうだろう。しかし、そういうふうに移行するにしても、それは、「交点AがBよりも安定的だから」ではない。別の理由がある。
そしてまた、「交点 B から 交点A に移る」にしても、その移行は一挙になされるわけではない。その移行には、逐次的な過程がある。では、どんな過程か? それは、次のようなものだ。
- まず、交点 B の状態にある。そこで C と Y が定まる。ここでは、1番目の直線と2番目の直線がともに成立している。(両者の交点だから。) このときの C と Y の値を C1 および Y1 と書く。
- 需要が縮小する。すると、2番目の直線から3番目の直線に、直線が交替する。
- ここでは、生産量は B 点のときと同じ Y(つまり Y1 )であるが、消費は、同じ Y に対して、「 0.8Y + Cb 」から「 0.7Y + Ca 」へ、減少する。この C を C2 と書く。
- この C2 に対し、 「 C = Y − I 」(つまり Y = C + I )から、新たな Y の値を得る。その Y を Y2 と書くことにする。これは縮小した需要(C2 )に対応する生産量(Y2 )である。
- Y2 は、生産量であると同時に、所得である。この Y2 という所得に、1番目の式を適用すると、第3項と同様にして、新たな消費の値「 0.7Y2 + Ca 」を得る。これを C3 と書く。
- この C3 に対して、第4項を適用する。それで得た値 Y3 に、第5項を適用する。
- 同様のことを繰り返す。すると、生産(所得)は、
Y1 → Y2 → Y3 → ……
というふうに減少していく。消費は、
「 0.7Y1 + Ca 」 → 「 0.7Y2 + Ca 」 → 「 0.7Y3 + Ca 」 → ……
というふうに減少していく。
こういう逐次的な過程がある。そしてこれは、「デフレスパイラル」そのものである。すなわち、
「生産(所得)の縮小」 → 「需要の縮小」 → ……
というふうに、無限循環する過程があるわけだ。
では、この無限循環の過程は、最終的には、どうなるか? 生産も消費も無限に縮小するか? 違う。循環のはてに、1点に収束する。その収束する先が、「交点 A」である。そのことは、図を描いてみれば、すぐにわかるだろう。
この収束点。それが「交点 A」だ。そこは、ワルラス的調整過程における「安定的な位置」ではなくて、「スパイラル(無限循環)の収束する先」であり、「需要と供給の相互影響のはての最終的な落ち着き場所」である。
それゆえ、修正ケインズモデルにおける「交点 A 」は、「均衡点」と呼ぶよりは、「収束点」と呼ぶ方が正確である。そこで、以後は、「収束点」と呼ぶことにしよう。
ここで大事なことは、次の2点である。
- (i) 交点 A は、「均衡点」ではなくて、「収束点」である。収束点は、「最も安定的な状態」のことではなく、「相互影響が繰り返されたはてに最終的に落ち着く場所」のことだ。換言すれば、収束点は、「静的なモデルの安定点」ではなく、「動的なモデルにおいて時間的な変化を見たときの最終的な到達点」である。
- (ii) 修正ケインズモデルでは、時間的に無限循環(スパイラル)が発生するが、その無限循環のはてに、収束する。つまり、発散することはなく、ゼロになることもなく、一定の値に留まる。── その収束する先が、「収束点」である。
ともあれ、以上によって、需要と供給(生産)との「相互影響」が明らかになったわけだ。これによって経済の動的な変化がわかった。── それが修正ケインズモデルのもたらしたことだ。
( ※ より詳しい意味は、翌日以降で。)
● ニュースと感想 (8月18日)
8月17日 の最後では、「修正ケインズモデル」に関して、 (i) ,(ii) の2点を示した。この2点について、さらに詳しく説明するべきことがあるので、本項以降で示そう。 [ (i) は、このあと4日間ほど。(ii) は、それ以後で。]
(i) を再掲すれば、次のとおり。
交点 A は、「均衡点」ではなくて、「収束点」である。収束点は、「最も安定的な状態」のことではなく、「相互影響が繰り返されたはてに最終的に落ち着く場所」のことだ。換言すれば、収束点は、「静的なモデルの安定点」ではなく、「動的なモデルにおいて時間的な変化を見たときの最終的な到達点」である。
このことについて、さらに説明しよう。「均衡点」と「収束点」の違いに関しては、このあと数日間、いろいろと説明するが、本日はまず、次の 《 I 》 と 《 II 》 の違いを示す。
《 I 》 到達時間
需給曲線における「ワルラス的調整過程」のはてに到達する「均衡点」なら、そこでは単なる「ワルラス的調整過程」が働くだけだから、ミクロ的に簡単に片付く。しかるに、「修正ケインズモデル」における階段状の経路をたどったはてに到達する「収束点」なら、途中でマクロ的なスパイラル的な過程が働く。こちらは簡単に片付くことはない。
そのことは、必要な時間の大小となって現れる。つまり、「均衡点」に到達するための時間はごく短いが、「収束点」に到達するための時間はかなり長い。── そのことを具体的に示そう。
(1) 均衡点
「均衡点」に到達するには、ほとんど時間がかからない。
たとえば、同じ商品で別々の価格がついていれば、たいていは1日かそこらで価格が修正されて、同じ価格になるものだ。「他店よりも1円でも高ければ値引きします」という店なら、瞬間的に値引きが実現して、同じ価格になる。一般に、高い価格の店では売れ残るので、しだいに価格は下がる。安い価格の店では、品切れになるので、その価格の商品は消える。かくて、「一物一価」が実現する。そして、その価格で均衡する。(実際には、いくらかのバラツキは残るが。)
(2) 収束点
「収束点」に到達するには、かなり長い時間がかかる。
需要の縮小が発生するのは、短い時間で済む。(消費性向の低下が起こるだけだ。これは心理的なものだから、短い時間で澄む。)
しかし、そのあとが問題だ。縮小した消費にともなって、生産や所得の縮小が発生するには、時間がかかる。まずは「在庫の積み増し」が発生する。つまり、生産はなかなか縮小しない。
また、いったん生産が縮小しても、それが所得の減少に結びつくには、かなり時間がかかる。(残業手当の減少は、1カ月単位。ボーナスは、半年単位か1年単位。賃下げなどは、1年単位。いずれも、かなりの時間がかかる。)
というわけで、修正ケインズモデルでは、階段状の経路をたどるには、かなりの時間がかかる。収束点は、「最終的な極限値」のようなものだから、「実際にはそこには到達できない」とか、「収束点に近づく過程が永遠に続く」(いまだ移行中)とか、そういうふうに解釈する方がいいだろう。
( ※ この件、後日の[ 参考 ]の「アキレスと亀」を参照。)
《 II 》 経路の阻害
「修正ケインズモデル」では、階段状の経路をたどることが阻害されることがある。つまり、経路が中断して、収束点にたどりつけないことがある。そのことを示そう。
(1) 均衡点
「均衡点」ならば、こういう中断はありえない。「ワルラス的調整過程」が働くときには、その均衡点に到達するのが原則だ。
例外的に、均衡点に到達しないとしたら? それは、寡占や独占によって、不完全競争になっている場合が考えられる。しかし、それはそもそも、市場経済が正常に働いていない場合だ。市場経済が働いている状態であれば、原理的に、均衡点に到達するはずだ。
(2) 収束点
「収束点」ならば、どうか? 収束点に到達せず、途中で経路が中断することがある。収束点に到達するためには、階段状の経路がすべて正常に機能する必要があるのだが、そうならず、経路をたどることが阻害されることがあるからだ。
それは、生産の増減が、所得の増減に、うまく反映しない場合だ。これは、「賃金の硬直性」と言い換えることもできる。具体的には、次の2つの場合がある。
- 生産が縮小するとき
生産が縮小したら、その分、所得が減少するはずだ。しかし実際には、そうなるとは限らない。賃金には下方硬直性があるので、所得は下がりにくいのだ。
だから、階段状の経路をたどろうとしても、変化すべき割合が減ったりして、ぐずつくことになる。その分、マクロ的には、景気悪化の速度が遅くなるわけだ。
( ※ これには、良い意味と悪い意味の、二つがある。「企業が賃下げを少な目にする」というのは、景気悪化の進行を遅らせるので、マクロ的には良い意味がある。しかし、それが過度になると、「赤字なのに、無理をして、賃下げをしない」ことになる。すると、かえって企業が倒産して、悪い意味となる。)
- 生産が拡大するとき
生産が拡大したら、その分、所得が増加するはずだ。しかし実際には、そうなるとは限らない。それは、企業が生産を拡大して利益を得ても、労働者に分配しないで、企業が利益を独占する場合だ。
こうなると、もちろん、景気拡大のスパイラルが発生しない。特に、不況からの景気回復のとき、企業が利益から労働所得への配分をケチると、景気回復のスパイラル効果がそがれる。( → 8月14日 の、トヨタの例。どこかの小さな1企業だけがやるなら問題はないが、業界のリーダーとしての会社がそうすることで自社の行動を全企業に波及させるとマクロ的に問題が生じる。)
以上、「生産縮小」と「生産拡大」のいずれの場合も、スパイラル的な過程(階段状の経路をたどること)が阻害される。特に、「生産縮小」の場合には、収束点に向かっていくとき、収束点になかなかたどりつかないことになる。
( ※ 「均衡点」ならば、そこにすぐにたどりつけるのだが、「収束点」ならば、そこになかなかたどりつけない、ということ。)
[ 補足 ]
ついでに余談ふうに、少し補足しておこう。 《 II 》 で述べたトヨタの例についての話題だ。
企業が利益を労働者に配分しなければ、「所得増 → 生産増」という景気回復のスパイラル過程が阻害される。……これが、《 II 》 で述べたことだ。(トヨタがその例。)
これについて、次のような反論があるはずだ。
「所得というのは、労働者の所得とは限らず、企業の所得もある。別に、労働者へ利益を配分しなくても、企業が利益を上げれば、(マクロ的に国民全体を見たときの)所得はあるはずだ。だから、所得増加によるスパイラル的な過程は、あるはずだ」
この反論は、話の前段は正しい。しかし、後段が正しくない。つまり、「だから〜」以降が正しくない。
たしかに、企業が利益を得れば、それはそれで、所得は増加していることになる。ただし、その分の金が、需要増加に反映しないのだ。
労働者ならば、給与が増えれば、限界消費性向の分だけ、支出が増える。しかし企業は、そうではない。利益を上げても、限界消費性向の分だけ、支出を増やすわけではない。その利益は、単に「内部蓄積」に回されるだけだ。そして、内部蓄積に回された金は、銀行の預金になるだけだから、金は眠ってしまう。だから、その利益がスパイラル的に生産を拡大する効果はないわけだ。
もう少し正確に言おう。企業が利益を上げたとき、景気が好況ならば、企業は投資を増やす。しかし景気が不況ならば、企業は投資を増やさない。すると、金は内部蓄積に回されて、金は眠る。
たとえば今、トヨタが 5000億円の利益を上げて、その 5000億円を労働者への配分に回せば、それに応じた分、労働者の支出は増える。さらに、トヨタを見た他社も労働者への配分を増やすから、国全体では、数兆円の個人消費拡大の効果がある。それがさらに、スパイラル的に増えて、その何倍かの経済拡大の効果が発生する。
一方、トヨタが 5000億円の利益を上げて、その 5000億円を内部留保に回せば、経済は少しも拡大しない。つまり、企業の所得については、「限界消費性向の分だけ投資が増える」とは言えないわけだ。
( ※ どうせなら、トヨタが利益をゼロにすれば、製品が値下がりするので、他の商品の消費が増えるはずだ。だから、トヨタが利益を上げれば上げるほど、トヨタの内部留保ばかりが増えて、銀行に眠る金ばかりが増えて、景気はどんどん悪化していくわけだ。……これはまあ、当たり前の話である。企業が成長するためには、消費者としての中産階級が必要不可欠である。中産階級の金を奪えば奪うほど、売上げが伸びなくなって、その国の産業は伸び率が低下する。これは、中南米でよく見られる例だ。一部の特権階級が富を独占し、大衆は貧困。だから産業が育たない。……トヨタがめざしているのは、そういう中南米状態なのだろう。日本のアルゼンチン化。さすがに、経団連の会長を出す会社は、考えることが違う。)
( ※ 余談だが、政府の「法人減税」の方針は、規模が1兆円。トヨタの年間利益は、5000億円。以前に比べて、倍増で、大儲け。なのに、労働者への賃上げは、ほぼゼロ。……だから、政府が景気対策するよりは、トヨタが景気対策をする方が、ずっと効果がある。国よりもトヨタの方が、はるかに景気への影響力をもつ、というわけ。皮肉な話だが。……ま、小泉としては、国家予算をあれこれいじるより、トヨタの労組の頬をひっぱたいて、「ストライキをやれ」と言った方が、よほど景気回復の効果があるはずだ。悪いのは、トヨタの経営者ではなくて、トヨタの労組なのだから。小泉にその度胸がないのなら、トルシエにでも頼むべし。)
( ※ 冗談だと思われると困るので、核心を示そう。本質的に言えば、「不況」とは、「金が眠ること」である。個人が消費せずに金を貯蓄する。企業が投資せずに金を内部留保に回す。こうして貯蓄ばかりを増やして、需要も生産を増やさない状況が、「不況」である。── だから、トヨタのように利益を上げた企業が、内部蓄積という倹約に励めば励むほど、不況はどんどん悪化していくのである。「トヨタが内部蓄積を増やすのは、企業として当然のことだ」と是認する阿呆もいるが、それは、「不況のときに個人が貯蓄をするのは、個人として当然のことだ」と是認するのと同様である。それはまた、「不況のときには、不況を悪化させるのが当然のことだ」と是認するのと同様だ。問題は、当然とかどうかとかではなくて、何とかして不況から脱することなのだ。現状を是認するだけなら、猿でもできる。)
● ニュースと感想 (8月18日b)
前項(本日別項)の続き。
前項では、「均衡点」と「収束点」の違いについて説明した。ここで、解説しておこう。なぜ、この二つの違いに注目するべきか、ということだ。
それは、この二つのものは本質的に違うのにもかかわらず、同じようなものであると誤解されているからだ。
たいていの経済学書を見るといい。「二つの線の交点は、均衡点だ」というふうに、簡単に片付けられている。「需供曲線の交点も、ケインズのモデルの交点も、どちらも二つの線の交点であり、均衡点である」というふうに。(前項の冒頭では、「方程式の解」とか「可能な点」とかいうふうに述べた。)
しかし、そうではないのだ。この二つは、まったく別のものなのだ。換言すれば、ケインズのモデルについての、従来の経済学における解釈は、間違っているのだ。
そのことを示すために、前項の 《 I 》 と 《 II 》 で説明してきたわけだ。
[ 付記 ]
ついでに、数学的な説明を加えておこう。(特に読まなくてもよい。)
(1) 均衡点
「ワルラス的調整過程」における「均衡点」。これは、(需要と供給の)二つの曲線の交点である。ここでは、二つの曲線がともに成立することを意味する。── だから、この点は、単純に「方程式の解」と理解される。
(2) 収束点
「修正ケインズモデル」における「収束点」。これは、点 B から出発したあと、点が時間的にどんどん移行していったすえの、最終的な到達点(A)である。
実際に点が存在するのは、二つの直線の上ではなくて、階段状の線の上である。二つの直線は、点が移行していく途上の「壁」にすぎない。いわば、ビリヤードの球が、壁に跳ね返されて、次々と動いていって、最後には、ある点に落ち込むようなものだ。
二つの直線は、「条件を満たす点の集合」ではない。だから、点 A は、単純に「方程式の解」と理解するべきではない。むしろ、「級数を解こうとしたら、その問題が、(グラフを仮想線とした)方程式と等価になった」「ゆえに求める位置が解けた」というふうに解釈するべきだろう。
● ニュースと感想 (8月19日)
「均衡点」と「収束点」の違いについて、引きつづき考えよう。
前項で述べた違いは、「外形的」な違いと言ってもいい。数学的にモデルの動きを計算すると、機械的にわかる。 (数学的には、「収束点」というのは、収束する関数や数列の極限値である。)
一方、「内容的」な違いもある。これは、ちょっと見ただけではわからないが、いっそう大切なことである。それを述べよう。
「均衡点」と「収束点」の違いで、一番大切なことは何か? それは、「均衡点はそこに至るのが望ましいが、(交点 A という)収束点はそこに至るのが望ましくない」ということだ。換言すれば、「均衡点は、最善の点だが、(交点 A という)収束点は、最悪の点である」ということだ。
( ※ 念のために補足しておく。「収束点」が常に最悪であるとは限らない。景気悪化の場合においては、「収束点」は交点 A である。交点 A は、悪化の過程の極限値であって、最悪の点である。ただし、景気悪化ではなくて景気回復の過程では、別の意味の収束点も考えられる。これについては、後日また考察する。)
さて。上記のような意味で、「均衡点」と「収束点」(交点 A )とは、まったく正反対のものだ。このことは非常に大切なことだ。決定的な違いがあると言ってもいい。天国と地獄ほどの差がある。
しかるに、これまでの経済学は、この決定的な違いを理解しなかった。「どちらも均衡点だろう。だからどちらも、自然にそこに至るはずであり、そこに至るのが当然なのだ」というふうに是認してきた。しかし、そうではないのだ。
そのことを説明しよう。
まず、均衡点だが、これが「望ましい点」「最善の点」だというのは、当然である。「下限直線」に阻害されて、そこに届かないこともあるが、そういう場合には、「需要曲線を左シフトする」とか、「供給曲線を右シフトする」とか、「下限直線を下シフトする」とか、そういう工夫をして、何とか、均衡点にたどりつくように努力すればよい。……とにかく、「均衡点に届くことが大切だ」というのは、従来の経済学でも、トリオモデルによる経済学でも、事情は同じである。
次に、収束点(交点 A )だが、これは、「望ましい点」「最善の点」であるどころか、むしろ、「望ましくない点」「最悪の点」である。なぜか? それは、この点の意味を考えてみれば、すぐにわかる。先のグラフにおいて、点 A というのは、「デフレスパイラルの最終到達点」である。それは、「もうこれ以上は悪くならない点」である。つまり、「最悪の点」である。……形の上では、一見、均衡しているように見えるが、その実状は、「これ以上は悪くはならない」という、どうしようもない状態だ。
だから、「この地点にたどりつこう」とするのは、「景気を一挙に最悪の地点まで景気を悪化させよう。景気をどん底状態にさせよう」ということだ。そして、「どん底では、均衡している。どん底こそ、すばらしい状態だ」と述べるのが、従来の経済学だ。
むしろ、本当は、「この地点にたどりつくまい」とするべきなのだ。「景気が悪化しつつあるのなら、なるべく悪化の度合いを遅らせよう」とか、「最悪にたどりつかないうちに、一刻も早く最悪から遠ざかろう」とか、「この蟻地獄のようなデフレスパイラルの状態から、何とか脱しよう」とか、そういうふうに努力するべきなのだ。つまり、収束点に向かう力に反抗するべきなのだ。
結局、「均衡点と収束点」には、「天国と地獄」ないし「白と黒」と言えるぐらいの、大きな差がある。だから、両者をはっきりと区別しなくてはならない。「収束点」を「均衡点」と名付けるような立場は、真実を見誤っているのだ。
「均衡点」と「収束点」は、「そこが安定的である」という共通点はある。つまり、「そこに状態が引き込まれていく」という共通点はある。(どちらもブラックホールようなものだ。) そういう意味で、外見的にはいくらか似ている。しかし、内容的には、まったく別のものなのだ。この本質的な違いを、はっきりと理解しておく必要がある。
[ 余談 ]
たとえ話を示そう。
「絶世の美女との結婚こそ、最高の幸せだ。これ以上はありえぬ極限的な状態だ。そこでは安定していられる。それがほしい!」と男は叫んだ。
「よろしい」と悪魔が答えた。「それと同じものをあなたに与えましょう。これ以下はありえぬ極限的な状態だ。そこでは安定していられる。それを与えます。さあ、死ね!」
男は、均衡点を望んで、かわりに収束点を得た。最高の状態を望んで、かわりに最悪の状態を得た。しかし彼は、その違いがわからず、満足した。なぜなら彼は、経済学者だったからである。
[ 注記 ]
この例では、「収束点 = 最悪の点」となる。ただし、これは、「悪化していく過程における収束点」だからである。「悪化していく過程」でなければ、「収束点 = 最悪の点」とはならない。……このことについては、後日また述べる。
( ※ 「収束点」というのは、単に数列などの極限値を意味するにすぎない。それが内容的にどういう意味をもつかは、過程が「悪化していく過程」であるかどうかによる。悪化していく過程であれば、行きつく先は「最悪の点」である。)
● ニュースと感想 (8月19日b)
「アキレスと亀のパラドックス」という有名な話がある。これについて、余談ふうに示しておこう。(特に読まなくてもよい。)
なお、ここで主張したいことは、「収束点に至るには、無限の回数がかかる」ということである。
( ※ 以下の本文では、パラドックスについて説明する。そのあとの [ 補説 ] では、経済学との関連を説明する。)
「アキレスと亀のパラドックス」というのは、次のような話だ。
“ 亀が時速2キロで進む。アキレスが時速4キロで亀を追う。するとアキレスはいつまでたっても亀に追いつけない。なぜなら、アキレスが1メートル進むと、亀は 1/2 メートル進む。アキレスがまた 1/2 メートル進むと、亀は 1/4 メートル進む。アキレスがまた 1/4 メートル進むと、亀は 1/8 メートル進む。……これが無限に繰り返されるので、アキレスはいつまでたっても亀に追いつけない。”
この話は、もちろん、おかしい。アキレスが亀に追いつけないということはない。
では、この論法は、どこがおかしいか? 論理自体は、おかしくない。おかしいのは、言葉の使い方だけだ。言葉に二重性があるので、一見、矛盾のように見えるだけだ。
その言葉は、「いつまでたっても」という言葉だ。これは、「回数が無限に」という意味と、「時間が無限に」という意味と、双方がある。その二つを混同しているわけだ。上記の論法では、回数は無限だが、時間は有限だからだ。
「いつまでたっても」というのを「回数」の意味で解釈するのならば、上記の主張は正しい。こういう論法の回数を無限に繰り返しても、アキレスは亀に追いつけないからだ。
「いつまでたっても」というのを「時間」の意味で解釈するのならば、上記の主張は正しくない。論法の回数は無限だが、論法の1回にかかる時間は 1 ,1/2 ,1/4 ,……というふうに、どんどん小さくなっていくからだ。無限小が無限個集まったすえに、有限の時間ができる。それはそれで、矛盾はない。
結語。
「いつまでたっても、追いつけない」というふうに語るのは、「いつまでたっても」という言葉が曖昧(両義的)であったわけだ。
・ 「論法の回数をどんなに増やしても、追いつけない」というのならば、正しい。
・ 「時間をどんなに増やしても、追いつけない」というのならば、正しくない。
この両者(回数と時間)を混同すると、パラドックスが生じるわけだ。あるときは回数だと解釈し、あるときは時間だと解釈するからだ。
( ※ たとえ話 : 一人の人間を、あるときは男だと解釈し、あるときは女だと解釈すれば、矛盾が発生する。)
[ 付記 ]
もうちょっと本質的に示せば、このことは、数学の「区間縮小法」と同じである。
f n = 1/2n
と置いて、
1 , 1/2 , 1/4 , 1/8 ,…… , 1/2n ,……
というふうに、区間の幅を半分ずつに縮めていく。1だった区間幅が、どんどん無限小に近づいていく。これがつまり、「アキレスと亀」の距離に相当する。
だから、「アキレスはいつまでたっても亀に追いつけない」というのは、「人は1メートルの距離をいつまでたっても進めない」というのと同じである。
これは、数学における「無限大」の論議と同じである。「有限をいくら増やしても、無限大には達せない」(ただし無限大を一挙に実行すれば、無限大に達せる。)
[ 補説 ]
以上は、「アキレスと亀」の話だった。このあと、経済学と対比させよう。
上記の例では、「アキレスが亀に、いつまでたってもたどりつけない」ということはない。なぜなら、先の方に進むにつれて、距離が小さくなり、それにつれて、かかる時間も小さくなるからだ。
一方、「修正ケインズモデル」においては、「収束点にたどりつけない」ということはある。なぜなら、(階段状の経路の)距離が小さくなっても、かかる時間は小さくならないからだ。(所得と生産との相互影響が発生するのためには、金額の多少に関わらず、一定の時間が必要である。通常、1年かそこら、必要だ。)
というわけで、収束点にたどりつくには、「1年 × 無限回」つまり「無限の時間」がかかる。だから、「修正ケインズモデル」においては、「アキレスと亀」とは違って、「いつまでたっても収束点にはたどりつけない」ことになるわけだ。
( ※ ただし、現実には、ある程度までは近づくので、あまり意味はないかもしれない。それでも、「収束点に近づくまで、何年間もかかる」ということは、しっかりと理解しておいた方がいいだろう。)
● ニュースと感想 (8月19日c)
「均衡点」と「収束点」の違いについて、これまでいろいろと示してきた。ざっとまとめれば、次の通り。
- 均衡点
「ワルラス的調整過程」における「均衡点」は、自然にその状態に落ち着く。
その状態にたどりつくまでに必要な時間も短い。
- 収束点
「修正ケインズモデル」における「均衡点」は、スパイラル的な過程のはてにたどりつく到達点である。
- そこに到達せずに、途中で阻害・中断されることがある。
- そこに到達するまでに、「所得」による影響が何度も必要である。そのたびごとに、かなりの時間を要する。
- 到達点にたどりつくまでには、無限のスパイラル的過程を経るための、無限の時間が必要である。(事実上、到達できない。)(アキレスと亀。)
[ 付記 ]
以上は、外形的な話。内容的には、「最善/最悪」という違いもある。このことは、前々項で述べたとおり。
● ニュースと感想 (8月20日)
「修正ケインズモデル」と「トリオモデル」との関係について。
「修正ケインズモデル」について、いろいろと述べてきたが、これと「トリオモデル」との関係について考えよう。特に、「均衡点」のことをめぐって考える。
左点と右点は、「トリオモデル」と「修正ケインズモデル」とで、どう示されるか? まず、これを考えよう。
(1) トリオモデル
「トリオモデル」では、「需給ギャップ」は、「∀」という形の水平線部分である。
また、この水平線部分の左端が「左点」であり、右端が「右点」である。(定義。)
(2)修正ケインズモデル
「修正ケインズモデル」では、右点は、需給ギャップの発生する直前の均衡点だから、交点 B である。このときの生産量と、現実の生産量との差が、「需給ギャップ」になる。
では、現実の生産量とは? 第1期には、交点 B の真下の交点。(縮小した消費の分しか生産されないので。)
その交点から左に移った交点が、第2期の所得である。その真下の交点が、第2期の消費であり、第2期の生産である。
( ※ このあたり、8月17日 の記述を参照。)
さて。左点は、「縮小した消費の分だけの生産量」、つまり、「現実の生産量」だが、それは、グラフでは、「 C = 0.7Y + Ca 」という直線の上で、
「交点Bの真下」 → 「次の点」 → 「次の点」 → …… → 「 交点A 」
というふうに、次々と移動していく。(いずれも、青い垂直線の根元。値は、横軸の Y を見る)
一方、右点は? こちらは、交点 B のまま、不変である。
となると、「需給ギャップ」は、「右点の生産量 − 左点の生産量」だから、上の青い水平線の量を次々と加算していった値となる。その値は、時間につれてどんどん増えていき、交点 A に達したとき、最大値(極限値)となる。
まとめれば、こうだ。── (消費性向の低下によって) いったん需給ギャップが発生すると、スパイラル的に需給ギャップは拡大する。その拡大には、(極限としての)最大値がある。
( ※ グラフで具体的に示そう。交点 B の生産量を Yb と書き、交点 A の生産量を Ya と書く。Yb は、グラフでは Y1 と同じである。さて、このとき、スパイラルが進行するにつれて、生産量は、
Y1 → Y2 → …… → Ya
というふうに変化していく。
需給ギャップは、「 Y1 − Yn 」であり、その最大値が、「 Y1 − Ya 」( = 「 Yb − Ya 」)である。これが「需給ギャップ」の最大値となる。)
( ※ 縦軸と横軸の関係について示しておこう。「 C = Y − I 」という直線の傾きが45度であることに注意するとよい。すると、青線を ┘ という形の組み合わせと見たとき、その縦線と横線との長さは同じである。たとえば、一番最初に交点 B から出た直後の青い縦線と、その次の青い水平線は、長さが等しい。ケインズのモデルでは、縦線の方に注目しているが、修正ケインズモデルでは、横線の方に注目している。実質的には、同じこととなるが。)
[ 付記 ]
この件、普通の経済学の教科書に記してあることとは、少し異なる。
普通の経済学の教科書では、「修正ケインズモデル」ではなくて、ケインズのモデルに従っている。それによると、交点 A は、収束点ではなくて、均衡点であるから、速やかにそこに達することになる。つまり、「修正ケインズモデル」における「需給ギャップの最大値」に、さっさと到達することになる。というか、すでに到達してしまっていることになる。 ( cf. 8月15日 ,8月16日 )
実を言うと、ケインズのモデルでは、「動的な変化」「時間的な変化」ということは、あまり考えない。「すでに不況の最悪点に達してしまっている」というふうに考えるのであって、「不況の最悪点に達する途上の過程」というのは、考えない。
「経済を動的にとらえる」という最も肝心な問題に対して、その基本となるモデルを、ケインズは実質的に提出したも同然だ。ケインズは、それだけの成果を上げたのだ。なのに、その成果を、みすみす取りこぼしてしまったわけだ。
そして、それというのも、そもそもの話、「経済を動的にとらえる」という視点が欠けていたからである。だから、手に入れたものが何であるかを理解できないまま、数学的な解釈もわからないまま、宝の持ち腐れにしてしまったのだ。
その腐った宝を磨いて、ピカピカに仕立て直したのが、「修正ケインズモデル」である。これは、「一次関数をグラフ化する」という、中学生レベルのことをやれば、誰でもわかるはずだ。また、ケインズの方法が、循環的な方法を採っていて、数列の一種としてとらえられるということも、高校生レベルの数学でわかるはずなのだ。にもかかわらず、これまで、経済学者たちは、そういうことをやらなかった。
結局、従来の経済学が間違っていたのは、経済学者には、中学・高校レベルの数学を使えなかったからなのだ。
( ※ 実を言うと、もう一つ、「消費性向の変化」という点に、彼らは気づかなかった、という点もある。)
● ニュースと感想 (8月20日b)
前項の続き。
前項では、「トリオモデル」を参照して、「修正ケインズモデル」の意味を考えた。今度は逆に、「修正ケインズモデル」を参照して、「トリオモデル」の意味を考えてみよう。
そもそも最初の課題は、「経済を動的にとらえること」だった。では、その観点から、「トリオモデル」を動的にとらえると、どうなるか?
前項で知ったことをもとにすれば、次のように結論できる。
トリオモデルで動的に考えると、右点は変化しないまま、左点がどんどん左に移動していき、需給ギャップが拡大していく。(「∀」の水平線部分がひろがる。) ただ、その動きはだんだん遅くなり、最終的には、一定の需給ギャップになったところで頭打ちになる。
[ 付記 ]
「修正ケインズモデル」では、右点は変化しないと見なしている。ただ、「供給力」を変化させよう、という政策もあるだろう。
「供給力を削減すれば、需給ギャップは解消して、不況は解決する」というアイデアがある。これは、「縮小均衡」と呼べる。しかし、「縮小均衡はダメだ」ということは、すでに説明した。そちらを参照。( → 8月06日 )
( ※ 上では、「そちらを参照」と書いたが、いちおう記しておくと、こうだ。……「商品が売れなきゃ、工場をぶちこわしてしまえ」なんてのは、ヤケのやんぱちであって、正気の沙汰ではない。こんなことは、まともな頭があれば、すぐわかる。逆に、「供給を拡大せよ」という政策もある。サプライサイドないし構造改革。これは、まともでないというよりは、論理倒錯であって、狂気。)
● ニュースと感想 (8月20日c)
前項の続き。
本日別項の、前々項 と 前項では、同じことを、「トリオモデル」と「修正ケインズモデル」の双方で表現しただ。こうして述べたことから、二つのモデルの関連がわかるだろう。
これは重要なことである。なぜなら、古典派の市場経済原理(トリオモデルによる)と、ケインズの需給ギャップ発生の原理(修正ケインズモデルによる)が、関連づけられたことになるからだ。
結局、「古典派とケインズ派の統合」が、部分的になされたことになる。
[ 付記 ]
「トリオモデル」と「修正ケインズモデル」とでは、一長一短があることがわかる。
・ 経済を静的にとらえるには、トリオモデルの方が適している。
・ 経済を動的にとらえるには、修正ケインズモデルの方が適している。
ただ、一般的には、こう言える。── 経済を静的にとらえるのは簡単であるが、経済を動的にとらえるのは困難である。前者(静的)は、簡単な真実なので、たやすく真実に達せる。後者(動的)は、複雑な真実なので、なかなか真実には達せない。
なお、修正ケインズモデルの方は、経済を動的にとらえることができるが、これは「完璧」というわけではない。事実を単純化した上で、単純なモデルを使っているにすぎない。
現実には、現実の経済は、これほど単純ではない。だから、現実の経済をもっと正しく扱うには、修正ケインズモデルをもっと拡張していく必要がある。
この件は、今後の議論となる。(数日後から。)
● ニュースと感想 (8月21日)
「修正ケインズモデル」からは逸れるが、本項では非常に重要なことを述べる。それは、
「不況の本質は何か?」
ということだ。不況とは、なぜ、単に経済が縮小しただけでは済まずに、悪い状況となるのか? 「過剰消費」をする拡大しすぎの経済が縮小しただけなら、別に問題はないはずなのに、なぜ、それだけでは済まずに、不幸な状況となるのか?
( ※ この問題は、「均衡点」や「収束点」の問題と、密接に関連する。そこで、「修正ケインズモデル」の話題からは逸れるが、本日はこの話題について述べる。)
まず、初めに、次の問題を立てる。
「トリオモデルにおける左点は、均衡点なのか?」
これは、「均衡点」や「収束点」の問題だ。そして、この問題を突き詰めていくと、「不況の本質は何か」という問題への回答が与えられるのだ。
では、以下では順に、いろいろと考えていこう。
「トリオモデルにおける左点は、均衡点なのか?」── これが問題である。これについて考えていこう。
まず、「左点が収束点であるか?」ということについては、前日分で示したとおりだ。左点は、「縮小した消費」に対応する直線上を移動する点である。それが行きついた先に、「収束点」がある。(行きついたあとでは、左点と収束点は、一致する。)
一方、「左点がどういう状況であるか?」ということについては、以前、考えたことがある。8月04日 がそうだ。そこでざっと示したのは、次のことだ。── 左点というのは、「一時的に小康を得ているが、一刻も早くそこから脱したい」ような状況なのである。そこは、マイナスを最小にしているので、次善の状態となっている。しかし、しょせんはマイナスの状態だから、さっさとそこを脱して、プラスの領域に移行したいのである。
このことについて、8月05日 では、「平均費用」と「限界費用」という用語で説明した。ただ、この二つの用語を使うと、実は、もっと明確に説明することができるのだ。
では、いよいよ、説明を始めよう。
(1) 安定的か否か
「トリオモデルにおける左点は、均衡点なのか?」
というのが肝心の問題だ。これについて考えてみよう。
左点は、「ワルラス的調整過程の均衡点」という意味では、均衡点となっていない。それは、当たり前だ。左点は、「∀」という形において左方の交点に位置する。「ワルラス的調整過程の均衡点」という意味での均衡点は、「∀」という形において下方の頂点に位置する。両者はまったく別のものだ。
では、左点は、別の意味で(何らかの)均衡点となっているだろうか? これについては「イエス」という答えが出そうに思える。実際、経済学の教科書では、修正ケインズモデルにおける交点 A (これも左点に相当する)について、「均衡している」と記述してあるのが普通だ。というのは、そこでは需要と供給が一致していて、ともにそこから離れようとしないからだ。そういう意味で、「均衡している」と見なすわけだ。
しかし、これは適切な解釈ではない。たしかに、左点では需要と供給が一致していて、そこから離れようとしない。そういう意味では、「安定的」である。一応は。しかし、そこでは、「真に安定している」わけではないのだ。
このことについては、すでに8月04日 に述べた。需給ギャップが生じたとき、左点と右点との間で、状況は(落ち着かずに)不安定的になっているのだ。
つまり、左点にいちおう落ち着いているようだが、実際には、左点に行ったり、右点に行ったり、その中間に位置したりで、不安定になっているのだ。なぜなら、左点というのは、しょせんは赤字を出す状態であり、そこは企業にとって存続可能な状態ではないからだ。
結局、左点というのは、安定した点ではないのだ。単に「小康」を得ているだけなのだ。一見、安定しているように見えても、実際には、その間も、赤字がどんどん蓄積していく。いわば、癌患者で、癌の病巣がどんどんひろがっていくように。それは、「生きている」状態というより、「死につつある」状態である。「まだ死んでいない」のはたしかだが、「明日にも死ぬかもしれない」のだ。そういう状況を、「安定している」と呼ぶべきではないのだ。
結局、左点が「安定的ではない」ことはわかった。では、左点は「均衡点ではない」と言えるのか?
これについて考えるには、「均衡」というものをよく理解する必要がある。「均衡」というのは、相反する二つのものが釣り合っていることを言う。では、どのような二つのものが?
そのことは、次の (2) でわかる。
(2) 下向きの力と上向きの力
重要なことを示そう。
左点では、二つの力が働いているのだ。すなわち、下向きの力と、上向きの力である。(なお、下向きか上向きかは、価格に関して。)
- 下向きの力
下向きの力は、「ワルラス的調整過程における均衡点に届こう」とする力である。
そもそも、「均衡点から離れれば、均衡点に近づこう」とする力は、常に発生する。たとえば、価格が高すぎれば、下げようとする。生産量が多すぎれば、減らそうとする。そうして需給曲線の交点(その価格と量)に近づこうとする。── こういうふうに、「ワルラス的調整過程」の力は、普通の経済状態のときも含めて、常に働く。もちろん、不況のときも、その力は働く。それは、左点においては、「下向きの力」(価格を下げようとする力)となる。
- 上向きの力
上向きの力は、「下限直線よりも上に行こう」とする力である。下限直線よりも下では、(採算割れで)赤字となる。しかし、「企業の存続」のためには、赤字を出すわけには行かない。また、ある程度の利潤も必要だから、下限直線よりもいくらか上の方に移りたい。── そういうふうに黒字を求める力が働く。それは、左点においては、「上向きの力」(価格を上げようとする力)となる。
( ※ これは企業にとっては「利潤の最大化」を求める力である。なお、「利潤の最大化」は、「価格の最高化」とは異なる。価格が上がりすぎると、量が減って、かえって利潤の総額は減ってしまうからだ。)
さて。こういうふうに、「下向きの力」と「上向きの力」が、せめぎあっている。この両方がうまく釣り合うところで、状況はとりあえず安定する。
こういうふうに、二つの力が釣り合うという意味では、左点は「均衡状態にある」と言えるだろう。実際、現実の状況を見ても、価格や量がメチャクチャになって不安定化することはなく、一定の範囲内に収まっているが、それは、ここで述べた二つの力が釣り合っているからだ。そういう意味では、左点の状況は、「均衡状態にある」と言ってもいい。
ただし、である。その状況は、先に (1) で述べたように、「安定的である」とは言えないのだ。
普通、経済学で「均衡点」と言えるためには、次の二つのことが必要である。
・ そこで力が均衡している
・ そこが状態が安定的である
そして、安定的であるためには、(採算割れで)「赤字」になっていないことが必要なのだ。もし、この条件が満たさず、赤字になっていると、短期的な安定を得ることはできても、長期的な安定は得ることができない。なぜなら、赤字の企業は次々と倒産していくからである。……そういう状態を、「小康」とか「一時的な安定」とか呼ぶことはできるが、実は、「破局に至る途中過程」であるにすぎない。「まだ死んでいない」だけのことだ。
結局、肝心なのは、そこで「力が均衡しているか否か」ではなくて、そこが「安定的であるか否か」のである。つまり、そこで「存続可能であるか否か」(赤字を出さずに済むか否か)なのである。
(3) 平均費用と限界費用
これから述べることが、本項の核心である。
左点というのは、これまでのトリオモデルの定義では、「∀」という形の水平線部分の、左端の点だった。その水平線に属しているのであれば、価格は採算価格なのだから、黒字でもなく赤字でもなく、原価ぴったりのはずである。だから、企業は、黒字にはならなくても、赤字にもならないはずだ。とりあえずは、利潤がゼロのまま、存続が可能なはずである。特に安定した状態ではなくても、別に不安定な状態ではないはずである。
トリオモデルというものを、おおざっぱに考える限りは、そのように考えてよいだろう。ただし、もっと正確に考えると、それでは済まないのだ。── なぜなら、「下限直線」というものには、「平均費用」と「限界費用」の、二つの意味があるからだ。( → 8月05日 )
下限直線は、「平均費用」と「限界費用」の、どちらであるとも見なせる。長期的には「平均費用」と見なしていいが、短期的には「限界費用」と見なしていい。── ここに、食い違いが生じる。では、この食い違いの結果、どうなるか?
企業がどういう行動を取るかを、考えよう。そもそも、「平均費用」と「限界費用」とは、どう違うか? 「平均費用」には、「限界費用」に、「固定費用」の分が加わっている。その分、「平均費用」は高い。逆に言えば、その分、「限界費用」は低い。── となると、次の事実が判明する。
「その価格が、平均費用よりも低く、限界費用よりも高いのであれば、その価格で追加販売することで、企業は利潤を増やす(赤字を減らす)ことができる」
そして、これに従って、企業は行動を取る。例で示そう。
鉛筆を生産する。平均費用は 10円で、限界費用は 7円である。
今、不況のせいで、9円で販売しているとする。当然、企業は赤字である。放置すれば、倒産する。いつまでもこんな状態は続けられない。(不安定な状態。)
さて。企業がさらに追加生産するとしよう。その追加生産の分は、8円で販売する。8円で販売しても、限界費用(7円)を上回るのだから、企業の利益は増えるはずだ。企業は、さっそくそれを実行する。
ところが、他企業は、その分、シェアを失って、赤字が拡大する。だから、他企業は、価格を改訂して、自社もまた8円で追加販売する。その分、元の社は、9円で販売していた分のシェアをうしなるので、その分も、8円で販売するしかなくなる。
結局、こういう状況がめぐりめぐって、市場全体の価格は、9円から8円に下がる。
そして、こういう価格下落圧力は、市場価格が「限界費用」という下限に至るまで、ずっと働くことになる。
こういうわけだ。つまり、ワルラス的調整過程による「下向きの力」というのは、「限界費用」に至るまで働く。この場合は、下限直線は「限界費用」である。(つまり、ワルラス的調整過程にとっては、下限直線は「限界費用」である。)
一方、赤字回避のための「上向きの力」というのは、「平均費用」よりも上になろうとするように働く。この場合は、下限直線は「平均費用」である。(つまり、赤字回避のためには、下限直線は「平均費用」である。)
ここに矛盾が発生する。なぜなら、
・ 企業にとっては、平均費用よりも上の価格が必要である。(存続のために。)
・ 市場においては、(平均費用より下の)限界費用まで価格が下がろうとする。
となるからだ。前者は「平均費用より上」、後者は「平均費用より下」。だから、双方を満たす領域は、存在しない。
結局、どうなるか?
左点は、「利益ゼロ」(黒字でも赤字でもない)という状況である。そこに留まっている限りは、特に問題はない。しかし、実際には、そうならない。下限直線には二つの意味があるからだ。── 企業の方は、せめて平均費用の価格に留まっていたい。しかし市場の方は、その下の限界費用の価格まで下がろうとする。
下限直線を「平均費用」と見るとしよう。すると、不況のときは、左点には落ち着かず、もっと下方の点(価格の低い点)に落ち着こうとするのだ。企業としては、左点に留まっていたい(利潤ゼロでいたい)のだが、実際には、左点よりも下方の点(赤字の点)に移ってしまうのだ。そのような点で、「下向きの力」と「上向きの力」が均衡して、いちおう落ち着く。
力の均衡する点というのは、「利潤ゼロ」となる点ではなくて、「赤字」となる点なのだ。かくて、赤字が必然となるのだ。
そして、これが、「不況」ということの本質だ。つまり、「放置すれば、均衡点に落ち着いて、状態は安定する」ということはない。「放置すれば、とりあえずは力の均衡する状態に落ち着くが、そこは、赤字となる点であり、状態は安定しない」ということだ。
不況というのは、経済システムが死に向かって崩壊しつつある過程なのである。たとえ状況が安定しているように見えても、それはそのとき限りの安定であり、ずっと続く安定ではない。ただの小康にすぎない。だから、「均衡点はすばらしい」とか、「均衡点は安定した状態だ」とか、そういう説は成立しないのだ。
まとめ。
不況という状況は、左点ではなくて、その少し下方である。そこでは、「利益ゼロ」ではなくて、「赤字」の状況となる。そういう状況で、(上向きの力と下向きの力が)一時的に均衡する。
この状態は、真に均衡している状態ではないし、安定的な状態でもない。企業にとっては、「生存可能」ではなく、「生存不可能」な状況である。ここでは、経済システムが徐々に崩壊しつつある。
だからこそ、不況は、ただの「縮小した経済」というのとは、異なるのだ。ただの「縮小した経済」は、それが(ワルラス的)「均衡状態」にある限り、問題はない。単に過剰消費や過剰労働が解消されるだけだ。しかし、不況は、それとは異なる。不況という状態は、「均衡」ではなくて、「不均衡」である。「健康」ではなく、「不健康」である。ここは、「崩壊途上の小康状態」にすぎない。だからこそ、そういう状況は「悪い状況」と言えるわけだ。
[ 付記 1 ]
とにかく、「不況のときは赤字が必然化する」ということが大事だ。
「不況というのは、好況に比べて、景気が悪い状態だな」というのは、正しい認識ではない。「赤字」というのは、企業の生存が否定されることであり、それはまた、人間にとって最低限度の所得を失って生存を否定されることである。
単に「景気が良くない」(賃下げになる)というのなら、単に「貧乏になる」ことだから、まだしも耐えられる。しかし、「不況になる」(失業する)というのは、「金を失う」ことだけでなく、「生命を失う」ことなのだ。実際、不況の今、年間 3万人を越える自殺者が出ている。
企業にとっては、「利益を減らすこと」と「赤字になること」は、まったく意味が異なる。人間にとっても、「賃金を減らすこと」と「失業すること」(無収入になること)とは、まったく異なる。……そして、不況というのは、後者が必然になることだ。ここに不況の本質がある、と考えてよい。
[ 付記 2 ]
本項の主張は、従来の経済学とは異なる。比較して、示そう。
- 古典派
「不況なんて、経済が縮小しただけさ。ちっとも悪くはないね」(神の手がうまく取りはからってくれるさ。)
- ケインズ派
「不況というのは、労働者が失業するのが問題だ。悪いのは、失業問題だけさ」(失業者に穴を掘って埋めさせれば、それで十分。)
上記のような従来の説に比べ、本項は、「不況というのは経済システムそのものを崩壊させるような、決定的に悪い状況だ」と主張している。そして、そう主張できるのは、トリオモデルを使ったからである。
[ 補足 ]
本項では、トリオモデルを用いて、以前よりも詳しく考えている。下限直線に2種類のものがあることを認めて、その二つの下限直線の効果を考察している。その意味で、「トリオモデルを拡張している」というふうに受け止めてもよい。
ただ、特に気にするほどのことはない。そもそも、普通は、この2種類を区別する必要がない。細かい点は考慮せず、「下限直線は1種類のものだ」と考えてかまわない。そして、とくに細かい点を考慮する必要があるときだけ、そうすればいい。それだけのことだ。
● ニュースと感想 (8月22日)
前項に述べたことから、「物価下落」と「不況」の関係がわかる。それは、「物価下落は不況をもたらす」ということだ。つまり、「物価下落 → 不況」というわけだ。こういう因果関係がある。このことを説明しよう。
( ※ ただし、ここでいう「物価下落」は、ある程度以上の幅をもつものとする。つまり、「過剰な物価下落」である。)
まず、単に価格が下がっていくだけなら、それは単なる「物価下落」である。これには良し悪しの意味はない。単に現象を描写しているだけだ。
では、「不況」(倒産・失業の発生)とは、どういう状況か? それは、トリオモデルを見ればわかるとおり、「下限直線」を割る状態(企業が赤字になる状態)である。── つまり、「小幅の物価下落」ではなくて、「ある程度以上の幅の物価下落」である。
もし物価下落が起こっても、それが小幅の物価下落であれば、「下限直線」よりも上にいることができるので、赤字は発生しない。そこは、あくまで均衡状態であって、不均衡状態ではない。この状況は、不況ではない。倒産や失業も、ほとんど発生しない。なるほど、ごく一部の劣悪な企業は倒産するが、その分、優秀な企業が伸びる。だから、かえって状況は最適化していく。
特に、「良い物価下落」という状況がある。それは、物価下落の原因が、「下限直線の下シフト」である場合だ。このとき、パソコンや輸入品がコスト低下で値を下げていくが、それは、(低コストで生産できるという)優良企業が増えるのと同じことだから、好ましい状況だ。前段落で述べた場合と同じく、このときも状況は最適化していく。
しかし、である。「下限直線の下シフト」は、一部の産業だけでなら起こることもあるだろうが、全産業でいっせいに起こることはありえない。年平均の生産性の向上は 2.5% 程度である。これを大幅に上回る値が、全産業でいっせいに達成されることはありえない。(そんな夢みたいな状況があれば、それはそれですばらしいことだが、そんな夢みたいなことを目標とするエコノミストは、「雨乞い」をする非科学的な呪術師も同然である。)
では、下限直線が下シフトしないのに、物価が全般的に低下するとしたら? それは、需要の縮小が起こった場合だ。このとき、どうなるか? ある程度までの需要縮小と物価下落なら、問題ない。しかし、ある程度よりもひどくなると、需要縮小にともなって、価格が大幅に低下する。特に、下限直線よりも下の領域に移る。── このとき、トリオモデルにおける「不均衡」の状態となる。つまり、「不況」となる。(前項で述べたように、「悪い状況」となる。)
そういうわけだから、「全産業における物価下落」は、ある程度以上に進むと、「不均衡状態」つまり「不況」をもたらすのである。── これが冒頭で述べた結論だ。(原因は、「下限直線割れ」である。)
結局、「物価下落」というのは、好ましい状況ではないわけだ。「商品が安く買えるから、消費者にとっては好ましい」と主張するのは、消費者の面だけ見て、生産者の面を見ていない。生産者にとっては、ある程度以上の物価下落は、「赤字」を意味する。それは「不況」つまり「倒産・失業」つまり「経済システムの崩壊」を意味する。
「物価下落」は、均衡状態に留まっている限りは好ましいことだが、いったん不均衡状態にまで入ると、大きな弊害が発生するのだ。
[ 付記 1 ]
「全産業における物価下落」は、なぜ起こるか? もちろん、「総需要の縮小」つまり「消費性向の低下」によって起こる。だから、経路を示せば、次のようになる。
総需要 全産業での 下限直線 赤字 倒産・失業
の縮小 ┬→ 物価下落 ┬→ より下へ → 発生 → などの不況
│ │
ワルラス的調整過程 下限直線は不変
[ 付記 2 ]
「不均衡状態」について、「経済システムの崩壊(死)」と表現した。このことの本質は、「不可逆性」にある。
「均衡状態」における「稼働率低下」ならば、需要の拡大にともなって、元の状態に回復する。つまり、「可逆性」がある。しかし、いったん倒産した会社や、いったん(倒産で)失業した労働者や、いったん(失業で)自殺した人間は、元の状態に戻れるわけではない。
不況はそういう「不可逆性」をもたらす。不況のとき、経済システムは、衰弱するだけでなく、部分的に死ぬのである。壊疽(えそ)のように。ここに大きな問題があるわけだ。
( → 1月20日 ,1月21日。 「不可逆性」)
[ 補説 ]
下限直線の変化について。(特に読まなくてもよい。)
本項ではここまで、「下限直線が下シフトとする」という効果を無視してきた。なぜ無視したかといえば、この数値(生産性向上率と同じ)は、長期的にほぼ一定していて、年ごとに大きな変化はないからである。(一見、統計上の数値は変動するように見えるが、それは設備の稼働率が向上するか低下するかに依存しており、技術的進歩などによる質的な生産性向上とは別の理由による。)……つまり、年ごとに大きな変化がないのならば、そんなものはいちいち考慮する必要はないわけだ。特に、景気変動を考察するときは。
ただ、考慮しないとはいえ、生産性の向上(下限直線の下シフト)がないわけではない。それは、景気変動に対して影響しなくとも、何らかの点で影響するはずだ。では、どんな? ── そのことを示そう。
下限直線の変化による影響を考える。
修正ケインズモデルでは、「(需要縮小を引き起こすべき)消費性向の低下は、1回限り」と見なしている。たとえば、限界消費性向の「 0.8 → 0.7 」という変化である。こういう1回限りの変化を「需要の縮小」として、グラフで描いた。
しかし、現実には、「消費性向の低下は、1回限り」とは言えない。なぜか? 1回の消費性向の低下だけを見れば、失業者はいまだ、「失業保険を受ける」「貯蓄を崩す」ということが可能である。彼らは無収入であっても、失業保険を受けたり、貯蓄を崩すことで、消費をすることができる。その分、消費は減少しない。つまり、国全体の消費性向は余り低下しない。
だが、やがて、失業保険をもらえなくなるし、貯蓄も底を突くなくなる。こうなると、彼らは、破滅する。生活保護を受けるか、犯罪を犯すか、死ぬか、いずれかとなる。……そして、いずれの場合も、消費は急激に減る。消費性向は再度、低下する。
こういう「消費性向の再度の低下」という過程は、国民全員が失業するまで(国全体の経済システムが完全に崩壊するまで)続くだろう。だから、修正ケインズモデルに従う限り、最終的な「収束点」は、「全員の死」(国家経済の完全破綻)である。
しかるに、現実には、そうならない。経済は悪化の一途を取ることはなく、悪化がぐずついたり、少し回復したりするものだ。では、なぜ?
それは、「生産性の向上」によって、「下限直線の下シフト」があるからだ。人々が必死に努力して、生産性を向上させる。すると、低い価格で生産できるようになる。だから、原価割れとならず、(ワルラス的な)均衡点に達することができる。……かくて、不況(不均衡状態)から、脱することができるわけだ。
結局、「生産性の向上」があるから、経済は「完全な破綻」を免れることができる。その意味で、「生産性の向上」は、たしかに重要である。
とはいえ、これに過大な期待をかけるべきではない。「生産性の向上」というのは、マクロ的には、「年 2.5%」から大きく変動することはない。せいぜい、±1% 程度であろう。一方、需給ギャップというものは、GDPの 5%〜10% にもなる。だから、「生産性の向上で不況を解決しよう」というのは、期待過剰であり、お門違いなのである。
なるほど、「生産性が年5%向上すれば、下限直線が年に5%下がるので、それで不均衡状態は解決する」という説は成立する。しかし、「生産性が年5%向上すれば」ということ自体が、荒唐無稽なのだ。だから、その主張全体が荒唐無稽であるわけだ。
生産性の向上率は、長期的にほぼ一定であり、あるとき急に向上することはない。そんなうまい話があるはずがない。たとえれば、「生産性が急に向上すれば」というのは、「急に手元に所得が増えれば」とか「空からお金が降ってくれば」とかいうのと同じようなものだ。「不況解決のために生産性を向上させよう」と主張するのは、「空からお金が降ってくるように祈ろう」と主張するのと同じようなものだ。ともに、雨乞いと同じく、不可能なことを望むだけのことだ。
経済学者たるものは、そんな荒唐無稽な主張をするよりは、実現可能なことを主張するべきだ。つまり、「生産性を一挙に向上させよう」とか「下限直線を一挙に下げよう」とか、ありえもしない夢を主張するよりは、「マクロ政策で需要を一挙に増やそう」というふうに主張するべきなのだ。
[ 注釈 ]
誤解を防ぐため、注釈しておく。
私は別に、「生産性の向上が必要ない」と言っているわけではない。「生産性の向上」は、もちろん大切だ。しかし、「1企業だけでなくマクロ的に全企業で」、かつ、「例年を上回る大幅な率で」、生産性を一挙に向上させよう、というのが、馬鹿げている、と言っているだけだ。
だいたい、政府がそんな掛け声をかけるだけで、国全体の生産性が一挙に向上するくらいなら、経済学なんてものは、必要ない。経済学者は何もしないで寝ていればいいし、企業の経営者は何もしないで寝ていればいいし、労働者も何もしないで寝ていればいい。何しろ、政府が掛け声をかけるだけで、どんどん生産性が向上するんだから。そんな「打ち出の小槌」があるのなら、誰も努力をする必要はない。
小泉が「構造改革」と1回唱えるたびに生産性が向上する、というのなら、われわれはみんな寝ていればいいのだ。
もちろん、現実には、そうならない。人々が血のにじむような努力をして、ようやく、例年よりもすこしだけ多く生産性を向上させることができる。努力が足りなければ、不況のマイナス効果に飲まれて、生産性は大幅に悪化する。
( ※ なお、生産性の大幅な向上は、国全体では不可能だが、個別の産業では、可能なこともある。たとえば、無駄の多い農業とか、特殊法人とか、国家公務員とか、そういうところでは、一挙に生産性を大幅に向上させることもできるだろう。最近、自動車産業でも、大幅な生産性の向上(コスト低下)を実現できているようだ。マクドナルドや牛丼屋も、巧みな工夫により、大幅な生産性の向上を実現できているようだ。……ただし、こういうことは、いつでもどこでも可能なわけではない。自動車業界も、マクドナルドも、牛丼屋も、今後ずっとコスト低下を何度も何度も実現できるわけではない。)
( ※ 以上のようなことに気づかない経済学者が、「生産性の向上はいくらでも可能だ」と主張するわけだ。こういう経済学者は、口先だけで、「生産性を向上せよ」と主張する。お気楽なものだ。彼らは現実を無視して、無駄な言葉ばかりを生産性しているわけだから、彼らの生産性は最悪だろう。)
● ニュースと感想 (8月23日)
前々項(前々日分)および 8月04日 の補足。(読まなくてもよい。つまらない話。)
前々項の (1) では、需給ギャップが生じたときの状況として、次のように述べた。
「左点にいちおう落ち着いているようだが、実際には、左点に行ったり、右点に行ったり、その中間に位置したりで、不安定になっている。」
このことの例を示そう。(もちろん、つまらない話。お暇な人向け。)
(a) 右点に行こうとすること
現在の市場価格で状況が安定化するには、右点の生産量が必要となる。
たとえば、「単価が 100円で、生産量が 10万個」。これが可能となるならば、企業は赤字とならないので、状況は安定する。企業は 10万個の生産をめざす。
(b) 左点に行こうとすること
しかるに、現実には、(a) のようにはならない。需要が縮小しているからだ。たとえば、「単価は 100円でも、生産量は8万個」となる。それ以上は、作っても在庫となるだけだ。赤字となるが、やむなく、企業は8万個の生産をめざす。
しかし、このとき、生産量の減少にともなって、単価が上昇する。一方、限界コスト割れとはならないので、多めに安く生産して、いっそう価格を下げ、いっそう自分の首を絞める。( → 前々項 )
これが左点の状況だ。
(c) 二者択一
結局、右点でも、左点でも、企業は赤字となる。そういう状況はとうてい受け入れられない。にもかかわらず、企業としては、右点と左点(およびその中間)しか、選択肢がない。となると、経営者は、次の二者択一を迫られる。(その中間も可能。)
・ 安全経営 …… 当面、小額の赤字が出ることを我慢して、左点を選択。
・ 期待経営 …… 景気が回復して在庫がはけることを期待して、右点を選択。
前者を選択すれば、企業は確実に赤字になる。ただし、小額の赤字で済む。
後者を選択すれば、うまく行けば黒字だが、悪くすれば大赤字である。下手をすれば、大量の売れ残りが出て、倒産する。
それぞれの結果は、次のようになる。
・ 前者を選択 …… 政府が無策なら、小額の赤字。政府が賢明なら、小額の赤字。
・ 前者を選択 …… 政府が無策なら、大幅な赤字。政府が賢明なら、大幅な黒字。
現実には、前者を選択する企業も、後者を選択する企業も、どちらも出てくるだろう。で、そのあげく、どうなるか?
政府が賢明なら、過剰生産した無謀な会社が得をする。たとえ大量に生産しても、すでに景気は回復しているので、すべて売れるから、赤字は出ない。一方、慎重に生産を縮小した会社は、売るものがないので、小幅の赤字を甘受するしかない。
政府が無策なら、慎重な会社は小幅の赤字で済む。一方、過剰生産した会社は、大量の売れ残りが出て、大幅な赤字を出す。どんどん倒産していくだろう。(現実に、そうなっている。)
さて。以上のような状況は、簡単に見て取れる。経営者なら、すぐにわかることだ。となると、この二つの例を見て、経営者は、どちらにするか、右往左往するわけだ。景気が悪いままだと思えば前者を選択し、景気が良くなると思えば後者を選択する。特に、ちょっと景気が良くなりかけたとき、楽観的になったり、慎重になったり。なかなか定まらない。
こういう状況では、価格は安定するが、量は安定しないだろう。 このとき、(右点と左点の間で)状況は不安定になっている。
( ※ なお、企業の在庫水準は、増えたり減ったりするが、たとえ増えても減っても、そのことは、ただちには景気の回復を意味しない。……この点、不況時の「先行指数」という経済指標は、あまり当てにならない。)
● ニュースと感想 (8月23日b)
時事的な話題。「法人税減税」の話。(朝日・朝刊・経済面 2002-08-21 )
法人税減税をめぐって、政府税調会長と竹中大臣が対立。前者は、「需要不足のときに法人税を減税しても無意味」という主張。後者は、「長期的な観点からサプライサイドで法人税減税をやるのだ」と主張する。
まったく、二人とも頭が悪すぎる。子供にもわかるように説明しよう。(竹中は「サプライサイド」一辺倒。税調会長は、「法人税減税」への批判は正しいのだが、「投資減税」という自分の提案が間違いで、これもサプライサイド。どちらも同罪である。)
(1) 長期的
「長期的な観点から」という視点はわかる。しかし、今は、緊急の状態なのだ。長期的な観点などを重視すべき時期ではないのだ。しかも、不況のときには、「長期的な観点から」というのが、逆効果を持つ。そこに気づくことが大切だ。
たとえ話。「人の体力を増進するためには、長期的な観点から、運動をして栄養を補給することが大事だ。これこそ物事の根本だ」と竹中医師は主張した。その主張を受け入れた風邪患者は、どうなったか? 下痢状態なのに、お粥ではなくて肉を食べたので、ますます下痢がひどくなった。発熱しているのに、運動をしたので、ますます熱が上がった。病状はひどく悪化してしまった。……南堂医師は、こう見立てた。「病人に対しても、健康人に対しても、同じ処方をする? それは、馬鹿のひとつ覚えだね。医師の資格なし。殺人犯も同様だ。」
(2) 有効性
企業に1兆円を渡して、それで何か効果が出るか? 企業はそれを、ありがたがるか? 「金をもらえれば喜ぶだろう」と竹中は思うようだが、企業の立場になって考えよう。企業としては、どう受け止めるか?
法人税減税や投資減税なら、「今は減税、将来は増税」と言われても、何の意味もない。もともと設備は過剰なのだから、それで得た金を単に預金するだけだ。ちっともありがたくない。(政府の尻馬に乗って、投資を増やしたりすれば、余剰設備が増えるだけであり、赤字拡大で倒産してしまう。)
一方、国民への減税なら、「今は減税、将来は増税」なら、企業としては(直接的には)1円も効果はない。ただし、国民に金が入るので、国民が企業の商品を買ってくれる。それは、企業としては、どういう意味があるか? 「不況の今には、1兆円分の売上げ増加。好況の将来には、1兆円分の売上げ減少」だ。これなら、企業にとっては、ありがたい。将来、黒字のときに黒字の幅が減るのは、特にどうということはない。しかし、赤字の今、赤字が解消するということは、倒産を免れると言うことであり、最重要の課題であるからだ。
(3) 帳尻
では、(1) (2) を勘案すると、どうなるか?
法人税減税は、国民への減税に比べて、好ましくはないが、悪くもないだろうか? いや、悪い。なぜなら、企業へ1兆円の金が渡れば、その分、国民の金が減ってしまうからだ。1兆円という金は、空から降ってくるわけではないからだ。(ここをどうも、サプライサイドの人は勘違いしているようだが。1兆円、空から降ってくるから、それを企業に渡せばよい、と思い込んでいるようだ。)
どうせ1兆円の金を使うならば、その金を、企業でなく国民に渡すべきだ。そうすれば、消費が増える。一方、企業に渡せば、「金は空からは降ってこない」と知っている国民は、将来の増税を見込む。ゆえに、国民は消費を減らす。つまり、ただでさえ需要不足の状況が、いっそう需要不足となる。かくて、不況は、ますますひどくなる。
(4) 金額
以上のように、法人税の減税は、やればやるほど、不況を悪化させる。(消費となる金が奪われ、銀行に眠る金が増えるので。)
ただし、である。法人税をやめて、国民への減税をやればいいか、というと、そうとも言えない。なぜなら、1兆円ぐらいでは、ほとんど効果はないからだ。その程度だと、「景気の悪化」を少しだけ緩和する効果はあるが、根本的に治癒する効果はない。しょせんは、スズメの涙であり、焼け石に水である。このことは、小渕内閣のころの減税が無効化であったことからもわかる。
必要なのは、「国民への」「大規模な」減税なのである。
[ 付記 ]
経済学を理解すれば、結論は、ただ一つしかない。なのに、経済学音痴の大臣が、現状を改善するどころか、悪化させる政策ばかりをめざしている。
なぜか? 彼は、「サプライサイド」を信じている。「サプライサイド」というのは、周知の通り、「古典派」の一派であって、「セイの法則ゆえに、不況は存在しない」という立場である。
彼らは、「不況は存在しない」と主張しているのだから、不況対策というものは、もともと選択肢に入っていないのである。大臣は言う。「わが輩の辞書に、不況という語句はない」。
ゆえに、国民は今日もまた、現実無視の妄想的な政府のもとで、現実の不況に苦しみ続けるのである。
( ※ 彼らは、トリオモデルを理解しない。下限直線という存在に気づかない。だからこそ、不況というものを存在しないと見なすのだ。……たしかに、下限直線というものが存在しなければ、不況というものは存在しないだろう。)
( → 8月07日 の最後 「法人税減税」 )
[ 補記 ]
ここまで書き終えたあとで気づいたのだが、朝日・朝刊・経済面 2002-08-22 にも、趣旨の似た話が書いてある。そちらも参照。
( ※ 朝日には珍しく、まともな記事である。「政府の問題点を指摘する」というマスコミの本分を果たしている。こういうまともな記事は、実に久々だ。これまではさんざん嘘とデタラメばかりを書いて、政府の提灯持ちばかりをやって来たのだが。小泉の洗脳効果から、抜け出したのかな?)
[ 補説 ]
関連して、「法人税・税率」について述べておこう。
「内閣府の調査では日本の法人税は欧米よりも重い」というのは、実は、論理的な詭弁である。ここを理解していない人が多いようなので、指摘しておく。
税額が重いか軽いかは、率と額の二つの比較法がある。
・ 率 …… 利益額に対する法人税の率を比較
・ 額 …… 売上高に対する法人税の支払額を比較
両者で、どう異なるか? 経済体質が同じならば、どちらで比較しても同じだ。しかし、経済体質が異なると、結果は異なる。おおむね、日本の企業は売上高に対する利益率が低い。長期的には、平均して、日本は5%程度であり、欧米は 10%程度である。率を同じにすると、企業の税負担率が、日本では欧米の半分で済むことになる。(売上高比の利益率が低いから)。
では、日本の企業が利益率が低いのは、なぜか? 「短期的な利益を犠牲にして、規模の拡大をめざす」という長期的戦略のためだ。それはそれでいい。ただの経営方針の違いにすぎない。しかし、だからといって、企業の税金まで減免する、というのは、話の筋が通らない。マクロ的に見れば、企業の税負担は、欧米に比べて半額で済むことになる。その分、国民が多くの税を払うことになる。
マクロ的な企業の税負担率は、企業の経営方針に左右されるべきではないのだ。単に法人税率だけを見て、「税率を同じに」とすれば、マクロ的に企業ばかりが税負担を免れて、国民ばかりが税負担をすることになる。いびつな租税負担となる。その結果、企業にばかり富が偏在することになる。(実際、不況前の30年ぐらいを見ると、そういう傾向が見られる。)
結論はわかった。あとは、方法だ。方法的には、どうするべきか?
マクロ的には、企業の税負担の額を下げる必要はない。ただし、法人税の税率そのものは、数パーセント程度は下げてもいいだろう。そうすれば、うるさい企業も納得できるだろう。では、税率を下げたことによる減収の埋め合わせは? 各種の控除を廃止すればよい。今は企業のための控除(損金扱い)が多すぎる。たとえば、自動車を買って利用しても、個人ならば税負担があり、企業ならば損金処理(税の免除)。……こういう不公平をなくすために、各種の控除(損金処理)を廃止するべきだろう。たとえば、環境税を課して、その分の控除を認めない。(排ガスを撒き散らすという有害行為に対して、個人だと課税されるが、企業だと損金で課税されない、という不公平な現状を改める。)こういう形と併用するなら、法人税の減税は意味がある。
とにかく、比較するべきは、法人税そのものの税率ではない。率よりも額を見るべきだ。つまり、国家歳入における、法人所得税総額と個人所得税総額との比率を見るべきだ。あるいは、GDPにおける法人所得税総額の割合を見るべきだ。……これらを各国で比較すれば、日本は欧米よりも、企業を優遇しているとわかるだろう。(特に、不況の今は、ほとんど法人税を払っていない企業が多い。社会資本をさんざん利用して、税負担はゼロ、というわけ。排ガスを撒き散らしても、さして課税されない。)
《 翌日のページへ 》
(C)
Hisashi Nando. All rights reserved.