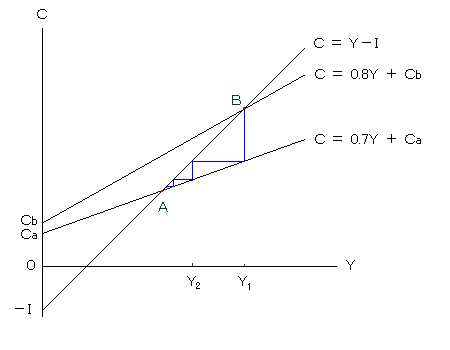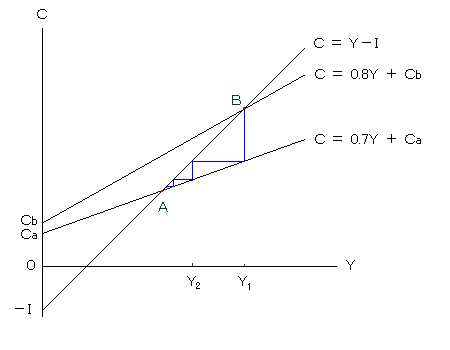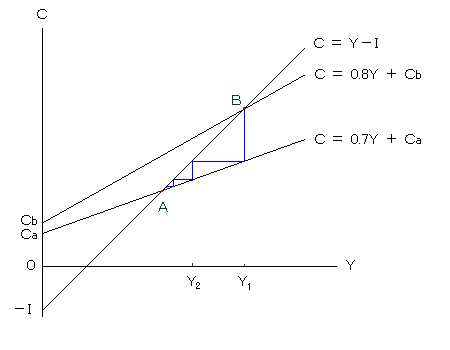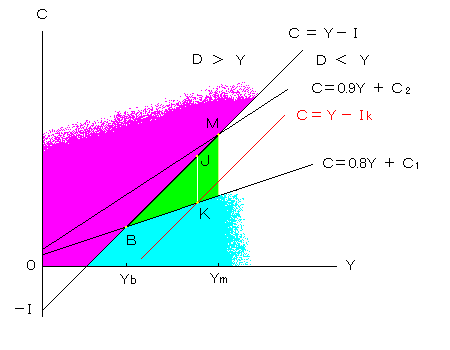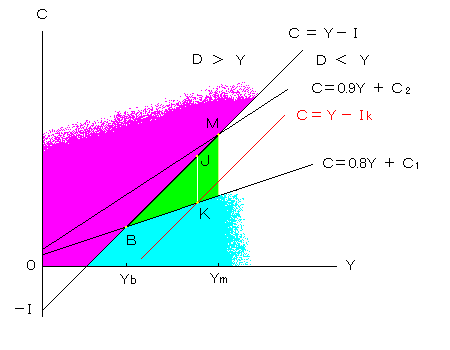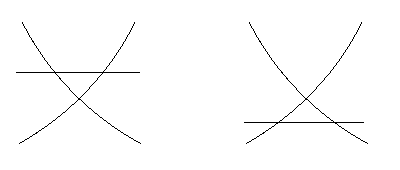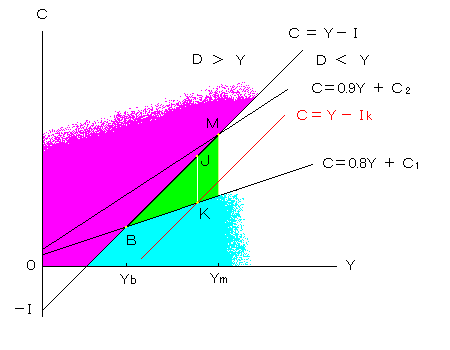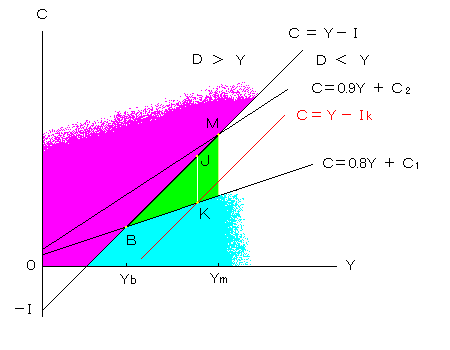[ 2002.09.03 〜 2002.09.20 ]
《 ※ これ以前の分は、
2001 年
8月20日 〜 9月21日
9月22日 〜 10月11日
10月12日 〜 11月03日
11月04日 〜 11月27日
11月28日 〜 12月10日
12月11日 〜 12月27日
12月28日 〜 1月08日
2002 年
1月09日 〜 1月22日
1月23日 〜 2月03日
2月04日 〜 2月21日
2月22日 〜 3月05日
3月06日 〜 3月16日
3月17日 〜 3月31日
4月01日 〜 4月16日
4月17日 〜 4月28日
4月29日 〜 5月10日
5月11日 〜 5月21日
5月22日 〜 6月04日
6月05日 〜 6月19日
6月20日 〜 6月30日
7月01日 〜 7月10日
7月11日 〜 7月19日
7月20日 〜 8月01日
8月02日 〜 8月12日
8月13日 〜 8月23日
8月24日 〜 9月02日
9月03日 〜 9月20日
のページで 》
● ニュースと感想 (9月03日)
本項では、重要なことを述べる。それは、「景気回復策の成否」についてだ。
どんな景気回復策であれ、それによる効果はいくらかある。では、その効果は、十分であるのか? つまり、その景気回復策をした結果、見込み通り、不況を脱出して、成功することができるのか?
これは、重要な問題である。たとえば、最近、「1兆円程度の減税を実施しよう」という意見が出ている。なるほど、1兆円規模の減税は、それはそれで、いくらかは効果があるかもしれない。では、そのことで、景気は回復するという予測は立つのか? それとも、「少しは効果があるだろう」という、いい加減な見込みでやっているだけなのか? 経済学的に何の根拠もなしに、当てずっぽうな憶測だけで、一国経済を運営しているのか?
まず、簡単にわかることだが、ごく小額の景気刺激策では、景気回復効果はないだろう。たとえば、総額1億円ほどの減税では、これで国民各人に1円の金が行き渡るが、それっぽっちでは、景気が回復するはずがない。
同様なものとして、「地域振興券」というものもある。これは、1億円ではなく、7000億円程度が使われたが、このくらいの規模でも、まったく効果がなかった。
こういう歴史的事例から、「不十分な額の減税では、効果がない」とわかる。
そこで、次のことが問題となる。
・ 景気回復策が十分な効果をもつすには、どのくらいの額があればいいか?
・ 不十分な額では効果が上がらないとしたら、それは、なぜなのか?
こういうことを、理論的に示すことが必要だ。従来の経済学では、そういうことにはろくに言及していないが、このことはたしかに、経済学で重要な問題なのである。
( ※ ここで肝心なのは、「不況のとき」という条件である。不況のときでなければ、景気刺激策は、確実に効果が出て、景気は拡大する。ただ、不況のときは、そうはならないのだ。その理由を探りたいわけだ。)
ではいよいよ、説明を始めよう。
先に、修正ケインズモデルに基づいて、次の図を示した。
さて。前項 でも述べたとおり、景気回復策には、原理的に、次の二つの方法があることがわかる。
・ 消費性向を上昇させる方法
・ 直線の上シフトまたは下シフトによる方法
前者は、タンク法によるもの。「消費性向を上昇させる」わけだが、そのことによって、状況が、交点 A から交点 B へと移行する。(水色の線)
後者は、公共事業,民間投資,減税[民間引き受けの国債]によるもの。「直線の上シフトまたは下シフト」を起こすわけだが、すると、二つの直線の間隔が開き、そのことによって、状況が、交点 A から (交点 A’ を経由して)交点 E に移行する。(青色の線)
この二つの場合に分けて考えよう。
(1) 消費性向を上昇させる方法
上のグラフでは、消費性向が 0.7 から 0.8 に上昇することで、交点 A から交点 B に移行する。
では、消費性向をこのように上昇させるには、何が必要か? それには、十分な額の減税が必要となる。
減税の額が非常に少ないと、消費性向はほとんど上がらない。(だから景気拡大の効果がない。)
減税の額が中途半端だと、消費性向が 0.7 から 0.75 ぐらいに上がる。すると、収束点は、交点 B ではなく、交点 A と交点 B の中間となる。そこに収束する。(グラフで試しに、傾き 0.75 の直線を引いてみるとよい。新たな交点を得られる。)
では、この新たな交点で安定するか? 単純に考えれば、ここがグラフの交点だから、ここで安定しそうだ。「均衡点」というものを妄信している経済学者ならば、「ここで均衡する」と主張するだろう。しかし、思い出してほしい。ここは、均衡点ではなく、収束点であるにすぎない。経済的な効果(ここではタンク法の減税のこと)が、最終的にここでストップする、ということを意味するだけだ。
では、そのあとは? 収束したあと、どうなるか? (以下では、 Yb は、「需給ギャップの解消する生産量」のこと。)
- もしこの時点で、不況を脱出していれば(生産量が Yb に戻って需給ギャップが解消していれば)、もはや赤字発生による倒産や失業の心配はない。だから、人々は安心して、消費を増やす。だから、消費性向は元の水準( 0.8 )に戻って、そこで安定的に推移するだろう。
( → 9月01日 「タンク法の景気回復策」。…… 減税による貨幣錯覚で、消費性向が 0.77 に上昇したあと、現実に景気が良くなっていることで、消費性向が元の 0.80 に落ち着く。)
- もしこの時点で、不況を脱出していなければ(生産量が Ybに戻って需給ギャップが解消していることがなければ)、赤字発生による倒産や失業の心配がある。だから、人々は不安に駆られて、消費をまた減らす。消費性向はふたたび以前の低い水準( 0.7 )に落ちる。かくて、また元の交点 A に戻ってしまうのである。(下の図を参照。ただし出発点は、B ではない。)
結局、減税の効果が消えたあとで、そのときに不況が解決しているかどうかで、結果は異なる。
もしそのとき、不況が完全に解決していれば、あとは景気は自立的に進む。
もしそのとき、不況が中途半端に解決しているだけならば、景気はいまだ自立できない。そのあとも減税を継続すれば、その状況を保てるが、減税を継続しなければ、景気はふたたび元の交点 A に戻ってしまうことになる。
(2) 直線の上シフトまたは下シフトによる方法
公共事業,民間投資,減税[民間引き受けの国債]の場合は、どうか? つまり、一定額の需要を新たに追加する場合は、どうか? (上の (1) では、所得に対する消費の割合を上昇させたが、(2) では一定額を追加するわけ。)
実は、この場合も、事情は (1) と同様である。
景気刺激の額が非常に少ないと、直線のシフト量は非常に少ない。(だから景気拡大の効果がない。)
景気刺激の額が中途半端だと、直線のシフトの量は半分ぐらい起こる。その場合、収束点は、交点 E ではなく、交点 A と交点 E の中間となる。そこに収束する。(グラフで試しに、シフト量が半分の直線を引いてみるとよい。新たな交点を得られる。)
[ ※ もう少し細かく説明しよう。交点 A から交点 E に移行する経路は、次の通り。── 最初は、交点 A にいる。そのあと、投資 I を増やすか、消費の定数 Ca を増やす。前者は、公共事業または民間投資補助によって、所得の直線を下シフトさせる。後者は、減税によって、消費の直線を上シフトさせる。そして、そのいずれの場合も、二つの直線の間の距離が開く。つまり、交点 A から交点 A’に移行する。(または、それと同じことになる。) そのあとは、乗数効果によって、青い線をたどることで、交点 E に移行する。……交点 E でなく、途中の点に移行する場合も、事情は同様で、変化量が半分ぐらいになるだけ。]
さて。交点 A と交点 E の中間のあたりの点に収束する。では、その点で安定するか? この場合も、事情は (1) と同様である。
もしそのとき、不況が完全に解決していれば、あとは景気は自立的に進む。
もしそのとき、不況が中途半端に解決しているだけならば、景気はいまだ自立できない。そのあとも公共事業や減税を継続すれば、その状況を保てるが、公共事業や減税を継続しなければ、景気はふたたび元の交点 A に戻ってしまうことになる。
まとめ。
結局、(1) であれ、(2) であれ、(タンク法であれ、他の景気刺激策であれ)、いずれにしても、結論は同じである。
・ 景気回復策は、一発で不況を脱出するだけの、大きな額が必要である。
・ 額を小さめにすると、効果が無効となる。
だから、「最初にドカン」が必要になるわけだ。逆に、不十分な額を何度も投入すると、それらの総額は巨額になるが、各回の効果はいずれもゼロなので、ゼロの積み重ねでゼロとなる。いくら大金を投入しても、効果はゼロとなる。つまり、ケチケチしていると、かえって損をする、というわけだ。
そういうことが、理論的に導き出されたことになる。
[ 補説 ]
なお、本質を示そう。背景説明ふうだが、これは重要な話だ。
景気刺激策は、最初に十分な額が必要である。なぜかと言えば、それによって、「需給ギャップ」を解消するためである。(需給ギャップを解消すれば、景気は自立するが、需給ギャップを解消しなければ、景気は自立しない。)── ここでも「需給ギャップの解消」が、本質的な核心となっている。
どんな景気刺激策であれ、その景気刺激策によって、経済はいくらか拡大する。そこまでは、誰にでもわかる。しかし、肝心なのは、その景気刺激策によって、「需給ギャップが縮小したか否か」ではなくて、「需給ギャップがすっかり解消したか否か」なのだ。
もし需給ギャップが解消していれば、倒産も失業もないので、消費性向は 0.8 となる。その場合、新たな収束点で、安定的に均衡状態を保つ。
一方、もし需給ギャップが解消していれば、倒産も失業もあるので、消費性向は 0.7 に戻る。その場合、いったん新たな収束点に達しても、ふたたび景気悪化の経路をたどって、交点 A に戻ってしまう。
結局、こうだ。「元の木阿弥になるか否か」は、新たな収束点に達したとき、「ふたたび消費性向が下がるか否か」に依存する。そしてそれは、その時点で、「需給ギャップが解消しているか否か」に依存する。
そして、「需給ギャップが解消しているか否か」は、そのときの生産量が、「需給ギャップのない生産量」(Yb)に達しているかどうかで決まる。
この意味で、「需給ギャップのない最低の生産量」(Yb)というものがある。── 生産量が Yb 以下であれば、需給ギャップが発生して、経済は不均衡状態となる。生産量が Yb 以上であれば、需給ギャップが解消して、経済は均衡状態となる。
このような「十分な額の生産量」を、ケインズでは、「完全雇用のときの生産量」というふうに述べた。しかし、本当は、そうではない。必要なのは、「完全雇用を達成するための生産量」ではなくて、「均衡状態を達成するための生産量」なのである。── この両者の違いは、数日後から、また詳しく説明する。
● ニュースと感想 (9月04日)
前項(前日分)に関連して、さらに考えてみよう。
景気回復策には、「最初にドカン」が必要である。つまり、十分な額を一挙に実施する必要がある。ケチケチしていては、効果がなくて、元のもくあみである。
では、具体的には、どのくらいの額が必要だろうか?
修正ケインズモデルで考えれば、交点 A から交点 B (よりも右上)に移ればいい。それより左下では、不足である。
だから、需給ギャップを解消するだけの効果があるには、初期支出額が、次の式を満たす必要がある。
初期支出額 × 乗数 ≧ 需給ギャップ
つまり、
初期支出額 ≧ ( 需給ギャップ / 乗数 )
一方、乗数効果の乗数は 「 1/(1−限界消費性向) 」 で与えられる。限界消費性向が 0.8 ならば、乗数は 5 。限界消費性向が 0.7 ならば、乗数は 3.3 。この値を、すぐ上の式に代入すれば、初期支出額の必要額はわかる。
今、需給ギャップの額を60兆円と仮定しよう。すると:
- 減税(タンク法)ならば、限界消費性向が 0.8 だから、初期支出額の必要額は、60兆円の5分の1の 12兆円。これで需給ギャップはなくなり、景気は回復する。
- 公共事業ならば、限界消費性向が 0.7 だから、初期支出額の必要額は、60兆円の 3.3 分の1の 18兆円。これでマクロ的な需給ギャップはなくなるが、景気は回復するとは言えない。産業間の比率が変更されるからだ。このあとさらに公共事業を恒常的に追加し続ける必要がある。「垂れ流し」とも言えるような状況だ。ざっと見て、合計 25兆円ぐらいは必要だろう。
結局、60兆円の需給ギャップがあるとき、必要額は、減税(タンク法)ならば 12兆円。公共事業ならば 25兆円。これが最低限度、必要な額だ。これよりも少ないと、額が足りなくて、元のもくあみとなる。(1990年代の減税は、いずれも、この額に足りなかったから、無駄になったわけだ。)
現実には、安全性を見て、15兆円を実施するのがよいだろう。また、「均等(同額)」でない場合は、消費性向を一挙に上げる効果が薄れるので、20兆円ぐらいの減税を実施するのがいいだろう。(それ以下では、失敗する可能性がかなりある。)
なお、ここでは「需給ギャップ」を 60兆円と見ているが、もし 100兆円だったとすれば、その割合で、減税の額を増やす必要がある。
とにかく、減税というのは、多すぎて困ることはないが、足りないと困るのである。多すぎるのは、あとで増税で帳消しにできるが、足りないと、すべて無駄に消えてしまう。
[ 付記 ]
「1度に 15〜20兆円」というと述べた。小心な財務省の役人などにとって、この額が過激に思えるようであれば、かわりに、「1度に 10兆円」というのを2連発にしてもいい。まずは、一発目を実施する。それで十分な回復効果があると見込まれれば、ゼロ金利政策などで帳尻を合わせる。一方、十分な回復効果があるかどうか不明であるときは、さらに 5兆円 〜 10兆円 の景気刺激を、半年以内に追加する。(ぐずぐずしていると、一発目の効果が消えてしまうので、遅れないように注意する。)
[ 補説 ]
上記では、乗数が限界消費性向によって異なっている。このことに注意しよう。
一般的には、次のように言える。
・ 好況のとき …… 限界消費性向が高く、乗数が大
・ 不況のとき …… 限界消費性向が低く、乗数が小
よく聞く話だが、「最近は、乗数があまり大きくない。2を少し上回るぐらいにしかならない」という説がある。(経済企画庁などの調査。)
これは、必ずしも不思議ではない。次のような理由が考えられる。
・ 人件費の比率が低く、所得に回る額が少ない。
・ 限界消費性向が低いので、所得を得ても消費しない。
・ 結局、効果が土建産業で閉じており、他の産業に波及しない。
昔ならば、人件費の比率が高かったので、労働者の所得を通じて、そこから全産業に波及した。しかし最近は、人件費の比率が低いので、土建産業の関連産業(工機など)に波及するだけで、全産業にはあまり波及しない。そういうことなのだろう。
となると、上の修正ケインズモデルで採用した「乗数 3.3 」というのは、まだ甘すぎることになる。もっと低い値(例 2.2)を採用すれば、公共事業で必要な額は、もっと大きくなる。
[ 参考 ]
本項の試算では、「公共事業だと 25兆円、減税だと12兆円」と述べた。つまり「公共事業は減税よりも、効果が小さい。だから、大きな額が必要となる」という結論となる。
これは、「公共事業は減税よりも、効果が大きい」というケインズの主張とは、正反対である。 ( → 8月29日 「ケインズの主張」)
なぜ、こういう違いが出たか? それは、「消費性向の向上をもたらすか否か」による。消費性向の向上をもたらすのであれば、その分、最初の支出額は小さくて済む。
減税(タンク法)ならば、消費性向の向上をもたらす。ただし、減税は減税でも、「民間引き受けの国債」による減税だと、消費性向の向上は見込めない(直線の上シフトだけである)ので、この場合は、ケインズの主張するとおりになる。つまり、減税の方が効果が小さい。 ( → 8月29日 )
( cf. 9月02日 各種の景気刺激策の一覧 )
● ニュースと感想 (9月05日)
補足的な話。
前々項でも、前項でも、「最初にドカン」が必要だ、ということを示した。
そのことを、たとえ話またはモデル的に示そう。
「最初に十分な力を加えないと、元の木阿弥になる」ということの例 or モデル or たとえ話。
(1) 人工衛星
人工衛星をロケットで打ち上げるとする。最初に十分な速度[第一宇宙速度]をもてば、人工衛星は地球の周りを自立的に周回する。最初に十分な速度がないと、飛行機のように、たえずエンジンで加速し続ける必要があり、そのエンジンの力がなくなった時点で墜落する。
(2) 自転車
自転車に乗ろうとして、練習している子供がいる。子供を自転車に乗せたあと、親が後ろから「えいっ」と押して、最初に勢いを付ける。最初に十分な速度があれば、そのまま倒れずにどんどん進むが、最初の速度が不十分だと、横から支えてやらない限り、倒れてしまう。
( ※ 経済で言えば、中途半端な景気刺激で、一時的に不況の底から抜け出すが、やがてはまた不況の底に落ちてしまう。効果を持続させるためには、その後も毎年、景気刺激を継続する必要がある。そして、その継続が途切れたところで、坂を転げるようにして、不況に戻ってしまう。麻薬みたいなもの。── 実際、こういうことは、歴史的に見られる。小渕内閣などでは、何度も減税を実施したし、その総額は巨額になった。しかし、一回の額が不十分であったため、効果を発揮しないまま、また元の不況に戻ってしまったのである。減税というものは、小分けに少しずつ実施するのでは、効果はすべては蒸発してしまうのである。その分の金はすべて貯蓄に回る、と考えてよい。また、1990年の景気悪化以降、何度かの減税も実施したが、これらもまた、効果は上がらなかった。だから今もって、不況が継続している。)
(3) 立てた棒
立てた棒がある。フラフラしていたが、たえず制御することで、立たせておいた。ところが、制御に失敗して、倒してしまった。そのあと、また立てようとする。しかし、いったん倒れた棒は、元の立てた状態に戻すには、最初に「エイッ」と強い力を加える必要がある。
- 力が十分なら、倒れた棒は、 _ 状態から | 状態へと移行する。
- 力が不十分だと、倒れた棒は、 _ 状態から / 状態へと半分ほど移行したあと、ふたたび _ 状態に戻ってしまう。元のもくあみ。
結語。
ともあれ、(1) 〜 (3) のような例を示した。
一般的に、一定の閾値(いきち)があり、それ以下では無効、それ以上では有効となる。そういう例は、いくらでもあるわけだ。
こういうことは、だいたい、自然科学では常識的なことだ。自然科学者ならば、誰でもわかる。
ただし、経済学者だけは、頭が悪いせいか、そういうことを理解できない。……たとえば、財務省あたりは、「景気刺激策は、額が小さければ小さいほどいい」と思い込んで、なるべく値切ろうとする。そうして、ケチった減税を何度もやる。その結果、合計額は莫大になって、莫大な損をする。あげく、「こんなに莫大な減税をやっても、ちっとも効果がなかった」と言い張る。彼らは、閾値(いきち)というものを理解できないのである。
● ニュースと感想 (9月06日)
追記的な話。
前々々項でも、前々項でも、「最初にドカン(巨額の景気刺激策)」が必要だ、ということを示した。つまり、それは、景気回復のための、必要条件である。(景気回復のためには、最初に巨額の景気刺激策を実施することが必要である。)
では、それは、十分条件であるか? つまり、最初に巨額の景気刺激策を実施すれば、景気回復は必ず達成できるのだろうか?
これについては、「イエス」と思えそうだが、実は、「ノー」である。「最初にドカン(巨額の景気刺激策)」をやったとしても、それでうまく景気回復ができるとは限らない。(実は、もう一つ、別の条件を満たさなくてはならない。)
実際、最初に巨額の景気刺激策を実施しても、うまく景気回復ができない場合がある。それは、景気刺激策が、「減税」でなく、「公共事業」である場合だ。減税ならば、これを巨額に実施すれば景気は回復するが、公共事業ならば、これを巨額に実施しても景気は回復するとは限らない。
具体的に例を示そう。ピラミッドだ。ピラミッド建設で、景気は回復するか? 国中に失業者があふれているときに、彼らを雇用して、ピラミッドを造る。それで、失業者は消えるし、ピラミッドもできる。しかし、労働者や他の経営資源を奪われたために、他の産業はすべて壊滅する(または、縮小する)。政府は人々に、薄給でなく高給を払いたいところだが、たとえ高給を払っても、ハイパーインフレで、貨幣価値が無意味になるだけだ。なぜなら、そもそもピラミッド以外は何も生産していないから、いくら貨幣があっても、商品を買えない。つまり、人々は、貨幣価値のない葉っぱをもらうのと同様である。
というわけで、いくらピラミッドをたくさん造っても、巨大な墓ができるだけで、人々の富は何も増えない。ピラミッドがたくさんできればできるほど、生産力が奪われ、人々の手に入るものは少なくなるばかりだ。公共事業が増えれば増えるほど、人々は貧しくなるばかりだ。これをもって「景気は回復した」とは言えないのである。単に失業者が奴隷になるだけだ。
一般的に、無意味な公共事業では、そうなる。たとえば、本四架橋とか、東京湾横断道路とか、水余り地域の貯水ダムとか。……これらはすべて、ピラミッドと同様だ。こういうガラクタをいくら造ったとしても、一時的な需要創出効果があるだけで、本質的には景気は回復したことにならない。( 穴を掘って埋める のも同様。)
では、なぜ? 理論で示すと、次のようになる。(前項までの話を下敷きにしている。)
(1) 総需要の量と内容
総需要の量が十分だとしても、その内容が問題となる。
なるほど、公共事業を増やせば、総需要の量は増える。そのことで、総生産が元の水準まで戻るかもしれない。しかし、たとえ総生産が元の水準に戻っても、経済そのものが元の水準に戻ったわけではない。量的には戻っても、質的に変わってしまうからだ。つまり生産量の、産業間の比率が変わってしまうからだ。( → 8月26日 )
公共事業を増やしたとき、総需要は拡大するが、景気がいいのは土木産業ばかりで、一般の産業は景気が悪いままだ。土木産業では、黒字と人手不足が発生するが、一般の産業では、赤字と失業が発生する。── 要するに、一国のなかで、インフレとデフレが同時に発生するだけだ。
これを見て、「一国全体をまとめて見れば、インフレでもデフレでもないぞ」という主張が、ケインズの主張だ。しかし、あまりにも、おおざっぱすぎる。インフレとデフレがうまく混ざって、中和すればいいのだが、そういう具合には行かない。いくら土木産業が好景気だからといって、他の産業が好景気になるわけではない。パソコン生産の工場で、ダムを造ることはできない。
結局、単に総需要だけを増やしても、ダメなのだ。産業間の比率をそのままにするのが原則であり、特定産業だけを伸ばして総需要を増やしても、メリットどころかでメリットが生じるのだ。
( ※ このことは、ケインズ派批判になっているが、マネタリストにも同様のことは言える。マネタリストは、投資促進で、設備投資関連の産業ばかりを伸ばそうとする。これもまた、全産業を均等に戻そうとせず、特定の産業だけを伸ばそうとする。どちらも、同じ穴のムジナ。)
(2) 経済の自立
総需要を拡大することで、本質的に景気が回復したか否かは、そこで経済が自立できるかどうかで決まる。
減税(タンク法)ならば、交点 A から交点 B に移行する。そして、そこで自立する。(元の均衡状態に戻ったわけ。)
公共事業ならば、交点 A から(交点 A’を経由して)交点 E に移行する。では、そこで自立できるか? 図を見ればわかるとおり、交点 E では、投資は増えた状態( Ie )になっている。だから、交点 E で投資を減らせば、投資が Ie から I に減少するのにともなって、45度の線も、「 C = Y−Ie 」から「 C = Y−I 」に上昇する。
すると、ふたたび「需要不足」(需給ギャップ発生)という状況が発生する。つまり、45度の線に比べて、交点 E は、下方に離れた位置にある。だから、あとは、先に述べた「景気悪化の過程」とほぼ同じ経路をたどって、ふたたび交点 A に戻ってしまう。(下図を参照。B の下方の青線の足を E と見なす。この E を出発点として、「 C = Y−I 」という直線との相互影響で、景気悪化の過程が起こる。)
つまり、公共事業で一時的に景気を回復して、交点 E に達しても、それは、あくまで公共事業の増加によるものである。だから、公共事業を中止したとたんに、燃料切れのような状態になって、ふたたび元の交点 A に戻ってしまうのである。── つまり、交点 E では、経済が自立していないわけだ。(自立しているか否かは、前項および前々項を参照。)
では、なぜ、経済が自立していないのか? 「生産量が元の水準を回復したのならば、経済は自立するはずだ」とケインズならば主張するだろう。総需要だけに着目するから。── しかし、経済が自立するための条件は、総需要だけではないのだ。次の二つの条件 (i) ,(ii) がある。
- 景気回復後の生産量が、均衡点の生産量( Yb )を、上回っていること。
- 景気回復後の消費性向が、元の消費性向に戻っていること
前者は、総需要の問題だ。「最初にドカン(巨額の景気刺激策)」が必要だ。そして、それがあれば、乗数効果などを通じて、最終的に均衡点の生産量を上回るようになる。 (前々項で述べたとおり。)
後者は、消費性向の問題だ。総需要だけでなく、消費性向も問題となる。これについては、次の (3) で説明する。
(3) 消費性向の向上
上の二つの条件 (i) ,(ii) のうち、(i) を満たしていたとする。つまり、交点 E における生産量が、交点 B の生産量( Yb )を、上回っているとする。
ここで、公共事業を元の水準まで減らせば、45度の線は上にシフトする。すると、その線に比べて、交点 E では、消費が少なすぎるので、そのあと、「 C = Y−I 」という直線によって、交点 A まで景気が悪化してしまうわけだ。(先に述べたとおり。)
さて。生産量が十分であるのに、そうなってしまうとしたら、なぜか? 消費が少なすぎるからだ。消費が少ないから、同じ生産量で、「 C = 0.7Y + Ca 」という直線上の点に位置することになる。逆に、消費が十分であれば、そうはならない。たとえば、「 C = 0.8Y + Cb 」という直線上の点だ。同じ生産量でも、この直線上の上に位置すれば、消費不足は発生しない。だから、そこで安定する。(右にも左にも移行しない。そこ自体が安定点である。)
結局、状況が安定するためには、生産量が拡大するだけではダメで、消費もまた拡大している必要があるわけだ。つまり、総需要が拡大するだけではダメで、消費性向も上昇している必要があるわけだ。(それが、「二つの条件 (i) ,(ii) がともに成立する」、ということ。)
では、消費性向を上昇させるには、どうするべきか?
第1に、タンク法の減税ならば、もともと消費性向は上昇している。( 0.7 → 0.77 など。) その場合には、このあと特別に消費性向を操作する必要はない。
第2に、タンク法以外(定額の財政支出で直線を上シフトまたは下シフトする方法をする方法)では、そのとき消費性向が上昇するか否かは、人々の心理しだいとなる。人々が先行きについて楽観して、「世の中バラ色だなあ」と思えば、消費を増やすだろう。たとえ実際に潤っているのは土木産業ばかりで、一般産業の人々の財布は薄っぺらでも、「何とかなるかもしれないなあ」と楽観すれば、景気は回復するだろう。一方、「世の中お先真っ暗だなあ」と悲観すれば、景気は回復しないだろう。儲かっているのは土木産業ばかりで、自分に波及するのは1年後に半分、2年後に4分の1、というふうに判断して、「今はまだまだ貧乏だ。おまけにアメリカの景気も悪いし、輸出も望めないなあ」と思えば、「当分の間は、財布のヒモを引き締めよう」と思うようになる。こうなると、公共事業の効果が切れたとたんに、麻薬切れと同様で、ふたたび景気は下降していく。
まとめ。
景気の回復には、総需要の拡大のほか、消費性向の上昇が必要である。
消費性向の上昇は、タンク法以外の場合では、人々の心理に依存する。人々の心理が明るければ、景気は回復する。人々の心理が暗ければ、景気は悪化する。
[ 付記 ]
とにかく、最終的には、「消費性向が元に水準まで上がる」ことが必要である。それが不況脱出の本質的な条件だ。(必要条件であり、かつ、十分条件である。)
生産量が十分に拡大しても、消費性向が元の水準まで上がらなければ、その生産量拡大は、あくまで公共事業に支えられたものにすぎない。当面は不況でないとしても、公共事業を減らせば、また不況に逆戻りすることになる。一種の上げ底景気である。この先、経済悪化を避けるためには、公共事業というカンフル剤を慢性的に投入しつづける必要がある。── そういう状況は、現象的には「不況ではない」と呼べるかもしれないが、本質的にはとても「不況を脱出した」と言える状況ではない。
不況を解決するということは、ピラミッドを建設したり、穴を掘ったりして、失業者をなくすことではない。実際の生産を元の水準に戻すことだ。つまり、自動車やパソコンなどの生産を元の水準に戻すことだ。そして、そのためには、ピラミッド産業の需要を増やすのではなくて、(下がった消費性向を高めることで)自動車やパソコンなどの需要を増やす必要がある。単に数字的に紙幣のやりとりをして、名目的な生産額を高めればいいのではなくて、実質的な生産物(価値あるもの)を元の生産水準まで高める必要があるのだ。── その本質に気づくことが大切だ。
( ※ ガラクタの生産と価値物の生産とでは、名目価格では同じ額を生産するとしても、実質価格では月とスッポンほども違う。そこに核心がある。単に名目価格だけにとらわれると、「穴を掘って埋めればいい」というふうに考える。)
[ 補足 ]
「消費性向が上がるか否かは、人々の心理に依存する」と述べた。ただし、人々の心理に依存するということは、まったくの「あなた任せ」ということにはならない。人々の心理そのものを動かす経済操作もある。
それは、「物価上昇」だ。物価上昇があれば、「アメとムチ」効果により、人々の心理を掻き立て、消費性向を高めることができる。
「アメとムチ」効果つまり「物価上昇」は、どうすれば得られるか? 不況のときなら、減税や公共事業しか有効ではないが、いったん不況を脱したあとなら、金融政策が有効となる。だから、不況を脱したあとでも、金融緩和を続けていれば(つまり、金利を上げなければ)、物価上昇が発生したあとも、物価上昇が継続する。かくて、消費性向は高まる。こうして、不況を見事に脱することができる。
結局、不況期には金融政策は無効だが、不況脱出後には金融政策が有効になるから、
「 不況のときは:ケインズ政策 → 不況脱出後は:金融政策 」 (*)
というふうにすることで、不況を脱出することができるわけだ。(後段の「不況脱出後は:金融政策」というのは、「インフレ目標」の考え方に近い。)
( ※ このやり方で、「景気回復」は成功するだろう。ただし、それがベストかどうかは、タンク法との比較でわかる。タンク法ならば、特に何も変わらず、単に消費性向が上がるだけだ。単純に不況から好況へと移行するだけだ。損もなく、得もない。一方、上記の (*) のやり方では、損と得が同時に発生する。土建産業は拡大して、一般産業は縮小する。土建関係者はボロ儲けして、一般国民は損をする。おおざっぱに言えば、物価上昇の分だけ、一般国民は損をする。だから「インフレ反対」と国民は叫ぶだろう。実際、国民は物価上昇の分だけ損するわけだから、「インフレ反対」という理屈は一理ある。しかし、国民が損した分、土建産業はボロ儲けするし、政治家は袖の下をもらえる。国民にとって有益なのは、タンク法の方だが、政治家にとって有益なのは、「ケインズ政策 → 金融政策」の方なのである。だから、政治家には、こちらが人気があるのだろう。)
● ニュースと感想 (9月07日)
時事的な話題。
「物価連動国債」を、財務省が提案したという。消費者物価指数に連動する、という形。元本は保証しない。デフレ期には元本割れを起こすので、デフレ期には誰も買うはずがない、という国債。(各紙・朝刊・経済面 2002-09-04 )
誰も買うはずがない国債を提案する、というのも馬鹿げた話だが、そもそも、話の根本を理解していないようだ。「物価連動国債」というのは、かつて提案されたこともあるが、それらはいずれも、「福祉対策」としての国債である。高齢者などが老後の安定を得るために、実質的に損をしないことを保証する国債だ。こういうのは、あくまで、弱者を守るための福祉的な政策であって、金融政策ではない。
金融政策で行なうなら、「短期金利に連動する形」という形でしかありえない。これこそが最も正当である。また、これが、最もリスクが少なく、かつ、コストが少ない。
問題が出るのは、「物価上昇率」と「短期金利」とが乖離した場合だ。たとえば、景気の回復過程で、物価上昇率が2%となり、金利は(インフレ目標で)ゼロ%だったとする。物価連動国債ならば金利は2%だが、短期金利連動国債ならば金利はゼロ%だ。このとき、市場で取り引きされる物価連動国債は、(利回りの分を見込まれて)元本が暴騰する。そのあとで、短期金利が上昇して、物価上昇率に追いつくと、物価連動国債は、(有利性が失われるので)市場における元本が反落する。また、インフレ懸念が出て、金利が上昇すると、物価連動国債は、(利回りの損を見込まれて)暴落する。……こういうふうに、たとえ物価上昇率が安定していても、短期金利との比較で、暴騰したり暴落したりする。非常にリスクの高い商品となる。とても素人の扱えるものではない。あくまでプロが売り買いする、プロ向けの相場品となるだろう。(素人にとっては、こんなものより、普通の民間の長期債権の方が、ずっとマシだ。途中で暴落したり暴騰したりすることはないので、安定性が高いからだ。株でなく、債券を買うのだから、その方がいいに決まっている。暴騰や暴落を楽しみたいのならば、株でも買えばいい。)
これに比べて、短期金利連動国債ならば、何も問題はない。暴騰したり暴落したりすることはない。この点では、長期国債よりも優れている。また、利子は、短期金利に連動する形だから、普通の長期国債に比べて、リスクが少ない分、金利も低くなる。だから国は、長期国債を、短期国債並みの低金利で発行できる。つまり、国としては、利払いを少なくできるわけだ。これは債務を圧縮する効果がある。
こちらが本道なのだ。あくまで金融政策の本道を歩むべきだろう。「物価連動債」なんてのは、金融政策としては外道である。メリットよりも、デメリットが大きい。こんなものは、発行しない方が、マシである。
( → 3月19日 の (3) )
● ニュースと感想 (9月07日b)
時事的な話題。
「ペイオフ」と「株価下落」の関連。
ペイオフについては、何度も述べてきたとおりだ。
- 不況期に、そんなことを実施すると、不安を掻き立て、ひどいことになる恐れがある。そんな危険を冒すべきではない。
- 不況期には、すべてが劣者となるので、優勝劣敗の原理が働かない。( → 8月10日 )
という2点だ。(つまりは、不況期にはペイオフを実施するべきではない、ということ。ペイオフを実施していいのは、不況を脱したあと。)
さて。上の2点のうち、今は、後者が大事だ。なぜならば、現在、株価が下落しているからだ。「株価下落」→「含み資産低下」→「銀行財務の劣悪化」という過程が働くからだ。
最近のように、株価が下落していると、含み資産の低下から、まともに存続できる企業は、東京三菱だけになりそうだ。ここで、「優勝劣敗による市場の最適化」というペイオフ実施論者の意見に従うと、東京三菱以外の全銀行が倒産しなくてはならない。なぜなら、いずれも財務内容が劣悪だからである。しかも、その財務内容が劣悪な理由は、それらの企業が劣悪である(赤字経営である)からではない。銀行は多くは、黒字経営だ。しかるに、他の企業が赤字であるせいで、株価が下落して、銀行の財務内容は劣悪になる。こういう状況で、「東京三菱以外は全部つぶしてしまえ」というのがペイオフ賛成論者だ。
一方、郵貯がある。郵貯の資金を使う財政投融資というのは、中小企業などに貸し付けていて、焦げ付きが多い。だから、郵貯の経営というのは、劣悪の極みである。しかるに、国家が保証しているせいで、郵貯の経営状態は劣悪ではない。(なぜなら悠長の出した赤字は、郵貯ではなく国がかぶるからだ。) また、郵貯は、固定資産税を初め、さまざまな税が減免されている。というわけで、劣悪の極みである郵貯は、ペイオフをしても安全である。
だから、ペイオフ実施というのは、「優秀な銀行は、つぶしてしまえ。劣悪な郵貯は、つぶすな」ということだ。そして、その末にあるのは、「劣悪な政府をもった日本をつぶしてしまえ」ということだ。
[ 余談 ]
「ペイオフ実施」というのは、それ自体が劣悪な主張なのである。こんなデタラメな主張は、さっさと淘汰されるべきだ。ところが、不況のせいで、人々の頭が錯乱しているので、デタラメな主張も堂々とはばかるのである。
● ニュースと感想 (9月08日)
新聞批評。(朝日・経済面 2002-09-07 )
二人の経済学者の主張。インタビュー形式。
(1) 岩田規久男
「限度なしの国債買い上げ」というウルトラ量的緩和論。「それで株・不動産に資金が回り、資産価格が上昇し、それが波及して景気が良くなる」という理屈。
まったく、メチャクチャな意見だ。難点を列挙する。
- 「株・不動産に資金が回るから、インフレになる」というのは、成立しない。バブル期を見よ。物価は3%程度で安定したまま、物価は上昇しなかった。単に資産インフレが発生しただけだった。「貨幣量増加 → インフレ」ではなく、「貨幣量増加 → 資産インフレ」なのだ。
- 「資産インフレでインフレが起こる」と述べているが、その理由が「資産価値が増えるから、担保能力が増して、企業の投資が増える」だって。今は、「投資意欲があるのに金がない」のではない。だからこそ、金利はゼロなのだ。「投資意欲があり、担保が足りない」のならば、金融市場で「需要過剰、供給不足」だから、金利は高くなるはずだ。話の根源を勘違いしている。(不良債権論者と同じ間違い)
- 「資産インフレでインフレが起こる」と述べているが、そのために莫大な資産インフレをふたたび起こせば、バブルの成長と破裂という地獄をふたたび繰り返すことになる。「資産インフレなしのインフレ」が好ましいのに、何だってわざわざ、「資産インフレ」(バブル)という大失敗を繰り返す必要があるのか。狂気。
- 米国を見てもわかるとおり、バブルというのは、あるとき突然、破裂する。インフレは制御可能だが、バブルは制御不可能なのだ。なのに、話の論理が錯乱している。「資産インフレを起こせ」と唱えて、同時に、「インフレは制御可能だ」と述べている。何を言っているのだ? 「資産インフレを起こせ」と唱えたら、「資産インフレは制御可能ではない」と言うべきなのだ。ここで「インフレは制御可能だ」と述べるのは、論理になっていない。
- 基本的には、「市場に出した金が、実際に使われる」という妄想の上に立っている。「金が滞留すること」、つまり、「流動性の罠」を理解していない。
(2) 賀来景英
量的緩和否定論者。朝日には珍しく、(1) への批判を載せて、紙面のバランスを取っている。この意味では、なかなか良い。読者にも親切だ。新聞記事というのは、こういうふうに構成するべきだ。これは、好ましいので、褒めておこう。
ただ、人選が、ちょっとまずい。経済学に無知なせいか、一番肝心な点が、論拠から抜けているからだ。記事の主張では、「量的緩和が無効だというのは明らかだ」と述べる。ただそれだけ。論拠なし。これでは、いくら正しい意見を言っても、説得力が全然ない。単に (1) と反対の意見を言っているだけだ。他人の意見を否定するだけなら、小学生でもできる。「おまえは正しくない、おまえはバ〜カ」と言っているだけだ。ガキですね。(こんなのを載せる新聞というのもどうかしているが。)
「量的緩和が無効だ」と述べるのなら、その根拠も述べるべきだ。つまり、「いくら資金を投入しても、滞留が発生するだけだ、という『流動性の罠』という現象が発生している」と。たったの45字で説明できる。それがないから、「ガキの言い分」にすぎないのだ。
記事の見出しからして、狂っている。「小出しの金融政策は無意味」というのは、岩田の主張であって、(2) の方の主張ではない。(2) の方は、「金融政策そのものが無意味だ」と述べているし、むしろ、「制御不能の状態になるから、金融政策を大幅にやるのはダメだ」とも主張している。見出しを見れば、「小出しがダメなら、大出しをせよ」というふうになるが、「小出しはダメだが、大出しはもっとダメ」というのが本人の主張だ。(そしてそれは正しい。) 「小出しがダメだから、大出しをせよ」というのは、(1) の方の主張だ。記者はとんでもない勘違いをしている。
なお、(2) の主張をする本人は、サプライサイドに属する。「経済体質の悪化が不況の原因だ。だから経済体質を強化せよ」というわけだ。しかし、こんなのが間違いだと言うことは、歴史を見れば、すぐにわかる。「バブルのころは、日本の経済体質はすばらしかったが、そのあとでは、日本の経済体質は急速に悪化した」というのか? そんなことはあるまい。バブル期に比べれば、企業の体質は強化されている。しかし、個々の企業がいくら体質を強化しても、マクロ的に需要が縮小していては、どうにもならない。どんなに優秀な製品を作っても、買ってくれる客がいなくては、どうしようもない。そこを理解することが大切だ。彼の主張は、「バブルのころは、日本の経済体質はすばらしかった」ということであり、結局は、「日本の経済体質がすばらしいから、バブルが起こるのだ」という、当時のバブル礼賛と同じだ。バブル信者。事後追認。現状肯定。……単純に言えば、「勝ったものになびく」という、お調子者だ。
( ※ この人の主張は、同日の読売・経済面にもある。凡庸で、コメントに値せず。)
総評。
記者の経済学的知識が欠落している。基礎知識が抜けているから、ピンボケのインタビューをしたり、相手の難点を付けなかったり、正反対の見出しを付けたりする。
インタビューをするなら、次の点を理解するべきだ。
- 不況の理由は、投資不足でもないし、企業体力の劣化でもない。(前者はマネタリストの主張。後者はサプライサイドの主張。)消費不足である。
- 「貨幣数量説」を正しく理解するべきだ。貨幣の供給は、物価または資産価格を上げる。物価を上げるとは限らず、資産価格だけを上げることもある。後者の場合は、インフレではなく、資産インフレが発生する。
- 「インフレ目標」と「資産インフレ」の関係を正しく理解するべきだ。物価上昇率だけをメドにして、過剰な資金供給を実施すれば、莫大な資産インフレが発生して、制御不能な状態となる。(バブルの再来だ。)そして、制御できなくなった据えに、バブルは破裂する。再度の地獄。
- 「流動性の罠」について理解し、説明するべきだ。つまり、「いくら資金を投入しても、使われずに滞留することがある」と。そして、「今はその状況なのだ」と。そして、その結論は、「資金を莫大に投入しても、滞留が莫大になるだけで、意味はない」ということだ。(そして、その意味のない金が、いつか意味をもったとき、資産インフレというバブルが発生する。)
特に、最後の「流動性の罠」が、一番肝心だ。この一番肝心なことを抜かしている限り、記事は、アンコのないアンパンのようなものだね。( hamburg のない hamburger かな。er と呼ぶべきかも。なお er は日本語の「え〜」「あの〜」であり、無意味な言葉。)
[ 付記 ]
マネタリズムというものは、不況期には無効になる。その理由については、数日後に、修正ケインズモデルを使って説明する。(「ケインズ派 & 古典派」との関連。)
● ニュースと感想 (9月08日b)
時事的な話題。
過程の金融資産がどんどん減少している、とのこと。(各紙・朝刊 2002-09-07 )
つまり、「人々が、消費しないで貯蓄するから、景気が悪化するのだ」という段階を通り越して、もっと悪い状況になっているわけだ。
消費性向が低下しただけではなく、所得そのものが減少していることになる。これは、修正ケインズモデルにおける「景気悪化のスパイラル」が進んでいることを示す。
ここまで悪化すると、小さな景気刺激策では、とても回復のメドが立たない。「景気の底打ちにともない、そのうち景気は回復する」というような甘い考えは、捨てた方がいいだろう。「底深くで低迷する」という状況になりそうだ。
● ニュースと感想 (9月08日c)
時事的な話題。株価がまた低下したことについて。
「いつになったら、景気は回復するのか? もうバブル破裂から、12年もたったのだから、そろそろ景気循環で、景気は回復してもいいのでは?」
と人々は思うかもしれない。しかし、それは、勘違いである。
・ 過熱した景気は、必ず縮小する。(過剰消費のあとは過少消費)
・ 縮小した景気は、拡大するとは限らない。(縮小状態の継続。)
というふうになるからだ。つまり、上れば必ず下がるが、下がったあとは上がるとは限らない。そういうふうに非対称性がある。
前者(上がれば必ず下がること)は、当然だ。人は、生産した以上には、消費できない。年収 400万円の人間が、毎年 500万円の消費をしていれば、いつかはそのツケ払いを迫られる。ツケ払いができなければ、破綻する。当たり前のことだ。( → 9月02日 の [ 参考 ] ,6月13日 )
後者(下がっても上がるとは限らないこと)は、ここ数日、述べてきたことを理解すれば、わかるだろう。一時的な小さな景気後退ならば、単に消費しないで貯蓄しているだけだから、そのうち、貯蓄を崩して、消費が増える。しかし、長期的な本格的な景気後退(つまり不況・デフレ)だと、所得そのものが減ってしまうから、たとえ消費を減らしても、貯蓄が増えるわけではない。こうなると、どん底である。ここから抜け出すことは、容易ではない。「景気循環」というふうに、「いつかは戻る」ということは成立しないのだ。
理論的に言えば、交点 A という収束点に、いったん落ち込んでしまったら、放置するだけでは、そこから回復することはできない。何らかの景気回復策が必要となる。
( cf. さまざまな景気回復策については → 9月02日 )
結語。
景気回復には、放置しているのではダメで、まともな景気回復策を取る必要がある。まともな景気回復策を取らない限り、この先ずっと景気が回復しないこともある。米国のバブルがはじけたとなると、この先、大転落を起こして、失業率が倍増するかもしれない。日本中の銀行が倒産するかもしれない。(そうなったら、ペイオフ賛成論者は、大喜びだろうが。「わーい、わーい、銀行を全部倒産させちゃった! 大成功!」と。)
なお、まともな景気回復策とは、需要拡大策のことを言う。「ゼロ金利下での量的緩和」という無効な策は、まともではない。「構造改革、企業体質強化、生産性向上」というのは、需要対策ではなくて供給対策なので、見当違いであり、まともではない。こんなことをやっている限り、時間が浪費されるだけだ。もう 12年も浪費している。
( ※ 「いったん落ち込んでしまったら、放置するだけでは、そこから回復することはできない」というのは、「ナッシュ均衡」などと関連する。これは、後日、改めて考察する。数週間先に。)
● ニュースと感想 (9月09日)
時事的な話題。景気の近況。
5〜6月ごろには、けっこう先行きの見通しが明るい、という意味の記事が出ていた。1〜3月は、輸出の増加で、企業の業績がやや持ち直したし、個人消費もいくらか良くなった。企業経営者の業績予想も良く、先行指数が明るい見通しとなった。……などなど。(朝日・経済面 2002-09-07 に関連記事あり。)
私は、全然、こんなのを信用していなかった。輸出増加は、円安による一時的なものだが、米国景気の悪化にともなって、円安はつぶれたし、輸出の見通しも暗い。先行きの見通しが明るいのは、円安という一時的な現象の上にたつ妄想。個人消費が増えたのは、単身者世帯がマーチなどの新車を買っただけの話で、所帯持ちは逆に消費を減らしているから、「単身者重視」という政府統計の統計ミスが出ただけ。……一番肝心なのは、四月から賃下げになった、ということだ。仮に、定昇がゼロだとしたら、一人一人は賃上げ率がゼロでも、国全体では、本来の定昇の分だけ、経済は縮小する。(高齢の高所得者が消えて、若手の新卒者か失業者が増えるので。)
さて、結果は? 法人を重視した新統計によると、4〜6月には、企業の売上げも利益も、過去最大と言える大幅な減少。特に、製造業でなく、非製造業で、この傾向が著しい。(朝日・朝刊・経済面 2002-09-06 )
もっともな話だ。個人消費が縮小すれば、製造業よりも、非製造業の方が影響を受ける。たとえ輸出企業が堅調でも、非製造業が不況だ。そもそも、GDPの大部分を占めるのは、製造業ではなくて、サービス業である。つまり、国民の多くは、製造業ではなくてサービス業で所得を得ている。
なのに、経済学者は、「円安で景気回復」だの、「企業の設備投資増加」だの、「構造改革で企業の生産性向上」だの、そういうことを主張している。これらはまったくの見当違いなのだが。なぜなら、そういうことは、サービス業では、あまり意味がないのだから。
( ※ 本項を読んだ新聞記者がいたら、ちゃんと、上記のことを検証してほしいですね。「円安」「法人税減税」という提案で、本当に、サービス業の景気が良くなるのか? たとえば、円安や法人税減税で、床屋や豆腐屋や映画館などの景気が良くなるのか? そうならないようなら、そんな経済政策は国民にとっては無効なのだ。……減税と比べて見よ。)(まったく、古典派ないしレーガノミックス信者の誇大妄想ばかりを報道する新聞記事には、うんざりだ。)
[ 参考 ]
なお、「法人税の減税」については 8月23日b の最後の [ 補説 ] も参照。「日本の法人税率は高い」という馬鹿げた主張を、相も変わらず、新聞は書き続けているが。
また、「都市再生の公共事業」というケインズ派的な主張もあるが、これについては、12月27日c を参照。
● ニュースと感想 (9月09日b)
前項の続き。
景気回復策として、「生産性を向上させよ」「企業の体質を強化せよ」という意見が、相も変わらず、出ている。しかし、そういうことは、間違いである。個々の企業ならば、そうすることで、赤字から黒字になるだろう。しかし、そんなことをしても、不況は解決しないのである。
実証することも可能だ。それは例の「IT革命」だ。「米国ではIT革命があったから、米国は景気がいい」という説が幅を利かせていた。しかし、その説が正しいならば、現在も米国は景気がいいはずだし、日本も 1990年代後半には景気が良かったはずだ。しかし、そうなっていない。「IT革命で生産性が向上した」というのは、いくらかは正しいが、しかし、そのことが景気には結びつかないのだ。
なぜか? これは、当たり前のことだ。古典派の大好きな「需給曲線」を見るだけでもわかる。価格は、需給のバランスだけで決まる。コストが低下すれば、価格も下がる。それだけのことだ。
結局、「生産性の向上で景気回復」と唱えるのは、需給曲線というものを理解できない人々なのである。「コストが下がれば、企業の利益が増える」と思い込むだけで、「コストが下がれば、市場価格が下がる」ということを無視する。つまりは、「市場経済」という原理を理解できないわけだ。
結語。
景気を回復しようとして、いくら生産性向上によって、コスト低下を実現しても、それは何の役にも立たない。特定の企業だけでコスト低下を実現すれば、その企業は、市場価格の変動がないまま、コスト低下のメリットを享受できる。しかし、全企業がいっせいにコスト低下を実現すれば、もはや利益の向上は得られない。
その証明は、簡単だ。……百年前に比べて、現在は、圧倒的にすばらしい生産性の向上を実現している。しかし、今の景気は、百年前よりも劣る。景気の良し悪しは、市場の需給バランスだけで決まるのであり、生産性なんかはほとんど関係がないのだ。
[ 付記 1 ]
サービス業の例を示す。
床屋が生産性を向上させるとしたら、客の一人あたりにかける時間を下げて、安価で大量に髪を刈ることだ。しかし、それは単なる「サービス低下」にすぎない。質の悪いサービスを、安価で提供するだけだ。ほとんど意味がない。一般に、サービス業では、高価格で高品質のサービスを提供する店と、低価格で低品質のサービスを提供する店と、双方があって、階層分化している。前者が後者に転じたからとしても、単に「高級 → 低級」という業態転換が発生しただけであり、生産性が向上したことにはならない。)
一般的に、人件費が大部分を占めるサービス業では、「生産性の向上」というのは、あまり意味がない。サービスの内容というのは、はっきりとは目に見えないから、単に、客が払った額で計算するしかない。客が多く払えば、生産性向上。客が少なく払えば、生産性の悪化。つまり、好況ならば、生産性の向上。不況ならば、生産性の悪化。……それだけのことだ。
だから、「生産性の向上」なんてことを主張するより、さっさとマクロ的に総需要を拡大すればいいわけだ。サービス業が多い、という現実から、そういう結論が得られる。
[ 付記 2 ]
マクドナルドや吉野家は、徹底したコスト削減努力をして、価格低下と利益向上を実現した。「だから、これを見習え」と主張する人がいる。現実無視の妄想であろう。
なるほど、マクドナルドや吉野家は、そういうことができた。しかし、それは、国内シェアが1位の大企業であるからだ。こんなのが可能なのは、日本全体では、ほんの一握りでしかない。日本の大部分のサービス業は、零細企業である。これらの企業では、マクドナルドの真似をして、米国から資材を一括大量購入することなど、とてもできない。どう考えたって、たいていの企業で、「価格半減」なんて、できっこないだろう。
また、仮にマクドナルドの真似をして、生産性を向上させたとしても、国全体を見れば、問題は解決しない。マクドナルド1社だけなら、価格半減で、自社の売上げを増やすことができる。しかし、あらゆる企業が価格半減をしたら、たがいにシェアを食い合うので、自社の売上げを増やすこともできない。「価格低下でシェア向上」というのは、1社だけなら成立するが、国全体だけでは成立しないのだ。(マクロ経済学の常識。こういうことを理解できない無知な記者が、あれこれと新聞記事を書き立てる。)
また、生産性向上をすれば、価格は低下するが、同時に、失業問題が発生する。ある企業が労働者を半減させてコストダウンしても、日本全体では、多大な失業者が発生するだけだ。(シェアは増えないから、企業利益も増えない。) その多大な失業者を、うまく吸収できればいいが、一挙に多大な職場を提供することなど、不可能である。今の失業者は、370万人ほどいるが、これだけの失業者を吸収する新規企業など、あるはずがない。
では、解決策は? 当然、既存の全企業が、少しずつ失業者を吸収することだ。それしか、解決策はない。つまり、景気回復しか、解決策はない。逆に、「既存の全産業で大量の失業者を発生させ、それを特定の一部産業だけで吸収しよう」なんていうのは、とんでもない妄想である。そして、その妄想を、「構造改革」と呼ぶ。その骨子は、「生産性向上で景気回復」「全企業で失業者を発生させ、存在しない企業で失業者を雇用する」ということだ。……こういうことを、政府もマスコミも、進めようとする。狂気。
( ※ なぜ狂気かと言えば、狙う方向が正反対だからだ。「生産性向上」を狙えば、既存企業は、労働者をどんどん解雇する。しかし本当は、失業者をどんどん雇用するべきなのだ。ただ、総需要が一定のままでは、失業者を雇用することはできない。だから、あらかじめ、総需要を増やす必要がある。ここが肝心だ。この点を見失うと、「生産性向上」をめざすことで、「失業増大」をめざすことになる。── 小泉も政府も古典派経済学者も、みんなそうだ。彼らはそろって、山頂をめざすと夢見ながら、「大不況」という大穴をめざして進んでいるのである。レミングの集団自殺。旗振り役は、マスコミ。ハーメルンの笛吹き。)
● ニュースと感想 (9月10日)
これまで見たのは、「不況時の変化」だった。このあとは、「好況時の変化」を見ることとしよう。
まず最初に、これまでのことを、簡単に整理しておこう。以下で順に説明する。(1) は、不況期について。 (2) は、景気回復期について。(好況期については、次項以降で。)
(1) 不況期
不況については、次の図で示せる。
つまり、交点 B から、交点 A へと、移行していく。その原因は、消費性向の低下( 0.8 → 0.7 )である。ここで起こっていることは、「消費減 → 生産減 → 所得減 → 消費減 → ……」というスパイラルである。こうして景気が悪化していく。
(2) 景気回復期
景気の回復期については、次の図で示せる。
(a) 消費性向の向上の場合は、交点 A から交点 B へ、水色の線をたどって移行する。
(b) 定額の支出追加の場合は、交点 A (交点 A’を経由して)から交点 E へ、青色の線をたどって移行する。
( ※ 前者は、タンク法の減税。後者は、投資・公共事業・民間引き受け減税。)
以上の (1) (2) のいずれも、景気は平常よりも悪い場合の話である。(不況の進んでいく途中、または、不況から回復する途中。)つまり、いずれも、交点 B よりも左側にいる状態である。
では、交点 B よりも右側にいる状態(好況の状態)では、どうなるか? それが、このあとのテーマとなる。
● ニュースと感想 (9月11日)
時事的な話題。「少子化」問題。
「少子化問題を解決するには、職場の雰囲気や経営者の考え方を変えない限り、現状の政策には限界がある」という主張。(朝日・朝刊・オピニオン面 2002-09-10 )
こういう間違った主張が出るのは困りものだ。経済の分野でも、「個々の企業が頑張ればいい。国には責任がない」という意見がよく出るが、それと同じで、少子化の分野でも、「個々の企業や労働者が正せばいい。国には責任がない」という意見だ。
はっきり言おう。個々の企業間でバラツキが出るとしたら、それは個々の企業の問題だ。しかし、国全体で特定の傾向が出るとしたら、それは個々の企業の問題ではなく、国の問題なのである。「マクロ経済」というものをよく考えるべきだ。
日本では少子化が進んでいる。としたら、それは、個々の企業や労働者に問題があるのではなく、国に問題があるのである。こういう国の責任を免責するような記事は、まったくの困りものだ。少子化は、人殺しではないが、人口を減らすという意味では、人殺しにも似ている。そして、政府が人殺しのような悪事をやっているのに、「政府は責任がありません、国民の責任です」と、責任転嫁をする。まったく、最悪のマスコミだ。(こういうふうに政府の弁護ばかりするマスコミは、私は大嫌いだ。)
少子化は、国の責任である。少子化が進んでいるのは、国が「少子化を進めよう」という政策を取っているからだ。そんなことは、一目瞭然ではないか。下記の通り。
- 長時間労働 (労働時間がやたらと長いので、女性が就職できない。)
- 1日の残業規制がない(残業税がない)
- サービス残業という違法行為を見逃す(犯罪の放置)
- 休日不足(年休取得が少ない)
- 人員削減(一人あたりの労働時間が増える)
- 雇用人頭税(社会保障の企業負担がある。必然的に人員削減と長時間労働。)
- 男女差別
- 男女差別を放置し、罰則がない。
- 解消の促進策もない。
- 育児負担(育児に金がかかりすぎるので、子供を減らす)
- 幼稚園・保育園が不足。高額。
- 大学の授業料が、バカ高値。
- 奨学金制度の不足。(仕送りしたら親が破産しそう。)
- 児童手当もない。( or 不足)
結語。
日本には、「少子化促進」の制度が、以上のように、たくさん整っている。これほど「子供を減らせ」という制度が十分に整っている国は、ほとんどあるまい。出産に対しては、「福祉整備」のかわりに、「国民虐待」だ。
こういう状況では、「子供を減らす」という選択をするのが最も賢明である。「子供を増やす」という選択をするのは、よほど経済観念がない人だけだろう。
少子化は、起こるべくして起こったのである。国が「こっちへ進め」という制度を整えたから、その制度に従って、国民はその方向へ進んだだけだ。つまりは、国の政策に従っただけだ。
なのに、「どうして国民はそうしたのか?」と問うのは、頭がイカレている。政府は、自分が何をしているか、わかっていないのだろう。そしてまた、マスコミも。
( ※ 自民党は、「福祉の充実は、経済活力をそぐ」と主張して、福祉を削減してきた。そうして出産する国民を虐待しているのだから、国民はそういう政策に従って当然なのである。)
[ 付記 ]
正しくは、どうするべきか? もちろん、上記の各項を、正反対にすればよい。北欧では、そうしている。
最近、法人税減税が話題になっているが、これなど、「盗人に追い銭」だろう。犯罪者に金をプレゼントするわけだ。どうせなら、上記のような犯罪をする企業には、罰金を科するべきなのだが。(そして、その分、善良な企業に減税をすればいい。)
[ 余談 ]
だいたい、長時間労働ばかりしていては、帰宅後、愛の行為にも励めない。そこに注目するべきだ。経済学はやはり、愛を重視するべきだ。……というのは、脱線気味の話だが。
● ニュースと感想 (9月11日b)
好況時の変化は、どうなるか? それは実は、非常に話は複雑になるので、簡単には説明できない。詳しい説明は、あとで述べることでして、とりあえずは、要点を示しておこう。次のようになる。
- ケインズのモデルでは、「不況を脱した状態」とは、「完全雇用」の状態である。そのときの生産量 Y は、グラフ中の1点の値であり、YF または YF のように書かれることが多い。
- 修正ケインズモデルでは、「不況を脱した状態」とは、(需給の)「均衡状態」のことである。そのときの生産量 Y は、グラフ中の1点ではなく区間の値であり、一定の幅をもつ。
- この区間の中は、(需給の)均衡状態である。
- この区間の左端を「下限均衡点」と呼ぶ。その生産量は Yb と書く。
- この区間の右端を「上限均衡点」と呼ぶ。その生産量は Ym と書く。
- この区間の外では、(需給の)「不均衡状態」となる。(詳しくは、後述。)
図で示すと、次のようになる。
・ B は下限均衡点であり、その生産量は Yb である。
・ M は上限均衡点であり、その生産量は Ym である。
・ B と M の間が、均衡状態となる区間である。(これを、区間 BM と書く。)
ここで注目するべきことがある。それは、「区間 BM は、いかにして与えられるか?」ということだ。
その答えは、図を見れば、つかめるだろう。つまり、消費性向の直線だ。限界消費性向が 0.8 のときに、交点 B を得る。限界消費性向が 0.9 のときに、交点 M を得る。……このことについては、詳しくは、後述する。
[ 付記 ]
参考として、ケインズのモデルとの、比較を示しておこう。
ケインズのモデルでは、YF を下回れば不況であり、YF を上回れば(需要超過による)インフレである。均衡するのは、YF というただ1点のみである。
修正ケインズモデルでは、Yb を下回れば不況であり、Ym を上回れば需要超過である。その中間の区間では、不況でも需要超過でもなく、均衡状態となる。
( ※ だから、ケインズのモデルの1点 YF を、Yb と Ym の間の区間に引き延ばしたのが、修正ケインズモデルだ、と言ってもよさそうだ。── この意味で、修正ケインズモデルは、ケインズのモデルを拡張したものである。逆に言えば、ケインズのモデルは、修正ケインズモデルにおける特殊な場合[消費性向の変化のない場合]である。)
( ※ 現実の世界はどうか? 現実には、ケインズのモデルが成立するような特殊な場合は、まずありえない。換言すれば、現実の世界には、「均衡状態」というものが、1点だけではなく、ある長さの幅で存在するのである。これを無視したところに、ケインズのモデルの難点がある。)
( ※ 「均衡点」というものを重視する考え方に難点があることも、ここでわかるだろう。「均衡点が安定的だから、そこに落ち着く」というというのが、従来の経済学の考え方だ。しかし、実際には、「均衡状態」というのは、ある幅を持つことができる。そこでは、ただ一つの状態だけが許容されているわけではなくて、パラメーターを変動させた多くの状態が許容されている。── 具体的に、どのようなパラメータを変動させることができて、どのような状態が許容されているかは、次項で示す。)
★ 本項では、要点だけを示したが、次項以降では詳しく説明をしていく。
● ニュースと感想 (9月12日)
前項の図における「均衡状態」の区間について説明しよう。
区間 BM (つまり、下限均衡点と上限均衡点の中間)では、均衡状態となる。(一方、下限均衡点以下では不況となるし、上限均衡点以上では需要超過となる。)
さて。では、この区間(均衡区間)では、どうして、均衡状態を保てるのか? ケインズのモデルでは、均衡状態を保てるのは、ただ1点だけであった。なのに、なぜ、一定の幅で均衡状態を保てるのか?
まず、この区間の根拠を示そう。
下限均衡点は、直線「 C = Y−I 」と、直線「 C = 0.8Y + C1 」との、交点として与えられる。これが B だ。
上限均衡点は、直線「 C = Y−I 」と、直線「 C = 0.9Y + C2 」との、交点として与えられる。これが M だ。
そして、この B と M の間が、区間 BM となる。
( ※ なお、0.8 や 0.9 という値に、特別な意味はない。とりあえず例示的にこの値を取っただけであり、少しぐらいズレた別の値でもいい。)
さて。肝心なのは、直線「 C = Y−I 」だ。なぜ、この式が成立するのか? その理由は、次の通り。
- 貯蓄は、生産から消費を引いた残りとして、定義される。つまり、「 S ≡ Y−C 」である。ゆえに、「≡」を「=」に置き換えて、「 S = Y−C 」が成立する。(これは恒等式。)
- その式で、右辺と左辺で移項して、「 C = Y−S 」が成立する。(これも恒等式。)
- 「 I = S 」が成立する。(つまり、投資は貯蓄に等しい。これが大事。)
- 上の ii ,iii から、「 C = Y−I 」が成立する。
かくて、「 C = Y−I 」という式を得られた。
ここで、問題は、第iii項だ。なぜ、「投資は貯蓄に等しい」と言えるのか?
実は、このことは、常に真実となるわけではない。「投資は貯蓄に等しい」と言えないこともある。しかし、均衡状態においては、「投資は貯蓄に等しい」と言える。なぜか? それは、金融市場を通じた「貯蓄 → 投資」という資金の流れがあるからである。
- 貯蓄が増えれば、金利が下がり、投資需要が増える。
- 貯蓄が減れば、金利が上がり、投資需要が減る。
こういうふうに、金利の上下を通じて、貯蓄の増減に応じて、それとは逆方向に投資が増減する。かくて、貯蓄と投資は、常に同額となるのである。そして、貯蓄とは、生産から消費を引いた残りだから、結局、「消費が増減すれば、その分だけ逆に、投資が増減する」ことになる。
つまり、消費に変動があっても、それを補う方向に投資が増減することで、「消費と投資の和」である需要は、常に生産額に一致するように保たれるわけだ。
結局、「需要と供給は一致する」と言えるわけだ。そして、その理由は、消費の変動を、投資の変動が補うからである。それが可能なのは、金融市場で、貯蓄が投資に向かうからである。
なお、「需要と供給は一致する」というのは、「セイの法則」の前段にあたる。そして、均衡状態では、このことが成立するわけだ。
ケインズは、「需要と供給は一致する」のではなく、「需要が供給を決める」と主張した。その主張は、不況では成立する。しかし、不況を脱したあとでは成立しない。
つまり、ケインズの主張は、不均衡状態(不況)では正しいが、均衡状態では正しくない。そういうことが、修正ケインズモデルからわかる。
そして、「均衡状態」および「不均衡状態」を、ともに説明できることで、修正ケインズモデルは、「ケインズ派」と「古典派」の統合を、一歩進めたことになる。
なお、前項の図で言えば、
・ 区間 BM …… 均衡状態。 古典派的。
・ B より下 …… 不均衡状態。ケインズ的。
修正ケインズモデルは、この両者を含む。(双方を包含している。それだけ広い理論である。)
[ 付記 1 ]
均衡状態では、消費の減少は、投資の増加となる。そのことは、金融市場における金利の変動を通じてなされる。ここまでは、すでに述べたとおりだ。
ただ、金利の変動には、金融当局が介入できる。そのことで、「貯蓄 → 投資」という資金の流れを、加速したり減速したり、コントロールできる。── それが、金融政策の意味だ。
金融政策というのは、単に貨幣供給量をコントロールしたり、預金の利息をコントロールすることを意味するだけではない。そういうことをすることで、「貯蓄 → 投資」という資金の流れをコントロールし、それによって、「 C = Y−I 」という関係を通じて、一国経済全体をコントロールすることだ。
そして、このコントロールを失敗すると、「貯蓄 → 投資」という資金の流れが不自然になり、「 C = Y−I 」という関係が成立しなくなる。そうすると、もはや均衡状態は達成されなくなり、不均衡状態となる。
不均衡状態になるとどうなるかは、次項以降で説明する。とにかく、金融政策の本質は何かは、ここで示したとおりだ。
( ※ なお、金融政策が適切であれば、うまく均衡状態を保てるので、通常の場合は、景気調整は金融政策だけでも足りる。)
[ 付記 2 ]
「貯蓄 → 投資」という資金の流れは、金融市場を通じてなされる。ただし、金融市場に流れない金がある。タンス預金がそうだ。その分は、この説明では、無視している。
仮に、均衡状態において、人々が預金をしないで全額をタンス預金すると、どうなるか? 「消費の減った分だけ投資が増える」ということが成立しなくなる。こうなると、均衡が崩れてしまう。
実際には、タンス預金の増減が発生しても、それを補う方向で、金融当局が資金を供給する。だから、特に問題は発生しない。(そういうわけだから、タンス預金の分は、無視しても構わない。)
[ 付記 3 ]
トリオモデルとの関連も示しておこう。
区間 BM では、均衡状態となる。これは、トリオモデルでは、需給ギャップのない状態[下限直線に阻害されていない状態]を意味する。
そして、区間 BM (特に下限均衡点 B )よりも左下に移行すると、需給ギャップが発生して、不均衡状態となる。これは、トリオモデルでは、需給ギャップのある状態[下限直線に阻害されている状態]を意味する。
● ニュースと感想 (9月13日)
前項の続き。
「貯蓄 → 投資」という資金の流れがある、と前項で述べた。このことを考慮すると、すでに述べたことは舌足らずであることに気づく。(「補正を要する」と言ってもいいくらいだ。)
修正ケインズモデルについてすでに述べたときは、「投資 I は一定である」ということを前提としていた。たとえば、次の図もそうだ。ここでは、「 C=Y−I 」という直線を描くとき、「 I 」を定数だと考えている。
しかし、もはや、「投資 I は一定である」ということは成立しなくなるのだ。「投資 I は変動する」となるのだ。── 「貯蓄 → 投資」という資金の流れがあるのならば。つまり、消費が減った分、投資が増えるのならば。
では、このことを考慮すると、どうなるか?
その問いに対する答えは、先に「乗数効果」で示したことを見ればわかる。
初めに B にいる。単純に消費性向が低下すれば( つまり I が定数のまま消費性向だけが低下すれば)、グラフで B から A に移る。そのあと、公共事業などの投資拡大があれば、投資が I から Ie に拡大する。それにともなって、 A から A’に移り、さらに、「 C=Y−Ie 」によって、 E に移る。
こういう過程がある。これは、「消費性向の低下のあとで、投資の追加があった場合」である。しかし、「消費性向の低下と同時に、投資の追加があった場合」でも、話は同様となる。このときは、「 B → A → A’ → E 」という長たらしい経路はたどらず、短絡的に、「 B → E 」という経路をたどる。しかも、B と E とで、生産量は同じになるはずだ。なぜなら、消費が減った分、ちょうどぴったり、投資が増える(補う)からだ。
結局、どういうことか? まとめれば、こうだ。
- 投資 I が一定ならば:
消費性向の低下は、(投資は不変なので)消費の縮小だけをもたらす。いったん消費の縮小が起こると、それがスパイラル的に進んで、生産量がスパイラル的に縮小する。
- 投資 I が一定でなければ:
消費が減れば、その分、投資が増える。両者の和である生産量は不変である。消費性向の低下は、消費を減らすが、同時に、投資を増やすから、単に、消費と投資の割合を変化させるだけだ。
前者は、「投資 I が一定」ということを仮定している。── 不況のときには、そうなりやすい。実際、不況のときは、投資はやたらと増えず、ほぼ一定である。そして、たしかに、スパイラル的に景気が悪化する。
後者は、「消費 C と投資 I との和が一定」ということを仮定している。── 均衡状態では、そうなりやすい。そして、たしかに、消費の減少を、(貯蓄の増加と金利の低下をを通じて)投資の増加が補う。
なお、後者は、理想的にはそうなるはずだが、実際には、きっちりそううまく行かないことが多い。実際、こういう調整がきっちり働けば、景気の変動などは起こらないはずだ。しかるに、実際には、景気の変動が起こる。── それはつまり、こういう調整がきっちり働かないことを意味する。現実は理想のようには動かないことになる。つまり、古典派の信じるような「市場による調整」は、完璧に働くわけではない。( → 後述の [ 付記 ] )
ただ、「市場による調整」は、完璧には働かないとしても、だいたいは働く。十割ではなくても、八割か九割は働く。だから、均衡状態では、消費性向の変動があっても、生産量はほとんど不変のままである。(消費の縮小を、投資の拡大が補う。ギャップはほとんど生じないし、スパイラル効果もほとんど発生しない。)
結語。
「市場による調整」(つまり 「貯蓄 → 投資」という資金の流れ)が、完璧に働けば、消費の変動を、投資の変動が補うから、生産量は変動しない。
しかし、実際には、「市場による調整」は、完璧ではなくて、「調整の遅れ」が発生する。となると、「投資 I が一定である」というときの効果が、いくらかは生じることになる。その分、生産量の変動が発生する。ただし、それはあくまで、「調整の遅れ」による分である。基本的には、均衡状態では、景気は安定的である。
( ※ 桃色と水色の図は、均衡状態の図としては、そのままでは正しくはない。正常に均衡している状態では、「消費性向の低下があっても、45度線の下シフトが同時に発生するので、生産量の変化が起こらない」と理解するべきである。)
( ※ ただし、45度線の下シフトは、完璧に働くわけではないから、その分、45度線の下シフトを無視して、「 I は一定である」というふうに見なせる度合いが増すわけだ。)
[ 付記 ]
古典派の信じるような「市場による調整」(「貯蓄 → 投資」という資金の流れ)は、完璧には働かない。その理由は、こうだ。
そもそも、消費というものは、心理的なものだから、急激に大きく変動する。たとえば、飛行機の自爆テロとか、不正会計の発覚とか、バブルの破裂とか、皇太子の結婚とか、猛暑や冷害とか、そういったことで、急に大きく変動する。
しかるに、投資というものは、そう簡単には急激に大きく変動しない。なぜなら、投資というものは、設備を償却するのに、数年間がかかるからだ。急に消費が増えたからといって、気楽にホイホイと設備を増やせば、翌年、急激に消費が減ったとき、設備が遊休する。大赤字の発生。倒産の危機。……だから、まともな経営者は、そんなことはしない。
結局、投資というものは、数年程度の中期的な判断でなされるのだ。消費の短期的な急激な変動には、対応しきれない。ゆえに、「市場による調整」は、完璧には働かない。
[ 注記 ]
桃色と水色の図は、「45度線の下シフト」を示していないので、均衡状態の変化を述べるには、不十分だと言える。とはいえ、投資 I というものをとりあえずは所与の値としてみれば、一時的には投資 I というものを定数と見なすこともできる。
だから、均衡状態においても、桃色と水色の図を捨てることはしないで、このまましばらく使っていくこととしよう。( 45度線の下シフトもいっしょに考えれば十分だ。)
( ※ 不況のときなら、そもそもの話、「投資 I は一定である」と考えていいから、いちいち補正や留保をする必要はない。……このことゆえ、次項の話に続く。)
[ 参考 ]
参考として、間違った考え方を示しておく。(間違いであるから、特に読まなくてもよい。ただし、よくある間違いだから、参考にはなるだろう。)
上の説明では、「消費が縮小したら、その分、投資が増える」と述べた。そこで、次のような考え方が、登場しそうだ。
「消費が減ったあと、投資の分を追加して、直線を(幾何学的に)上シフトさせればいいではないか。 E を(幾何学的に)上シフトさせれば、B に重なる。だったら、最初から、消費と投資を加えておけばよい。そういうグラフを描けばいい」
と。なるほど、一理ある。そして、これ(グラフをこういうふうに上シフトして理解する解釈法)は、ケインズのモデルで見られる方法である。(従来の経済学における解釈法だ、といってもよい。)
しかし、この解釈法は、不正確なのである。「消費に投資の分を加えて、上シフトさせる」ということは、縦軸を「 C でなく C+I にする」ということだ。そして、それならそれで、初めからそういう方針で統一するべきなのだ。だが、もしそうしたならば、問題が生じる。
具体的に示そう。(以下では、横軸は Y であり、縦軸は C+I である。)
(1) 「 C = Y−I 」という直線。45度線。……
こちらは、I を右辺から左辺に移項して、「 C+I = Y 」と書き直すだけでよい。つまり、原点を通る形で、書き直せる。こうすると、かえって見通しが良くなる。(ケインズのモデルでは、そうしている。)
(2) 「 C = 0.8Y + Ca 」という直線。消費性向の直線。……
こちらは、「 C+I = f (Y) 」という形にすると、この f (Y) は、ほとんど理解しがたい変な形になる。なぜか? そもそも、消費性向は、「 C = 0.8Y + Ca 」によって、「 C と Y の関係」を示すのであって、「 C+I と Y の関係」を示すのではない。そして、もし「 C+I と Y の関係」を示すという方針で話を進めると、すでに示したグラフとは別の、理解しがたいグラフになってしまうわけだ。
結局、「 I を足して、その分、上シフトする」というような解釈法だと、(1) はうまく行っても、(2) はうまく行かない。しかも、こういう「足し算して、上シフト」ななんていうのは、とても数学的とは言えない、メチャクチャな考え方と言える。そのことが、上の「 (1) はうまく行くが、(2) はうまく行かない」という形で現れるわけだ。
こんな間違いは、初歩的な数学ミスであり、素人じみたミスである。たいていの経済学者は、数学をよく理解できないようだ。
「座標軸が何であるかは、固定しなくてはならない」という原則がある。一つの座標軸を、異なる二つの意味に受け取るなんてのは、あまりにも非数学的・非論理的であり、齟齬(そご)を引き起こすのだ。
● ニュースと感想 (9月14日)
前項の続き。
前項では、前々項の舌足らずだったところを、補足した。しかし、まだ舌足らずなところがあるので、さらに補足する。
前々項では、消費の減少を投資の増大が補うように、「貯蓄 → 投資」という資金の流れがある、と述べた。
前項では、この投資の増大が「45度線の下シフト」という形で表示できる、と述べた。
ただし、である。こういうことは、常に可能であるわけではない。一定の制限がある。この制限を示す。
いきなり結論を言おう。「消費の減少を投資の増大が補う」ということが可能なのは、特定の領域だけで成立する。その領域は、次の図で、緑色の領域(三角形領域)として示される。
この図の読み方は、次のように説明される。
- 区間 BM は、(需給の)均衡が成立する区間である。
- 区間 BM のどこに決まるかは、消費性向によって定まる。消費性向が 0.8 〜 0.9 という範囲内のどこかの数値(たとえば 0.88 )を取ると、その消費性向の直線と、45度線との交点が、一意的に定まる(たとえば J )。そこが現状の位置である。
- 今、J にいるとする。ここで、消費が急に縮小したとする。すると、生産はまだ変化しないで、消費性向だけが急に低下する。すると、図における位置は、J の下方に移動する。( J と K の中間地点。)
- J と K の中間地点のうち、どこでもいいのだが、今は特に、許容される最大幅で消費が縮小して、K に移ったとする。この点は、消費性向が 0.8 になる状態だ。
- このとき、消費の縮小の幅(長さ JK )に対応するだけ、投資が拡大すればよい。つまり、投資が I から Ik まで拡大して、その分、45度線が下シフトすればよい。(図の赤線)
- こうなると、消費の縮小(消費性向が 0.88 → 0.8 )の分、投資の拡大( I → Ik)がある。つまり、消費の縮小を、投資の拡大が補う。
- 以上のようになれば、状況としては、J から K に移行するだけである。生産量 Y は変化しない。(スパイラルが生じない、という点に注意。もし投資の増大がないと、先に述べた「景気悪化の過程」をたどり、スパイラル的に生産が縮小していく。)
というわけで、緑色の領域内にいる限りは、消費の縮小を投資の拡大が補えるわけだ。
この緑色の領域を見ると、重要なことがわかる。下方均衡点 B に近づくにつれて、しだいに点状にすぼまっていく、ということだ。上の例で言えば、Bに近づくにつれ、長さ JK が短くなっていくわけだ。
なぜか? それは、 B に近づくにつれ、金融政策が無効になっていくからである。B という点は、下限均衡点である。ここでは、金利をゼロにしても投資が増えない。45度線を下方シフトできる量がゼロになっている。そういうわけで、B に近づくにつれて、長さ JK が短くなっていく。
この緑色の領域を見ると、もう一つ、重要なことがわかる。緑色の領域の下方は、水色の領域である、ということだ。では、この水色の領域は、どういう意味があるか?
実は、「消費性向が 0.8 (下限均衡点と同じ限界消費性向)」という直線は、「金利ゼロ」ということを意味する。(詳しい説明は次項で。) そして、金利はゼロよりも下がらないので、この直線よりも下には移行できない。投資を増やす( 45度線を下シフトする)という方法では、この直線よりも下に移行できない。
しかるに、消費がどんどん縮小すれば、消費性向が 0.8 よりも下がって、この直線より下に移行する。
すると、どうなるか? 消費性向が 0.8 よりも下がったとき( K よりも下の水色領域にいるとき)には、消費が縮小するが、投資は(金利ゼロの制約で)増えない。だから、投資の縮小を、投資の拡大が補えない。つまり、需要不足( C+Ik < Y )となる。こうなると、あとは「景気悪化の過程」というスパイラルをたどることになる。
結語。
(1) 緑色の三角形領域のなかにいる間は、たとえそこが一時的に需要不足( C+I < Y )の状況であるとしても、投資の拡大による 45度線の下シフトが補うことができるので、需要不足を解消できる。景気はスパイラル的に悪化することはなく、その点で現状維持となる。(単に消費と投資の比率が変化するだけ。)
(2) 緑色の領域よりも下方(水色の領域)にまで移ると、消費の縮小が非常に大きくなるので、たとえ金利をゼロにしても、投資の増大が不十分である(消費の縮小を補うには足りない)。つまり、本質的な需要不足( C+Ik < Y )が発生して、需要不足が解消できないままとなる。景気はスパイラル的に悪化していき、生産量はどんどん縮小していく。(収束点にたどりつくまで。)
[ 付記 ]
上の (1) では、「その点で現状維持となる」と述べた。なぜか? それは、 45度線の下シフトによって、桃色領域と水色領域の境界も下シフトしたからである。
最初は、「 C = Y−I 」という直線が境界となっていた。その下方が、水色領域であり、ここは「 C < Y−I 」(つまり「 C+I < Y 」という需要不足)を意味した。
45度線の下シフトのあとは、「 C = Y−Ik 」という直線が境界となる。その下方が、水色領域であり、ここは「 C < Y−Ik 」(つまり「 C+Ik < Y 」という需要不足)を意味する。
かくて、桃色領域と水色領域の境界も下シフトする。
だから、需要縮小によって下方の点に移ったとしても、そこ(たとえば K )で、現状維持となるのである。なぜなら、そこは、「 C = Y−I 」という直線を基準にすれば需要不足領域ではあるが、「 C = Y−Ik 」という直線を基準にすれば需要不足領域ではないからだ。
[ 補記 1 ]
緑色領域の中では、任意の位置に動くことが可能である。
緑色領域の中は、上下方向は、金利調整によって決めることができる。左右方向は、いったん景気悪化または景気好転の方向にスパイラル的に動かしたあとで、金利調整によってスパイラルを止めればよい。……たとえば、利上げをすると、景気悪化のスパイラルに乗って、左下方向に移行する。そのあとで、利下げをすると、景気悪化がストップし、低めの生産状態で、経済状態が維持される。逆も同様。失業の多いときは、先に利下げを実施して、いったん景気を好転させ、そのあとで利上げをして、インフレをストップするとよい。)
こうして、金利を変化させることで、現状の位置を移動させることができる。だから、もちろん、「最適の金利」なんてものは、存在しない。金利操作というものは、自動車のハンドルのようなものだ。ときどき右や左に切り替えて、最適の路線を取ればよい。そうしないで、常に一定の路線しか取らないと、前方に障害物が現れたとき、衝突する。融通の利かない金利政策とは、そういうものだ。
[ 補記 2 ]
「景気変動」についての「均衡」という概念について補足しておこう。(需給の均衡とは別。)
経済学者はやたらと「均衡」という言葉を使いたがる。そして景気変動についても、「均衡」という状態があると信じる。たとえば、「景気悪化が終わって均衡する」とか、「景気過熱が終わって均衡する」とか。「だから均衡点を探そう」などと考える。
しかし、そういう意味の「均衡」(≒ 安定)というものは意味がない、とわかる。なぜなら、区間 BM のどこでも、そういう意味の「均衡」(≒ 安定)は達成されるからだ。単に金融政策を最適に実施すればよい。利下げや利上げを最適に実施すれば、そこで、景気変動はなくなり、景気は安定する。しかるに、利下げや利上げが、一方の側に過剰であれば、その方向に景気は不安定化する。
「景気が均衡点にむかって進む」のではない。「人が(政府が)景気を一方に動かそうとしている」だけなのだ。「均衡点はどこにあるか探すこと」が問題なのではなく、「均衡点をどこに置くか決めること(利下げや利上げを決めること)」が問題なのだ。均衡点は、どこにでも、設定可能なのである。(緑色領域の中であれば。)
( ※ だから、私は、こういう意味では「均衡点」という言葉を使わず、「収束点」という言葉を使うことにしている。)
● ニュースと感想 (9月15日)
前項 の続き。
前項で述べたことから、「下限均衡点はいかにして決まるか」ということもわかる。簡単に言えば、「金利ゼロを意味する消費性向の直線(傾き 0.8 )が、45度線( C = Y−I )とぶつかる、交点」のことだ。
以下では、もっと詳しく、説明しよう。
前項までは、モデルを元にして考えてきた。そこでは、「傾き 0.8 」の消費性向の直線が先にあった。この直線が 45度線とぶつかりところが「下限均衡点」となった。また、この直線によって、「緑色領域の下辺」が決定された。
本項では、現実を元にして考えることにしよう。すると、現実には話が逆だ、とわかる。消費性向の直線が「下限均衡点」と「緑色領域の下辺」を決めるのではない。逆に、「下限均衡点」と「緑色領域の下辺」が、消費性向の直線を決めるのである。詳しく言うと、次のようになる。
「緑色領域の下辺」は、「その点において投資を最大限に拡大できる幅」によって決まる。たとえば、初めに J という位置にいれば、その量(投資を最大限に拡大できる幅)は、長さJK(つまり Ik − I )によって与えられる。この量だけ下方に位置するところが、K という点である。
Jが区間 BM の上を次々と移動すれば、それに応じて K も次々と移動する。そうして、緑色領域の下辺が決まる。
K という点では、投資の拡大できる幅が最大になっている。そして、投資を最大にするのは、「金利ゼロ」という状況であるから、K という点は、「金利ゼロ」によって与えられる、とも言える。
K よりも上(JとKの中間)の点では、金利をゼロに下げるまでもなく、もっと高めの金利にするだけで、必要な投資幅に達する。そして、必要な投資幅に達したわけだから、その点では、消費性向の低下による消費の縮小を、投資の増加で補うことができるわけだ。(金利をゼロにしなくても。)
K よりも下の点では、金利をゼロまで下げても、必要な投資幅に達しない。しかも、金利をゼロよりもさらに下げることもできない。となると、必要な投資幅に達しないままだから、その点では、消費性向の低下による消費の縮小を、投資の増加で補うことができないわけだ。(金利をどのような値にしても。)
結局、K という点は、「金利ゼロ」のときの投資の拡大幅を与え、その K という点が、緑色の領域の下辺を決めるわけだ。
わかりやすく、表でまとめてみよう。次のようになる。( K は投資の拡大幅が最大になる点。)
| \ | 緑色領域の点 | 水色領域の点 |
| Kとの位置関係 | K よりも上 | K よりも下 |
| 必要な金利 | ゼロ以上の一定値 | ゼロでも不足 |
消費縮小を
投資拡大で | 補える | 補えない |
| 需給ギャップ | 金融政策で解消可能 | 金融政策で解消不可能 |
さて。この緑色の領域は、三角形である。つまり、投資を拡大できる最大幅である長さ JKは、右側にいるときには大きいが、左に移るにつれて小さくなっていく。そして、ある一点で、長さがゼロになる。ここが、下限均衡点 B である。
このようにして、下限均衡点は決まる。(詳しくは次々項。)
以前の説明と、本項の説明とを、比べてみよう。次のような違いがある。
モデルを元にしたときは、「(傾き 0.8 の)消費性向の直線が投資拡大の最大幅を決める」と天下り的に想定した。
現実を元にしてみると、投資拡大の最大幅が先にあるのであり、それに応じて消費性向の直線が決まる。
この違いは、何をもたらすか? それは、「緑色の三角形領域の下辺が、直線になるか否か」ということだ。
モデルを元にしたときは、「傾き 0.8 」の消費性向の直線が三角形の下辺を決めたので、この下辺はもちろん直線である。
現実を元にしてみると、点 J が「 B からM へ」と移行していくとき、その対応する投資の最大幅を意味する点 K は、うまく直線上をたどってくれるとは限らない。直線ではなく、曲線になるかもしれない。上方に曲がったり、下方に曲がったりするかもしれない。たとえ直線だとしても、別の傾きの直線になるかもしれない。はっきりとしない。
ただ、下限均衡点 B のそばでは、ほぼ直線になっていると近似していいだろう。というわけで、上の図は、それなりに根拠があるわけである。
さて。
さらに、別の重要な問題を考えよう。それは、修正ケインズモデルとトリオモデルとの関係だ。
修正ケインズモデルにおける 45度線は、需要不足を決める境界線である。45度線よりも下では、需要不足が発生する。そして、需要不足とは、需給ギャップの発生であり、また、トリオモデルにおける「下限直線割れ」のことである。
ただし、である。45度線よりも下の領域(需要不足が発生する領域)であっても、緑色の領域であれば、需給ギャップを解消できる。つまり、消費の縮小を、投資の拡大で補える。だから、緑色の領域では、トリオモデルにおける「下限直線割れ」が発生しても、その「下限直線割れ」を解消できるのだ。
しかし、同じく 45度線よりも下でも、下限均衡点 B よりも左側では、そうは行かない。そこでは緑色の領域が消える。つまり、消費の縮小を、投資の拡大で補うことができない。だから、下限均衡点 B よりも左側では、トリオモデルにおける「下限直線割れ」が発生したあと、その「下限直線割れ」を解消できないのだ。
以上のことからわかることがある。上の図において、「緑色の領域」は、「金融政策によって需要不足を解消できる領域」を意味する。つまり、
・ 緑色の領域では、金融政策が適切ならば、「下限直線割れ」は発生しない。
・ 緑色の領域では、金融政策が不適切ならば、「下限直線割れ」が発生する。
というふうになる。さらにまた、
・ 水色の領域では、金融政策がどうであれ、「下限直線割れ」は発生する。
(つまり、金融政策が無効である)
というふうになる。表でまとめれば、次の通り。
\政策
領域 \ | 政策が
適切 | 政策が
不適切 |
| 緑色 | ○ | × |
| 水色 | × | × |
○ …… 均衡。 「下限直線割れ」が発生しない。
× …… 不均衡。 「下限直線割れ」が発生する。
かくて、修正ケインズモデルとトリオモデルとの関係が示された。この二つのモデルは、独立しているわけではなく、相互に密接に関連しているわけだ。そこで、この二つを合わせて、「双子モデル」と呼ぶことにしよう。
また、対称的に示すために、トリオモデルを「女モデル」、修正ケインズモデルを「男モデル」とも呼ぶことにしよう。(俗称でそう呼ぶ。双子には、男の子と、女の子とがいるわけだ。なお、この俗称を使うかどうかは、まだ決めていない。)
( ※ なお、「女モデル」という言葉の由来だが、トリオモデルの下限直線つきのモデルの図形が、「女」という漢字に似ていることに由来する。下図の左側を参照。)
従来、古典派は、市場原理を示すモデル(女モデルの原型)を主に使い、ケインズ派は、動的な変化を示すモデル(男モデルの原型)を主に使った。それらは特に関連づけされなかった。しかし、本項で示したように、女モデルと男モデルは、密接な関連があるのだ。ここに経済学の核心がある。経済学のほとんどは、双子モデルを使って、理解される。そのことに留意しよう。
● ニュースと感想 (9月16日)
前項の後半で述べたことをまとめてみよう。
ひとことで言えば、緑色領域は、「金融政策が有効な領域」を意味する。そして、その具体的な内容は、次のことを意味する。
- 上限均衡点 M に近いところ
- 消費性向が高い。
- 貯蓄が少なく、投資は少ない。
- 金利は高い。
……ゆえに、金利を下げる余地は大きく、投資拡大の余地も大きい。
- 下限均衡点 B に近いところ
- 消費性向が低い。
- 貯蓄が多く、投資は多い。
- 金利は低い。
……ゆえに、金利を下げる余地は小さく、投資拡大の余地も小さい。
なお、緑色領域が、「金融政策が有効な領域」だとすれば、水色領域は、「金融政策が無効な領域」である。
水色領域については、同様に、次のようにまとめることができる。
- 下限均衡点 B (または、それ以下)
- 消費性向がとても低い。
- 貯蓄がとても多い。投資は貯蓄を下回る。(資金の余剰が発生。)
- 金利はゼロ。
……ゆえに、金利を下げる余地もなく、投資拡大の余地もない。
なお、「トリオモデルにおける下限直線割れ」は、上の図の水色領域のことを意味するのではない。誤解しないよう、注意しよう。
「トリオモデルにおける下限直線割れ」は、単に「需給ギャップの発生」を意味する。そして、そうなるかどうかは、「 C+I < Y 」(需要不足)となるか否かによって決まる。
「 C+I < Y 」は、45度線よりも下の領域である。そこでは原則的に、需給ギャップが発生する。しかるに、金融政策を適切に実施すれば、I を増やすことで、45度線を下シフトできるので、水色領域そのものを下シフトできる。そうすれば、需給ギャップは発生しなくなる。(つまり、「 C+Ik < Y 」とならなくなる。)そういうことが可能なのが、緑色領域だ。
だから、緑色領域は、「トリオモデルにおける下限直線割れ」が、発生するともしないとも言えない。金融政策しだいで決まるわけである。( → 前項で述べた表を参照。)
[ 付記 ]
「緑色領域は、金融政策が有効な領域である」と述べた。つまり、範囲を緑色領域だけに限定している。これは、古典派やマネタリストの考え方とは異なる。
古典派やマネタリストの考え方では、「金融政策は常に有効である」となる。つまり、「どんなに景気が悪化しても、金融政策は有効である(投資を拡大することができる)」となる。しかし、そんなことはないのだ。
「下限均衡点」に注目しよう。下限均衡点よりも左下では、金融政策が無効である。つまり、「貯蓄 → 投資」という資金の流れを拡大できない。「貯蓄 > 投資」という関係になったあと、「貯蓄 − 投資」に相当する「滞留分」を埋めることができない。
このことは、「流動性の罠」を意味する。そして、現実がそうなっていることは、明らかだろう。金利をゼロ以下に下げることはできない。また、いくら量的緩和を実施しても、資金は金融市場のなかでぐるぐる回るだけだ。「貯蓄 → 投資」という資金の流れは発生せずに、「貯蓄 → 貯蓄」という資金の循環が発生するだけだ。
なのに、マネタリストはなぜ、金融政策が常に有効であると考えるのか? それは、マネタリストが、しょせんは古典派であるからだ。そのことが、本項の説明からわかる。
「金融政策が有効になる範囲」つまり「緑色領域の範囲」を決めるのは、「下限均衡点」である。だから、「金融政策が常に有効である」というのは、「緑色領域の左端がない」つまり「下限均衡点がない」ということである。
そして、前項でも述べたように、「下限均衡点がない」ということは、「トリオモデルにおける下限直線割れが発生しない」ということであり、「需給の均衡が常に成立する(需要不足にはならない)」ということだ。これは、古典派の立場そのものだ。
だから、「金融政策が常に有効である」という考え方は、「需給の均衡が常に成立する」という古典派の考え方と同じなのだ。そして、「需給の均衡が常に成立する」というのは、「不況などは存在しない」というのと同じだ。ならば、「金融政策が常に有効である」という結論は当然なのである。(不況でないときは、金融政策は有効なのだから。)
結局、こうだ。マネタリストは、「金融政策によって投資を必ず増やすことができる」と主張する。なぜなら、「不況などは存在しない」からだ。── しかし、である。彼らは気づいていないようだが、そういう考え方には、矛盾がある。なぜなら、もともと「不況などは存在しない」のであれば、「不況を解決するには金融政策で」と主張すること自体が無意味だからだ。不況が存在していないのなら、存在してもいない不況を解決するための方策など、まったく無意味だ。
マネタリストは、「不況対策には、金融政策が有効である」と主張する。しかし、その考え方は、「不況はこの世に存在しないこと」を前提しているのである。彼らの考え方は、明らかにおかしい。では、なぜ、そういうおかしなことを主張するのか? ── それは、彼らが、「均衡」というものを無条件に信じているからである。「均衡」を信じているから、供給に対して、それに等しい需要が発生する。金融市場では、資金供給に応じた資金需要が必ず発生する。商品市場(財市場)では、商品供給に応じた商品需要が必ず発生する。かくて、資金余剰(滞留)も発生しないし、供給余剰(需要不足)も発生しない。
こういうふうに、マネタリストと古典派とは、本質的には同根なのである。同じ根から生じた二枚の葉のようなものだ。あるいは、一枚の派の裏表のようなものだ。……そういう根源的な核心を、双子モデルにおける二つのモデル(女モデルと男モデル)の関係が、明らかにしてくれるわけだ。
なお、「緑色領域は、金融政策が有効な領域である」と言ったが、同時に、こうも言える。「緑色領域は、古典派が有効な(正しい)領域である」と。── つまり、古典派の考え方が成立するのは、図の緑色領域だけであって、他の領域では正しくないのだ。水色領域では、需給の均衡は成立せず、需要不足となる。ここでは、ケインズふうの考え方が成立する。そして、緑色と水色の領域をともに含む「修正ケインズモデル」は、古典派とケインズ派を統合していると言えるわけだ。
( → 9月12日 でも似た話を述べた。そこでは「緑色領域」でなく「区間 BM」が古典派の領域だと述べた。それを、本項では、もっと正確に述べているわけだ。細かく言えば、「区間 BM」は「必ず均衡」の領域であり、「緑色領域」は「均衡にできる」領域である。)
[ 余談 ]
マネタリスト批判。
一部のマネタリストは、政府の無為無策を批判するが、チャンチャラおかしいとしか言いようがない。「目くそ鼻くそを笑う」というよりも、もっと悪い。彼らは自分が政府と同じ穴のムジナ[同じ鼻くそ]だということがわかっていないようだ。
小泉や竹中にせよ、量的緩和論者にせよ、いずれも「需給ギャップは生じない」という基本概念に立脚している。そういう基本概念を前提とした上で、小泉や竹中は「構造改革」「供給力向上」を唱え、マネタリストは「量的緩和」を唱える。言っている形は異なるが、いずれも「需給ギャップは生じない」という基本概念から派生したものにすぎない。「需給ギャップは生じない」ということを、別の分野で言っているだけだ。
なのに、マネタリストは、自らの愚かさに気づかない。それというのも、彼らは、自らの出自を理解できないからだ。自分は天国から生まれた天使なのだと錯覚しているが、本当は彼らは地獄から生まれた悪魔なのだ。そのことを理解できないまま、自らを天使だと思い込んで、悪魔を批判しているのである。自らを知るべきだろう。
ただし、悪魔に鏡を見せれば、おのれの醜悪さに驚いて、卒倒するだろうが。
[ 付記 ]
新聞記事。(朝日・朝刊・経済面・特集コラム 2002-09-15 )
「国債購入がどんどんふくらんでいる(市場金利は低下・債券相場は上昇)」ということを報道している。つまり、いくら量的緩和をしても(長期金利を下げて貯蓄を不利にしても)、貯蓄は減らず、投資も増えない、という構図。
金融政策が無効になっていることを示す。マネタリズムの無効化。
( ※ 数量的に計算してみよう。現在、10年物の国債の年利は1%。十年分で 10%。平均的な名目金利を 3%と仮定すると、3.3年分。残りは 6.7年。つまり、だいたい7年ぐらいはゼロ金利が続く、という見通しとなる。金融政策が無効になる状態[不況]が7年間は続く、という見通しだ。それだけ状況が悪化しているわけ。)
( ※ ついでだが、今から 10年前、長期国債の年利は 3%前後であり、「こんな低金利の長期国債を買うのはバカだ」と思われた。ところが実際には利口であった。そのあとは国債金利は低下するばかりだったのだから。今も、「7年ぐらいはゼロ金利が続く、と思うのはバカだ」と思うかもしれないが、さあ、どうなることでしょうか。このあと、日本経済が破綻すれば、市場金利は 10年ぐらいゼロ金利になるかもしれない。となると、超低利の長期国債を買った人は利口だったことになる。バカなのは、政府。最悪なのは、経済学者[マネタリスト]。)
● ニュースと感想 (9月17日)
前々項の根拠の話。(理論的な説明。面倒なら、読まなくてもよい。)
前々項の前半では、緑色領域の下辺がいかにして決まるかを示した。ただ、前々項で述べたことがどの程度まで正当であるかが、問題となる。
前々項で示したところでは、緑色領域の下辺は、「投資拡大の最大幅」によって決まるとされた。では、このようにして決まる下辺は、先に示したモデルにおける傾き 0.8 の直線(下限均衡点を通る消費性向の直線)と、まさしく一致するだろうか?
本当のことを言おう。両者は、一致するとは限らない。ここまでの説明では、モデルを単純化するために、一致すると見なしてきたが、それはあくまで、便宜上のことだ。実際には、いくらかズレることもある。
では、ズレが生じるとしたら、問題か? 実は、問題ではない。つまり、前々項で述べたことは、ぴったりそのまま数値的に正確でなくても、たいして問題ではない。そのことを示そう。
まず、正解を探すこととしよう。緑色領域の下辺は、「投資拡大の最大幅」によって決まるとされた。では、このようにして決まる方法では、緑色領域の下辺は、どのような直線となるか? その直線は、「 C = 0.8Y + Ca 」という式で示されるのではないとしたら、正しくはどのような式で示されるか?
実は、そんな「正解」などはない。正解となる直線も存在しないし、正解となる式も存在しない。── なぜならば、「投資拡大の最大幅」は、状況しだいで、いろいろと変化するからだ。つまり、状況に応じて、緑色領域の下辺は、上下に少し変動する。唯一無二に決まるわけではない。
たとえば、図の J の位置にいるとしよう。このとき、金利にゼロにすると、長さJK に相当する金額だけ、投資が増える。この金額は、「 Ik − I 」で示される。
この金額が、ある現実の状況において 40兆円だとしよう。しかし、別の現実の状況においては、同じく 40兆円になるとは限らないのだ。モデルにおける元の位置が同じく J だとしても、現実の状況が変われば、長さJK に相当する金額も変わる。もし景気の先行きの見通しが明るければ、40兆円よりも大きくなるだろうし、もし景気の先行きの見通しが暗ければ、40兆円よりも小さくなるだろう。
具体的に例を示そう。1990年の日本だ。バブルが破裂して、消費性向が急激に低下した。図の J の点から K の点まで、消費性向が急激に下がった。それまでは傾き 0.9 だったが、そのあとは傾き 0.8 となった。それだけ消費が縮小した。ここで、金利をゼロにすれば、消費の縮小(40兆円)を、投資の拡大(40兆円)が補えるはずだった。つまり、かろうじて、緑色領域に留まることができて、水色領域には入らずに済むはずだった。
しかし、である。1990年8月、湾岸戦争が勃発した。イラクのクウェート侵攻。中東の石油価格の急騰。たちまち、先行きの経済の見通しは非常に暗くなった。先行きの見通しが暗いのだから、企業はとても投資を拡大する気にはなれなかった。── このとき、「投資拡大の最大幅」は、40兆円から、急速に縮小したはずだ。つまり、緑色領域の下辺は上昇したはずだ。緑色の三角形は、上下につぶれる形で、狭くなったわけだ。となると、K という点は、もはや緑色領域からはみだしてしまって、水色領域に入ることになる。
( ※ この件は、以前、説明したことがある。「真の不況」「仮の不況」という言葉で。── 緑色領域の状況ならば、金利をゼロにすることで解決するので、「仮の不況」である。水色領域の状況ならば、金利をゼロにすることで解決しないので、「真の不況」である。 → 8月30日 )
結局、「投資拡大の最大幅」は、状況しだいで、いろいろと変化する。だからこそ、特定の値などはない。値を正確に示す数式などもない。というわけで、上のモデルにおいては、とりあえずは 傾き 0.8 の直線を取ったわけである。(特に強い根拠があるわけではなくて、だいたいの値として。)
この直線(図における緑色領域の下辺)は、正しいわけではないが、間違っているわけでもない。正確であるわけではないが、大きくズレているわけでもない。とにかく、おおまかには、このような直線で示すことができる、と考えていいわけだ。
さて。
「おおまかには、このような直線で示すことができる」と、すぐ上で述べた。では、なぜか? このことについて、以下で、示そう。
( ※ 新しい結論を示すわけではない。結論なら、すでに述べたとおりだ。以下では、根拠を示すだけである。── 情報と言うよりは、論理展開である。読むのは面倒かもしれないから、いちいち精読しなくてもよい。
)
結論は、こうだ。「緑色領域は、だいたい、図のような形になる」ということである。つまり、「緑色領域の下辺は、少しぐらいは上下に変動するとしても、だいたいは図で示したような直線になる」ということだ。── そのことは、具体的には、次の2点を意味する。 (いずれも、区間 BM のなかの話。)
(1) 投資拡大の最大幅は、M に近づくにつれ、大きくなる。
(2) 投資拡大の最大幅は、B に近づくにつれ、小さくなり、ついにはゼロになる。
この2点が成立すれば、だいたい図のような三角形になることはわかるだろう。そこで、以下では、この2点について順に説明しよう。
(1) 投資拡大の最大幅は、M に近づくにつれ、大きくなる。
「M に近づくにつれ」というのは、「右方に行くにつれ」ということであり、「生産量 Y が拡大するにつれ」ということだ。それはまた、消費性向が 0.8 から 0.9 へ上昇していくということだ。(図の直線 BM を見ればわかる。確認してほしい。)
だから、右方に近づくにつれ、Y (= C+I )における消費と投資のうち、消費の占める割合が大きくなり、投資の占める割合が小さくなる。金利は上昇する。
となれば、このあと、投資を増やす余地が拡大するのは、当然だ。投資は縮小しているのだから、投資を増やす余地は大きい。需要はすでに大きく伸びている(販売市場がある)のだから、投資をする意欲も湧く。金利はすでに高くなっているのだから、金利ゼロまでの余地も大きい。
というわけで、投資拡大の最大幅は、M に近づくにつれ、どんどん大きくなる。
( ※ ここで述べたことは、わりと当たり前の話である。ただ、前項で述べたことと似ているので、違いを示そう。前項では、モデルが先にあって、その説明として、ここで述べたようなことを記した。一方、ここでは、こういう状況が先にあり、だからこそモデルの緑色領域がほぼ三角形になることを示した。……実際には、緑色領域の下辺は、直線とはならないかもしれないし、状況によって変化することもあるだろう。モデルで示したように、きれいな三角形になるとは限らない。)
(2) 投資拡大の最大幅は、B に近づくにつれ、小さくなり、ついにはゼロになる。
まず、「B に近づくにつれ、小さくなる」というのは、(1) と同じことだから、当たり前である。単に (1) を言い換えただけだ。
問題は、「ついにはゼロになる」ということだ。つまり、ある点において、金利引き下げによる投資拡大の幅が、ゼロになる。金利をいくら下げても、もはや投資を拡大できない。そのような点が、必ず、45度線上に存在する。── このことを示す必要がある。
このことは、背理法で示される。(以下の 【 】 内は、説明。読まなくてもよい。結論は、すでに上に記した。)
【 仮に、そうでないとしよう。つまり、「金利引き下げによる投資拡大の幅がゼロになるような、そういう点 B は存在しない」と仮定しよう。つまり、「45度線上のどんな点でも、金利引き下げによる投資拡大の効果は、ゼロにはならない(多少はある)」と仮定しよう。
これは、図形で言えば、こうなる。緑色領域は、左下に行くにつれて、どんどん細くなるが、45度線のところで消える( ∠ のような形の角を作る)ことはなく、45度線に沿って先へ細く伸びていく(先すぼまりの形)。つまり、緑色領域の下辺は、直線ではなく、45度線に近づくにつれて下に曲がり、45度線に沿って漸近線のように進んでいく。
そのとき、どうなるか? 下限均衡点 B とは、緑色領域の下辺と 45度線との交点なのだから、下限均衡点 B が存在しない( or ずっと左下にある)ことになる。つまり、区間 BM は左下まで長く伸びていって、ほとんどすべてが均衡状態の区間だということになる。
仮に、下限均衡点が、非常に低い位置(左下の位置)にあったとしよう。だとすると、その点において 45度線と交差するような消費性向の直線は、非常に小さな消費を示す直線となる。図では、B において 45度線と交差するのは、「 C = 0.8Y + Ca 」という消費性向の直線だったが、非常に低い位置で 45度線と交差するのは、「 C = 0.1Y + Co 」というような消費性向の直線だろう。(これはほとんど、Y 軸にくっつきそうな水平線である。地べたを這うような感じだ。)
逆に言えば、消費性向がこれほど悪化する(同時に生産が 10分の1ぐらいまで縮小する)ということのない限りは、いまだに均衡状態を保てるのである。── しかし、そんなことが、あるだろうか? もちろん、ない。消費性向が極度に縮小して、生産が極度に縮小しても、それでもなおかつ、経済が正常状態を保っている、なんてことは、現実にありえない。
ゆえに、矛盾が生じる。だからこそ、最初の仮定は、正しくない。(背理法。)
( ※ ただし、ここにおける「矛盾」は、「論理矛盾」ではなくて、「現実に矛盾すること」だ。どういうことかというと、最初の仮定は、論理的に正しくないと言うことではなくて、現実に適合しない不適切なモデルだということだ。) 】
[ 付記 ]
なお、幾何学的には、「カタストロフィの理論」で説明できる。修正ケインズモデルでは、緑色領域の範囲内では、金利の低下によって均衡を保つことができるが、だんだん左下に行くと、緑色領域の左下の端に達して、もはや金利を低下させることができなくなる。……そこがカタストロフィの特異点だ。この特異点よりもさらに左下に移ろうとすると、状況が別の状況に転じてしまう。
そして、このことは、「トリオモデルにおいて、需要曲線の左シフトにつれて、カタストロフィの特異点が現れる」ということと、同じことである。( → 7月29日 の [ 付記 ])
ここでも、双子モデルのたがいの相似性が明らかだろう。
● ニュースと感想 (9月18日)
前項に関連する、細かな話。(重要ではないので、読む必要はない。)
前項では、9月15日の根拠を示した。そして、「緑色領域の下辺というものは、状況の応じて変わるから、あまりはっきりとは決まらない」と示した。しかし、「それでは物足りない、もっと詳しいモデルがほしい」と思う人もいるだろう。そこで、そのための助けとなる話を、オマケふうに付け加えておく。
緑色領域の下辺というものは、たしかにはっきりとは決まらない。とはいえ、まったくあやふやというわけでもない。図においては、単純に直線を引っ張って、この直線によって示した。これはあまりにも単純なモデルだった。もうちょっと、うまいモデルも考えることができるだろう。つまり、「一本の直線で済ませる」という単純なモデルのかわりに、「複雑な曲線を用いて緑色領域の下辺を決める」というモデルを提出することもできるだろう。そして、それは、先のモデルよりは良いモデルとなっているのである。
( ※ なぜなら、そうして得られた最適な「複雑な曲線」は、最悪でも、「元の直線」と同じになる。そして、元の選択肢を含んで、もっと多くの選択肢があるのであれば、必ず、元よりは良くなるに決まっている。)
そこで、複雑な曲線を得るために、基本的な原理を考えてみよう。次のような原理が考えられる。
(1) 自然調整と金利
金融市場が理想的に動くと仮定する。つまり、「消費が縮小して、貯蓄が増えると、その分、投資が増える」ということが、理想的に実現されると仮定する。
こういう理想的な状況では、自然調整によって、うまく市場金利が変化し、消費の縮小を投資の増加が補う。
このときは、金利がどの値になるかは、いちいち考慮する必要はない。自然に最適の金利に落ち着く。その金利がどのくらいになるかに関係なく、消費の減少を投資の増大が補う。
(2) 金融政策による介入と金利
上記の自然調整は、現実には、完璧には働かないものだ。消費が低下しても、投資が十分に増えないことがある。逆に、消費が増えたとき、投資が十分に減らないことがある。つまり、市場による調整が不完全となることがある。
こういうときは、市場の調整の不足を、金融政策が補う必要がある。つまり、金利の変動を、市場に任せず、金融当局が意図的に方向付けをする必要がある。(マネタリズムなら、「Xパーセントルールで足りるぞ、自然調整だけでいい」と主張するだろう。しかし、そんなに単純な話ではないのだ。そんな単純な話で済むくらいなら、日銀もFRBも必要ない。現実には、中央銀行の役割は、大きい。)
こういうときに、金融政策の影響は、どうなるか? (金融政策の問題だから、金利の変動を先に取ってから、それによる景気の変動を考える。)
- 金利を下げると、投資( I )が増える。
- 投資( I )が増えるということは、「 C = Y−I 」という直線が下シフトすることを意味する。
- 一定量(たとえば1%)だけ金利が下がったときの、投資の増加分を、 ΔI と書くことにしよう。すると、ΔI は、定数ではなくて、さまざまな変数(状況)に依存する量である。
- 生産量 Y
への依存。(Y が大きいときは、ΔI も大きく、Y が小さいときは、ΔI も小さい。……なぜ、そうなるか? 考えれば、すぐにわかる。供給能力は一定だから、需要や生産が拡大するにつれ、供給能力の余裕がなくなり、投資の意欲がどんどん湧く。)
- 景気
への依存。(景気の上昇局面では、ΔI は大きく、景気の下降局面では、ΔI は小さい。)
- 金利
への依存。(そのときの金利しだいで、ΔI も変化する。)
- 景気の下降局面では、Y が小さくなり、それにつれて、ΔI はどんどん小さくなる。(上の a. b. より。)
以上のことを参考にして、適当に数式をいじれば、何らかのモデルを作ることができる。
ただし、である。しょせん、モデルはモデルである。本当のことをいうと、「現実に近い正確なモデル」なんてものは、必要もないし、意味もない。なぜか? われわれが欲するのは、「ズレの少ないモデル」ではない。「真実の核心を知るための、現実を単純化した、簡潔なモデル」である。ズレを少なくすることが目的なのではなくて、真実の核心を知ることが目的なのだ。……だから、いくらズレが少なくても、複雑でわかりにくいモデルは、かえって真実から遠ざかってしまうのである。
( ※ これはなかなか、教訓的な話だ。)
[ 付記 ]
上の (1) (2) では、自然調整が完璧ではないということを示した。その理由は、いろいろとあるが、特に、「タイムラグ」の影響が大きい。消費は人々の心理に応じて、即時的に次々と変動するが、投資の方は、消費の変動に応じて、即時的に変動を吸収することはできないのだ。以下のことを参照。
・ 金融政策は、効果が発現するまで、タイムラグがある。
・ 設備投資は、やはりタイムラグがある。( → 5月14日 の (3) )
・ 公共事業は、波及効果が他の産業に及ぶまで、タイムラグがある。
・ ただし、減税は、タイムラグがほとんどない。( → 5月14日 の (2) )
● ニュースと感想 (9月19日)
「金融政策と財政政策」について。(マネタリスト批判。特に重要な話ではない。論理遊びふう。)
9月15日 ,9月16日 では、「緑色領域は、金融政策の有効な領域である」とを示した。そこでは、「下限均衡点 B に近づくにつれ、金利を下げることで投資を拡大できる幅が小さくなる」ということを示した。
これは、次のことを意味する。
「均衡状態のうちに留まっていても、下限均衡点(不況との境目)に近づくにつれ、金融政策の有効性がゼロに近づく」
では、金融政策の有効性がゼロになったあとは? もちろん、財政政策しかない。(財政政策として、ケインズは、「公共事業を」「政府が投資の拡大を」主張した。私は「減税を」「投資でなく消費の拡大を」と主張した。)
さて。ここで気づくことがある。それは、こうだ。
- 景気が悪化するにつれて、金融政策の有効性はどんどん小さくなる。
- 「現時点で、金融政策が有効だ」という主張が正当であるとしたら、それは、現時点では、金融政策による小さな有効性でも足りるということを意味する。
- ならば、同等の景気回復効果を、小さな財政支出でも実現可能である。
それはつまり、こういうことだ。
今、マネタリストが、「景気回復には金融政策で」と主張している。さて、金融政策が有効となる幅(投資を拡大できる幅)は、景気の良いときには大きいが、景気の良くないときには小さい。景気の良くないときに、彼らは「金融政策で」と主張する。しかし、彼らの主張のように、景気の良くないときは、金融政策の効果も小さいのだから、金融政策で景気回復ができるとしたら、小さな効果で景気回復ができるということになり、もともと需給ギャップの幅は小さかった、ということになる。そして、だとしたら、同じ効果を小幅の財政支出でもまかなうことができることになる。
だから、マネタリストが「景気回復には金融政策で」と主張するのならば、ケインジアンは「景気回復には小幅の公共事業で」と主張してもいいわけだ。
そして、大きな需給ギャップがあるときは、もちろん、小幅の公共事業だけでは需給ギャップを解決できない。
ということは、結局、「景気回復には金融政策で」というマネタリストの主張は間違いだ、ということになる。
● ニュースと感想 (9月19日b)
「マイナスの実質金利」への批判。(本筋とはあまり関係ない話。)
「金利を下げることで、消費の減少を、投資の増加が補うことができる」とすでに示した。このことから、「金利」というものの意味がわかる。「金利」には、以下で述べるような意味がある。
まず、「 C = Y−I 」という式(または直線)がある。これが基本だ。この式を保っている(この直線上にある)限り、均衡状態から特に逸脱することはないはずだ。
さて。この式が成立するには、「 S = I 」が成立していることが前提である。しかるに、S と I が同じであるという保証はない。同じになるには、「貯蓄 → 投資」という資金の流れが、滞らずになされる必要がある。しかし、現実には、(タンス預金などで)この流れが阻害され、 S と I の食い違いが生じる。( → 9月12日 )
S と I の食い違いがあると、「 C = Y−I 」という式が成立しなくなり、「 C < Y−I 」となる。つまり、需要不足となる。そこで、 S と I の食い違いをなくように、方向付けをする必要がある。── それが、「金利」の意味だ。
もし金利がなかったら? たとえば、イスラム社会では、「利息」が禁じられている。デフレの日本でも、金利はゼロである。
こうなると、資金は、銀行預金には向かわず、タンス預金に向かう。なぜなら、人々は現金の利便性(「貨幣愛」ともいう)ゆえに、タンス預金を好むからだ。( cf. 流動性選好説 )
そして、タンス預金が増えるということは、金融市場の外にある金が多大になるということだ。金融市場が不健全になり、資金がうまく流れなくなり、投資が阻害される。「金利がないゼロ」という状況は、そういうふうに、貨幣経済を歪めるのだ。
「金貸しの利益は、不労所得であり、けしからん」という意見がある。「自分では働かないで、ただ金を得るなんて、許しがたい」とか、「高利貸しのシャイロックはけしからん」とか。……しかし、そういう素朴な市民感情に従うと、かえって貨幣経済が歪んで、状況は困ったことになるのある。
「金を貸す」という仕事は、一見、何も生産していないように見える。何も生産していない銀行員が、世間水準よりもずっと高給を取ったり、世間的に高学歴の優秀な人材が銀行に就職するのは、おかしなことに見える。しかし、実は、おかしくはないのだ。銀行はたしかに、何も生産していない。しかし、そのかわり、無駄を削減しているのである。「金が眠っている」というのは、大きな無駄だ。その無駄を消して、「金を有効に働かせる」ということが、銀行の役割だ。銀行は、たしかに、何もプラスを生んでいないが、巨大なマイナスを消している。その巨大な効用は、そこらの靴屋や八百屋のレベルよりもはるかに上だ。だからこそ、銀行には、世間的に最優秀レベルの人材が必要とされるのである。
さて。金利には、このような意味がある。では、金利がゼロになったら? もちろん、金利の意味がなくなる。となると、人々は「貨幣愛」ゆえに、銀行預金をしなくなり、タンス預金をするようになる。つまり、「貯蓄と投資の差額」が巨額にふくらむ。(実際、このことは、近年の金融統計からも明らかとなっている。)── ここでは明らかに、金融市場が歪んでいる。
では、さらに状況が進んで、「金利ゼロ」どころか、「マイナスの金利」(名目金利でなく実質金利)にというふうになったら? これが問題だ。実際、「インフレ目標」政策では、このことが提唱される。
上記のことからわかるように、「マイナスの金利」というものは、「金利の意味」を、真っ向から否定している。経済学の原理に反する、とさえ言える。「金利がゼロ」というイスラム社会を、「経済学の常識からハズレる」と呼ぶとしたら、「金利がマイナス」というインフレ目標政策は、「経済学の常識とは正反対だ」とすら言える。── では、このことを、どう解釈すべきか?
結論から言おう。「マイナスの金利」というのは、やはり、あってはならないのである。なぜならそれは、「資金の流れ」を阻害し、一国の貨幣経済をひどく歪めるからだ。
さて。「マイナスの実質金利というものは原理的におかしい」という結論が出たのは、「金利」というものの意味を理解したからだった。話として大事なのは、ここまでである。ここまで理解しておけば、一応は十分である。「マイナスの金利は狂気的だ」という本質を、つかむことができたからだ。
( ※ ただ、原理的な話だけでなく、もっと具体的な細かな話もある。「マイナスの実質金利には、実際にはどのような弊害があるか」という問題だ。これは別の話となるので、これについては次項で述べる。)
● ニュースと感想 (9月20日)
前項の続き。(本筋から逸れる話なので、読まなくてもよい。)
マイナスの金利の具体的な弊害を示そう。
ただし、以下の話は、具体的ではあるが、細かな話である。そしてまた、二番煎じである。というのは、すでに何度も述べてきたことだからだ。「そんな話は聞いたことがあるぞ」と思う人も多いだろう。だから、あらかじめ、以下は「すでに述べたことの二番煎じだ」と注記しておく。(ことさら新しい情報があるわけではない。)
「マイナスの金利にはメリットがある」という説がある。(インフレ目標政策など。) しかし、これには、根本的な難点がある。こういう説は、物事の半面しか見ていないのである。── つまり、「右手で得して、左手で損した」というときに、右手だけを見て「得した得した」と騒いでいるだけなのである。左手という片側における損を見失っているのである。 ( → 5月15日b )
具体的には、こうだ。「マイナスの実質金利」は、たしかに、投資をする企業にはメリットがあるが、貯蓄をする国民にはデメリットがあるのだ。── たとえば、「マイナス2%の金利」にしたとする。投資した企業は「2%得した!」と喜べるが、貯蓄した国民は「2%損した!」と苦しむのである。そして、両者の差し引きは、トントンだ。つまり、「企業が得する」だけではなく、「企業が得して、その分、国民は損する」のである。(ここを理解しない経済学者が多い。彼らは、「マイナスの金利で投資が有利になる」「企業の得だけが発生する」と騒ぎ立てる。金がどこかから湧いてくると思っているらしい。)
さて。企業と国民の差し引きではトントンでも、全体としてプラスの効果があるのならば、それはそれでいい。たとえば、単純な物価上昇なら、「消費した人が得、消費しない人が損」で、差し引きではトントンだが、全体としては、プラスの効果がある。(消費した人が得になるので、消費が促進され、そのことで、景気が回復するから。正しいことをした人が優遇されることで、全体が正しい方向に推移するから。)
では、マイナスの金利はどうか? 物価上昇と同じく、マイナスの金利も、全体としてはプラスの効果があるだろうか?
ここが議論の分かれ目だ。インフレ目標賛成論者は、「プラスになる」と主張する。その理由は、次の通り。
「貯蓄が過剰で、投資が不足している。だから、貯蓄を冷遇し、投資を優遇すればいい。そうすれば、貯蓄が減って、投資が増える。」
なるほど、うまく行けば、そうなるかもしれない。しかし、この説明には、難点がある。
・ 「投資優遇で、投資が増える」
・ 「貯蓄冷遇で、貯蓄が減る」
このいずれも、成立しがたいからだ。以下、順に示す。
(1) 「投資優遇で、投資が増える」
次の (a) (b) という二つの問題がある。
(a) 設備の稼働
そもそも、本質的に考えてみよう。不況のときは、設備が過剰だ。こういうときに、投資を優遇するからといって、企業は投資をするだろうか?
もしその設備が稼働するのであれば、企業は「得する」と思って、投資をするだろう。しかし、である。設備が稼働するのであれば、プラスの低金利のころに、とっくに投資をしているはずだ。なぜなら、設備が稼働するのなら、そのことで、利益を出すのだから。(利益を出さないのであれば、投資をしない。ゆえに、投資をするのであれば、利益を出す。)
つまり、企業が今、投資をしないのは、もともと設備が稼働しない(利益を出す見込みがない)からだ。こういうときに、「マイナスの金利」で設備投資を推進しても、企業は、遊休させる設備のために投資などはしない。当たり前。
結局、核心を言えば、こうだ。「投資を優遇すれば、投資が拡大する」というのは、その投資した設備が稼働する場合に限られる。それはつまり、「需要不足ではない場合」に限られる。だから、「需要不足である場合」には、投資優遇による効果は、ほとんどないのである。
( ※ 失業問題も同様だ。企業は、遊ばせるため設備に投資することがないように、遊ばせるための労働者を雇用することもない。たとえば、少しぐらい賃下げをしても、もともと労働力が余剰であれば、新規雇用などはしない。むしろ、解雇したがる。……こういうことは、事情がそっくりだ。もし「マイナスの金利」が有効であるなら、「賃下げによって失業率の低下」ができるはずだ。では、現実には? もちろん、企業は新規雇用よりも解雇をしたがるし、投資拡大よりは有利子負債の縮小をしようとする。根本的に言って、金利の問題ではないのだ。賃下げや低金利が有効なのは、企業の設備が遊休していないときだけだ。)
(b) 流動性の第2の罠
ただし、「マイナスの金利」がまったく無効であるということにはなるまい。投資を増やす効果は、まったく効果がゼロということはなくて、いくからは効果があるだろう。
しかし、問題は、その程度だ。不況期には、もともと投資意欲が縮小している。となると、少しぐらい投資優遇をしたからといって、とても需要不足を解消するほどにはなるまい。しょせん、消費が大幅に縮小したときは、投資の拡大だけでそれを補うことはできないのである。(たとえば、消費が9割減になったときには、投資がそれを補えないのは当然だ。)
それでも強引に投資を増やそうとするならば、途方もない投資優遇策が必要となるだろう。たとえば、「マイナスの金利」ならば、実質金利をマイナス 20%にする(物価上昇率をプラス 20%にする)というような。こういうのは、まったく馬鹿げた話だ。
現実を見ても、現在の巨大な需給ギャップを解消するには、投資を 30兆円ほど拡大する必要があるが、それには、金利をマイナス 10%以上にすることが必要だろう。つまり、金利をマイナス2%程度にする程度では、焼け石に水で、景気回復効果はほとんどあるまい。
( → 4月30日b 「流動性の第2の罠」 )
( → 9月03日 「小規模な景気回復策は無効」)
(2) 「貯蓄冷遇で、貯蓄が減る」
「貯蓄冷遇で、貯蓄が減る」。だから、「貯蓄が減った分、消費が増えて、景気が良くなる」というシナリオだ。しかし、こういうシナリオの通りには行かない。なぜか? 「貯蓄が減れば、消費が増える」というのは、経済学の分類上(帳簿上)ではそういうなる、というだけのことであって、実体経済ではそうなりそうにないからだ。
もっとはっきり言おう。「貯蓄冷遇」は、「消費の増大」ではなくて、「資産投資の増大」をもたらす。これを見て、経済学者は、「貯蓄が減って、土地や株を買った。そういう消費が増えた」と主張する。土地や株という資産は、「疑似貨幣」なのである。経済学の分類状では、「貯蓄」には含まれないが、実質的には「貯蓄」と同様なのだ。銀行預金が減って、土地や株への投資が増えれば、名目的には「貯蓄」が減るが、実質的には「貯蓄」は増えない。銀行預金を下ろして、自動車やパソコンを買えば、生産量も増えるし、国民所得も増える。しかし、銀行預金を下ろして、土地や株を買っても、生産量は増えないし、国民所得も増えない。
なぜか? 株や土地は、資産であるから、生産されないのだ。資産とは、「生産されないもの」のことを言う。株や土地は、生産されずに、取引されるだけだ。誰かが買えば、誰かが売る。誰かが得れば、誰かが失う。1億円のものを2億円で売れば、売り手は1億円得するが、買い手は1億円損する。
「でも、国全体で土地の価値を上げれば、富が増えるはずだ。たとえば、総資産が 500兆円から 1000兆円に増えれば、500兆円の富が増えるはずだ」と思う人が出てくる。「だからそのために、貨幣供給量を増やそう。貨幣数量説で、それが可能なはずだ」と主張する。── とんでもない勘違いである。貨幣数量説では、名目価格が上がっても、物価が上がるだけで、富は少しも増えない。総資産が 500兆円から 1000兆円に増えたとしたら、それは、富が増えたということではなくて、貨幣価値が低下したということを意味するだけだ。(そこを理解できないエセ・マネタリストが、「資産インフレは富を増やす」とか、「資産デフレは富を減らす」とか、メチャクチャなことを主張する。自己矛盾。)
話を戻そう。「貯蓄冷遇」は、「消費拡大」ではなくて、「資産投資の拡大」をもたらす。人々は、先行きが不安で消費をしないが、「貯蓄冷遇」があるゆえに、仕方なく、「疑似貨幣」である「資産」に投資するようになる。そのあげく、「資産インフレ」が発生することとなる。これが (2) の結論となる。
さて。
以上の (1) (2) で述べたように、「マイナスの金利」は、「投資拡大」も「消費拡大」も起こさず、「資産インフレ」だけを起こすこととなる。実際、それだけが合理的な行動なのである。企業にせよ、国民にせよ、「マイナスの金利」のときは、「投資」や「消費」ではなくて「資産インフレ」だけが有利だ。(「消費や投資をするはずだ」と主著崇敬在学者は、現実が見えていないようだ。実際、所得上昇のない状況で、ご本人は消費を府屋鋤があるんでしょうかね?)
では、「資産インフレ」というものは、どういう影響があるか? それなら、もちろん、さんざん痛い目に遭って、よくわかっているはずだ。
「資産インフレ」は、制御が困難である。資産インフレが上昇することならば、「金利の引き上げ」や「量的な引き締め」で抑制できる。しかし、資産インフレの下落(バブル破裂)は制御が非常に難しい。── なぜか? 資産の上昇過程では、資産を買うのに多額のマネーが必要だ。しかし、資産の下落過程では、資産を売るのに何の制限もない。単に市場で「売ります」と告知するだけでいい。電話一本で済む。そして、人々がいっせいにそういう行動に走れば、ただちにバブル破裂が発生する。かくて、バブル破裂は、制御困難となる。
バブルの膨張と破裂というものは、経済を非常に傷つける。そのことは、すでに、日本もアメリカも体験したはずだ。なのに、いまだに懲りないで、「もう一度バブルを発生させよ」とか、「今度のバブルはうまく制御しよう」などと、とんでもないことを主張する。
はっきり言おう。1990年のバブル破裂で、日本経済がひどく傷ついたのは、日銀だけのせいではない。たしかに、もうちょっとうまくやれば、あんなにひどくはならなかっただろう。急いでゼロ金利にしておけば、景気の急速な悪化は防げたかもしれない。しかし、たとえ急速な悪化は防げても、悪化の幅自体は小さくできなかっただろう。かつてバブル時に莫大な富を浪費した以上、その浪費のツケを発生する時期が来るのは確実だ。「いや、そんなことはない、永遠にバブルを続ければよかった」などと考えるのは、狂気である。それはいわば、「サラ金から永遠に金を金を続けていればいい。そうすれば、大金を借りて、返さずに済む」と主張するのと同じだ。また、「バブルによって生産が増えるから、それで帳尻が付く」なんて主張をするのは、「好況期に減税をすれば、税収が増えて財政黒字になる」と主張したレーガノミックスと同じだ。どちらも、途方もない楽観的な妄想である。
狂気の経済学ほど、人々をたぶらかすものはない。レーガノミックスやら、バブル礼賛のマネタリズムやら。……オウムやビンラディンは、狂気の妄想で莫大な損害と破壊を招いたが、それよりもずっとひどいのが、経済学者だ。彼らの狂気は、国家そのものを全面的に弱体化させる。
そして、そういう狂気の経済学者の信じる説の一つが、「マイナスの金利」だ。これは貨幣経済を破壊して、資産を最優先にしようとするものだ。これだったら、まだ石器時代の方がマシだ。巨大な石の通貨でも使っていればいい。どんな通貨であれ、通貨を否定するよりは、ずっとマシである。
[ 参考 ]
同じような論拠の「資産インフレ批判」は、何度か述べた。
「マイナスの金利」の批判も、何度か述べた。( → 5月16日 など。)
「インフレ目標」には、「流動性の第2の罠」という問題もある。( → 4月30日b )
[ 付記 ]
「インフレ目標つき量的緩和」なんていう主張もある。実は、これは、話が矛盾・錯乱している。
そもそも、「インフレ目標が必要だ」ということの論拠は、「金融政策が無効になっているから」つまり、「量的緩和が無効であるから」だ。
だから、「量的緩和が無効だ」という前提のもとで、「インフレ目標を」と唱え、同時に、「(無効な)量的緩和を実施せよ」と唱えているわけだ。論理矛盾。
どうせなら、「量的緩和が無効だ」という前提のもとで、「インフレ目標を」と唱え、同時に、「(無効な)量的緩和をやめよ」と唱えるべきなのだ。これなら、筋が通っているのだが。
《 翌日のページへ 》
(C)
Hisashi Nando. All rights reserved.