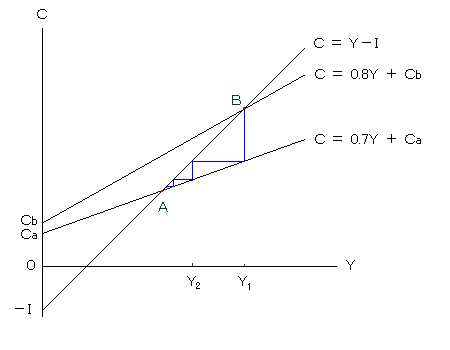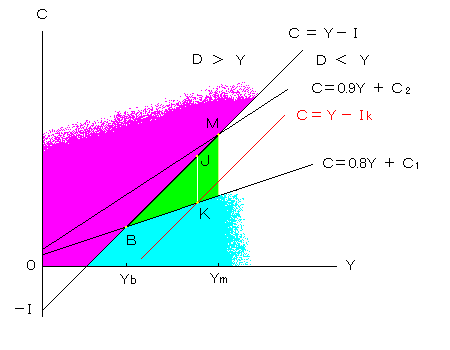[ 2003.4.15 〜 2003.4.24 ]
《 ※ これ以前の分は、
2001 年
8月20日 〜 9月21日
9月22日 〜 10月11日
10月12日 〜 11月03日
11月04日 〜 11月27日
11月28日 〜 12月10日
12月11日 〜 12月27日
12月28日 〜 1月08日
2002 年
1月09日 〜 1月22日
1月23日 〜 2月03日
2月04日 〜 2月21日
2月22日 〜 3月05日
3月06日 〜 3月16日
3月17日 〜 3月31日
4月01日 〜 4月16日
4月17日 〜 4月28日
4月29日 〜 5月10日
5月11日 〜 5月21日
5月22日 〜 6月04日
6月05日 〜 6月19日
6月20日 〜 6月30日
7月01日 〜 7月10日
7月11日 〜 7月19日
7月20日 〜 8月01日
8月02日 〜 8月12日
8月13日 〜 8月23日
8月24日 〜 9月02日
9月03日 〜 9月20日
9月21日 〜 10月04日
10月05日 〜 10月13日
10月14日 〜 10月21日
10月22日 〜 11月05日
11月06日 〜 11月19日
11月20日 〜 12月02日
12月03日 〜 12月12日
12月13日 〜 12月24日
12月25日 〜 1月01日
2003 年
1月02日 〜 1月13日
1月14日 〜 1月24日
1月25日 〜 1月31日
2月02日 〜 2月11日
2月12日 〜 2月22日
2月23日 〜 3月07日
3月08日 〜 3月16日
3月17日 〜 3月25日
3月26日 〜 4月06日
4月07日 〜 4月14日
4月15日 〜 4月24日
のページで 》
● ニュースと感想 (4月15日)
「モデルと現実」について。
モデルと現実とは、どういう関係にあるかを、述べておこう。
物理学で言うモデルは、一種の「真理」としての位置を与えられる。たとえば、万有引力の法則だ。簡潔な数式で示され、現実の質量運動が原理的にこの数式に従うことが経験的にわかっている。実際には、実験結果が理論とはズレることも多いのだが、その場合は、空気抵抗など、外部の邪魔が入ることによってズレるだけであり、そういう邪魔をなくせば(たとえば真空中では)、実験結果が理論にどんどん近づくことがわかっている。
ここでは、「現実がモデルに従う」わけだ。
経済学ではどうだろうか?
そもそも、何らかのモデルがあるとしても、その妥当性が問題となる。そのモデルが現実を正確に反映しているという保証がない。ある場合には、そのモデルが現実を反映しているように見えるとしても、別の場合にもそうだという保証はない。また、実験によって、検証することもできない。
となると、その妥当かどうかもわからないモデルを使って、何らかの論理的な結論を出したとしても、その結論が信頼できるかどうかは、わからない。
そして、そういう誤りの典型的な例が、4月11日(合理的期待形成仮説の批判)で述べたことだ。「現実と一致することもあるように見えるが、本当は現実とは大きくズレているモデル」(現実を反映していないモデル)を使って、論理的な結論を出すが、そもそも、そのモデルが間違っているわけだから、いくら精緻な論理を組み上げても、何の意味もない。
では、トリオモデルや、修正ケインズモデルでは、どうなのか?
第1に、トリオモデルだが、これは、簡単すぎる。単に下限直線による阻害がある、とわかるだけだ。特に論理的な結論が出るわけではない。単に「不均衡」という現象が発生することを理解するためのモデルであるにすぎない。
第2に、修正ケインズモデルだが、ここでは、複雑な論理的な結論が出る。「循環的な過程」とか、「収束点」とか、「乗数効果」とか、「下限均衡点」とか、「上限均衡点」とか、「区間 BM」とか、「長さJK」とか、「緑色領域」とか、そういう論理的な結論が出る。
こういう論理的な結論は、どこから生まれたか? それは、ただ二つの仮定だ。すなわち、次の二つの直線だ。
C = 0.8Y + C1
C = Y − I
ここでは、二つの直線がある。前者は、上記では 0.8 という数値を取っているが、 0.9 などの値に変化することもある。後者は、45度線であり、固定されている。
そして、この二つの直線によって示される領域として、次の図が示された。
そして、さらに「循環的な過程」というふうに話が進むわけだが、それというのも、上の二つの直線に基づいている。どちらの式にも C と Y とが現れているので、
「 Y → C → Y → C → Y → C → ……」
というふうに循環するわけだ。(数列の形で。)
そして、そこからさらにいろいろと話が発展していったわけだ。
とすれば、肝心なのは、次のことだ。
このモデルでは、上の二つの式だけが仮定されている。そして、現実の経済が、上の二つの式を満たすのであれば、上の二つの式から得られる論理的な帰結に、現実の経済もまた従う、ということだ。
このことは、大切である。
修正ケインズモデルでは、「縮小均衡がどうのこうの」というふうに説明している。そういう説明について、「これは南堂の個人的な主張だ」と思う人もいるかもしれない。しかし、そう思うとしたら、正しくない。修正ケインズモデルから論理的に得られる結論は、論理的なものであるから、誰かが個人的にどう思うとか思わないとか、そういう問題ではないのだ。誰がどう思うと、これは「1+1=2」と同じように、必然的に得られる結論である。主観の介在する余地はないのだ。
主観の介在する余地があるとしたら、最初の二つの式だけだ。その二つだけが仮定だからである。「それはおまえが勝手にそう思っているだけだろう」と批判できるとしたら、この二つの式だけなのだ。
( ※ これは、数学における「公理的空間における公理」と同様である。たとえば、ユークリッド幾何学は、ユークリッドの公理だけを仮定して、そこからユークリッド幾何学が導き出される。何かを批判するとしたら、その最初の公理だけである。)
さて。では、修正ケインズモデルにおける二つの式は、どれだけ妥当性があるか?
(1) 消費直線
「 C = 0.8Y + C1 」という直線だが、これについては、前にも述べたとおりだ。つまり、ここでは、簡単にするために、一次式で示しているだけのことだ。正確に知るためには、複雑な数式で複雑な曲線を描いてもいいが、それで異なるのは、細かな数値が少し変わるというぐらいのことだ。「おおざっぱに正しい」というふうに、本質を突くためには、この程度の簡略化をしても、特に問題はない。
問題があるとしたら、「この式がまるきり見当違いだ」というような場合だ。しかし、そういうことは、まずあるまい。この式が妥当であることは、多くの経済学者が肯定している。(たとえば、「この式が不正確である」というのではなく、「そもそもこんな関数関係はない」ということは考えられるが、現実には、こういう関数関係があると考えられる。ここのところが、「モデルと現実」との関係で、基礎的な部分だ。)
私の主張で、他人と違って新しいところがあるとしたら、「限界消費性向が(心理的な影響で)たやすく変化する」ということだ。
とはいえ、「限界消費性向は変化しない」というケインズの説を採りたければ、それはそれだけのことだ。あとは、二つの説で、どちらが現実に適合するか、という問題となる。ケインズの主張からは、「均衡点は、完全雇用のただ一点だけであり、均衡を保ったまま生産量が拡大することはありえない」となる。そういう結論がおかしい、ということは、私がこれまで何度か指摘したとおりだ。
(2) 生産直線
「 C = Y − I 」という直線だが、これは、「 Y = C + I 」という式を移項しただけである。そして、この式が保証するという保証は、もともと、ない。たとえば、「 Y > C + I 」となることもある(つまり需要不足)。逆に、「 Y < C + I 」となることもある(つまり需要超過)。
だから、「 C = Y − I 」という式が正しいかどうか、ということを考えても、あまり意味がない。実際には、それが当てはまらないこともある、と初めからわかっているからだ。そして、当てはまらないことがあるのであれば、その分、補正をした方がいいとも言える。
たとえば、そのズレを δ と書くことにしよう。「 C ≠ Y − I 」のときには、「 δ = ( Y − I ) − C 」 というふうに δ を定義できる。とすると、新たに、「 C = Y − I − δ 」という式を書ける。
ここで δ は定数である保証はなく、 Y に応じて変化する関数であるかもしれない。ともかく、そのようにして、「 C = Y − I − δ 」という式に応じた曲線を描ける。それは、「 C = Y − I 」という直線にほぼ並行していて、 δ だけのズレがある曲線だ。
そして、この「 C = Y − I − δ 」が、「 C = Y − I 」よりも正確さの度合いを増した曲線だ、ということになる。そういうふうに補正できるわけだ。
すると、どうなるか? その補正の効果としては、「乗数効果」のときの話が少し変わる。乗数効果を考えるときは、階段状の経路をたどった。そのとき、45度線で反射していた。しかし、本当は、不均衡状態では、「 C = Y − I 」は成立せず、「 C = Y − I − δ 」が成立しているのだから、この曲線にぶつかって反射するべきだったのだ。
そして、需要不足のときは、 δ は正の値(ゼロ以上)であるから、この補正された曲線は、45度線よりも少し下に位置する。(図で言えば下方に位置する。)ゆえに、乗数効果の階段状の経路をたどるとき、本当は、先に述べた理論(45度線を仮定していた理論)よりも、少し小さな効果しかもたらされないことになる。
つまり、需要不足が発生しているときには、乗数効果は、先に述べた理論は不正確であったのだ。本当は、もっと小さな効果しか生まれないはずなのだ。
そういうことが判明することとなる。
( ※ ただ、だからといって、先に述べた理論が間違いだと言うことにはならない。正確さが不足していると言うだけのことだ。 δ というズレの分までも考慮すると、話が複雑で面倒になるから、乗数効果という本質を考えるときには、このズレの分までも考察する必要はない。あとで細かく考えたくなったときに、このズレの分も考慮に入れて、補正すればいいわけだ。)
( ※ なお、この δ という量は、実際には、かなり小さい値である。上の例では、 500兆円に対する 5兆円であるから、1%である。実際には、もっと小さく、1%未満と考えていいだろう。この δ という値が大きいのは、消費性向が急激に変化したときだけである。たとえば、バブル破裂した時期。この時期、生産量は急激に低下したが、同時に、消費性向も急激に低下したはずだし、 δ は急激に拡大したはずだ。一方、2002年ごろは、慢性的に不況になっている状態だから、 δ はあまり大きくないはずだ。……というわけで、慢性的な不況の最中には、 δ というものはほとんど無視できるわけだ。)
[ 補足 ]
この δ は、「需要不足の量」と考えていいが、普通言われる「需給ギャップ」とは異なる。注意しよう。
たとえば、不況の最中に、生産量が 505兆円で、需要が 500兆円だとする。このとき、差し引きして、5兆円の超過生産(在庫積み増し)が発生する。この5兆円が δ である。これは、現時点における「需要不足の量」である。
一方、普通言われる「需給ギャップ」は、根元的な「需要不足の量」である。それは、「下限均衡点の生産量」と「現時点の需要」とのギャップだ。下限均衡点の生産量が 540兆円で、現在の需要が 500兆円だとすれば、差し引きして、40兆円が「需給ギャップ」となる。
普通言われる「需給ギャップ」は、この 40兆円の方だ。上の5兆円の方( δ )も、「需給ギャップ」と呼ばれることもなくはないが、あまり正当な用語法ではない。たとえば、「縮小均衡では需給ギャップが解消する」と言われることもあるが、そういう言い方はあまり正当な用語法ではない。「縮小均衡では、需給が均衡するが、需給ギャップは解消するどころか最大になる」と述べるのが正当であろう。
なお、用語がまぎらわしければ、次のように区別してもよい。
需要不足 …… 現時点における供給と需給の差 ( δ )。
GDP不足 …… 下限均衡点の生産量と、現時点での生産量(= 需要)との、差。
( ※ この区別は、かなり大切だ。たいていの古典派は、「 δ を縮小させることで均衡が回復する」と考える。それゆえ、設備廃棄や人員解雇などで、縮小均衡をめざす。しかし、本当は、 δ を縮小させるよりは、需給ギャップ[GDP不足]を縮小させるべきなのである。そのためには、当面は、 δ を放置してもいい。たとえば、無駄な人員を解雇せずにいてもいい。とにかく、 δ にとらわれず、生産量を拡大することが大切なのだ。── だから前にも、こう述べた。「大切なのは、均衡にすることだけでなく、同時に、生産量も拡大することなのだ。生産量に注目せよ」と。 → 1月20日 )
( ※ ついでだが、 δ という記号は、ギリシャ文字の一つで、「デルタ」と読む。これは小文字であり、大文字は Δ である。)
● ニュースと感想 (4月16日)
前項では、「 δ は実際には小さな値である」ということを示した。このことは、「修正ケインズモデルでは、消費性向の低下にともなって、大きな需給ギャップが生じる」ということと、矛盾するように見えるかもしれない。そこで、説明しておく。
「供給と需要の差」(供給に対する「需要超過」または「需要不足」の量)というのは、現時点の量を見れば、小さいのである。たとえば、需要が一夜にして大幅に縮小するのならば、その差は大きくなるだろう。しかし、現実には、需要の縮小には、何十日かかかる。バブル破裂直後でさえ、約1年間かかった。その間、企業は、むやみやたらと生産をしているわけではない。つまり、やたらと在庫を溜めているわけではない。今日では、「カンバン方式」などの在庫管理が進んでいるから、在庫は最小限で収まっているはずだ。つまり、現実における「供給と需要との差」つまり「在庫の積み増しの量」は、きわめて小さい。
それにもかかわらず、需給ギャップはある。なぜか? ここで言う「需給ギャップ」とは、「現時点における供給と需要とのギャップ」( δ )ではないのだ。需要の方は「現時点の需要」でいいが、供給の方は「現時点の供給」ではない。では、何か? その「供給」とは、「下限均衡点の供給」つまり「赤字にならないで済むような供給」である。
たとえば、生産量が1万個のときにコストが 100円である、としよう。その場合、 100円というコストにするには、生産量が1万個でなくてはならない。生産量が 9500個では、赤字になってしまう。このとき、1万個と 9500個との差が、その商品の需給ギャップとなる。
ここでは、需給ギャップは、500個である。(金額で言えば、500×100円 = 50000 円 だから、50000円だ。) この際、それだけの需給ギャップがあるが、現実の生産過剰の分は、在庫の分だけである。その量( δ )は、ほとんどゼロに近い。
( ※ 上の例は、あくまで、たとえ話である。「需給ギャップ」というのは、個別商品には当てはまらず、マクロ的な場合にのみ、当てはまる。上のように「需給ギャップが 50000円」なんていうことは現実には無意味であり、マクロ的に何十兆円かの需給ギャップがあるだけだ。この点、勘違いしないでほしい。上の例は、あくまで、たとえ話である。)
● ニュースと感想 (4月16日b)
「均衡点とは何か」について。
従来の経済学においては、「均衡点」という概念が非常に重視される。たとえば、「一般均衡理論」というようなのは、「経済学の王座を占める」とさえ見なされているようだ。しかし、そもそも、「均衡点」とは何なのか? それについて、モデル論の立場から考えてみよう。 (前に述べたことも参照。 → 3月09日 [付記2] )
基本的に言えば、こうだ。「均衡」という状態は、ただの「収束点」である。そこでは、たしかに需給は均衡するが、そこで状態が安定するとは限らない。そこからさらに変化することがないというわけでもない。むしろ、そこから先、どんどん変化するものだ。たとえば、均衡に達したあと、経済成長をする。
(1) 縮小均衡にいたる過程
従来の経済学では、「均衡点」というものは、「数学的な解」とされた。そこは「最も安定的な状態」であるとされた。(価値判断を入れて、「最も望ましい状態」ということは必要とされない。)
しかし、現実には、「最も安定的な状態」ではない。そのことは、先にも示したとおりだ。修正ケインズモデルにおける「収束点」は、「循環的な過程の行きつく先」である。それは「最も安定的」というのとは違う。
特に問題なのは、「縮小均衡」となる場合だ。その点では「縮小均衡」が実現するが、そういう「縮小均衡」の点が最も安定的であるわけではない。「縮小均衡」というのは、単に「循環的な過程がもはやそれ以上は進まない」ということを意味するだけだ。現在でも、日本経済はある一点をめざして進みつつあるようにも見えるが、その一点をどんどんめざしているわけではない。むしろ、そこから逃れようとしているのだ。にもかかかわらず、そこしか行き場所がないから、そこに落ち着くというだけのことだ。
たとえて言おう。メガホンに向かって、外から叫ぶと、音波は奥の一点に収束する。音波は、奥の一点が安定的であるからそこに引きつけられるのではなくて、そこしか行き場所がないからそこに収束するだけのことだ。
結局、このポイントは、何か? それは、こうだ。
「修正ケインズモデルで示すのは、需給の不均衡が何をもたらすか、という、変化の過程である。需給の不均衡(= 需給ギャップ)があると、その不均衡が縮小する方向へ、状況が進む。その際、需給の不均衡は縮小していくが、同時に、生産量が変化する。そういうふうに、需給の不均衡が、生産量の変化をもたらす。」
ともあれ、「(需給の)不均衡の変化」と「生産量の変化」が、同時に発生する。そして、この二つのうち、注目するべきは、前者ではなく、後者なのだ。つまり、大切なのは、「需給の不均衡が解消するかどうか」ではなくて、「生産量が増えるか減るか」なのだ。
古典派の経済学者は、「不均衡の解消をめざそう」とだけ考える。このとき、「生産量の変化に着目する」ということを忘れる。目立つものに目を奪われて、肝心のものを見失う。だからこそ、私は、何度も強調するのだ。「均衡が大切なのではない。生産量が大切なのだ」と。
(2) 均衡点の移動 (均衡状態で)
均衡状態になったとしても、そのあとさらに均衡点が移動することがある。(これはマクロ的な効果だ。)
ミクロ経済学ならば、均衡点に達した時点で、話はおしまいである。「均衡が実現しました」と言って、もはやそれ以上は、何も語ることはない。
マクロ経済学では、そうではない。均衡点に達したあとでも、さらに語るべきことがある。何か? 「均衡点の移動」である。これは、どういうふうに発生するか? 「需要曲線のシフト」および「供給曲線のシフト」によってだ。
「需要曲線のシフト」および「供給曲線のシフト」。── これが大事だ。これを、ミクロ経済学では考慮しないが、マクロ経済学では考慮する。ミクロ経済学を重視する古典派の経済学者ならば、これを無視するが、まともな経済学者ならば、これを無視するわけには行かない。
「需要曲線と供給曲線のシフト」は、「均衡点の移動」をもたらす。つまり、「均衡が達成されたから、それで話はおしまい」ではなくて、「均衡を保ったまま均衡点が移動していく」ということがある。そういうことを考察する必要がある。
そして、こういう動的な変化をになうのが、「修正ケインズモデル」である。「均衡状態における景気の変化」については、「インフレ」(好況)や、「リセッション」(景気後退)として、すでに説明した。 ( → 10月26日 以降 )
(3) 消費性向の変化
これまでの修正ケインズモデルの議論では、消費性向の変化は単純化されていた。たとえば、「 0.9 → 0.8 」とか、「 0.8 → 0.7 」とか、そういうふうに、二つの値における変化である。
しかし、現実には、そういう単純な話では片付かない。「ゆるやかに消費性向が低下する」という状況では、「 0.8 → 0.79 → 0.78 → 0.77 → 0.76 → …… 」というふうに変化するだろう。すると、消費性向の低下による景気悪化が、累積的に発生することになる。
これは大事だ。というのは、「 δ は小さい値だ」ということを説明するからだ。前項でも述べたが、 δ はかなり小さい値だ。つまり、現実経済においては、「在庫過剰」とか「余剰生産」とか、そういう「需給の不均衡」の量は、かなり小さい値である。(「カンバン方式」などによる在庫縮小の生産方式が関与している。) では、 δ が小さい値なのに、なぜ、「 δ を原因とする生産量の縮小」が起こるのか? それは、消費性向がどんどん低下していくからだ。つまり、いったん縮小均衡に近づいたと思ったら、ふたたび消費性向が低下して、新たに δ が発生するからだ。……そして、そういうことの積み重ねで、生産量がどんどん低下していく。
こういう「消費性向の低下」は、心理的なものである。これが進んだのは、政府の施策のせいだろう。「構造改革」や「不良債権処理」や「ペイオフ解禁」による倒産促進のマクロ政策。、「増税」や「社会保険料値上げ」や「失業手当削減」という所得削減政策。さらには、「失業率悪化」「倒産続出」「賃下げ」という経済指標のアナウンス効果。……これらがあいまって、消費心理はひどく低下していくはずだ。それが「消費性向の低下」をもたらす。
つまり、現在のデフレの悪化は、「循環的な過程が進むことによる生産量の縮小」と、「消費性向の低下による生産量の縮小」とが、ともに重なっているわけだ。
( ※ なお、「消費性向の低下」は、トリオモデルで言えば、「需要曲線の左シフト」とも理解できる。)
[ 付記 ]
上の (3) が、けっこう大切である。いったん修正ケインズモデルで説明が済むように思えても、その修正ケインズモデル自体が、さらに動的に変化していくのである。
とはいえ、この「消費性向のさらなる変化」は、実際には、ある程度、無視してもいい。つまり、「消費性向は、いったん低下したら、そのままずっと同じ低い水準に留まる」と考えてもいい。この件は、すでに述べたことがある。( → 3月30日 )
とはいえ、まったく無視していいわけでもない。1991年にデフレが始まったあと、景気は一貫してなだらかに低下していったわけではなくて、少し良くなったり、また悪くなったり、いろいろと変動していった。こういう変動は、「循環的な過程が進む」ということだけでは説明がつかない。
とはいえ、もう一つ、「循環的な過程が加速される」という現象もある。たとえば「賃下げ」によって縮小均衡に近づく。ここでは「賃金の下方硬直性」による効果がないので、「縮小均衡という均衡点に近づく」という変化が急速に進み、そのことで、経済は急激に縮小していく。── 2003年春の現象は、こういう効果だと見なされる。ただ、同時に、「消費性向の低下」もあるはずだ。つまり、賃下げがあれば、賃下げの分の額(正確には限界消費性向を乗じた額)だけ消費を縮小するのでなく、それ以上の額で消費が縮小しそうだ。
[ 補足 ]
本項の話は、次項の話の下準備である。続いて、次項を読んでほしい。
● ニュースと感想 (4月17日)
前項の続き。
前項に続けて、重要なことを、付け加えておく。それは、「下限均衡点の移動」だ。
「縮小均衡」の状態では、もはや需給は均衡していて、不均衡は解消している。つまり、トリオモデルにおける「下限直線割れ」(原価割れ)が発生していない。となると、ここではもはや、「下限均衡点より左下」であるとは言えなくなる。(なぜなら、需給が均衡していれば、金融政策が有効になるからだ。その境界となる点が、下限均衡点である。)
つまり、「縮小均衡」に達した時点では、もはや、下限均衡点はその位置にまで移動していることになる。下限均衡点は、デフレが進むにつれて、元の位置から、新たな位置へと、左下に移動したことになる。── こういうふうに「下限均衡点の移動」が発生しているわけだ。そして、それは、トリオモデルにおける「供給曲線の左シフト」によって生じる。つまり、供給能力が次々と失われていったから、需要は増えなくても、供給能力が減ったので、均衡が成立するようになったわけだ。
そして、このあとは、いったん均衡状態に達したから、金融政策が有効になる。
[ 付記 1 ]
ただし、注意しよう。「下限均衡点の移動」にともなって、「縮小均衡」が実現すると、金融政策が有効になる。このあとでは、金融政策によって、景気回復が可能となる。
では、それは、好ましいことか? 経済学者にとっては、好ましい。しかし、それ以外の全国民にとっては好ましくない。
なぜか? 何度も述べたとおり、「縮小均衡」とは、「最悪の点」であるからだ。「そのあとは良くなるだけだ」からといって、最悪の点に落ち込むことは、とても歓迎できない。
縮小均衡に達したとしよう。このとき、古典派経済学者は、「均衡が達成したぞ。状況は安定的になった。経済学の目的は果たされた」と叫ぶだろう。しかし本当は、「もはや最悪になったから、これ以上は悪くならない」というだけのことだ。「死者はこれ以上は死なない」というようなものだ。
縮小均衡のとき、たしかに、均衡は達成されている。だから、倒産も失業も、もはや拡大はしない。しかし、それは、倒産も失業も最大量になっているからにすぎない。「これ以上は悪くならない、あとは良くなるだけだ」というのは確かだが、「だからすばらしい」と言うべきではなくて、「だから最悪だ」と言うべきなのだ。
核心を示そう。「縮小均衡」のときに、金融政策が有効になるのは、「生産力がすっかり崩壊してしまったから」なのだ。それまでは多大な生産力があったのに、経済が崩壊し、生産力が崩壊した。このあと、何か生産したくても、生産できない。生産するためには、金を払って、生産力を整備するしかない。つまり、投資するしかない。だからこそ、金融政策が有効となる。
しかし、「生産力が崩壊したあとで、生産力を整備する」というのは、「捨てて、買い直す」というのと同じだ。まったくの無駄だ。初めからずっと持っていればいいのに、それができずに、捨ててしまった。そのあとで、捨てたものが必要だと気づくが、もはや捨てたものは存在しない。だから、金を払って、買い直す。その金がないから、銀行から借りる。銀行は喜ぶ。── しかし、国民にとっては、大損だ。喜ぶのは、銀行の都合ばかりを考えている、マネタリストだけだ。
ケインズ派は、公共事業で、「穴を掘って埋めろ」と言う。マネタリストは、設備投資で、「捨ててから買え」と言う。どちらも、同じである。狂気の沙汰だ。
縮小均衡というのは、いくらか安定的ではあるが、とても好ましい状態ではない。そこに到達する前であれば、設備はまだ存在していたのだ。そのときに需要が回復すれば、設備は捨てられることなく、有効になったのだ。
[ 付記 2 ]
上述のことから、わかることがある。
縮小均衡が実現すると、下限均衡点が左下に移動する。しかし、それを見て、「均衡状態が回復した」と喜んでもダメなのだ。また、経済学者としては、「下限均衡点をどんどん左下に移動すればいい」ということにもならない。
むしろ、下限均衡点が左下に移動する前に、さっさと景気を回復するべきなのだ。つまり、生産力が崩壊しないうちに、景気を回復するべきなのだ。
結局、大事なのは、均衡という状態を回復することだけでなくて、生産量そのものを回復することなのだ。
そして、そうとすれば、「根元的な需給ギャップ」(GDP不足)というのは、「当面の下限均衡点の生産量とのギャップ」ではなくて、「最初の下限均衡点の生産量とのギャップ」であるわけだ。
これまでは、単に「下限均衡点の生産量とのギャップ」というふうに述べてきたが、すぐ上で述べたとおり、「下限均衡点の移動」という現象が発生するとわかったからには、このように注記しておく方が正確だろう。
[ 補足 1 ]
4月15日の最後では、次のように書いた。
- 需要不足 …… 現時点における供給と需給の差 ( δ )。
- GDP不足 …… 下限均衡点の生産量と、現時点での生産量(= 需要)との、差。
これだけを読むと(つまり説明を読まないで上記の文章だけを読むと)、誤解されかねないところもある。そこで、誤解されないように、解説しておく。
δ は、現時点における「供給と需要の差」である。これは、45度線に対して、その上にあるか下にあるかで決まる。
GDP不足は、下限均衡点での生産量 Yb と、現時点での生産量 Y との、差である。
ここまでは、すでに述べたとおりだ。
さて。もう一つ、別の概念がある。すでに本項での述べたとおり、「下限均衡点の移動」がある。とすれば、下限均衡点が移動して行くにつれて、現時点での「GDP不足」の量も、少しずつ変化していくことになる。下限均衡点が左下に移動して行くにつれて、 Yb は縮小していくから、Yb と Y との差もだんだん縮小していく。
ここでは、現時点における「GDP不足」の量がある。そういうものもあるわけだ。そして、これもまた、「現時点における需給ギャップ」というふうに表現できる。
しかし、この値は、表現は似ていても、 δ とはまったく異なるものである。混同しないように、注意しよう。
具体的に言おう。バブルの破裂直後には、GDP不足は 530兆円と 500兆円の差で、 30兆円ぐらいあった。しかるに、その後、リストラが進んで、供給能力が崩壊していったから、GDP不足はどんどん縮小していったはずだ。20兆円とか、10兆円とか、そのくらいの値に縮小していっただろう。
一方、δ は、単なる在庫の積み増しの量であるから、常に、ごく小額であったはずだ。バブル破裂の直後には、かなり大きかっただろうが、急激な縮小が収まるにつれて、 δ はほとんど無視できるレベルに縮小していったはずだ。
もう少しわかりやすく言おう。 δ を解決するものは、稼働率である。稼働率を低下させれば、在庫の積み増しを防げる。一方、GDP不足を解決するものは、生産設備の供給能力である。これがある限り、GDP不足は解決できない。そして、これを解決する策は、生産設備を経済テロによって崩壊させるか、需要を増やすか、どちらかでしかない。古典派(の一部)は、「生産設備を破壊せよ」つまり「供給能力を減らせ」と主張し、私は「需要を増やせ」つまり「稼働率を上げよ」と主張する。どちらにしても、均衡は実現する。ただし、前者は「縮小均衡」であり、後者は「元の均衡」である。どちらをめざすかが、異なる。そして、その違いを、古典派は理解できないのである。彼らは、「どっちも均衡だろ。均衡すれば、それで景気は良くなる」と主張する。
かくて、現在、日本は「縮小均衡」をめざし、そのことで、デフレはどんどん進行していくのである。
[ 補足 2 ]
デフレがどんどん進むと、「縮小均衡」に達する。このとき、下限均衡点が十分に左下に行くので、「均衡」が実現する。このとき、「現時点におけるGDP不足」は、ゼロになっている。
では、「縮小均衡」が実現した場合、元の下限均衡点との間の「GDP不足」(本来の需給ギャップ)を、埋めるべきかどうか? これが、問題となる。そして、それに対する答えは、イエスともノーとも、簡単には言えない。
生産設備の崩壊の規模が小さければ、もちろん、元の生産量に回復するべきだ。そうすることが可能だからだ。
しかし、生産設備の崩壊の規模があまりにも大きいと、そうは言えない。なぜなら、元の生産量に回復するだけの生産設備が、とっくに崩壊してしまっているからだ。元のの生産量をめざそうとして、需要を拡大しても、供給が追いつかない。実力以上の生産をめざすことになる。すると、過剰な物価上昇が発生する。……だから、そんなことをめざすべきではない。
結局、元の生産量の水準まで戻すかどうかは、生産設備がどれだけ崩壊しているかに依存する。
では、その程度がどのくらいかは、どうすれば判明するか? それには、物価上昇率を見ればよい。物価上昇率が低ければ、まだ供給能力の上限には達していないことになるから、もっと需要を増やしてよい。しかし、あまりにも需要が増えると、「上限均衡点の突破」が生じて、「貨幣数量説ふうのインフレ」が起こる。こうなると、問題だ。
( ※ とにかく、そういうわけだ。だから、初めに帰って言えば、生産設備をあまり崩壊させない方がいいわけだ。つまり、下限均衡点が左下に移動させない方がいいわけだ。「下限均衡点を左下に移動すれば、デフレ対策ができる」と思うのは、総計である。そうすれば、今度は、「ハイパーインフレ」を招きやすくなる。一般的に言えば、一国全体の生産能力は高い方がいいから、下限均衡点は右上にある方が好ましい。大切なのは、下限均衡点を左下に移すことではなくて、需要の変動をなるべく少なくすることなのである。そして、それこそが、マクロ経済学の目的だ。経済学の目的は、「供給能力を成長させること」ではなくて、「需要を安定させること」なのである。この根幹を勘違いしてはならない。サプライサイドは、勘違いしているが。)
● ニュースと感想 (4月17日b)
時事的な話題。「縮小均衡」について。(すでに述べた話の繰り返しになるので、特に読まなくてもよい。)
読売新聞上にときどき、「縮小均衡」という言葉がよく出る。しかし、どうも、用語を正しく理解していないようだ。たとえば、次の例だ。
「企業の事業計画を見ると、売上高の伸びが小さい一方で、利益の急伸を予想している。……企業は生き残りのために、縮小均衡に追い込まれている」(読売・朝刊・経済面 2003-04-02 )
話を完全に勘違いしているようだ。「個別企業が縮小均衡に追い込まれる」ということはない。「縮小均衡」というのは、マクロ的な状況にのみ当てはまることだ。
個々の企業は、利益の増加をめざす。そうやって自分にとって有利になるようにする。しかし、個々の企業がそうすればそうするほど、国全体では売上げ(総生産)が縮小してしまう。……そういう「合成の誤謬」にあたるのが、「縮小均衡」である。
だから、「企業が生き残りのために縮小均衡に追い込まれる」ということはない。「企業が生き残りのために収益改善策(リストラ)をしたがる」ということがある。そして、そのとき、「国全体が縮小均衡に追い込まれる」のである。
話のポイントを突けば、こうだ。企業は「縮小均衡に追い込まれる」ということはない。あえて縮小均衡をめざしているのである。逆に、拡大均衡を望むのであれば(景気回復をしたいのであれば)、大幅な賃上げをすればよい。そうすれば、大幅な減税があったのと同じだから、景気は一挙に回復する。しかし、あらゆる企業がそうすれば景気は回復するが、たいていの企業は「自分だけは賃上げをしたくない」と望む。そうして賃下げを望む。そうして縮小均衡をめざす。
結局、企業は、「縮小均衡に追い込まれる」のではなく、「あえて縮小均衡をめざしている」のである。そして、それは、企業にとっては少なくとも「最悪」ではない。自社は赤字倒産を免れるからだ。一方、「量的緩和」論者の言う指示に従って、やたらと投資を拡大すれば、マイカルや高島屋のように、赤字倒産する。それは最悪だ。
結語。
不況とは、「企業があえて縮小均衡をめざす状況」である。「個々の企業が自分だけの得をめざして、一国全体の生産量を縮小させていく状況」である。そして、その根本的な解決策は、状況そのものを変えることであって、企業にどうこうせよと指図することではない。(たとえば、「投資を拡大せよ」と量的緩和をすることではない。)
不況というのは、状況の問題なのである。与えられた選択肢から最善を取る方法の問題ではないのだ。だから、国の経済政策は、「この選択肢を取れ」と強制することではなくて、「どの選択肢を取ってもダメ」という状況そのものを変えることなのだ。
企業は、愚かだから縮小均衡を選んでるわけでもないし、いやいや縮小均衡を選んでいるわけでもない。企業は、自らの最善の策として、縮小均衡になるような道を選ぶ。企業は、「最悪」のかわりに、「次悪」を選ぶ。そして、そのとき、国全体は、「最悪」になる。
「縮小均衡」に追い込まれるのは、企業ではなくて、国全体なのである。
( ※ 以上のことは、修正ケインズモデルからわかる。)
[ 付記 ]
最近、やたらと「株が下がった」とか、「景気がどんどん悪化している」とか、悲観的なニュースがしばしば報道される。
これは、当然のことだ。デフレとは、「縮小均衡に近づきつつある過程」なのだから、生産量がどんどん縮小して行くにつれて、状況はどんどん悪化していくわけだ。
多くの経済学者は、「企業が投資を増やせばよい」(だから量的緩和をせよ)とか、「個人が消費を増やせばよい」(だから貯蓄を崩すように貯蓄に課税せよ)とか、そういう意見を言う。いずれも、見当違いである。話の根源は、個人の所得が減っているからなのだ。財布に金がなくては、物を買えない。だから、物が売れず、生産が減り、そのせいで財布の金がますます減る……というふうになる。
こういう「デフレのメカニズム」を正しく理解することが大切だ。
先に、企業がどんどん賃下げをしたとき、多くの経済学者は、「企業の収益性向上のためには、それが正しい。さもなくば、赤字倒産をする。賃下げ万歳」と主張した。しかし、「そんなことをすれば、マクロ的には総所得が縮小するから、景気はますます悪化する」と、私は何度も主張しておいた。そして、その主張が、今まさしく現実化しているのである。 ( → 4月13日にも記したが。)
今、「景気がどんどん悪化している」と騒ぐのは、あまりにも愚かだ。そのことは、4月の「賃下げ」が決定した時点で、とっくに判明していたのだ。
わかりやすく言おう。「定昇なし」ならば、多くの人々は「賃下げなし」と感じている。しかし、マクロ的には、定年退職者の所得が失われる。新卒者が新入社員として所得を得るが、退職者に比べれば、ずっと所得は小さい。本来ならば、定昇があるから、各年齢が少しずつ所得を増やすはずで、全体としては、トントンになるはずだった。ところが、定昇がないから、退職者と新入社員の差額の分だけ、国民税対の所得は奪われてしまった。総所得が減るのだから、総需要は減るし、総生産も減る。
最近の景気悪化は、当然のことなのだ。それは、各企業が、自ら招いた結果なのである。「経団連のせい」と言ってもよい。
[ 補足 ]
核心を言えば、こうだ。「賃下げ」とは、「賃金の下方硬直性」を、なくすことだ。そして、それは、「均衡」に達することだ。ところが、その「均衡」とは、「縮小均衡」のことである。そこに近づくほど、生産量は低下して、GDPが縮小していく。それが「デフレスパイラル」だ。
だから、「賃金の下方硬直性」は、「均衡に近づくことを遅らせる」という意味があり、「GDPの縮小を遅らせる」という意味がある。逆に言えば、それを排除することは、「GDPの縮小を加速する」という意味がある。
ただし、「どちらが良いか?」と尋ねられても、「どちらも好ましくない」と答えるしかない。次の二者択一だ。
・ GDPが縮小するが、生き残った企業の収益性は解消する。
・ GDPが縮小しないが、企業の収益性が悪化する。
結局、「賃下げ」などのリストラは、してもしなくても、一長一短である。リストラは、個別企業にとっては得だが、マクロ的には損だ。(合成の誤謬だ。)
こういうときには、個別企業が何をしてもダメであり、マクロ的に総需要を増やすしかないのだ。……この結論は、すでに何度も述べたとおり。
● ニュースと感想 (4月18日)
「大幅な需給ギャップ」あるいは「リセッションからデフレへ」について。(あまり重要な話ではないので、読まなくてもよい。)
「修正ケインズモデル」について、細かな話を追加しておく。基本的なことはすでに述べたとおりで十分なのだが、細かい話をすれば、「リセッション・スパイラル」と「デフレ・スパイラル」とが込み入った場合もある。そういう場合では、事情が複雑になり、込み入った話が必要となる。そこで、解説しておく。
通常、「リセッション」から「デフレ」に移る場合には、消費性向が一段低下したあとで、さらに消費性向が下がることになる。次の図を見よう。
上の図では、傾きが「 0.8 」と「 0.7 」となっている。この場合は、「デフレ・スパイラル」である。一方、傾きが「 0.9 」と「 0.8 」となっていることもある。その場合は、「リセッション・スパイラル」となる。いずれにせよ、階段状の過程を取るわけであり、本質的には同じである。
通常は、傾きが「 0.9 → 0.8 」と低下することで「リセッション・スパイラル」が発生し、そのあとさらに、傾きが「 0.8 → 0.7 」と低下することで「デフレ・スパイラル」が発生する。
では、傾きが一挙に「 0.9 → 0.7 」と低下したら、どうなるか? あるいは、傾きが一挙に「 0.85 → 0.75 」と低下したら、どうなるか? いずれにしても、「 0.8 」という傾きを越えるので、リセッション・スパイラルとデフレ・スパイラルが続いて発生することになる。すると、どうなるか?
次の図を見よう。緑色の領域に注意してほしい。
消費性向の低下が大きいと、傾きが大きく下がる。すると、たとえば現時点が J だとしても、その後、下がる先は K ではなくて、もっと下の点となる。そして、そこはもはや、緑色領域ではなく、水色領域である。
とすれば、その時点では、あまりにも需給ギャップが大きいので、金融政策を最大化してゼロ金利にしても、消費不足を投資増加で補えない。つまり、「均衡」が達成されず、経済は縮小のスパイラルをたどる。
ただし、注意してほしいのだが、この時点ではいまだに、下限均衡点を割ってはいないのだ。となると、ここで生じているスパイラルは、単純なリセッション・スパイラルでもないし、単純なデフレス・パイラルでもない。この場合、現時点が下限均衡点よりも右上にあるという意味では、リセッション・スパイラルに似ているが、一方、収束点が下限均衡点よりも左下にあるという意味では、デフレス・パイラルに似ている。両者の折衷的な状態である。
そして、この過程がどんどん進むと、あるとき、下限均衡点のそばを通る。そばとはどこかといえば、下限均衡点の少し右下の場所である。詳しく言おう。まず、下限均衡点の少し右のあたりを通り、さらに少しずつ左下に移動していって、下限均衡点の少し下のあたりを通る。そして、最終的には、下限均衡点の左下にある収束点にたどりつく。
説明は、以上で終わる。特に何か、注目すべき事実が判明したわけではない。折衷的な場合には、折衷的な事態が起こる、ということを、詳しく説明しただけだ。ちょっと複雑で、わかりにくいところがあるので、いちいち解説しただけである。
[ 付記 ]
なお、このスパイラルを止める方法は、通常の方法で十分である。つまり、「金融政策」「公共投資」「減税」だ。上の議論では、「金融政策は最大化している」ことが前提されているから、あとは、「公共投資」や「減税」によって、縮小のスパイラルを止めることができる。……ごく当たり前の話だ。
[ 補説 ]
どうせ景気刺激をするとして、「金融政策」「公共投資」「減税」のどれが有効だろうか? これは、当たり前の話ではなく、興味深い話だ。少々、面倒だが。
今、消費性向が低下して、図の緑色領域で、点 J から、点 K へと消費が縮小したとしよう。この長さ JK が、消費縮小の幅である。これを補うために、同額の「公共投資」をするとしよう。すると、この長さ JK は、下限均衡点に近いときほど、長さが短くなる。
だから、均衡を回復することだけが目的であれば、なるべく景気が悪化してからの方が、公共投資の額は少なくて済む。下限均衡点に近づいているということは、それだけ縮小均衡の点に近づいているわけだから、小さな額でも、たやすく均衡に達することができるわけだ。
では、公共投資をするのは、遅ければ遅いほどいいか? なるほど、遅ければ遅いほど、財政赤字の額は少なくて済む。しかし、その分、経済は大きな景気変動をこうむる。財務省や政府は大喜びだろうが、国民は大損だ。これでは、本末転倒である。(財務省の役人ならば、そういう本末転倒をやりたがるだろうが。)
正解を言おう。下限均衡点に近づいていないとき(つまり景気があまり悪化していないとき)には、なるべく金融政策を多めに使うといいのだ。つまり、さっさと低金利にすればいいのだ。そして、ゼロ金利にしてもまだ景気が悪化するような場合には、公共投資を併用すればいいのだ。ここでは、「公共投資よりも、金融政策をなるべく優先するべし」という結論が得られる。── ただし、これは、ケインズ政策の否定を意味しない。このことが言えるのは、あくまで、下限均衡点を割っていない状態であり、ゼロ金利になっていない状態である。ゼロ金利になったあとでは、もはや金融政策は無効になっているのだから、「金融政策をなるべく優先せよ」と言っても、無意味である。要するに、古典派の得意な領域では古典派の意見が通るし、ケインズ派の得意な領域ではケインズ派の意見が通る。
なお、以上では、「金融政策と公共投資」との間で、優先度を比較した。「減税」は、話は別である。「金融政策と減税」との間で、優先度はどうか、という問題は、すでに述べたとおりだ。つまり、状況に応じて、最適の比率で「金融政策と減税」の配分を決めればよい。状況とは、「投資と消費をどういう割合で増やすか」という状況である。投資不足のときには金融政策が大切だし、消費不足のときには減税が大切だ。 ( → 2002年4月24日 の前後)
● ニュースと感想 (4月19日)
「修正ケインズモデルとトリオモデルの関係」について。
この二つのモデルの関係については、先に2箇所で述べた。そちらを参照してほしい。( → 9月15日 ,3月02日 )
要するに、こうだ。修正ケインズモデルにおける「景気悪化のスパイラル」とは、トリオモデルにおいて「需要曲線と供給曲線がともに左シフトすること」である。最終的には、需要曲線が供給曲線に追いついて、下限直線以上に均衡点が移動する。このとき、不均衡が解消して、金融政策も有効となる。
だから、こう言える。修正ケインズモデルにおいて「生産量が下限均衡点以下に低下すること」と、トリオモデルにおいて「下限直線割れ(原価割れ = 赤字)が発生すること」とは、同じことなのだ。
なぜか? トリオモデルにおいて「均衡点が下限直線より以上に位置する」ならば、企業としては、需給は正常に均衡する。つまり、企業にとっては、もはや赤字生産ではない。つまり、この先、生産を拡大しても、赤字になるとは言えない。均衡状態を保ったまま、同じ価格で、需要と生産が拡大しそうだ。(個別産業ではともかく、全体を見ればそうだ。)……だから、需給が均衡している状態では、企業には、投資意欲が湧く。ゆえに、金融政策は、無効ではなくなる。かくて、(金融政策の有効性で決まる)下限均衡点割れと、(市場の需給で決まる)下限直線割れとが、同じことになるわけだ。
● ニュースと感想 (4月19日b)
「均衡とシミュレーション」について。
すでに述べてきたところでは、均衡についていろいろと考えた。そして、
・ 生産量の変化
・ 均衡点の移動
・ 消費性向の変化
が大事だと述べた。(需給の)均衡が実現したからといって、それで話が片付くわけではなくて、上記のようなことも考慮する必要があるわけだ。
均衡点を得るだけならば、「グラフにおいて直線の交点を求める」だけで済む。簡単だ。しかし、上記のような複雑な時間的変化を追うには、どうすればいいか? もはや「直線の交点を得る」というような単純な方法では済まなくなる。
そのための方法としては、先にも述べた「シミュレーション」という方法がある。たとえば、一定の数値モデルを提出して、そこに数値を当てはめて、そのあと、コンピュータで変化を計算する、という方法だ。
この方法の美点は、次のことだ。
「2次元のグラフにこだわらず、いくらでも多い次元の図形を描ける」
つまり、変数をどんどん増やすことができるわけだ。そしてまた、
「時間を含めた逐次的な変化をおくことができる」
という美点もある。
では、シミュレーションならば、万能か? そうではない。そのことは、先にも述べた。シミュレーションは、細かな数値を使うが、その数値が、正しいという保証がない。となると、「精確に間違う」という結果になりかねない。
では、どうすればいいか? その答えも、すでに述べたとおりだ。すなわち、「おおざっぱに正しい」という方法を取る。そして、その具体的な回答が、「修正ケインズモデル」だ。冒頭に述べた三つ、すなわち、
・ 生産量の変化
・ 均衡点の移動
・ 消費性向の変化
については、その核心的な部分を、修正ケインズモデルで説明できた。そして、それだけわかれば、もう十分なのである。「このあと経済がどう変化するか」という細かな数値まではわからないかもしれない。それはそれでいい。「精確に間違う」のは、目的ではない。あくまで、「おおざっぱに正しい」だけでいいのだ。そして、「おおざっぱに正しい」というのは、経済政策について、「どうすればどうなる」「だから、こうすればいい」という指針が与えられることでもある。
修正ケインズモデルは、細かな精確な数値シミュレーションではない。しかし、修正ケインズモデルは、図形によるおおざっぱなシミュレーションにはなる。そのことが核心だ。
トリオモデルを見ているだけでは、需要曲線や供給曲線がどう変化するかは、わからない。しかし、修正ケインズモデルを見れば、おおざっぱに正しく知ることができる。そこに修正ケインズモデルの意義がある。
● ニュースと感想 (4月20日)
「他の景気循環モデル」について。
これまで、「トリオモデル」および「修正ケインズモデル」について、いろいろと再考察してきた。この二つについては、前項までで話を終える。
本項では、他の理論との比較をしよう。
他の景気循環理論としては、「加速度原理に基づく景気循環理論」や、「カルドアの景気循環理論」がある。これらについては、以前言及した。( → 6月10日 以降。)
そこでは、上記のような理論について、あまり肯定的でない見方をした。つまり、「モデルの仮定が満たされないので、モデル自体が無意味である」と。
本項では、さらに、「こういう景気循環モデルがまったく無意味である」と、強く否定する結論を出そう。
前に述べたのは、「二つある仮定がともに満たされない」ということだった。その仮定とは、
・ 調整速度が一定であれば。
・ 消費性向が一定であれば。
という2点である。
それゆえ、モデルとして、十分ではない、というわけだ。
このうち、特に後者は大事である。景気循環の本質は何か? 「消費性向の変化」が原因としてあり、そのあと、均衡点(収束点)に近づくにつれて生産量が変化するというスパイラルが発生することである。なのに、その根幹たることをすっぽかして、加速度原理だけで景気循環を説明しようとする。とすれば、そういう理論は、ほとんど無意味なのである。
また、さらによく考えてみると、たとえこの仮定を満たしていたとしても、加速度原理による景気循環理論は成立しない、とわかる。なぜなら、話の根源からして、間違っているからだ。このことを以下で示す。
加速度原理の要点は、「所得の増加が、(何倍かの係数で)投資の増加をもたらす」ということだ。ここが話の根幹である。しかし、この根幹そのものがおかしい。
なぜか? 「所得の増加」がもたらすものは、「投資の増加」そのものではなくて、「投資意欲の増加」にすぎないからだ。所得が増えれば、たしかに、投資を増やそうという意欲が何倍にも増える。(加速度原理の主張するとおりだ。)
しかし、このとき同時に、別の力も働く。それは、「金利の上昇」だ。これが、投資意欲に、水をぶっかける。景気が良くなれば良くなるほど、金利は上昇するから、逆に、投資意欲は抑制される。だから、「投資意欲が拡大したか投資が増える」とは、簡単には言えないわけだ。
要するに、現実の投資を決めるものは、次の2要素がある。
- 予想される販売量
- 予想される金利
この両者のかねあいで、投資が決まる。単純に a. だけで決まるわけではないのだ。「加速度原理による景気循環理論」では、そこを見失っている。
具体的に言おう。予想される販売量が、1割り増だとする。そのために、生産設備を1割拡大するので、例年よりもずっと多く設備投資をしたいとする。ここまでは、投資意欲の話だ。
しかし、である。このとき、金利がひどく上昇していれば、かえって損をする。たとえば、販売量が1割増えて、収益が1割増えても、払う金利がやたらと高くては、収益よりも利払いの方が高くなってしまう。結局、「増収減益」だ。これでは、いくら販売数量が増えても、何の意味もない。むしろ、設備投資をしないでいる方が、ずっと得だ。たとえば、何もしないでいれば、市場価格が上昇するから、利益率が上がる。投資をすれば損をして、投資をしなければ得をする。となると、金利が高いときは、投資をしたがらない。
結局、実際の投資を決めるものは、予想された「販売量」と「金利」の、双方なのだ。前者だけを見て決めるわけではないのだ。その意味で、「加速度原理による景気循環理論」は、無意味となっている。
しかも、それだけではない。マネタリズム的に「貨幣供給量の安定」をめざせば、「所得が増えたときほど、消費が増えているから、投資を減らす必要がある」となる。ここでは、総需要を安定させるために、「消費が増えたら、投資を減らす」という経済政策を取ることになる。(具体的に言えば、「何もしない」という経済政策だ。そのことで、貨幣供給量を安定させ、総需要を安定させるわけだ。)
一般的には、景気の良いときは、消費性向が高くて、消費が増えている。そういうときほど、金融当局は、物価安定のために、高金利政策を取って、景気安定をめざす。それがうまく行けば、投資も消費も縮小して、景気は冷える。逆に、それがうまく行かなければ、消費が減らないまま投資だけが縮小して、スタグフレーションになる。
まとめて言おう。
「加速度原理による景気循環理論」では、「投資意欲の増幅効果」を主張する。そこまでは正しい。しかし、実際には、「投資意欲」のほか、「金利」も影響する。消費がプラスになると、投資意欲は何倍にもプラスになるが、同時に、金利上昇の力が、投資をマイナスにしようとする。その力は実に強力で、投資がマイナスになるまで否応なく上昇する。(それが「金融市場における市場原理」だ。)
結局、「加速度原理による景気循環理論」では、「投資意欲がプラスになるから、投資も大きくプラスになる」と想定しているが、実際には、「投資意欲がプラスになるときには、投資は逆にマイナスになる」という傾向がある。それがマネタリズム的な政策だ。
現実には、どうなるか? 実は、そのいずれにもなる。
- 金利上昇が少ないとき
…… 加速度原理が働き、生産量がとても増大する。通常、物価も上昇する。
- 金利上昇が中間のとき
…… 加速度原理がうまく相殺される。投資が抑制されて、総需要は安定する。ただ、当面はそれでいいが、投資不足のせいで、将来は供給不足になる懸念がある。
- 金利上昇が多めのとき
…… 加速度原理が過剰に打ち消される。投資がひどく抑制されて、総需要が縮小する。景気後退だ。下手をすると、さらに悪化して、不況になる。
結局、どうなるかは、金利しだいである。金利しだいで、どうにもなる。それゆえ、金利を無視してモデル的に考える「加速度原理による景気循環理論」は、意味がないのである。
なお、仮に「金融を無視する」という立場に立つとしても、それもダメだ。なぜなら、そもそも、「何もしなければ金利が自然に変動する」からだ。そして、その「自然に変動する」ところを考慮しなければ、単に現実から遊離した、机上の空論になるしかない。
どんな命題であれ、仮定が偽であるならば、結論もまた偽である。そういう無意味な命題が、「加速度原理による景気循環理論」なのである。
[ 付記 ]
もう一つ、根元的な問題がある。それは、「景気循環の本質」だ。
そもそも、景気は循環しない。そこを理解しない限り、「加速度原理による景気循環理論」は根源からして間違っている。(たとえば、「周期的に循環する理論」というもの自体が無意味である。)
景気というものは、循環するするものではなくて、「不安定構造」を取るだけだ。次の図のように。
そして、この図の意味することは、好況と不況とで異なる。
-
不況の場合。
景気は単にスパイラル的に悪化するだけだ。つまり、奈落の底に向かって進むだけであり、「放置すれば元に戻る」ということはない。循環などはしない。(ここが肝心だ。)
ただ、いったん「縮小均衡」の点まで落ち込めば、あとはそこから均衡の過程で回復する可能性はある。とはいえ、前にも述べたとおり、「縮小均衡」の点に達するには、「循環的な過程」で、ほとんど無限に近い回数を経なくてはならない。また、いったん景気が悪化すると、消費性向がどんどん低下して、「縮小均衡に近づいたと思ったら、また縮小均衡の点が遠のく」というふうになりがちだ。
結局、何年も何十年も、景気悪化が続く可能性が高い。だから、とにかく、あまり状況が悪化しないうちに、状況を改善する必要がある。下限均衡点を割らないうちであれば、金融政策は有効だから、たとえ景気後退になっていたとしてお、景気は制御可能である。しかし、「金融政策の余地を残しておく」などと考えて、金利の引き下げをためらっていると、ぐずぐずしているうちに、急激に上図[右側]の ● が転げ落ちてしまう。そうなっては、もはや手遅れである。
- 好況の場合。
景気はスパイラル的になりがちだ。元祖マネタリストの主張では、貨幣供給量を一定にしておけば、金利の上昇を通じて、消費の増大を投資の減少で食いつぶすはずだ。しかし、実際には、そうはならない。なぜなら、貨幣の「流通速度」が上昇するからだ。かくて、「加速度原理」の主張するほどではないにしても、景気はゆるやかにスパイラル的に拡大していく。
ただし、それも、無限に続くわけではない。好況は、「需要超過」つまり「所得以上の過剰消費」があるから、発生する。とはいえ、「所得以上の過剰消費」なんてことが、いつまでも続くはずがない。バブル期ならば、資産価格を実際以上にあるとみんなで信じ合っていることもできるが、その妄想もいつか醒める。やがては、何もしないまま湧いてきたはずの所得が本当はなかった(実はゼロサムであった)という真実に気づく。とたんに、過剰消費が縮小する。過去の過剰消費の分まで、需要が急激に減ってしまう。……こういう形で、「伸びたものが縮む」形で、「景気循環」は発生する。
まとめ。
「景気循環」は、好況と不況とで異なる。
好況ならば、伸びたあとで、いつか必ず縮む。永遠に伸びることはありえない。少しずつならば永遠に伸びるとはできるだろう。しかし、急激に伸びたあとは、急激に縮む。
不況ならば、縮んだあとで、元に回復することもあるが、むしろ、ずっと縮みっぱなしになりがちだ。縮んだものを回復させるには、放置するだけでは足りず、適切なマクロ政策が必要である。しかも、いったん深く落ち込んだあとでは、マクロ政策の規模は、十分に大きくする必要がある。(「最初にドカン」だ。)
( ※ とにかく、景気変動については、修正ケインズモデルによって、物事の本質を考える必要がある。消費性向の変化や、金利の変動や、消費と投資の関係や、所得の効果など。これらを、総生産や総所得とも結びつけて、関係をしっかりととらえる必要がある。要するに、「加速度原理による景気循環理論」というのは、ごく簡単なモデルを仮定して、そのあと数学的操作をしただけであり、そういうのは、あまりにも幼稚すぎて、お話にならないわけだ。)
[ 付記 ]
本項で述べたことは、景気の不安定さを示すものとして、ごくおおざっぱに、直感的に理解するだけにとどめておいてほしい。実は、ここで述べたことは、あまり正確ではない。「景気の不安定さ」というものは、上記のような ∩ 型の図形で理解しきれるものではない。正しい説明は、このあと、別の理論で述べる。
当面は、ごくおおざっぱに、直感的に「ふうん」と納得するだけに留めてほしい。
( ※ なぜ、今ここで説明しないかというと、厳密に説明するには、「複数均衡点」というような話に突っ込まなくてはならないからだ。それでは、話が大がかりになりすぎて、とても簡単に説明がつかなくなる。詳しい事情は、「複数均衡点」について述べたあとで、関連する話として述べる。)
● ニュースと感想 (4月21日)
「他の経済モデル」について。
モデルについての話の最後に、「トリオモデル」や「修正ケインズモデル」とは異なるモデルを、いくつか述べておこう。いろいろとあるが、以下で列挙する。(前項で述べたのとは別のモデル。)
(1) 経済成長の理論
「経済成長の理論」というのがある。これは、景気の変動を扱うモデルとは別だ。つまり、「トリオモデル」や「修正ケインズモデル」とは、話の対象が異なる。
「経済成長の理論」としては、古典派の理論がいろいろとある。それで、特に問題はない。なぜなら、「経済成長の理論」というのは、「需給の均衡」が前提されているからだ。それならば、話は難しくない。
この件については、前にも述べたことがある。「資本蓄積の黄金律」や「消費のターンパイク定理」という用語がある。そちらを参照。 ( → 6月14日 )
簡単に言えば、こうだ。経済成長のためには、生産量を最適化すればよい。それには、投資と消費の比率を、最適化すればよい。投資が不足だと、もちろん、成長はそがれる。かといって、投資が過剰だと、せっかく投資をしても、所得不足で需要不足となり、設備が稼働しなくなる。だから、「生産能力」×「稼働率」にあたる「生産量」が最大となるように、投資を消費を最適化すればよい。そして、いったん最適化したら、あとはその比率のまま、投資と消費を伸ばしていけばよい。
上の話のポイントは、「投資と消費の比率に最適解がある」ということだ。
ただ、注意しよう。上の話は、単に「最適解がある」つまり「投資と消費の比率に最適の比率がある」ということを示すだけだ。「比率を変えたらどうなるか」というような動的な問題は、話の外にある。
こういう動的な問題は、マクロ経済学の扱うことだ。マクロ経済学であれば、「投資と消費の比率が変動すると、所得の変化を通じて、生産量がどう変化するか」ということを考えることになる。そして、それが、修正ケインズモデルを使ってやることだ。
では、その正解は? こうだ。
「投資と消費の比率の問題は、単にその比率だけを考えてもダメだ。まずは、総需要(= 投資+消費)と生産量とのバランスを考える。「需要超過か需要不足か」によって、所得を通じた生産量の変化が発生する。
一方、投資の拡大は、時間を経たあとで、生産能力(供給力)の拡大をもたらす。それは上限均衡点を右上に伸ばす効果がある。
現実の生産量は、上記のさまざまな要因がからまって決まる。あるときは上限均衡点が制約となるし、あるときは所得が制約となる。(ここまでは従来の経済成長理論と同じ。) さらに、そういう制約とは別に、「需要超過か需要不足か」によって、実際の生産量が動的に変化する。(この変化の過程は、修正ケインズモデルでわかる。)
マクロ経済では、そういうふうに、さまざまな要因がからまるわけだ。
( ※ 「経済成長の理論」は、それだけでは需要の変動を無視しているので問題だが、だとしても、それだけでもかかり有益である。たとえば、すべてが理想的に行っている状況[需要も変動しない状況]では、「投資と消費の比率を変えては行けない」とわかる。だから、「企業所得と労働者所得の比率を変えては行けない」と言える。「物価上昇を防ぐために賃下げをすればいい」と経団連はかつて主張したが、そういう考えだと、物価上昇は防げても、消費不足になるので、成長がそがれる」ということがわかる。目先の企業利益ばかりを追って賃上げを拒むと、せっかく作った製品を買ってくれる客がいなくなるわけだ。……そういうことがわからないから、かつてもに過剰投資をしたし、いまも設備過剰で困っているわけだ。そういう愚かさを指摘する有益さがあるわけだ。サプライサイドの経済学者は、「企業の収益性を向上させよ」と主張しているが、そういう経済学者は、「経済成長の理論」を理解できないほど愚かだ、とわかる。「投資と消費には最適の比率がある」ということがわからず、単に「投資を増やせ」とだけ主張する人々を、「サプライサイド」と呼ぶ。「企業が収益性を向上させれば、労働者・消費者の所得が減る」ということを、彼らは理解できないのだ。)
( cf. 経済成長の理論 → 6月14日 〜 6月15日 )
(2) IS-LM との関係。
cf.
IS-LM については、先にこう述べた。「 IS-LM 分析というのは、ごく短期的にのみ成立するのであって、長期的には成立しないのである。グラフで言えば、局所的にのみ成立し、大局的には成立しないのである」( → 4月07日 )
また、以前にも、詳しく言及した。( → 7月25日 ,7月26日 )
とにかく、短期的・局所的にのみ適用できるのであって、長期的・大局的には適用できないのだ。
また、マクロ的にも、金利ばかりを変数としていて、他の概念がない、という問題点もある。
IS-LM というモデルで、最も危険なのは、「経済現象のすべては金利を変数として動く」と考えがちになることだ。そして、この考えに染まると、不況のときに、やたらと「金利を下げよ」とか、「それでもダメなら量的緩和をせよ」とか、そういう金融政策ばかりを主張することになる。
ここで欠けているものは、次のことだ。
- 需要と供給とのバランス
- 消費と投資のバランス
- 消費性向変化(と、その効果)
- 所得と生産の相互影響
- 貨幣供給量の変化の影響
- 減税の影響
こういうものがまるきり欠けているのだから、そのモデル的な結論は、あまり信頼がおけない。
特に問題なのは、長期的な影響だ。IS-LM では、「金利を下げれば生産量が増える」という結論が出る。なるほど、短期的には、そうだ。しかし、長期的には、そうではない。生産量が増えているときは、好況であり、そういうときには、金利が高い。だから、「金利が低いときには生産量が増えている」というような IS-LM のグラフは、事実とは正反対なのだ。事実とずれが生じるというような問題ではなくて、事実とはまったく正反対のことが結論されるのだ。
IS-LM で示すようなグラフは、まったく成立しない。成立するのは、短期的な場合の局所的な話だけだ。その時点で、「金利を下げれば生産量を増やす」というふうに、増分の変化率の話はできる。しかし、「金利が低いときには生産量が増えている」というような大局的なグラフは描けないのだ。
にもかかわらず、そういうグラフを使って考えている IS-LM というモデルは、そのモデル自体が根本から見当違いだ、ということになる。 IS-LM というモデルは、「正確さが足りない」とか、「いくらか補正するべきだ」とか、そういう「未完成な」モデルではない。根本から狂っているモデルなのだ。どこをどういじっても、正しいものに補正することなどはできない。根本的に捨てるしかない。
( ※ なお、短期的・局所的な政策決定のためだけなら、いくらか役立つかもしれない。だとしても、長く線を引っ張って、グラフを描いたりしては、ダメである。そういうやり方によって、たまたま妥当な結論が出ることもあるが、そんなものには、何の根拠もない。)
( ※ IS-LM というモデルに、たった一つだけ意義があるとしたら、経済学の発展に寄与したということだけだ。たとえば、光の「波動説」や「粒子説」は、正しくない理論ではあるが、物理学の発展に寄与した。そういうふうに、学問の歴史の一里塚を占めるぐらいの意味はある。)
[ 補説 ]
IS-LM は、どこに欠陥があるのか? その核心を示そう。
さまざまな要素が考慮されていないというのは、「不完全」というにすぎず、根本的な欠陥ではない。根本的な欠陥は、「長期的には正反対の結論を出す」というところだ。では、その核心は?
答えを言おう。それは、「金利と他の量(貨幣量・生産量)とを、独立変数と見なしていること」である。この二つを、独立変数と見なして、2次元のグラフを書いている。そこに根本的な問題がある。なぜか? この両者は、短期的には独立変数であるが、長期的には関数関係にあるからだ。わかりやすく言えば、短期的には相互に独立しているが、長期的には相互影響があるからだ。
具体的に例を示そう。
第1に、IS 曲線だ。「金利を下げると、生産量が増える」ということは、短期的・局所的には成立する。しかし、長期的には、次のことが成立する。「金利を下げると、生産量が増え、その結果、資金需要が増えて、金利が上昇する」。つまり、「金利を下げると、金利が上がる」のだ。そして、このことは、現実に見て取れる。金利を下げて景気刺激をすると、インフレになって、金利が上がる。
第2に、LM 曲線だ。「貨幣供給量を増やすと、金利が下がる」ということは、短期的・局所的には成立する。しかし、長期的には、次のことが成立する。「貨幣供給量を減らすと、金利が上がり、生産量が減り、その結果、資金需要が減って、金利が下がる。それでもまだ景気回復が不十分なので、貨幣供給量をやたらと増やす」。つまり、「貨幣供給量を減らすと、貨幣供給量が増える」のだ。そして、このことは、現実に見て取れる。バブル期の最後に、貨幣供給量を減らすと、景気がひどく悪化したので、その後、やむなく、やたらと貨幣供給量を増やしている。
以上、第1と第2の例を示した。そのどちらにおいても、「二つの変数は、短期的には独立しているが、長期的には相互影響がある」という点が肝心だ。そして、IS-LM というモデルは、この長期的な相互影響を無視している。それゆえ、長期的な事柄には、正解とは正反対の結論を出してしまうのだ。
( ※ 「短期と長期」に関して、同様のことは、しばしば見られる。たとえ話ふうに言おう。企業は、研究開発投資をすると、その分、収益性が悪化する。やればやるほど、収益が悪化する。しかし、短期的にはそうでも、長期的には、そのことで収益性が向上するのだ。ここでは、「収益性を悪化させると、収益性が向上する」というふうになる。……賢明な企業は、そのことを理解している。たとえば、研究開発投資の売上高比が、他の企業の2倍にもなるキヤノンがそうだ。1月下旬の新聞報道によれば、キヤノンはソニーを上回り、業界最高の利益を得たという。一方、ほとんどの企業は、「短期的な収益性の向上」に気を奪われて、研究開発投資を減らしている。これでは、今は良くても、将来はひどいことになるだろう。)
[ 参考 ]
サイバネティックスというものもある。
これは、モデル論ではないが、その思想が、非常に有益である。その思想とは、こうだ。
「状況を最適化するには、ある変数を最適に制御することが大切なのではない。操作可能なすべての変数について、最適に制御することが大切だ。たとえば、船で言えば、舵だけを最適制御するだけでなくて、エンジンやら、帆やら、タンクによる浮力やらバランスやら、そういうさまざまなもの(操作可能なすべてのもの)について最適制御することが大切だ。」
なお、これと正反対の考え方は、経済学には、非常に多い。次のようなものがある。
- 金融政策だけ。(マネタリズム)
- 貨幣供給量だけ。(元祖マネタリズム)
- 有効需要だけ。(ケインズ派)
- 生産性だけ。(サプライサイド)
- 増減税でなく、減税だけ。(レーガノミックスふう。)
- 賃上げだけ。(労働組合)
- 物価安定だけ。(日銀)
- 構造改革だけ。(小泉)
こういうふうに、「××だけ」という主義ばかりだ。ついでに言えば、「政策をすべて動員せよ」と主張するエコノミストもいるが、彼らの主張には、なぜか、一つだけは委譲されているものがある。それは、「減税と貨幣供給量の調節」だ。すなわち、「タンク法」だ。
いったん深い不況になったならば、これだけが有効なのだが、なぜか、これだけが排除されている。それゆえ、今の日本は、いつまでたっても景気回復ができない。
日本の不況がいつまでも続くのは、ゆえなきことではない。「不況から脱する策」は、わかっているのに、あえてそれを拒んでいるからだ。
たとえ話。
瀕死の患者に、劇的な回復ができる薬を与えた。しかし、患者は、それを飲まなかった。「本当にこれは利くんですか? 本当に?」そういうふうに疑ってばかりいる。そして、疑いながら、どんどん衰弱して、死に向かいつつあるのである。── 結局、この患者に欠けているのは、病気から治る方法ではなく、その方法を受け入れる勇気なのだ。
● ニュースと感想 (4月22日)
「需要統御理論との関係」について。
前に、「需要統御理論」というものを述べた。( → 該当ページ ) それとの関係を考えよう。
そこで述べたことの要旨は、次の通りだ。
「経済を動的に考えると、『生産性の向上』というものがある。これが経済を静止させず、変化させる。経済が変化するのに、あえて静止しようとすると、歪みが生じる。── それが核心だ。」
「具体的に言えば、こうだ。生産性の向上により、その分、供給能力が拡大する。なのに、需給が拡大しないと、供給能力が拡大した分、需給ギャップが生じる。それが失業などの問題をもたらす。」
ここで、修正ケインズモデルと比較すると、何が問題となっているか? それは、「供給能力の拡大」である。
修正ケインズモデルは、経済の変動の原因として、「消費性向の変化」だけを考慮していた。ここでは、供給能力の変化については、考慮しなかった。しかし、経済学をいっそう正確に考えるには、供給能力の変化についても、考慮する必要がある。そして、生産性の向上があれば、供給能力の拡大が生じるのだ。
というわけで、修正ケインズモデルに追加して、生産性の向上の分も考慮する必要がある。
( ※ あくまで、追加的に考えるだけでいい。修正ケインズモデルを否定する必要はない。)
では、生産性の向上を考えると、どうなるか? 先に「需要統御理論」を提出したときには、「物価上昇によって、生産量の拡大をめざすべきだ」という結論になった。では、修正ケインズモデルをよく理解したあとでは、この結論は、どうなるだろうか?
がある。ここで、二者択一。
いきなり、結論を言おう。修正ケインズモデルを知ったあとでも、需要統御理論における結論は変わらない。ただし、いっそうよく、本質を理解できるようになる。その本質とは、何か? それは、「生産性の向上があるときには、生産量の拡大がないと、縮小均衡または景気後退のような状態になる」ということだ。
具体的に示そう。今、生産性の向上が3%あるとする。このとき、企業には、次の二つの選択肢がある。
- 生産量を3%増やして、解雇者を出さない。
- 生産量を同じにして、解雇者を3%出す。
前者は、積極路線である。生産量を3%拡大する。需要が拡大すると見込めるか、シェアを高めると見込めるか、いずれかの場合に、こうなる。(途上国や成長産業では、こうなりやすい。)
後者は、消極路線である。需要が拡大すると見込めないか、需要が拡大してもシェアを落とすと見込めるか、あるいは、生産量を増やしても利益が減ってしまうと見込めるか、いずれかの場合に、こうなる。(先進国や成熟産業では、こうなりやすい。)
この両者は、どちらも成立する。どちらにするかは、経営方針しだいである。また、企業としては、どちらを取ろうが、勝手である。どちらが良いとか悪いとかいうことはない。
ただし、個別企業にとってはそうだとしても、マクロ的には異なる。マクロ的には、前者と後者とでは、意味が異なる。前者ならば、特に問題がないが、後者ならば、失業が発生する。── そして、後者には問題があるということを指摘したのが、需要統御理論である。
ここで、修正ケインズモデルに返って考えよう。前者にせよ、後者にせよ、特に不況状態になっていないのだとすれば、どちらにしても、(需給の)均衡状態は保たれていることになる。だから、マクロ的な景気問題としては、どちらも特に悪いわけではないのだ。少なくとも、制御不能となって奈落の底に落ち込むような、デフレの問題は発生していない。
とはいえ、たとえ需給は均衡していても、「生産量の縮小による失業の増加」という問題が発生している。そして、これは、「縮小均衡」や「景気後退」のときと同じ問題なのである。
この場合は、少なくとも「需給ギャップ」という現象は発生していないから、不況対策のような強い景気対策は、特に必要ないことになる。とはいえ、選択肢は、次の三つだ。
-
ワークシェアリングをしないで、特定の労働者にしわ寄せをする。つまり、失業率を上げる。(当然、彼らの生活費を、他の人々が負担する必要がある。最悪。)
-
ワークシェアリングをすることで、一人あたりの所得と労働時間を減らす。そのことで、失業率を下げる。(いわゆる「シンプルライフ」路線である。これはこれで成立する。)
-
生産量を増やす。一人あたりの所得も減らさず、失業率も増やさない。
このうち、a
は、最悪だ。b
は、一応は成立するが、毎年、2.5% ぐらいずつ労働時間を下げるというのは、非常に困難だ。しかも、こうすると、国民の所得の向上は、全くないことになる。これでは困る。となると、残るのは、c
しかない。
実際には、b
と c
の折衷が普通だ。つまり、「基本的には、生産量の増加だが、ワークシェアリングもいくらか加味する」というふうになる。それが普通だ。
そして、そうすれば何も問題はない、ということを、「需要統御理論」および「修正ケインズモデル」から、結論できる。
さて。「物価上昇」との関係は、どうなるだろうか?
基本的には、「生産性の向上」の分だけ生産量の拡大があればよい。物価上昇は特に必要ない。
前に述べた「インフレ」の場合には、「需要の拡大に応じて、需給曲線の均衡点が移動して、価格が微弱に上昇する」と述べた。ただし、それは、「生産性の向上」がない場合の話だった。「生産性の向上」がある場合には、物価下落圧力が生じる。
実際には、どうなるか? 次の二つの、どちらにもなるだろう。
-
生産性の向上の分、物価の下落が生じるが、所得の向上はない。
-
生産性の向上の分、所得が増えるが、物価の下落はない。
そのどちらにでもなるだろう。
とはいえ、ここで、物価の効果が出る。物価下落が発生するときは、「アメとムチ」(の逆)によって、消費を減らした方が当面は得だ。となると、消費性向が下がる。そのことは、均衡していた状態を、(需給ギャップのある)不均衡へと、転じる圧力となる。だから、 i
を避けるために、物価上昇圧力を加える必要がある。
では、 ii
ならば、問題はないか? いや、別の問題がある。「限界消費性向は1以下だ」ということだ。それゆえに、所得が増えても、所得の上昇ほどには、需要は増えないのである。となると、何らかの「消費拡大策」が必要となる。それが「アメとムチ」としての、物価上昇だ。( → 「需要統御理論」簡単解説 )
結局、「生産性の向上」があるときには、失業をなくすためには、「生産量の拡大」が必要であり、そのためには、「物価上昇」が必要である。(これは「需要統御理論」からの結論。)
そして、そうしないでいると、たとえ「均衡」を保っていても、それは「縮小均衡」や「景気後退」と似た状態となり、好ましくないのである。(これは「修正ケインズモデル」からの結論。)
なお、正確に言えば、例外的に「景気後退」が好ましい状態がある。それは、景気が過熱した状態だ。だから、景気が過熱した状態では、「生産性の向上」は純粋に好ましい。しかし、景気が過熱していない状態では、「縮小均衡」や「景気後退」が好ましくないように、「生産量の拡大」なしの「生産性の向上」は好ましくないのだ。
[ 付記 1 ]
つまりは、「生産量の拡大」なしの「生産性の向上」は、一般的に好ましくない。それは失業を増やすというデメリットがひどすぎるからだ。
たとえば、不況のときだ。サプライサイドは、「収益性の向上のために生産性を向上させよ」と主張する。しかし、収益性が悪化した理由は、生産性が悪化したからではない。需要が減少したからだ。ここで、生産性を向上させても、失業者が増えて、総所得が減るから、逆効果なのだ。個別企業は、生産性の向上(たとえばリストラによる解雇)で、収益性を高めることができるが、国全体では、そうすれば総所得が減るので、かえって収益性は悪化してしまう。(これが修正ケインズモデルからわかることだ。)
[ 付記 2 ]
欧州でも、似た現象が見られる。特に需給ギャップが生じているわけでもないのに、失業率が極めて高い。これは「縮小均衡」に似た状態だ。
欧州では、生産性の向上にともなって、労働力が余るようになったのに、生産性の向上ほどには、生産量が拡大していない。そのせいで、自然に、失業者が増えたわけだ。
だから、ここでは、景気刺激策が必要となる。特に、「アメとムチ」によって需要を増やすという、物価上昇が必要だ。にもかかわらず、欧州では、逆に、財政緊縮策を取って、「物価の安定」をめざしている。めざす方向が正反対だ。だからこそ、欧州では、高い失業率に悩むのである。
なるほど、欧州では、物価上昇によって金を奪われることは少ない。しかし、その分、高い税を払っている。その税は、失業者の失業手当をまかなうために払う。金は失業者を失業させるために払っているのである。純粋な無駄である。一方、物価上昇は、得をする人がいれば損をする人がいるというだけで、純粋な無駄は発生しない。
物価上昇を恐れすぎると、税によって金を奪われる。所得増加をともなう物価上昇は少しも損ではないが、失業率上昇をともなう税率アップはひどい損である。この違いを理解できない人々が、欧州で莫大な無駄を発生させている。
( ※ 念のためにいえば、こういうのは、マネタリストの処方である。日本のマネタリストは、「物価上昇をめざせ」と主張して、経済を破壊しようとする。欧州のマネタリストは、「物価安定をめざせ」と主張して、経済を破壊しようとする。方向は正反対だが、どちらも同じだ。彼らは、物価ばかりに目を奪われて、生産量というものに注目しない。それが原因だ。)
[ 参考 ]
「生産性の向上」というのは、シュンペーターの主張(イノベーションによる経済進歩)と関連する。シュンペーターの供給重視の理論が、ケインズの需要重視の理論とは、別の範囲のものだ、という点は、本項冒頭からもわかる。
● ニュースと感想 (4月23日)
すでに述べてきたことは、初期の第3章・前で述べたことと、食い違いがあるとも思えるかもしれない。
第3章・前では、クルーグマン説の解説という形で、次のように述べた。
「物価上昇率として、 2.5% 程度は必要である。そうすれば、劣悪な企業は、賃上げをしないことで、実質的に 2.5% 程度の賃下げをすることができて、倒産しないで済むからだ。物価上昇率が 2.5% 程度ないと、賃金の下方硬直性ゆえに、賃下げができないので、劣悪な企業は赤字倒産してしまう」と。
ここでは、「賃金の下方硬直性」を批判して、「賃下げ」を勧奨しているように思える。とすると、最近の私の主張とは、矛盾しているように思える。
しかし、矛盾はしていない。なぜか? 上記の説明は、あくまで、均衡状態(不況でないとき)の話である。対象は、劣悪な企業だけである。一方、最近は、「賃金の下方硬直性」を是認して、「賃下げ」を批判しているが、これは、不均衡状態(不況であるとき)の話である。対象は、劣悪な企業ではなくて、全企業である。── そういうふうに、事情が異なる。
もっとはっきり示そう。「 2.5% 程度の物価上昇率が必要だ」というのは、「微弱なインフレが必要だ」ということだ。ここでは、物価上昇率と賃上げが同時に発生しているわけだ。そして、その程度の微弱なインフレが必要だ、ということでは、私の主張は一貫している。
一方、最近は、「強引な物価上昇を狙うのはダメだ」と言っているが、これは、「量的緩和だけで物価上昇を狙うのはダメだ。所得の増加が必要だ」ということであり、「物価上昇だけがあって、賃上げがないのはダメだ」ということだ。換言すれば、「スタグフレーションや資産インフレはダメだ」ということだ。
だから、何度も繰り返すが、大切なのは「国民の所得」つまり「総所得」なのである。「物価上昇率がどうのこうの」とマネタリストは言うが、肝心なのは、物価上昇率ではなくて、総所得なのだ。「物価が上がればインフレになる」とか、「賃下げをすればいいのだ。総所得なんか知ったこっちゃない」とか、そういうふうに「総所得」を無視した考え方を否定しているわけだ。
「物価上昇率」ばかりにこだわると、その点を見失う。混同しないように、注意しよう。
● ニュースと感想 (4月24日)
前項の続き。
経済というものは、基本的には、次の二つのタイプに分かれると考えていい。
- 動的経済
- 生産性向上率 …… 2%
- 経済成長率 …… 2%
- 物価上昇率 …… 3%
- 金利 …… 5%
- 企業収益率 …… 5%以上
- 静的経済
- 生産性向上率 …… ゼロ
- 経済成長率 …… ゼロ
- 物価上昇率 …… ゼロ
- 金利 …… ゼロ
- 企業収益率 …… ゼロ
(1) 動的経済
前者のタイプは、普通の経済だ。
生産性向上率は、2% ある。その分、実質の経済成長率が 2% ある。物価上昇率は、3% ある。名目の経済成長率は、5% となる。それにふさわしく、金利は 5% ある。企業収益率は、金利よりも高いので、 5%以上 ある。
(2) 静的経済
後者のタイプは、停滞した経済だ。
生産性向上率が、ゼロである。その分、実質の経済成長率も ゼロである。物価上昇率は、ゼロである。名目の経済成長率は、ゼロとなる。それにふさわしく、金利も ゼロである。企業収益率は、金利よりも高くならず、ゼロである。
考察。
ここで、「静的経済」というものを、考察してみよう。
- (実質の)経済成長率はゼロである。(これは静的経済の定義。)
- 企業収益率はゼロとなる。(経済成長がゼロであるせいで。)
そもそも、需要と供給が安定的に均衡していて、企業収益率がプラスになるのであれば、生産は利益を生むから、企業は投資をする。投資をすれば、その分、(需給曲線のグラフで)供給曲線が右シフトする。そういうふうに、企業収益率がゼロになるまで、供給曲線が右シフトする。だから結局、静的な経済では、企業収益率は限りなくゼロに近づかざるをえない。(もし企業収益率がゼロでなければ、企業は投資をするので、経済成長があり、静的経済でなくなってしまう。)
- 金利はゼロである。(企業収益率がゼロであるせいで。)
そもそも、金利がゼロよりも高くなるとしたら、資金需要があるからだ。それは、企業収益率がプラスの値であることを要求する。しかるに、企業収益率はゼロである。ゆえに、金利はゼロとなる。(この金利は、当然、名目金利。)
- 物価上昇率はゼロである。(企業収益率と金利がゼロであるせいで。)
仮に物価上昇率がゼロでなくて、プラスの値だとすれば、企業は投資によって利益を得る。現時点の価格で原材料を買って、1年後の時点で製品を売れば、物価上昇率の分ぐらいの利益は出る。これは、(名目の)金利がゼロであるときには、有利である。結局、物価上昇率がプラスであれば、企業は投資をして、成長率がプラスになる。
ゆえに、成長率がプラスでないときには、物価上昇率はプラスにならない。つまり、静的経済では、物価上昇率がゼロである。
結局、静的経済というものは、まったく好ましくないわけだ。
「経済成長なんか不要だ、物価上昇率がゼロである社会の方がいい」と思う人々もいる。しかし、そういう経済は、静的経済である。なるほど、物価上昇率がゼロであるので、物価上昇の痛みはない。しかし、そのためには、経済成長がゼロであることを要求するし、生産性の向上もゼロであり、企業収益率もゼロであることを要求する。
生産性の向上がゼロだとすれば、生活の質はまったく向上しない。実例としては、何十年も同じ経済レベルにとどまった、ソ連や北朝鮮がある。社会の進歩に取り越されるわけだ。それが長期間続けば、石器時代のような生活を送ることになる。
企業収益率がゼロだとすれば、わずかな経済の変動により、企業は容易に赤字となり、次々と倒産や失業が発生する。経済自体は「安定をめざす」と言っても、外部からの攪乱要因(外生的な要因)によって、強引に変動を起こされるが、そういう強引な変動に対して、きわめて脆弱なのである。
一方、動的経済では、そういう問題が一切ない。
なるほど、物価上昇の痛みはある。そのかわり、物価上昇を上回る経済成長がある。人々の生活の質は、生産性の向上の分、着実に向上していく。企業収益率もゼロではないから、外部からの攪乱要因に対して、踏み止まる余力がある。物価上昇率がプラスであるので、タンス預金は不利となり、余剰の資金を貯蓄として引きつける力があり、資金の無駄な滞留を防ぐことができる。金利はゼロではないので、預金金利がプラスとなり、貯蓄を引きつける力がある。同時に、貸出金利がプラスとなるので、その金利を払える企業だけが融資を受けることができて、資金配分の最適化がなされる。(パレート最適。)
結語。
「物価上昇率はゼロなのがいい」ということは、まったくありえない。それは、消費者にとっては好ましいが、経済全体を不自然に歪めてしまう。あまりにも多大な悪影響がある。
経済というものを一面的に見てはいけない。たとえば、「商品価格は低いほどいい」と消費者は言う。しかし、生産者にとっては、「商品価格が低い」というのは、「利益低下」または「赤字化」を意味するのだ。とすれば、消費者の立場からだけ見て、「商品価格は低いほどいい」と言うのは、間違っている。
「物価上昇率はゼロなのがいい」と消費者は言うが、物価上昇率がゼロであるという状況は、静的経済なのだ。それは、ひとつだけメリットがあるが、同時に、多大なデメリットがある。そういうものを望むべきではないのだ。
そしてまた、経済というものは、静的に考えるだけではいけなくて、動的に考えるべきだ。単に需給曲線による「需給の調整」だけを見るのならば、静的に考えてもいいだろう。しかし、経済というものは、動的に変化する。需要曲線も、供給曲線も、たがいに影響しながら、時間のなかで変化する。そういう変化を、はっきりと理解しなくてはならない。
「物価上昇率」というのは、単なるひとつの状態ではないのだ。それは、経済を変化させる要因なのである。物価上昇率だけを見て、それが良いとか悪いとか言っても、無意味である。物価上昇率というものは、それ自体を判断するべきものではない。それによって引き起こされるもの(経済の変動)を理解して、物価上昇率の良し悪しを判断するべきものなのだ。
ともあれ、物事を見るなら、その一面だけを見るべきではなく、そのあらゆる面を見るべきなのである。
[ 付記 ]
わかりやすく、たとえてみよう。
静的経済とは、いわば、「臆病者の生活」なのである。小さな安定にこだわって、外部の活気ある生活を怖がる。「外に出たら、何があるかわからない。こわい。それよりは、今のまま、静かに落ち着いた状態を保ちたい」と。そうやって、森の奥で、こっそりと静かに暮らす。世界ではインターネットやパソコンが普及しても、十年一日のごとく、朝から晩まで農作業をしている。「自分はこれで幸せなんだから、これでいいさ。小鳥といっしょに暮らすのが、一番いい」と信じる。そしてあるとき、病気にかかって、薬もないまま、ポックリ死ぬ。
動的経済とは、いわば、「活力と冒険の生活」なのである。小さな危険を顧みず、たえず進歩しようとする。興味にあふれ、外部の未知の領域をたえず知りたがり、少しでも進歩したがる。その結果、温暖化を招いたり、大戦争を招いたり、公害を招いたり、ひどい被害をふりまく。その一方で、宇宙でも稀に見るほど、さまざまな真実を解明していく。ほんの小さな惑星にいるくせに、百億年以上も前の宇宙誕生の原理を知り、はるかな遠い宇宙のかなたの現象まで知るようになる。この宇宙の基本的な原理を知るようになる。その好奇心は、宇宙船の爆発などの犠牲を払っても、なおやむことがない。あくまで自分たちの能力をひろげていこうとする。
以上の二つの道がある。どちらを選ぶかは、その生物しだいである。地球上のほとんどの生物は、前者の道を選んだ。ただ食べて、子供を産んで、死ぬことだけで一生を終える。しかし、人間だけは、そうではなかった。後者の道を選び、次々と知の領域をひろげていった。好むと好まざるとにかかわらず、人間というものは、後者の道を選ぶ生物なのだ。もし人々が前者の道を選びたいのであれば、神様に頼んで、人間であることをやめて、猿にでも生まれ変わるといいだろう。
[ 補説 ]
「物価上昇率がゼロなのに、経済成長があり、生活が豊かになる」という夢のような状況は、まずありえない、というのが、上記の結論だ。
ただし、例外的に、この夢のようなことが現実に起こる状況もある。それは「円高」という状況だ。
具体的には、80年代を見よう。急激な円高( 1ドル=240円 → 120円 )が発生した。これにともなって、輸入物価の下落が発生して、物価上昇率はきわめて低く抑えられた。
そして、この急激な円高があったにもかかわらず、貿易収支は黒字を保ち続けたのである。つまり、急激な円高で、国際競争力は急激に低下したと思えたのだが、そうはならなかった。なぜなら、輸出企業が、必死に努力したからである。そして、努力すればするほど、貿易黒字の縮小は起こらなかったから、ますます円高が進んだ。
このとき、企業はたしかに必死だった。しかしとにかく、日本はこの急激な円高を乗り越えた。なぜかと言えば、急激な「国際競争力の強化」「生産性の向上」が発生したからだ。(必死の努力によって。)
だから、(人為的な円高は別として、)自然発生的な円高がある状況では、「物価上昇率がほぼゼロなのに、経済成長があり、生活が豊かになる」という夢のような状況が、成立するのである。そして、それを可能にするものは、「死にものぐるいの努力」なのである。
結局、経済的には非常に幸福になりたければ、「死にものぐるいの努力」をすることだ。天国のような甘い生活をしたければ、地獄のような苦しい労働をすることだ。それならば、可能である。しかし、「遊んで、楽する」ということは、ありえない。これは、当然である。
( ※ ただし、例外的に、「遊んで、楽する」ということは、可能になることはある。それは、「過去の富を食いつぶす」という形だ。「過去においては、働いても貧しくする。現在においては、遊んで楽する」という形だ。これならば、帳尻は合う。……実際、円高の時期にも、これと似た状況が発生した。「過去の円高が不十分だったから、その分の円高が起こる」というふうになった。それはつまり、「過去において起こるはずだった物価安定が、今になって起こる」ということだ。「過去において得るべき利益を、今になって得る」ということだ。これは、逆に言えば、過去においては、不利益[= 余分の物価上昇]があったことになる。とはいえ、これはこれで、帳尻は合っている。)
《 翌日のページへ 》
(C)
Hisashi Nando. All rights reserved.